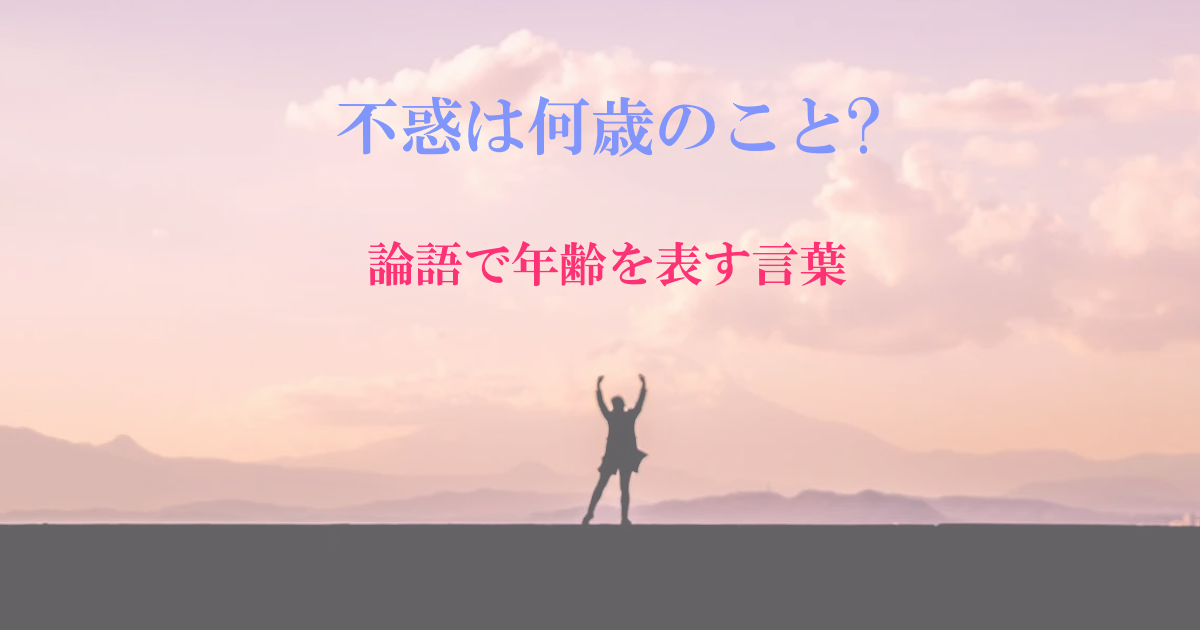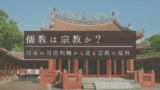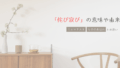日本では年齢の事を漢字で表す言葉があり、人生の事を論じる場合などに使われることがあります。
論語の年齢を表す言葉としては「不惑」や「知命」などが有名です。今回は、孔子が論語で述べた「年齢を表す言葉」とそれぞれの意味について紹介しています。
孔子と論語
孔子は、紀元前6世紀頃の中国に生きた思想家であり、後に「儒教」の祖と位置づけられる人物です。彼自身が書物を残したわけではなく、その言葉や対話は、弟子たちによってまとめられ、「論語」として伝えられてきました。
論語は、孔子の思想を知るうえで最も基本的な文献とされています。
孔子の思想は中国だけでなく、東アジア各地に広まり、日本や朝鮮半島でも長い時間をかけて受容されてきました。特に日本では、江戸時代に儒学が学問として整備され、武士の倫理や教育制度の基盤として取り入れられたことで、社会全体に深く浸透していきます。
その結果、現代の日本では、儒教を「宗教」として強く意識することは少ない一方で、礼儀や年長者への敬意、役割意識といった価値観の中に、孔子の思想が自然な形で溶け込んでいるとも言えるでしょう。
私たちは気づかないうちに、論語的な考え方に触れながら日常を送っているのかもしれません。
論語の「年齢を表す言葉」 ― 原文と現代語訳
「論語」の中で、孔子は自らの人生を振り返り、年齢ごとの心境の変化を次のように語っています。この言葉は『論語』為政篇に収められており、本来は為政者の徳や自己修養を語る文脈の中で述べられています。
(原文)
子曰、吾十有五而志乎学、三十而立、四十而不惑、五十而知天命、六十而耳順、七十而従心所欲不踰矩。
(現代語訳)
孔子が言った。私は十五歳で学問に志し、三十歳で、思想も、見識も確立した。四十歳で心の惑いもなくなり、五十歳で、天から与えられた使命を自覚した。六十歳で、何を聞いても耳にさからうことがなくなり、七十歳になると、自分の欲望のままに振舞っても、その行動が道徳からはずれることはなかった。
表にまとめると以下のようになっています。
| 年齢 | 言葉 |
|---|---|
| 15歳 | 志学(しがく) |
| 30歳 | 而立(じりつ) |
| 40歳 | 不惑(ふわく) |
| 50歳 | 知命(ちめい) |
| 60歳 | 耳順(じじゅん) |
| 70歳 | 従心(じゅうしん) |
この一節は、誰かに教訓を説くための言葉ではなく、孔子自身が歩んできた人生を簡潔に振り返ったものです。
そのため、理想像を押しつけるような響きはなく、あくまで一人の人間の経験談として語られています。
こうした語り口だからこそ、年齢を重ねた読者が自分自身の歩みと重ね合わせて読んだとき、そこに共感や示唆を見いだすことがあるのかもしれません。
以下では、この言葉を年齢ごとに分けながら、一般的な解釈を整理していきます。
論語における「年齢を表す言葉」の意味
ここからは、先ほど示した論語の一節をもとに、年齢ごとに表現されている言葉の意味を整理していきます。まずは一般的にどのように解釈されてきたかを確認しながら、順に見ていきましょう。
30歳 而立(じりつ) – 30にして立つ
孔子は30歳で学識や道徳観を確立して、世に立つ自信を得たとしています。
日本語ではあまりこの漢字(而)を使うことはありませんが、学生が親元を離れ、社会に出て生計を立てるようになることを「自立する」というため、言葉の響きとしては馴染みがあるのではないでしょうか。
ただ、孔子の言う而立には、「20代の間に学び経験したことに基づいて」という意味が含まれているので、社会に出て自立した生活をし始めるのとは少し意味合いが異なっています。新入社員や若き起業家として社会活動を開始したての頃は、ただただ必死で働いていたのが、徐々に周りの景色が見えるようになってくるものです。
自分の経験や実績を基に、社会の中で生きていく自信がつくのが、大体30歳になってからだったというのです。

日本の場合、こういった年齢の人たちの事を「働き盛り」と表現することがあります。ある程度の経験と実績があり、体も元気でエネルギーに満ち溢れているため、最も仕事ができる年齢帯と位置付けられているのでしょう。働いている人自身も、数々の経験を背景に、自信に満ち溢れていることが多いでしょう。
40歳 不惑(ふわく) – 40にして惑わず
孔子は40歳で心の惑いがなくなった(不惑)と述べています。惑いがなくなり、これからの人生のビジョンを明確に持つことができたと捉えていいでしょう。
40歳というのが遅いと感じる人もいるかもしれません。私自身、20代の頃には自分の人生はこうしていくのだという明確なイメージがあり、それに向かって邁進していたものです。恐らく、孔子自身もそうだったでしょうし、世の中で精力的に活動している多くの人が同じような気持ちで日々を生きていることでしょう。

しかし、ここでいう不惑というのは、そういった20代・30代といった若い時分の年月で培った経験を糧に、40代にして自分が進むべき道が明確化されたという意味と受け止めるべきでしょう。
漠然とした人生のイメージに基づいて、目の前の仕事に一生懸命がむしゃらに働いている20代や30代の気持ちと、孔子が40歳になった時に感じた「惑いがなくなった」という気持ちの間には、大きな違いがあるように思うのです。逆に言うと、一生懸命生きてきたからこそ、40代になった時に惑いがなくなる程の知見を得ることができたともいえるのかもしれません。
40歳を超えている方は、自分の人生を振り返ってみて如何でしょうか。何か人生の大きな決断をしたり、気持ちに区切りをつけて何かに取り組み始めた様な、そんな経験が40代の頃にあるでしょうか。
50歳 知命(ちめい) – 50にして天命を知る
40歳の不惑を超えて、孔子は50歳に天命を知ったと述べています。天命というのは、天から与えられた使命という意味合いですが、要するに「自分のなすべき事」が明確になったというのです。
ここでいう為すべき事というのは、天から与えられた使命なので、まさに「人生をかけて」取り組むべき事柄です。
私はまだ若輩のためその域には達していませんが、恐らく40歳で惑いがなくなって取り組みを続けていった結果、その先にある大きな使命のようなものが見えてくるといったことなのだろうと推測しています。
30歳で自信を確立し、40歳で惑いがなくなって何かに継続的に取り組み続けた結果、50歳になった頃には何かしらが理解できるようになるという人生の道標を孔子が示してくれていることは、40代で「継続は力なり」を信じて頑張り続けるモチベーションになるようにも思います。きっとその先に見えるようになる景色があるのでしょう。
継続して努力し続けることでしか、得られない結果もあるものです。
60歳 耳順 (じじゅん) – 60にして耳順う(みみしたがう)
孔子は50歳で天命を知った後、60代では人の意見を素直に受け止められるようになったと言っています。
悟っていると表現すると少し宗教的すぎる気もしますが、落ち着いて受け止めることができるということはそういう事のような気がします。若い時分には達観していると表現されることがありますが、そういった感じなのかもしれません。酸いも甘いも社会の理を理解した年齢になると、何事も驚かず冷静に対処できるようになるということなのでしょう。
70歳 従心 (じゅうしん) – 70にして矩(のり)を踰(こ)えず
70歳の矩(のり)を踰(こ)えずは、まず日本語的に読むことも理解することも難しい表現です。現代語訳にあるように、欲望のままに振舞っても道徳から外れなくなったという意味です。
日本では、論語の70歳は「従心(じゅうしん)」として知られています。
原文の「心のままに行動しても」の部分を抜粋した形のため、本来の趣旨からは少しずれた切り出し方のようにも思いますが、不踰矩(のりをこえず)では日本人には意味が伝わらないとされたのでしょう。
覚え方:人生ステップをまとめて記憶するコツ
論語の年齢を表す言葉は、どれも日常会話ではあまり使わないため、覚えにくいと感じる方も多いかもしれません。
ここでは、語呂やイメージを用いて、誰にでも覚えやすい方法をご紹介します。
語呂で覚える:に・ふ・ち・じ・じゅう
年齢を表す言葉の最初の音(読み)をつなげて覚える方法です。
| 年齢 | 漢字 | 読み | 頭文字の読み | ひとことで言うと |
|---|---|---|---|---|
| 30歳 | 而立 | じりつ | に | 自立する |
| 40歳 | 不惑 | ふわく | ふ | 迷わない |
| 50歳 | 知命 | ちめい | ち | 天命を知る |
| 60歳 | 耳順 | じじゅん | じ | 素直に聞ける |
| 70歳 | 従心 | じゅうしん | じゅう | 心のままにして過ぎない |
而立(じりつ)の「而」は、常用漢字ではないため難しいですが、「に」と読みます。
誤って「自立」と書いてしまうことも多いため、注意が必要です。
そのため、
- 音で覚えたい方:じ・ふ・ち・じ・じゅう
- 漢字も覚えたい方:に・ふ・ち・じ・じゅう
と覚えるのがよいでしょう。
音の近さが記憶の助けになるため、語呂で覚える方法はとても有効です。
人生のテーマで覚える
語呂だけでなく、「人生のどの段階にどんな力が備わるのか」と紐づけると、よりイメージしやすくなります。
| 年齢 | 言葉 | 人生のテーマ | 現代でたとえると |
|---|---|---|---|
| 30歳 | 而立 | 自立 | 自分の足で仕事や生活を築く時期 |
| 40歳 | 不惑 | 判断力 | 価値観が定まり、迷いにくくなる |
| 50歳 | 知命 | 使命 | 役割・責任を自覚する |
| 60歳 | 耳順 | 寛容 | 多様な意見を受け入れられる |
| 70歳 | 従心 | 円熟 | 心と倫理の調和、無理のない生き方 |
「自立 → 判断 → 使命 → 寛容 → 円熟」
と、成長曲線のように理解すると、ひとまとまりで覚えやすくなります。
自分自身や身近な人の今の立ち位置に当てはめてみると、一段と記憶に定着します。
孔子の実人生と照らし合わせると?
興味深いことに、孔子本人はこれらの年齢に完全に当てはまっていたわけではありません。
たとえば:
- 30歳の孔子は、政治的にはまだ無名の存在
- 50歳の頃にも理想と現実のギャップに苦しんでいた
- 70歳になっても “完全に揺るがない” 境地だったわけではない
むしろ、理想だからこそ年齢に区切って語ったと考えられます。
これは、論語の年齢の言葉が
「人生は理想に向かって少しずつ育っていくもの」
というメッセージであることを示していると言えるでしょう。
そのため、記憶する際には
「完璧でなくていい。向かっていく道しるべ」
として捉えると、五つの言葉が意味深く心に残ります。
人生は自分の物
孔子の教えは、迷ったときの道しるべとして役立つことがあります。
大きな決断をする際や、年齢に応じて人生を見直すとき、背中を押してくれる言葉にもなるでしょう。
しかし、すべての悩みが孔子の教えで解決できるわけではありませんし、人生観も人それぞれです。
論語の年齢を表す言葉も、あくまでひとつの指標に過ぎません。
自分に合った考え方を見つけ、それを道しるべとして歩んでいくことが大切です。
人生は、誰のものでもなく、自分自身のものなのです。
日本では儒教を哲学や思想として扱うことが多いですが、2021年には最高裁判所が「沖縄の孔子廟」を宗教施設と判断しました。
「儒教は宗教なのか」を、日本の司法判断から解説した以下の記事も是非あわせてご覧ください。
関連記事:日本では忘れられた「陽明学」
論語の背景にある儒教には、朱子学や陽明学などの派生思想があります。
日本では、江戸時代に朱子学(儒学)が官学として推奨されていました。
江戸中期には様々な思想が芽生え、その中の「陽明学」は儒学の一派ですが、理論派の朱子学を批判し、「行動が重要」と説きました。
幕末期には過激な思想の行動原理に使われたことから、日本では徐々に遠ざけられ、現代では多くの人が忘れてしまった「陽明学」ですが、中国ではビジネスなどを成功するためのマインドセットとして再注目を集めています。
陽明学の歴史と現代の状況について、以下の記事でまとめていますので、関心のある方は是非ご覧ください。