この世に存在するあらゆる物事には「歴史」があるものです。過去の出来事や偉人といった学問的な分類の「歴史」ではなく、過去からの風習や由来といった、時間の流れという意味の「歴史」について言及しているものをまとめています。
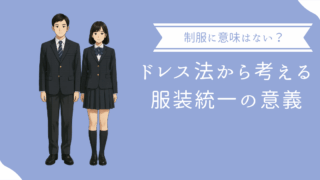 社会
社会 制服に意味はない? ― ドレス法から考える服装統一の意義
制服の自由化が進む現代。服装の統一に意味はあるのか?18世紀スコットランドの「ドレス法」を通じて、制服の意義と自由・規律のバランスを考えます。
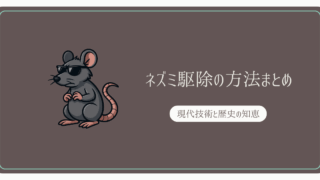 社会
社会 ネズミ駆除の方法まとめ ― 現代技術と歴史の知恵
ネズミ駆除にお悩みですか?毒餌・粘着シート・防鼠工事についてわかりやすく整理。さらに古代から江戸・明治まで、人々が工夫してきたネズミ退治の知恵も紹介します。
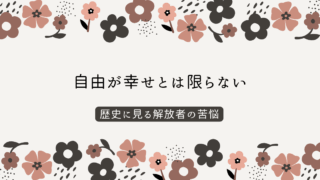 私見
私見 自由が幸せとは限らない ― 歴史に見る解放者の苦悩
自由は本当に幸せをもたらすのか。古代ローマの解放奴隷や南北戦争後の元奴隷の現実、現代日本の女性の社会進出を通して「自由と幸福」の関係を考えるエッセイです。
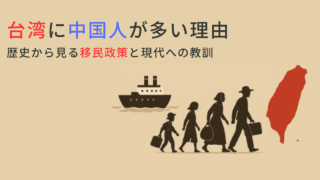 社会
社会 台湾に中国人が多い理由 ― 歴史から見る移民政策と現代への教訓
台湾に中国人が多い理由を歴史的移民政策から解説。清朝・戦後の大移住をたどり、現代の移民問題と比較しながら社会への影響を考えます。
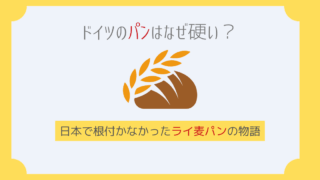 社会
社会 ドイツのパンはなぜ硬い?──日本で根付かなかったライ麦パンの物語
ドイツの硬いライ麦パンと日本の柔らかいパン文化の違い、歴史的背景や原料、定着しなかった理由をわかりやすく解説します。
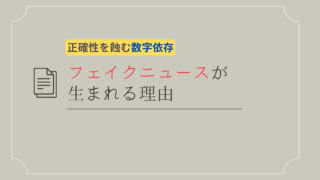 社会
社会 フェイクニュースが生まれる理由 ― 正確性を蝕む数字依存
SNSのフェイクニュースも、テレビ・新聞の虚偽報道も根本は同じ──数字依存が正確性を蝕む構造を分析し、脱却への具体策を提案します。
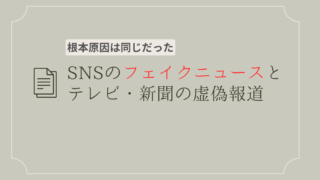 社会
社会 マスメディアの虚偽報道事例 ー SNSのフェイクニュースとの比較
SNSのフェイクニュースとテレビ・新聞の虚偽報道は、実は同じ構造的問題から生まれています。両者の事例を比較し、共通する原因と速度を落とさず正確性を高める改善策を考えます。
 歴史
歴史 近代インフラ整備の歴史 ― 日本の水道や電気はいつからあるのか
生まれた時からあるものは「あって当たり前」と思ってしまいがちです。今回は、明治時代以降にどのようにインフラが整備されていったのか、歴史を振り返ってみます。
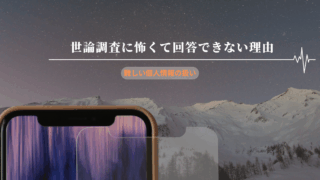 私見
私見 世論調査に怖くて回答できない理由 – 難しい個人情報の扱い
2025年の参院選において世論調査の電話を受けた(怖くて回答できなかった)自身の経験と共に、「情報リテラシーの高まり」と「個人情報の扱いの難しさ」について考えてみます。
 歴史
歴史 三隻の比叡(ひえい)の歴史 – 国防のための軍事力の是非
元々国土を守る軍を持っていなかった日本は不平等条約を結ばされ、その解消のために軍備を整え、列強の仲間入りを果たしました。今回は、日本の急速な近代化の中心にあった比叡(ひえい)という軍艦の歴史と共に、日本の国防について考えます。