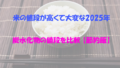最初に断っておきますが、この記事を執筆している私は、男女平等や少子化についての専門家でもなければ、世の中を変えたいといった激しい主張を持った人間でもありません。ただ地球上に生まれて、日本で育った一人の人間です。日々、学ぶことや人の意見を知ることを楽しんでいます。
男女平等や少子化といった社会的な内容を扱ってはいますが、ここに記していることが正解なのではなく、一人の考えとして受け止めていただければ幸いです。
今回は、現代において問題視されている少子化の原因が男女平等にあり、その解決策として一夫多妻制が合理的であると考える理由について述べています。人間社会の倫理観を超えて、生物的な視点から俯瞰して人類を見つめ直すと「見えてくるものがあるのではないか」という、ある種の問題提起ともいえるかもしれません。
男性(オス)と女性(メス)の生物としての役割
男女平等や少子化についての話を始める前に、その前提の話をまとめておきます。
人間は、一般的には知能が高いとされていますが、自分たちも生物の一種でありながら、他の生物とは違うと考える傾向があります。しかし、人が「生物」であることは、人自身の研究によって明らかにされており、純然たる事実でしょう。
人を含めた生物には、男性(オス)と女性(メス)が存在します。全ての生物は、食べて・眠って・繁殖するという行動を繰り返し、やがて死亡して生命活動を停止します。(「食べる」はエネルギーを外部から得るという意味合いで、人間と同じ摂取方法とは限りません)
性別が関係する「繁殖する」という行動においては、それぞれの性別で役割があると考えられていますので、それを以下の表にまとめてみます。
| 性別 | 繁殖の役割 |
|---|---|
| 男 (オス) | 数を増やす |
| 女 (メス) | 優秀な遺伝子を選ぶ |
男性(オス)が個体数を増やそうとし、女性(メス)が優秀な遺伝子を選ぶことで、生物全体としては「優秀な個体をできるだけ多く産む」ことになります。生物の本能に、「生存と進化」が機能として備わっていると考える事ができます。
男女平等により進む少子化
生物としての繁殖は、人間社会では「結婚」および「出産」ということになります。
現代は、ひとりのパートナーを選んで「結婚」するのが、世界的な倫理観としては多数派です。その倫理観は、人類の長い歴史の中で育まれてきたもので、昔も今も変わりません。
しかし、同じ倫理観の中で少子化は進行しています。
女性も活躍する社会が変えた「女性の結婚観」
男女平等が求められるようになってから、日本でも「女性も活躍する社会」というスローガンを掲げて、様々な政治的な制度の見直しなどが進められました。
男女平等の施策については賛否両論もありますが、今回は割愛します。以下の記事には関連したことをまとめてありますので、興味のある方はそちらもご覧ください。
男女平等が進められた結果、従来男性だけが社会で行っていた経済活動に、多くの女性も従事するようになりました。男性も女性も、人間として等しく同じ権利を持ち、自分の人生を決める事ができる社会であるべきなので、これは本当に素晴らしい社会の変革といえるのではないでしょうか。
女性も働いて、自分の力で生きていくことができる社会になったことは喜ばしい事ですが、これによって「女性の結婚観」には変化が起きています。
「生きる」ために「結婚する」しかなかった女性
働いて生きていくことが出来なかった時代の女性は、生きていくためには「結婚」するしかなかったといえます。女性は、結婚して男性に養ってもらうのが当然という価値観です。そのため、女性は養ってくれている男性に従うべきという考え「三従の教え」などが教育として徹底されました。(儒教教育)
三従の教えとは女性の生き方についての儒教道徳で、女性は「結婚前は父に、結婚後は夫に、夫が死んだら子に従う」というものです。完全なる男尊女卑思想ですが、女性が働けない江戸時代頃には「女性が生きるため」の考え方として教育され、一般に広まっていました。
そのため、働けない女性である「娘」が生き延びるために、親は見合いを行うなどして「嫁に出す」つまり「結婚させる」のが通例でした。女性としても、「結婚できるかどうか」は「生きるか死ぬか」だったわけです。
婚姻数の減少 – 「選ばない女性」と「選ばれない男性」
しかし、現代は女性も働いて自分の力で生きていけます。「結婚」することが「生きるための手段」ではなくなっているのです。今や、「結婚」は人生の選択肢のひとつでしかありません。

男女平等の思想が広まったことで、男性も女性も同じ人間として「自分自身が働いて生きていく」というのが、基本的な考えとして定着しつつあります。現代の感覚では、望まない結婚が横行していた時代を考えると、人権を無視した酷い時代だと嫌悪感を感じることでしょう。
ここでは「良し悪し」について言及するつもりはありません。男性は働いて、女性は結婚子育てという価値観を否定するものでもありません。男女平等は「人権的な観点」では進歩かもしれませんが、少子化や女性余りの婚活市場を鑑みても、現段階では違う問題がある状態と評価せざるを得ません。
昔は、見合いなどを通じて「女性に選ばれない男性」も結婚して女性を養うことが当たり前で、結婚して女性を養って初めて一人前という評価がされていたほどでしたが、今は「選ばれない男性」は結婚が難しく、生涯未婚で過ごすことになる時代ともいえます。
女性は生物としても、無理に「優秀でない男」を選ぶ必要はなくなりました。男性に養ってもらわずとも、自分の力で生きていけます。いい男性と巡り合わなければ結婚しないので、無理やり結婚していた(させられていた)時代に比べると婚姻数は減ることになります。
出生数の減少 – 持続困難な社会
もちろん男女平等の社会でも結婚はありますが、その数は減少傾向です。結婚する男女が少なくなれば、出生数は減少するしかありません。現代の倫理観において、結婚していない男女が子供を産み・育てるという行動は非難され、社会的にも受け入れられません。
結果論ではありますが、男女平等を進めたことで婚姻数は減り、少子化が進むというのは、ある種当然だったともいえるでしょう。
人間はその高度な知能によって、子孫を残すために生まれてきたのではないという価値観を作り上げました。自分の人生は自分のものであり、生物ではなく「ひとりの人間」なのだという考えです。
生物としての本能を理性で抑え込みながらも、全ての人間が平等であれば、「将来的に人間という種が絶滅しても構わない」と考える人も多いでしょう。自分の人生には大きな影響がない事が容易に想像できるからです。
しかし、少子化が進んで人口が減少すれば、社会を維持することは困難となり、生活は次第に不便になっていくことになります。その進行は、人間の一生の中で観測できる程度には早く、他人ごとでは済まないかもしれません。一般的には、現在の状況のままでは、行政のサービスなども含めて様々なものが持続困難と考えられているようです。
生物として合理的な一夫多妻制
男女平等が進められ、その結果として少子化が進むことになりましたが、それは人類の「人権を尊重した結果」であり、受け入れるしかありません。少子化の問題は、日本だけでなく先進諸国全般の課題でもあり、行政によって対策も進められています。
少子化問題の対策として、子育て支援など様々な施策が実施されていますが、一般の意見として「一夫多妻制」や「多夫多妻」といった言葉を聞くことがあります。
少子化を問題視するかどうかは別として、ここでは生物として「一夫多妻制」が合理的であるかどうかを考えてみます。
優秀な子孫をたくさん残す – 生物としての観点
生物としては、最初に述べた通り「優秀な子孫をたくさん残す」本能があり、これにより生物種としての「生存と進化」が担保されていました。
現状の「一夫一妻」制と、少子化対策に有効とされることがある「一夫多妻」制を、表にして比較してみます。
| 性別 | 役割 | 一夫一妻の相手 | 一夫多妻の相手 |
|---|---|---|---|
| 男 | 数を増やす | 選んでくれた女性一人 | 選んでくれた女性全て |
| 女 | 優秀な遺伝子を選ぶ | 優秀な男性 | 優秀な男性 |
女性は一夫多妻になっても、一夫一妻制と同じように「優秀な男を選ぶ」という生物の役割に変化はありません。一方、「数を増やす」ことを役割にもった男性は、一人ではなく複数の女性を相手にすることができるようになり、生物としての役割を「より果たせる」ようになっているといえるでしょう。
「選ばれる男性」を選ぶ女性
女性は、(生物的・社会的に)優秀な男性を選びます。しかし、現行の「一夫一妻」制の価値観の中では、特定の相手(妻・彼女等)がいる場合には、身を引くことになるでしょう。この価値観(倫理観)は、宗教的な不貞や姦淫といった考え方に起因していますが、現代ではそれを正しいとするのが多数派であることは疑いようがありません。
しかし、女性が選ぶ優秀な男性は、当然他の女性からも選ばれます。
「選ばれる男性」は生物として優秀なため、複数の女性から選ばれるのは自然な事です。しかし、女性が本能として優秀な子孫を残そうとしても、人間の倫理観はそれを許しません。
男女平等によって女性も働いて生きていけるので、妥協してでも「選ばれない男性」を選ぶ必要はないのです。
選ばれようとするオスの原動力
女性に優秀でないと判断された男性は子孫を残せませんが、それは自然の摂理であり、生物の常と言わざるを得ません。そのため、生物界においては、メス個体(女性)に選ばれるために、力を誇示して他のオス個体(男性)と争ったり、美しさをアピールして求愛するといったことが行われているのです。

よく、男性の性欲が社会の原動力といった表現を目にしますが、これは自然や生物といった観点では当然の原理といえます。男性は女性に選ばれるために、優秀であることを誇示する目的で財力や権力を追い求めるものだと言えるでしょう。生物として多くの子孫を残す事こそが、男性の根源的な本能です。
要は、人間は他の動物と何も変わらないということです。男性の性欲は社会の原動力でもあり、「社会の発展」は優秀であることを誇示しようとした「オスの副産物」と捉えてもよいのかもしれません。
多夫多妻にすべきという風潮
少子化の原因にもなっている男女平等思想は、少子化対策の面においても活躍します。
一夫多妻制について論じると、男女平等を掲げる活動家の方々などから、「多夫多妻」とすべきだという指摘がされることがあります。一夫多妻と多夫多妻について、男女平等や少子化対策といった観点からみてみます。
多夫多妻とは – 不平等な一夫多妻制の問題を解決
一夫多妻は、男性は複数の女性と婚姻することができるのに対して、女性は複数の男性と婚姻することが出来ないという、権利面において不平等な制度です。
人権意識が高まっている現代において、男女不平等な制度は受け入れられることはないでしょう。
男性も女性も、等しく複数の異性と婚姻できるとする「多夫多妻」は、男女の権利が平等で、一夫多妻制の問題を解決する考えとされています。
少子化対策としての多夫多妻
男女平等の権利を重視して、一夫多妻ではなく多夫多妻とする考えは、現代の考え方に迎合しており良さそうに見えます。
しかし、「選ばれない男性」は、例え制度が多夫多妻であっても選ばれないでしょう。「選ばれる男性」は複数の女性から選ばれ、「選ぶ女性」は複数の男性を選ぶかもしれませんが、(生物的・社会的に)優秀でない男性はやはり選ばれません。複数の女性と結婚している男性の相手もまた、複数の男性と結婚しているという、頭の混乱する複雑な状態になりそうです。

少子化対策としては、妊娠・出産そして子育てを考慮すると、「女性が複数の男性」を選ぶというのは現実味がありません。仮に子育てを全て男性がするとしても、優秀な男性は複数の女性から選ばれるため、結果として大量の子供を育てることになり、やはり無理があります。妊娠・出産は女性にしかできないことからも、少子化対策としては一夫多妻制以上の効果は期待できないと考えられます。
男女平等の権利から「多夫多妻」にすべきという考えは理解できますが、これは人間の倫理観によるエゴであって、生物として合理的とは言えないでしょう。ただ、「男女平等で少子化対策を兼ねる」という意味合いでは、現行の倫理観では最良なのかもしれません。
倫理観で絶滅する皮肉な生物
少子化がこのまま進行していけば、人類はいずれ絶滅する結末を迎えるのかもしれません。
生物種としての「人類の絶滅」が、良いか悪いかは分かりません。地球上ではこれまでにも多くの生物が誕生し、そして絶滅してきています。人間にとって最も大事なのは、自分自身の命であり人生です。今日を生きる人間にとって「いずれ人類が絶滅する」ことは最重要事項には成り得ません。自分の命や生活に影響が出てはじめて、それは人間の関心事に成り得るでしょう。
ただ、高度な知能をもっているとされる人類が、その知能によって生み出した倫理観に基づいて絶滅する道を選ぶとは、なんとも皮肉なことです。
人は生物の生態や身体機能から多くを学び、高度な技術開発にも活用してきましたが、倫理観という曖昧な考えに縛られ、生物として重要な繁殖(生存と進化)については放棄しているとも考えられます。人間の社会では、虫の羽を応用して人工衛星を設計することは許されても、繁殖するために行われる生物の工夫は「見て見ぬふり」をしなければ、人道に反した差別主義者という烙印を押されかねないのです。これは先に述べた以下の考えによるものです。
(本記事「出生数の減少 – 持続困難な社会」より引用)
人間はその高度な知能によって、子孫を残すために生まれてきたのではないという価値観を作り上げました。自分の人生は自分のものであり、生物ではなく「ひとりの人間」なのだという考えです。
倫理観と宗教 – 人類の選ぶべき未来
倫理観の多くは宗教にすぎません。私たちが妄信する一夫一妻には、宗教上の理由で「牛を食べてはいけない」と同じくらいしか意味がないこととも言えます。しかしそれでも、一人の異性と生涯を添い遂げるという生き方には魅力を感じ、救われる人もいるでしょう。だからこそ長い歴史の中で世界的に受け入れられて広まったとも考えられます。
生物としての人間は、この先どのような道を選ぶのでしょうか。生物種としての本能を重視するのか、それとも理性と倫理観で絶滅するのか、はたまたその中間を模索して画期的なアイデアが生まれるのでしょうか。
現状の倫理観では到底受け入れられないと思われる「一夫多妻」や「多夫多妻」についても、生物の観点から改めて考えてみると、今私たちに必要なもののヒントが得られるような気もします。
今回の記事では、宗教(やそれに基づく倫理感)を引き合いに出してまとめていますが、私自身は何の宗教も信仰していない人間です。ただ、宗教の教えの中には、人生に役立つものもあると考えていて、それらを教養のひとつとして学びます。自分でも変な宗教観であることは自覚しており、以下の記事にもまとめていますので、興味のある方はそちらもご覧ください。