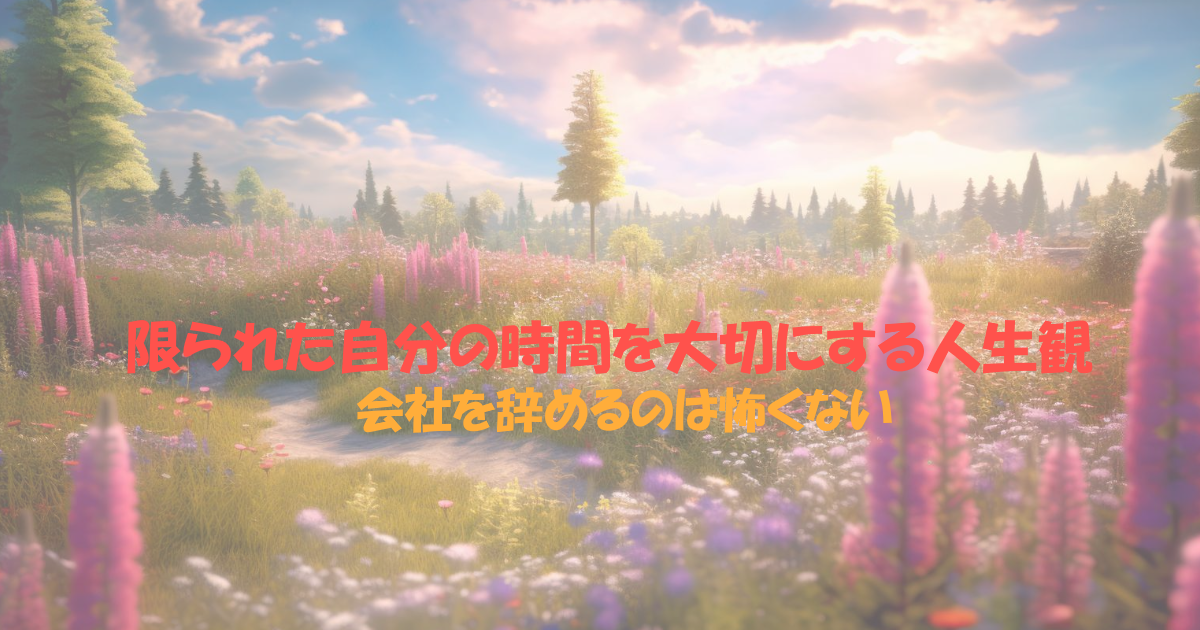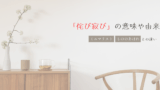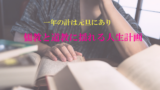多くの社会人は自身の経験や価値観から「会社を辞めるのは怖い」と感じるものです。働かなければ生きていけないというのが大前提にあるからです。今回は、「働くことが人生より優先」になっている日本人の人生観(固定観念)を広げる、ひとつの考え方を紹介します。
「仕事が人生」が常識な日本
2025年の4月には、社会に出て働き出した新社会人たちが、入社数日で会社を辞めていくということが大々的に報道され、退職代行会社の「モームリ」が業績好調という話題が広まりました。企業側の実体を隠した採用なども原因のひとつとされています。
新社会人を批判する声からは、社会人として「働くことは当たり前」で「みんな我慢しながら働いている」のだから甘えるなという、いかにも日本人らしい思想が見え隠れします。
会社で働くのが辛くて仕事を辞めたいと考えている人でも、辞めた後の事を考えると怖くてなかなか踏み出せないという人もいるでしょう。生活するためのお金をどうやって工面していくかを考えたり、世間体などを考えると、「定職についておかなければ」という強迫観念のようなものを感じることが多いです。
大型連休を取りやすい海外
「働くのが当たり前」という日本の常識は、実は世界的には特殊です。
日本では働くのが当たり前で、その先に自分の人生があります。しかし、世界的には(当たり前ですが)自分の人生があって、そのために働くという優先順位になっています。
この優先順位の違いによって、日本以外では「大型の休み」を取得したり、嫌なら「転職をする」のが日本以上に普通の事となっています。お金が充分にあるのであれば働かなくてもよい、というのが普通の考え方で、貯蓄が充分にあっても定年まで働き続けるのが「常識」なのが日本という事です。
会社を辞めて得られる穏やかな生活
一本とても素敵なvlogを紹介いたします。
以下の動画は、ご夫婦で会社を退職し、その後在宅で共働きしながら過ごされている40代の女性の、穏やかな朝食風景と共に心境などが綴られたYouTubeのショート動画です。
仕事を辞めるのが怖いと感じながらも一歩を踏み出してみると、その先には穏やかな新しい日々が待っていたという事例からは、自分にもできそうだという勇気がもらえます。大切なのは「健康と時間」と気付くことは、現代の日本社会では本当に難しいことです。
動画内では「常識にとらわれず」とありますが、この常識というものは定義があいまいな思想で、その多くは宗教から形作られていることが多いものです。立ち止まって「本当に正しいか」を考えることはとても大事な事でしょう。
会社を辞めても「人生は続く」
日本では、「人生イコール仕事」と言えるような常識が形成されています。生きている限り働いて「お金」を稼ぎ続けるように教育され、社会からの圧力もあるように感じます。
この背景には、日本国憲法にある「勤労の義務(27条)」も大きく影響していると考えられます。
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う
しかし、この勤労の義務には罰則の規定はなく、日本の司法も「努力目標」としていることは、あまり知られていません。
罰則を規定して、本当の意味で義務としてしまうと「重大な人権侵害」となり、また同憲法上で認められている職業選択の自由を侵害することにもなるためです。(つまり日本国憲法内で矛盾がある状態ともいえる)
この勤労の義務自体は、戦後復旧を目的として憲法に付け加えられた一文です。日本国民全員が頑張って、焼け野原となっていた日本を立て直す必要があったのです。
自由な人生を送る権利
日本では、自由な人生を送る権利が「日本国憲法」で認められています。一般的には「基本的人権の尊重」として知られています。働くことも、働かないことも、自分の人生は自由に決めて生きていく「権利」が認められているのです。
人生に自由は認められますが、人に迷惑をかけること等は当然その他法令に違反することになるため、生きていくための手段(お金)などを確保する必要はあるでしょう。
会社を辞めた後、自分の貯蓄で何年も生きていける人もいるでしょう。投資などの不労所得で死ぬまで働かずに生活が可能な人もいます。そういった人たちは「勤労の義務」を果たしていないことになりますが、当然法的にも何の問題もありません。
会社を辞めたことが無い人が感じる「恐怖」というのは、狭い視野による一種の「幻」のようなもので、会社を辞めても人生は続いていくもので、それは意外と平穏なものなのです。
「常識」という名の「固定観念」
勤労の義務ができる以前から、日本では「国のために頑張る」という独特の精神が形作られていて、今も日本人の根底に生き続けています。国のためでなくとも、会社のためだったり、組織やチームのために頑張るという考え方は、現代でも多くの日本人が持っている考え方でしょう。
日本のこういった考え方は「常識」ですが「固定観念」とも言え、その考えが「宗教」であることは、あまり知られていません。
儒教に染まっている「日本の常識」
日本の「頑張る」考え方は、「儒教」という中国由来の宗教によるものです。
日本では、江戸時代頃に幕府による統治を絶対的な物とするために、国民への「儒教教育」に力を入れてきました。儒教は学問として体系化され、儒学・朱子学と呼ばれました。儒教教育によって、「働いて出世する」ことが良いこととされ、そのために「努力して自分を高める」ことが常識とされました。
幕末期に広まった国学(国家神道)と融合する形で、明治期には「教育勅語」という国民への教育や道徳の基本方針が示されることになりました。この教育勅語は「国のために命を懸ける」という究極の儒教精神が盛り込まれており、これが先の大戦における悲惨さを助長したとも考えられています。
頑張って頑張って「後悔」する人生
頑張って努力して昇進して結果を出すという、日本の儒教的な人生がどのようなものかを、分かりやすく40秒でまとめられたYouTube動画を一本紹介します。
日本では、「定年退職した後」に、自分の「人生の時間」の使い方を後悔する人が少なくありません。もっと○○しておけばよかったと思っても、人生の時間は取り返すことができないのです。
儒教以外の「常識」を知る
日本では儒教的な生き方を正しいものと教育し、そのおかげで大きな発展をしてきたことは確かです。しかし、人生というのは「国のため」にあるわけではなく、個人のためにあるべきであり、優先順位を間違えないようにしなければなりません。
必要な分だけ働けばいいといった考え方は「道教」という中国の宗教に見られます。儒教と道教は、仏教と並んで「中国の三大宗教」と呼ばれます。
道教という宗教は、日本人としては馴染みがあまりないように感じるかもしれませんが、日本では14世紀ころに広まった考え方でもあり、道教を基にして作られた「侘び寂び」の精神は、知っている人も多いのではないでしょうか。
「侘び寂び」と「もののあはれ」
質素さを追求する「侘び」と、質素な中に幸福や美しさを見出す工夫をする「寂び」を合わせる考え方は、芸術分野では色の少ない水墨画や殺風景な日本庭園など、独特な美しい世界観を形作りました。この芸術と同じように、日々の生活においても、最低限の質素な生活の中に楽しさや幸せを見出そうとする「生き方」を考えてみるのです。
侘び寂びと似た考え方に、「もののあはれ」という美的理念があります。日本人でも知らない人が多い昨今で、外国人で知っている人がいると、日本人としては驚き、そして同時に自国の事を知らないことに恥ずかしさを感じることがあります。以下の記事では、「侘び寂び」や「もののあはれ」についてもう少し詳しく紹介していますので、興味のある方は是非ご覧下さい。
「マウントを取る」という儒教的な幸福観
日本は科学技術が発達し、裕福な食べ物などに恵まれていますが、実は幸福度は高くありません。一方で貧困な生活をしている発展途上国などは、生活は苦しいはずなのに逆に幸福度が高いということも珍しくありません。
儒教では、努力して人よりも優れ、人よりも出世し、人よりもお金持ちになることが良い事とする価値観が育ちやすく、現代でいう「マウントを取る」という発想は、完全に儒教思想によるものといえます。この価値観の上で感じられる幸福は、人と比較しての相対的な幸福であるといえるでしょう。

一方道教では、他人の事は関係なく、自分の穏やかで質素な生活の中に、自分が楽しいと思える価値観を見出していきます。道教の幸福は絶対的な幸福といえ、儒教と違って他人のいない世界であっても幸せを感じられるものです。
他人との「比較で得る幸福」は「不幸」と隣り合わせ
お金を稼いで、いい家に住んでおいしい料理を食べてお洒落な服装に身を包むというのは、日本人の感覚としては「幸福」なことと感じる事でしょう。この裏には、「他人よりも恵まれている」という相対性が隠れていることに注意が必要です。
その豊かさを誰にも伝えられない世界だった場合に、あなたはそれでも幸せを感じることが出来るでしょうか。もし幸福を感じられないのであれば、「本当はあなたには必要ないものだった」といえるでしょう。
また、あなたが最上位でなければ、あなたを見下して優越を感じている人が必ずいます。その時あなたは「劣等」や「不幸」を感じないでしょうか。
儒教の相対的な幸福は、同時にあなたに劣等感や不幸をもたらすものでもあります。
人はその劣等を克服するために「更なる努力」をするようになるため、国や組織の運営には「都合がよい仕組み」とされたのです。本来自分の人生の幸福には、他人の事は関係ないはずです。
見下し・見下される価値観に疲れてしまっても、絶望を感じる事はありません。それは「ただの宗教」にしか過ぎないのです。日本や韓国など一部の地域だけで「常識」とされているだけで、世界の真理でも何でもないのです。
一度きりの人生を自由に生きよう
人は働くために生まれてきているわけではありません。他人と比べることを止めて、改めて自分の本当に「好きな事」や「やりたい事」は何なのかを考えてみるといいでしょう。
好きな映画やゲームを延々楽しみたいとか、目覚まし時計から解放されて「ただ自由に眠りたい」のようなものでも構わないと思います。今回紹介した動画の様に、組織の売り上げとか人事といった面倒ごとから解放されて、ゆったりとした朝食を夫婦で楽しむというのも、ひとつの幸せの形でしょう。
「お金は要らない = 人生の負け組」という主張
日本では、「お金は要らない」というと「稼げない人の負け惜しみ」とか「人生の負け組」といった評価をされることがあります。
儒教の呪縛から解放された後は、そういった言葉は気にならなくなるでしょう。逆に「可哀そう」とすら感じるかもしれません。
あなたを劣位に置くことで一時的な幸福を得ようとしているだけで、実際には劣等感に縛られていて、努力し続けることでしかアイデンティティーを保てない状態なのです。
他人と比較することでしか幸福を得られない儒教思想の中では、永遠に他人に見下される不幸が付きまといます。
人生は一度きり – 後悔のない「生き方」を
人生は一度きりです。他人に何と言われようと、自分が幸せだと感じる「生き方」を選び、後悔のないようにしたいものです。
自分の幸せを最優先にしようと思っても、そのために頑張ろうと考えると儒教的な思想にとらわれてしまうものです。取り返しのつかない時間と、生きるための健康こそ、何物にも代え難い大切なものではないでしょうか。