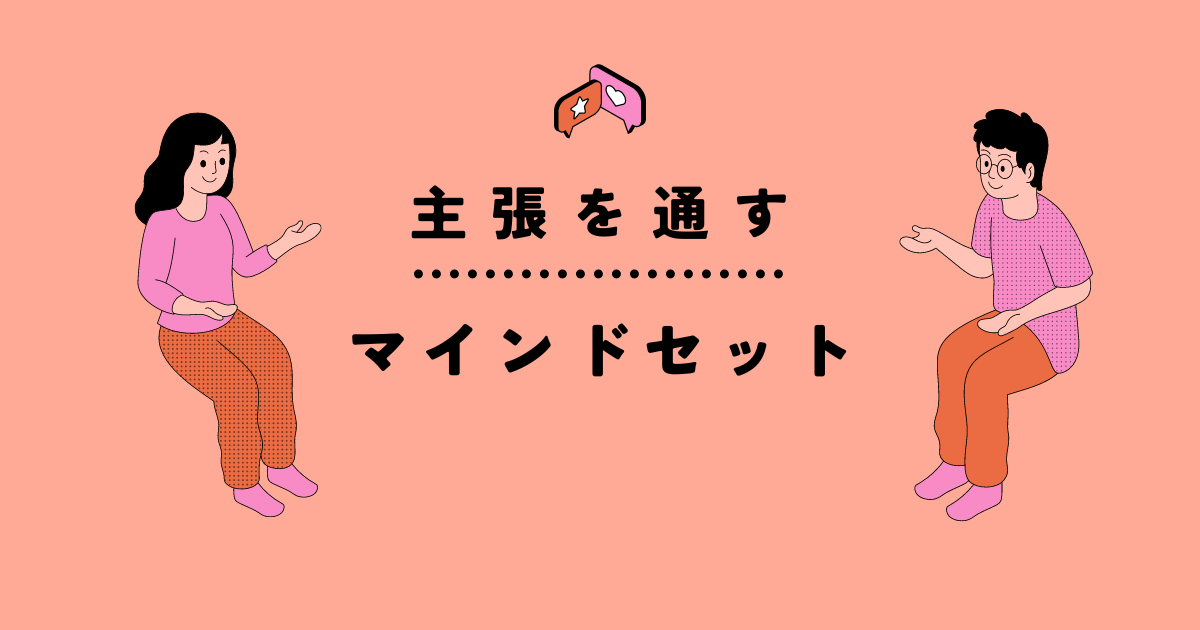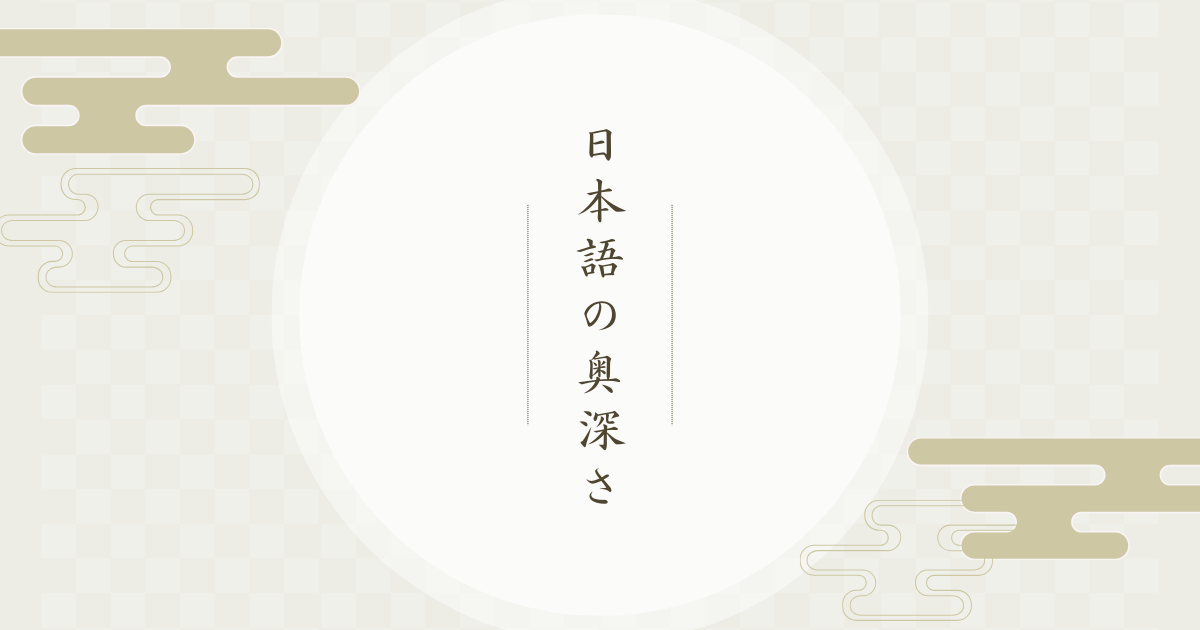新社会人や転職して新しい職場に入った後など、配属先の上司や教育係の人に、自分の行動や考え方を注意されることがあるでしょう。特に最近は、古臭い考え方を改めて、現代風の合理性を追求したやり方を取り入れるべきいう風潮もあり、若い人でも積極的に会社のルールや慣習に立ち向かう事例をよく耳にします。
何かを変えようとしたり、自分の考えを主張すると、必ずその否定や反対の声があがるため、「納得できない」と感じることもあるでしょう。今回は、自分の主張が通らず困っている人たちに向けて、少しだけ考え方や心持ち(マインドセット)のアドバイスを示してみます。うまくいかないことが少しずつ前に進むようになるかもしれないので、是非参考にしてみてください。
「主張」を押し付けるのではなく「相談」しよう
会社のおかしいと思う点や、改善すべき点に気づいたとき、そのことを発信することはとても大事な事です。ほとんどの人はそういった改善については考えもせず、日々を過ごしています。そのことについて気づいたあなたは、誰よりも真剣に会社の事を考えているのです。自信を持って発信していきましょう。

発信の仕方は様々ですが、まずは身近な先輩や信頼できる上司に「相談する」という形が無難です。そういった人がいない場合は、直接上司や自分の監督責任を持っている相手に時間を割いてもらって「直談判」するしかありません。
自分より目上の人に意見するというのは勇気が必要な事です。自信をもって挑みながらも、決して感情的にならず、自分の主張を述べましょう。
「自分の考えの方が正しい」は危険信号
重要なのは「自分はどう考えているのか」を伝えることです。「間違っているので直すべきだ」といった主張をするのは非常に危険です。
会社のおかしな点に気づいてその改善を迫る状況では、「自分の考え方が正しい」「会社が間違っている」と考えて行動に出てしまいたくなるものです。人間というのは、そういった状況になると、感情が先に立って周りが見えていないことに陥りやすいものです。
主張を伝える際には、冷静に「おかしいと気づいた点」と「自分の考える改善点」を述べましょう。
自分の主張がいつも受け入れられてくれれば何の問題もないのですが、時には上司に否定されたり注意されるということもあるでしょう。そういう時は「むかつく」とか「ダメ上司」といった負の感情が湧き起こり、売り言葉に買い言葉で感情的に反論してしまうと、信頼関係が修復不能なほどに破壊されてしまうことになりかねないので、冷静に議論する事を忘れないようにしましょう。
納得できない時の考え方と行動
ここから紹介する内容は、部下や後輩が会社や他の先輩に対しての「文句や愚痴を言っている」のを耳にした際に、意見を汲み取りながら、同時に教育として伝えていた内容でもあります。そういったむかつく上司に出会った時に、どのように対処すると良いかといったマインドセットの一例として紹介しますので、是非参考にしてみてください。
自分が何かを主張して、上司や先輩などに否定的な立場を取られると、むかついたり、腹が立ったりして納得できないといったことがあるでしょう。反論して口論になった後、時間が経っても気持ちに整理がつかないと、同僚や近い先輩に「愚痴をこぼす」といった行動に出てしまいたくもなります。
納得できないのは「自分が未熟だから」と考える
自分の考えを主張する際には、「自分の考え方が正しい」「会社または上司が間違っている」という発想になりがちです。難しい事ではありますが、まずは考え方を改めてみましょう。
上司や会社が反対しているということは、理由があるのです。
忘れてはならないのは、上司や会社はあなたよりも経験が豊富で思慮深いという事です。多くの場合、あなたが正しいと思っているその主張は、視野が狭く未熟なものだから、上司はそのことを指摘して反対しているのです。
よく学会の論文発表などで、発表者の問題点を指摘する際に「素人考えで恐縮ですが」という接頭語が使われています。これはとても謙虚さと皮肉さに溢れた便利なフレーズです。
自分が何かを主張する際には、「自分の考えが及んでいないかもしれない」ということを念頭に、「自分はこう考えるけどどうでしょう」といった謙虚なスタンスであることは重要です。この考え方は、相手との対話を円滑に進めるために役立つでしょう。
反論を受け止めた上で「改めて考えを巡らせよう」
謙虚に相手に話していたとしても、反論されると腹が立つものです。「だから何故分からないんだ」と声を荒げたくなることもあるでしょう。
しかし、そういった時は気持ちを落ち着かせ、ぐっとこらえて「分かりました」と一旦その場は引きましょう。もちろんですが、自分の主張をすべて伝えた上で、相手の注意や反論をすべて聞いてからのことです。
反論されて腹が立った状態で言い返すのではなく、一度持ち帰り落ち着いて考えを巡らせることが大事です。合理的に考えて改善点に気付き、冷静に上司に相談するという行動ができたのであれば、落ち着いて考えれば見えてくるものがあるはずです。
多くの場合、自分の主張は自分の見える景色の中で立案されたもので、上司はさらに広い景色の中でその主張を評価する立場にあります。
現場の改善を主張しても、企業全体のコストや人員の問題などで通らないということはよくある事です。これは自分が未熟だという典型で、その主張を通したいのであれば、上司の懸念する事項への対策も含めて立案しておかなければならないのです。それらを述べず、ただ狭い視野での主張をする行為は、子供が親に駄々をこねているのと同じであることだと気づきましょう。
一度受け入れて持ち帰り、反論された内容も踏まえたよりよい改善案をもって再挑戦するのもよいですし、新しい疑問が湧き出て納得できないということもあるでしょう。
納得できるまで「繰り返し挑戦して」自分を高めよう
なぜ上司がそのような反論や指摘をしてきたのか、持ち帰って考えても理解ができない場合は、その理由について、再度その上司に確認するしかありません。冷静になって相談すれば、上司も真摯に向き合ってくれて事情を話してくれるはずです。
もうこの段階にきていれば、上司の話している内容に耳を傾けられるでしょう。「自分に何が不足していたのか」、この主張をする場合には「何を考慮する必要があったのか」、しっかりと受け止めましょう。
上司の反論や指摘は、自分を育てる最高の教科書です。
自分の主張にダメ出しされると腹が立つものですが、自分の視野では気付くことが出来ない事を知るという最高の経験を積むことができています。感情的になっていると、上司が自分を高めてくれている状況に気付かないものですが、謙虚に相手の話を聞く態勢であれば、「そういう視点が必要だった」と受け入れられるはずです。
納得いくまで何度も繰り返し挑戦すれば、その度に視野が広がっていくことになります。この行動によって、あなたにはその上司と同じ「高い水準の視野や考え方が身に付く」ことになるでしょう。
説明ができない場合は更にその上司に相談する
残念ながら「ダメなものはダメ」といったように説明ができない上司や、説明の内容が意味不明・支離滅裂といった場合もあるでしょう。それでは疑問が解決しないし納得もできない、何より自分が成長できないままです。
こういった事態に遭遇してしまった場合は、さらにその上司に掛け合うしかありません。ここでも大事なのは「自分が未熟で理解できない」という謙虚なスタンスです。「上司が理不尽なことをいっている」という苦情では、残念ながらあなたも上司と同じレベルに成り下がってしまいます。

自分の考え、直属上司からの指摘・説明を添えて、どうしても理解・納得ができない旨を相談してみましょう。相手の時間を奪っていることについて、感謝やお詫びの気持ちを忘れないことも重要です。あなたと上司やその上司では、企業の中で時間当たりの価値が異なるのです。
真剣に相談すれば、きっとあなたの納得する答えが得られるでしょう。結果として自分の未熟さや不甲斐なさを痛感することになることもあれば、上司の指摘によって自分の主張の問題が発覚するといったこともあるでしょう。(最初と同じで、注意・指摘されたら一度飲み込みしっかり考える、を忘れずに)
自分の主張が正しかったとしても勝ち誇るのではなく、感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。
今回の一件ではあなたの主張が正しかったとしても、上司がそのポジションにいるということは、その会社はあなたよりも上司の能力を認めているのです。お詫びを伝えて今後のさらなる指導をお願いするくらいまでできれば、あなたが上司に並ぶのもそう遠くないはずです。
経験を積んで「上司よりも上」を目指していこう
あなたの周りにある物事は、あなたを育ててくれる大切なものです。上司はあなたにとっては「目の上のたんこぶ」な時もあるかもしれませんが、あなたの分まで責任を負う大切な役目を持っています。また、上司が最も身近な教材であることも確かです。
人間なので、良いところもあれば悪いところもあるものです。上司の全てを受け入れる必要もありません。上司の言動に対して不快感を覚えることがあったとしても、「学べるところを学ぶ」と割り切って、自分の糧にしていきましょう。あなたにとっては、上司の人間性を正すことよりも、自分の成長の方が大事なのではないでしょうか。
この世界の中では、あなたが100%全ての人格を尊敬できるような人とはほとんど出会うことができないでしょう。悪いところは真似をせず、良い点を認めて吸収していけば、謙虚に人を尊敬することができ、あなたも成長していけるはずです。
今回は前向きに頑張る話ばかりを紹介してきましたが、この考え方は「儒教的」であることを理解しておきたいところです。人は、働くために生まれてきたわけでもなければ、成長するために生まれてきているわけでもありません。頑張るのに疲れた人や、儒教から脱却したい人は、是非以下の記事も参考にしてみてください。