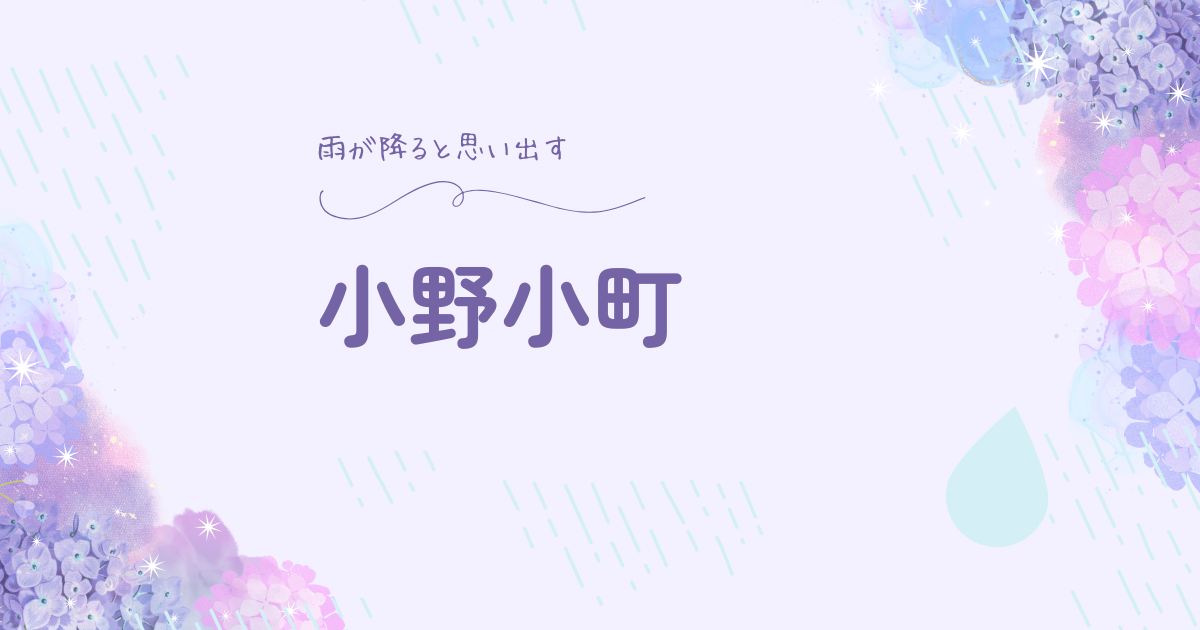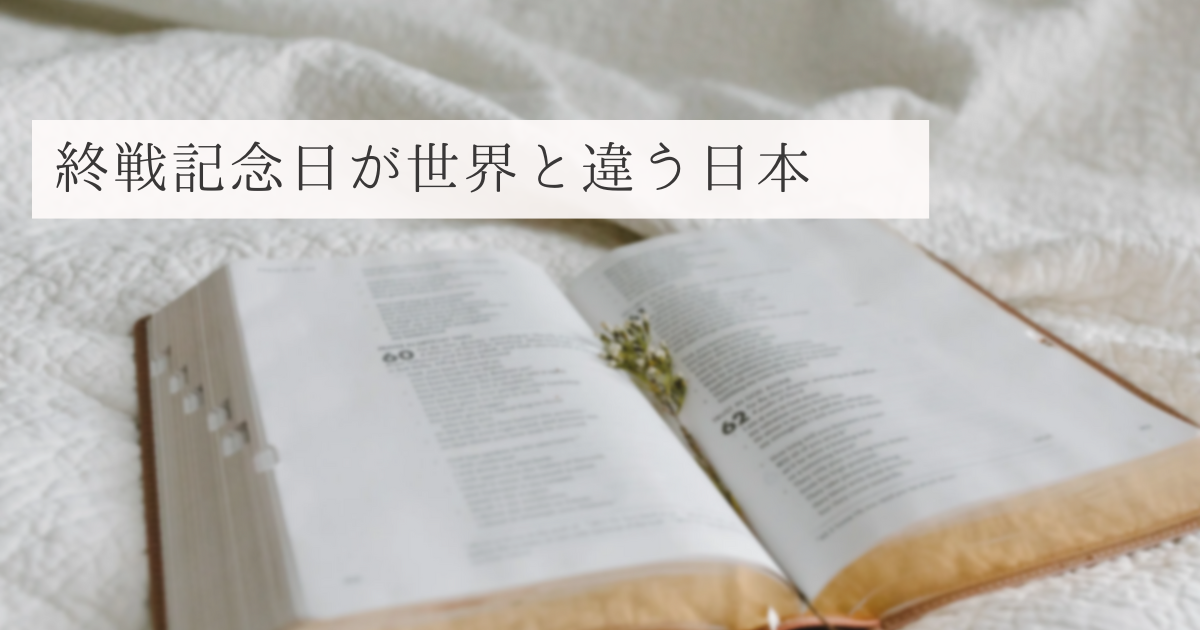雨が降ると憂鬱な気分になる人もいるかもしれませんが、家からあまり出ないからということもありますが、私は雨が嫌いではありません。
雨が降る様子を部屋の中から眺めていたり、雨の降る音を静かな部屋で聞いていると、ゆったりと時の流れや自然の豊かさを感じられるような気がするのです。そんな時間を楽しんでいると、ふと「小野小町」のことを思い出す時があります。小倉百人一首にも選ばれた彼女の有名な短歌は、「雨が降る様」と自分に降りかかる残酷な「時間の流れ」が技巧的に表現されていて、とても印象的です。今回は、そんな雨から小野小町、そして小野小町の歌から連想される「人の世」の真理について綴ってみます。
小野小町は世界三大美女の一人
小野小町という人は、平安時代を生きた歌人として有名です。現代ではお米の銘柄で「あきたこまち」が有名ですが、この名前は秋田県の出身とされている小野小町にちなんで命名されているそうです。
日本の義務教育課程で習う平安時代の女性と言えば、源氏物語の紫式部や枕草子の清少納言などがありますが、小野小町は彼女たちよりもほんの少し前に生きた人で、言うなれば「先輩」といった位置づけの人です。時代の順番的には小野小町から清少納言、そして紫式部となります。三人とも有名な歌人でもあり、詠んだ短歌がそれぞれ百人一首に選出されています。
その中でも特に小野小町は現代にまで伝わる程に、美しい女性であったとされています。日本では楊貴妃・クレオパトラと小野小町を合わせて世界三大美女とする場合があります。若くて美しい上に文学に通じて聡明な女性であれば、多くの男性から言い寄られていても不思議ではないでしょう。そんな充実した生活を過ごしていた女性が詠んだ歌が、とても切なくて物悲しいというのが、印象的で興味深いと感じる点ではないでしょうか。
有名な短歌 「花の色は」
小野小町と言えば、百人一首にも選出されているとても有名で代表的な短歌があります。
花の色は うつりにけりな いたづらに
わが身世にふる ながめせしまに
意味を現代の言葉で表現すると、以下のようになります。
雨が降るのを眺めながら色々考えているうちに、美しかった花の色は褪せてしまい、私の美貌もまた衰えてしまった。
私は短歌にそれほど詳しいわけではありませんが、短歌の技術的な部分では、「世にふる」と「ながめせしまに」という部分がそれぞれ2つの意味を持っていて、降り続く雨と年老いる自分、情景を眺めることと物思いにふけるという行動が含まれていて、倒置法になっている点も評価が高いそうです。個人的には、限られた音の中で2つの情景や想いが上手く表現されていることからか、とても奥深いものを感じる歌だと思います。
私はこの歌から色々な事を考えさせられます。
最も印象的なのは、自分自身を花のように美しいと表現した上で、その美しさが失われていく「時の流れの残酷さ」を嘆いているという切なさにあります。
1000年経っても変わらない人間の行動と心情
私個人としては、1000年以上前の人が、現代と同じように「雨を眺めている」という情景にも惹かれるものが有ります。
歴史上の人物は、時として絵空事や物語の登場人物のように勘違いしてしまいそうになりますが、実際に実在した人物であり、私たちと同じ人間です。この歌のように、同じように生きて、同じように悩んでいた「私たちと同じ人間」であることを感じると、実在した人物であることを強く思い出させてくれるように思います。
現代はインターネットやスマートフォンなど近代文明に溢れてとても便利になっていますが、時間の流れだけは昔から変わりません。
男性から注目されていた一人の女性が、歳を重ねることで徐々に自身の美貌の衰えを感じるというのは、現代でも感じる事がある心情でしょう。文明が発達して社会は複雑化していても、人の悩みの中には1000年以上も変化せず、解決もしないものがあるのです。
変化を恐れる女性「高内侍」 – 忘れじの
百人一首の短歌の中には、小野小町のように人の美しさの変化だけでなく、人の心の変化を危惧するような歌もあります。私の大好きな短歌(54番)を紹介します。
忘れじの 行く末までは 難(かた)ければ
今日を限りの 命ともがな
この歌のざっくりとした意味は以下のような感じです。
ずっと忘れないっていうけど、将来どうなるか分からないから、今日限りで命が終わればいいのに
この歌からは、「今が最高に幸せ」という気持ちと「幸せを失う恐れ」が感じられます。この短歌を詠んだ人は、百人一首上では「儀同三司母(ぎどうさんしのはは)」とされていますが、高内侍(こうのないし)としても有名で、藤原道隆の妻です。そして何より中宮(天皇の妻 / 現代の皇后)定子の母でもあります。道隆との間の三人の息子が全員出世して政治の中枢についたことから、百人一首の歌では別名が使われています。
全てを奪う高内侍の義弟 – 藤原道長
高内侍の夫である藤原道隆という人は学校教育ではあまり習いませんが、「藤原道長」は藤原氏全盛期の人物として習います。道隆は道長の兄で、高内侍からすると義理の弟にあたります。藤原道長は、彼の兄(道隆)世代までに築かれた藤原氏盤石の態勢を引き継いだに過ぎず、道隆や高内侍の世代までの活動で、藤原氏は日本の頂点にまで上り詰めています。
そんな頂点に上り詰めた彼女(高内侍)から紡がれた歌が「将来への不安」というのが、とても興味深いと思うのです。実際、道隆が亡くなった後に、道長に全てを奪われていくことになるのが、この歌を更に絶望的に感じさせます。幸せに満たされていてもどこか将来への不安を感じてしまうことは現代に生きる私達も共感できますが、「幸せすぎて死にたい」程の幸福と不安というのは、想像するのも恐ろしいと感じます。
そういう意味でも、全てを奪って頂点に達した藤原道長の以下の歌は、とても増長して唯我独尊的な印象をうけます。
この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも 無しと思へば
この歌の意味はそのままでも分かりそうですが、念のためざっくり記載しておきます。
欠けていない満月のように、この世は全て自分のもののようだ、ガハハハハ
旦那さんから「一生大事にするよ」と言われ、幸せをかみしめながらも将来を不安に感じる女性と、その夫婦からすべてを奪って頂点に達した弟が詠む増長した歌の対比は、なかなかにパンチ力が高いです。
変わらないものはないという真理 – 平家物語
時代的にはもう少し後ではありますが、平家の盛衰を綴った平家物語では「この世に変わらないものはない」と伝えられています。祇園精舎の鐘の音には、この世のあらゆることは変化していくのだという響きがあると、冒頭に書かれています。
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり
この冒頭文に続いて、盛者必衰(じょうしゃひっすい)「栄華誇った平家の治世が滅んだように、栄えているものは必ず衰える定めにある」が世の理だとしています。
小野小町は変化を憂い、高内侍は変化を恐れていましたが、世の中に存在するものは「必ず変化する」ものです。その変化の常があるからこそ幸せに輝きを感じ、また衰えていくものに美しさを感じるのかもしれません。
以下の記事は、日本人も失いつつある「もののあはれ」を知っている外国人に驚いたという内容です。記事内で、「もののあはれ」と共に「侘び寂び」などについても紹介していますので、興味のある方は是非ご覧ください。
現代の人にも通じる「戒め」
現代においても、今から上を目指そうと頑張っている人や、ようやく頂点に上り詰めたと勝利を噛みしめている人など、色々な人がいるでしょう。しかし、1000年以上も前から「変わらないものはない」と伝えられているように、物事は必ず変化しますし、盛者必衰は世の理です。
トップが強すぎて諦めかけている人は、トップはいつか絶対に崩れる日が来ると信じましょう。また、トップの座に君臨している人は気を付けなければなりません。平家物語では「驕れる者は久しからず」とあります。これは、頂点で胡坐をかいていたら、あっという間に終わりがやってくるという戒めでもあります。
変わらないものが有るとしたら、それは何か不自然で異常な状態にあるのでしょう。人の考え方や、社会の常識も含め、何事も変化するものであることを理解し、心構えをし、受け入れていくことも大事なのだと思います。
平安時代を題材にした現代の作品
折角なので、小野小町や今回紹介したことに関連した現代の作品をいくつか紹介してみようと思います。私は歴史全般が大好きで、インターネットや書籍、映画やアニメ、ドキュメンタリーなど、情報源には「こだわり」がなく、知識を得ることに節操がありません。
元々平安時代の興味の中心は枕草子(現代語訳)の書籍ではありますが、その後平安時代を題材にしたアニメなども視聴したところ、とても分かりやすくて、より一層の興味を得られたので、それらを紹介してみます。
ちはやふる
「ちはやふる」は、競技かるたを題材にしたとても有名なアニメです。ストーリーの中心は競技かるたなのでスポ根的な内容ですが、高校生の恋愛や短歌の奥深さにも触れられていて、楽しみながら平安時代の短歌を詠んだ人の心情を理解してくことができます。
特に、現代の人と平安時代の人との間の「共通する想い」をうまく表現していると感じる場面がいくつもあり、遠い世界に感じる短歌の世界を、自分の日々の生活と照らし合わせて身近に感じることができる点が、とても魅力的に感じました。
視聴したのは何年も前ですが、今でも印象に残っている場面がいくつもあります。その中でも特に大好きな歌が引き合いに出されたシーンは、台詞まで思い出せそうなくらい鮮明に覚えています。
かくとだに えやは伊吹の さしも草
さしも知らじな 燃ゆる思ひを
この歌では、「私の片思いの強い気持ちに、あなたは気づかないでしょう」という女性側の恋心が歌われていて、人を好きになるような心情が描かれた作品を視聴する度に思い出してしまいます。「ちはやふる」では、先輩に片思いする新入部員の女性の気持ちを表現する際に用いられていて、視聴後は特にこの歌を身近に感じるようになりました。
超訳百人一首 うた恋い。
「超訳百人一首 うた恋い。」は百人一首のそれぞれの歌が詠まれた時代や状況をアニメで再現したような作品ですが、作中の登場人物などが現代風で親しみやすく、「超訳」とあるように、かなり分かりやすい表現になっているので、短歌を詠んだ人の気持ちなどを理解するのに役立ちます。
先に紹介した平安時代の歌人である、小野小町、清少納言、紫式部などの人物や百人一首の歌についても登場するほか、「ちはやふる」の題名にもなっている在原業平の歌(17番)も第一話で取り上げられています。
百人一首をスポーツとして楽しむ場合には、記号的に暗記してしまうことが往々にしてありますが、この作品では各短歌の詠まれている状況などを再現してドラマ化しているため、歌を記号ではなく情景で覚えることができるでしょう。
何となく流して覚えていた恋愛の歌も、その詠まれた状況を知ると、詠んだ人の切なく苦しい思いなどを感じることができて、一層趣深く感じると思うのです。
平家物語 (2021)
「平家物語」は2021年に公開されたアニメ作品で、存在を知った時は、比較的新しい作品である事にまず驚きました。この現代に「平家物語」を題材として作品を生み出し、それをアニメ化しようとするのは、私のような一般人にはなかなか思いつかない発想だからです。
視聴するまでは、「平家物語」というと「祇園精舎の~」という冒頭文が辛うじて出てくるくらいの知識しかありませんでしたが、当時の人々の生活や情景が描かれているのを観ていくうちに、知らず知らずのうちに自分の中で、「平家物語は遠いもので、試験のための記号」のように分類していたことに気づかされました。
盛者必衰。驕れる者は久しからず。
という言葉にあるように、平家物語は軍記物であるにも関わらず、人の生き方に対する戒めのようなニュアンスが含まれています。作中では栄華を誇った平家の振舞いとその衰退が、主人公の幼い少女の琵琶法師を中心に描かれていくことになります。
三種の神器と二人の天皇陛下
平家物語のアニメには、京を追われた平家が持ち出した天皇が保管する「三種の神器」と、擁立された三種の神器を持たない京の新天皇の描写があり、個人的にはとても興味を惹かれました。
私は昭和から平成令和と生きてきているので、天皇陛下が同じ時期に二人いる時代というのが想像できません。鎌倉時代の後に南北朝時代と言われる天皇陛下が二人いる時期があり、その時代の人々の気持ちというか印象にはとても興味があったため、短い期間ではありますが平安時代末期に同じようなことが起きていたことにはとても驚き興味惹かれました。そして南北朝時代と同じように「三種の神器」がこの問題を解決し、天皇の正当性を示していることから、日本の歴史や国体について改めて考えさせられました。
日本はこの平安時代の終わりと共に、武士の「力こそ正義」の時代へと突入します。本居宣長が思い描いた理想の日本と「もののあはれ」の美的理念は、この時代を境目に失われていったと言えるのではないでしょうか。
1000年の 時を感じて ほっとする
平安時代は今よりも1000年以上も前の歴史ですが、そこに生きている人は今以上にスケールの大きな事象の変化について深く考えていたようにも思います。他に考えることややらなければならないことが少なかったということもあるかもしれませんが、人や自然の美しさや心情の変化を憂うといった感情を、短歌や文学の作品に綴るというのは、現代から考えるととても高尚な文化のように感じてしまいます。
雨が降っている様子を眺めているだけで、小野小町を思い出し、そして1000年以上続く人の営みに思いを馳せるような変人は私だけかもしれません。それでも、日々多くの物事が変化していく激動の現代の中で、こうして改めて「1000年経っても変わらない人の心情」を考えると、不思議と安心する様な、落ち着いた気持ちになれる気がするのです。