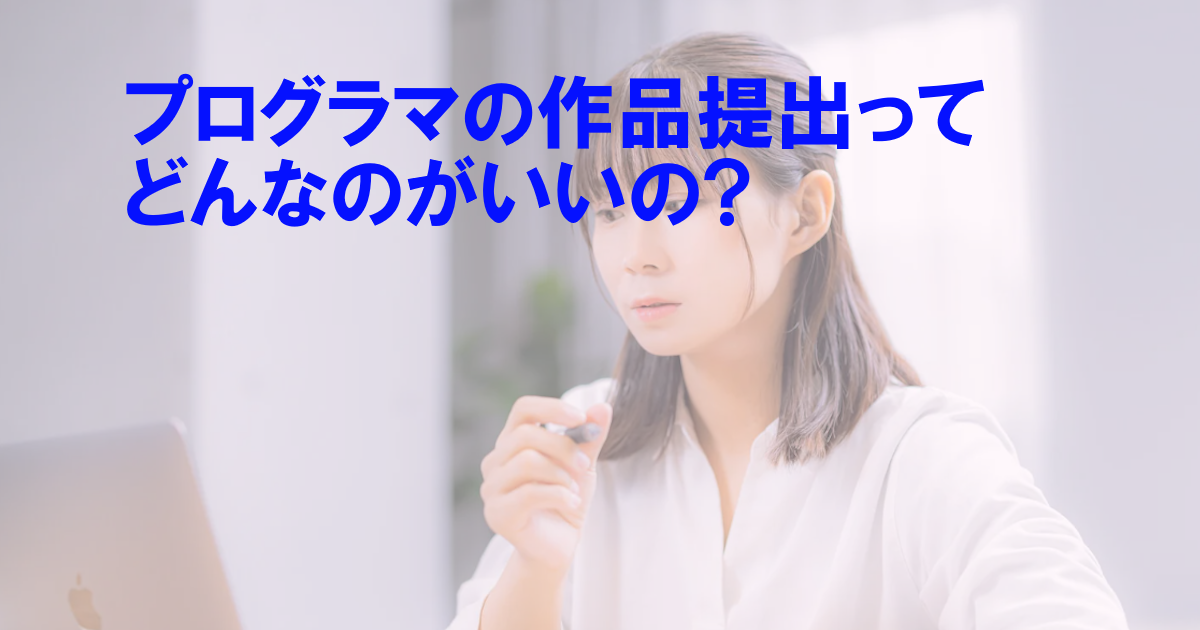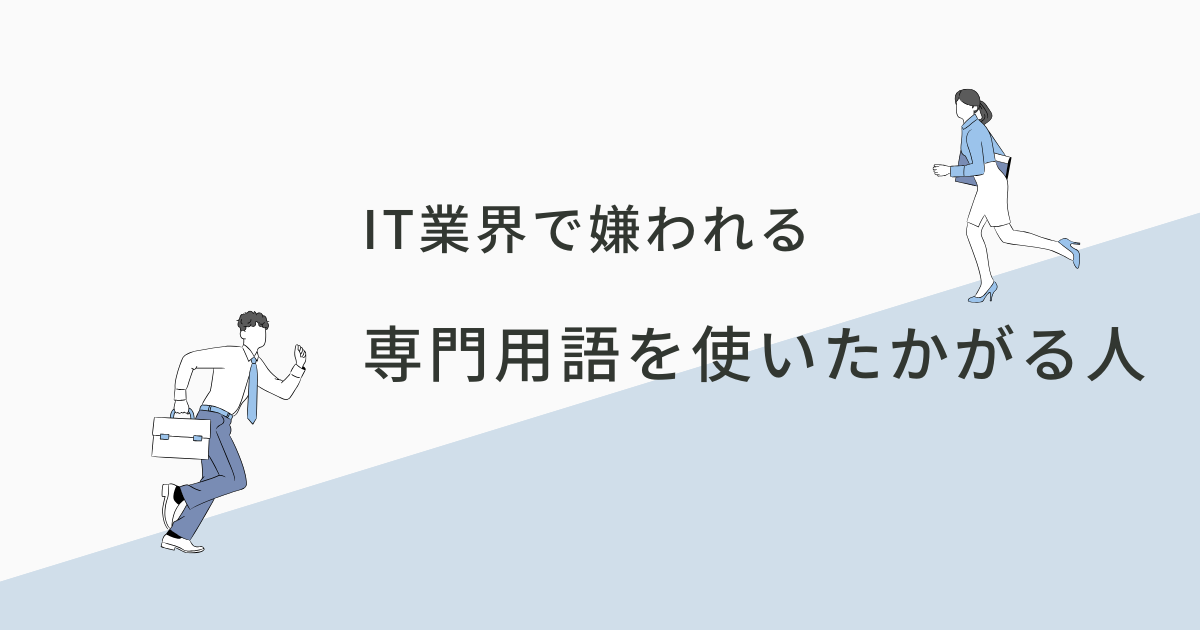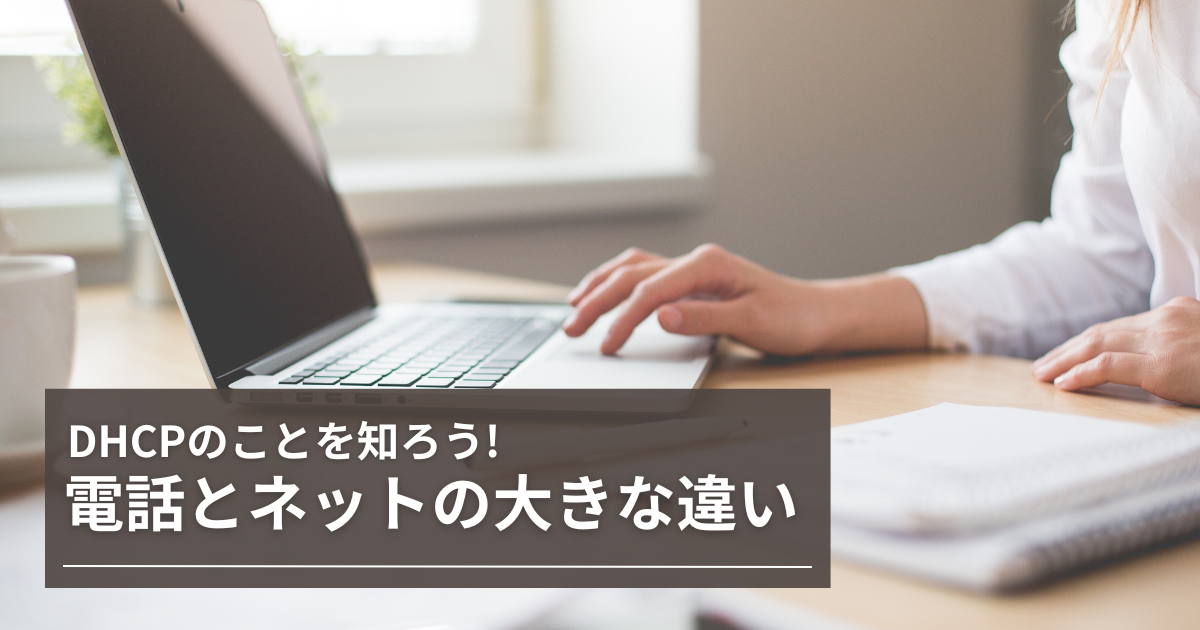IT企業の採用試験の応募では、「作品」の提出が求められる場合があります。プログラマー募集における作品は、応募してきた人の技術的な力量を推し量ることを目的として、企業側が提出を求めている場合がほとんどです。新卒採用の場合には、提出にあたっての所作・形式などによって社会人適性を判断されることも多く、中途の場合には即戦力となる人材かどうかを見極めるためにも利用されます。
今回は、IT企業のプログラマ採用で求められる「作品提出」にはどのようなものを提出すればよいのか等について、IT企業での採用担当の経験を基に、簡単なアドバイスと共に紹介しています。当然採用する側である企業によって、扱いや見解は異なりますので、ひとつの事例として参考にしつつ、自身の就職活動に役立ててください。
作品提出は面接外での貴重な「自己アピール」
採用試験での作品提出が必須ではなく任意となっている企業もありますが、作品提出は任意であっても可能な限り何かを提出するようにしましょう。
通常、採用試験の中で個人の自己アピールができるのは面接だけである場合がほとんどですが、作品提出は面接以外の時間で、事前に準備して自己アピールすることができる絶好のチャンスでもあり、採用試験の中では特に貴重な機会ともいえます。他の応募者よりも自分が優れていることを企業にアピールすることができれば、合格の可能性を高めることができますので、しっかりと有効活用しましょう。

貴重な自己アピールチャンスをできるだけ効果的に活かすためにも、提出する作品には気を使いたいところです。他の企業の採用試験に忙しかったり、学校の授業などの日々の活動の関係などで、時間を割くことが難しいこともあるでしょう。企業側も、改めて作品提出のために何かを制作して欲しいと考えているのではなく、これまでに制作した作品を見せて欲しいと望んでいるに過ぎません。基本的には、無理のない範囲で、自分が過去に制作したプログラムを提出する方向で考えましょう。
提出する作品の種類によって、企業側に与える印象は異なってきます。いくつか代表的な作品のパターンに分けて、それぞれ紹介していきます。
学校の課題を提出する場合は「面接対策」もしよう
新卒採用の場合の提出作品で多いのが、「学校の授業で製作」したプログラムです。同じ学校の学生が複数受験している場合、提出作品の内容が重複する可能性があります。
採用する企業側としては、学生が学校の授業で製作したプログラムを提出してきた場合、多くの場合その人に対する技術面での興味や関心を損ないます。
学校の先生が指示する通りに制作したプログラムには、何のこだわりも意志も、技術的な努力も込められておらず、「見る価値がほとんどない」ためです。作品提出が求められているので、その条件をクリアするためだけに提出した作品として、もしかしたら作品自体を見てもらえない可能性もあり得ます。
作品提出で自己アピールをするという観点から言うと、学校の授業で製作したプログラムを提出することはお勧めしません。
課題のプログラムを提出する場合の心構え
それでも時間的な制約などもあって、やむなく授業や課題で作ったプログラムを提出するしかないという場合もあるでしょう。そういった場合には、しっかりと以下のような事を考えてから面接に臨むと良いでしょう。
- 何故学校の課題のプログラムを提出したか
- 課題のプログラムに関する思いや感想
これらは特に、技術者による面接の場合に聞かれることが多い質問です。
プログラムの勉強以外に「何を」していたか
何故課題を提出したかの「理由」 を問われた場合、時間がなくてそれしか準備できなかったのであれば、素直にそれを伝えるだけでも構いません。企業側も授業や課題のプログラムを提出してきた段階で、個人的に技術的な自己投資をしてきたような人材でないことは百も承知です。
ただ、技術投資する時間もない程、何かに時間を取られてきたのであれば、その時間に何をして過ごしてきたのかを知りたいのです。学校に通っている期間というのは、社会人からすると自己投資する時間が充分にある期間なので、その期間をどのように使ったかを知ることで、企業側は人材の適性や本気度を測ります。
正解はありませんが、例えば「バイトやサークル活動が忙しかった」と回答した場合を考えてみましょう。どちらも学生の間にしか体験することが出来ない貴重な活動でもあります。本気でそれらに取り組んだことをアピールできれば、「技術的な部分以外で」興味を引くことができるでしょう。
面接の担当者が技術にしか興味がないような人であった場合には、残念ながらこの方法が通用しない場合もありますが、一般的な社会人経験のある普通のエンジニアが担当者であった場合は、一定程度理解してもらえるはずです。
課題のプログラムに関する思いや感想
企業側としては、学校の授業や課題で製作したプログラムが提出された場合でも、そこから少しでも技術的な適性を判断する材料を得ようとします。
そもそも作品提出は、その人の技術力などを知るためのものなので、その点に関する評価を何かしら得る必要があるのです。質問者としても、学校の先生に言われたとおりに作っているだけのプログラムなので、そこに技術的な苦労や思い入れがあるとは考えていません。
質問された場合には、作ったときの事を考えながら、素直な感想を述べましょう。作っている時に楽しくてプログラマーになりたいと思ったというような、志望動機に対する定番の答えでも構いません。ただし、当然「どのあたりが楽しかったのか」という質問にも回答する心構えは必要です。
課題にあたって他人との協力した体験談や、課題を改良して機能を付けるといった工夫などは、特にIT企業でチーム開発を率いているような技術者には好印象を与え、強く興味を持ってもらえるはずなので、積極的にアピールしていくと良いでしょう。
特定分野の勉強中アピールは効果的
面接官の興味を引きたいのであれば、提出する作品までは準備することが出来ていないけれども、「○○の分野に興味があって勉強中」です、といったような回答は好意的に受け止められる可能性が高いです。
その場合は、○○に挙げた特定分野について少し踏み込んだ質問がされる場合もあり、少し受け答えが難しく面接の難易度としては高くなってしまうかもしれません。また、あまりに知識が乏しい場合は「熱意はその程度か」と逆効果になる危険性もあるので、使いどころには注意が必要です。
分からない質問に対しては、背伸びせず、自分の勉強している範囲で回答しましょう。分からないことに対してどのような反応をするかは、技術者適性を知る貴重な情報です。見栄を張って知ったかぶりをするような人は、技術者としてだけでなく、他の分野の人からも敬遠されるため、自分の興味関心がある得意分野であったとしても、謙虚で素直な対応を心がけましょう。
大学の卒業研究は「専門性」をアピール
学校の授業で製作したものに近いですが、大学の卒業研究の課題で製作したプログラムを提出するのもひとつの手です。研究室の規模などにもよりますが、提出物の内容は他の人と重複することが少なく、特定分野に専門的になる場合が多いでしょう。
学校の授業の作品とは違って、一定の期間集中して研究した内容となるため、面接で触れられる場合には意外と話が弾むことも多いです。面接官も、日常で扱うソフトウェアと異なる作品が提出されてくると、それはどういった物なのか興味が湧いてくるものです。

卒業研究のプログラムを提出する場合は、しっかりと本気で研究に取り組んでおく必要があります。面接での質問は、プログラム作品の中身だけでなく、研究の目的など周辺の事情にまで及ぶ可能性が高いです。
自信をもって回答できるように、研究のテーマについて真剣に考えておきましょう。研究室の先生と行った議論や、過去の研究結果などを引用しながら、テーマについて知らない面接官に対して「研究の意義」を力説することができるくらいだと、強い自己アピールになります。
プログラム制作環境の選定についての質問
授業の作品とは違って、卒業研究のプログラムの場合は「何故その環境を選んだのか」といった、プログラム制作環境の選定について、面接で問われる可能性があります。その質問には、沢山あるプログラムの制作環境の中から、その環境を選んだ理由を知ることで、問題解決に対するアプローチや考え方を知ろうという意図が込められてます。
その環境しか勉強してこなかったとか、所持している制作環境がそれしかなかったという回答でも問題ありません。ありのままを回答しましょう。もちろん、自分のこだわりがあって語りたいのであれば、しっかりと自己アピールしていきましょう。
自分の意見を述べた後、逆に企業側に対して質問してみるのも、企業やプロの仕事の内容に真剣に興味がある事を示すことができて効果的な場合があります。
自分の最新作が卒業研究ということもある
余談ではありますが、私がIT企業を受験した際に提出した作品は、卒業研究で作成したプログラムでした。個人で様々なプログラムも作ってはいましたが、受験当時の最新のプログラムが卒業研究で、自分の中で最も技術的に新しい知識を盛り込んだものだったためです。
内容は画像の認識に関係したものでしたが、研究なので、どちらかというと学術的な要素が強いものでしたが、技術者の担当者を含め、面接頂いた方々には比較的興味を持ってもらえたように思います。
普段は自分のプログラムを作成していても、就職活動や卒業研究などで忙しくなると、なかなか自分の趣味のプログラムまで手が回らないということもあります。学校の授業で出された課題などと違って、自分の設計でプログラムを作成している卒業研究は、採用する企業側としても大きな判断材料になりますし、最低限ソフトウェア制作の技術力が備わっていることをアピールできますので、自信をもって提出しましょう。
個人製作のプログラム提出は超強力
学生時代から様々な活動をしている強力な応募者などが、稀にすごい作品を提出してきます。そういった応募者は、企業の採用関係者以外にまで噂になったりします。個人や複数人で製作したゲームなど、他の応募者とは一線を画す作品を提出すると、企業側の度肝を抜くこと間違いなしです。
採用試験全体において、強力なアドバンテージを得ることが出来て、筆記試験や面接で大きな失敗をしなければ、合格の可能性をかなり高めることができるでしょう。
そういった作品を提出してきた人と面接で直接お話しをすると、明らかに他の人とは違う「エンジニアオーラ」があふれ出ているものです。

私の経験している限りでは、こういった異色の作品を提出してきた候補者の中では、不合格となった人は記憶にありません。もちろん、企業側が内定を出したとしても必ず入社してもらえるわけではないため、その全員と共に仕事をすることができたわけではありませんが、入社した人がその後も凄い活躍をしていたことは言うまでもありません。
ゲームのような凝った作品はインパクト大
新卒採用の場合は、個人製作の特殊な作品の提出はそれほど数が多いわけではないため、企業側にとっても記憶に残りやすく、採用活動が終わった後も長い期間印象に残ります。落ちものパズルとか、シューティングゲームのような凝った作品を提出された場合は、あまりにもインパクトが強すぎて、採用後十数年経っても忘れられない程に記憶に刻み込まれます。
場合によっては、提出作品のゲームがIT企業内で広まり、業務時間中に「仕事の名目でプレイされる」こともあったりします。その行動によって、あなたの知らない間に、応募先の社員に名前が知れ渡っているということもあるでしょう。面接が始まる前から、企業は作品の制作者への興味が高まり、場合によっては面接前に「ほぼ合格」という判断がされている事すらあるかもしれません。
私の経験においては、筆記試験の結果が悪い学生であっても合格とし、面接も行って採用通知を出した例もあります。それほどまでに、インパクトのある作品提出は非常に強力な武器に成り得ます。
作品が強力でも「面接の油断は禁物」
ITエンジニアやプログラマーになりたいと本気で考えている人は、自然と日々の活動にその熱意が反映されているものです。プログラマーだけでなく、ITに関連している物なら何でも知りたいという知的探求心の塊のような人も世の中にはいるものです。自分がそういう種類の人材だと思うのであれば、自信をもってアピールしていきましょう。逆に、自分はそこまでじゃないと思うのであれば、そういった人たちに負けない自分の長所を考えて、しっかりアピールしていく内容を考えておきましょう。
こだわりが強すぎるて、いわゆるオタクの早口のような話し方になってしまうと、相手に効果的に伝えることができないこともあって逆にマイナス評価されてしまう危険性もあるので、落ち着いて話すことを忘れないようにしましょう。また、天狗にならず、謙虚な姿勢は大事です。
どれだけ技術者として高度な技術力が備わっていても、まともなコミュニケーションをとることが難しい候補者は、企業としては採用することができません。技術力だけで油断せず、面接の練習をしたり、目上の人と話す姿勢を学んでおきましょう。
作品も含めて自己アピールを大事にしよう
最後に、今回紹介した作品と、その作品を提出した場合の効果について、簡単な表にまとめておきます。
| 提出作品 | 効果や対策 |
|---|---|
| 学校の授業 | 技術者適性の加点はほぼ見込めない。その他の活動アピールでしっかり補填を。 |
| 卒業研究 | 専門性に活路を見出す。本気度が非常に重要。 |
| 個人の研究や活動 | 非常に強力な自己アピール。落ち着いて謙虚に。 |
作品提出は、就職活動の中では頭の痛い面倒なことかもしれません。提出が任意となっている企業や、提出が必要のない企業の中から受験する企業を選んでしまいたく人もいるでしょう。試験や提出物の内容ではなく、本当に働きたいと思える企業から就職先を選ぶようにしましょう。
今回は作品提出に注目して色々と紹介してきましたが、そもそも新卒採用の場合は技術力よりも適性が重視される傾向が強いです。社会人としてコミュニケーションが取れて、向上心がある人材であれば、採用時点の技術力はそれほど問われないことも多いのです。プロの技術力の高低に比べて、学生時代の趣味の範囲の技術力の高低はそれほど大きくないことが多いためです。
プログラマーに本当になりたいと考えているのであれば、その熱い思いをしっかりとアピールして、合格を勝ち取りましょう。