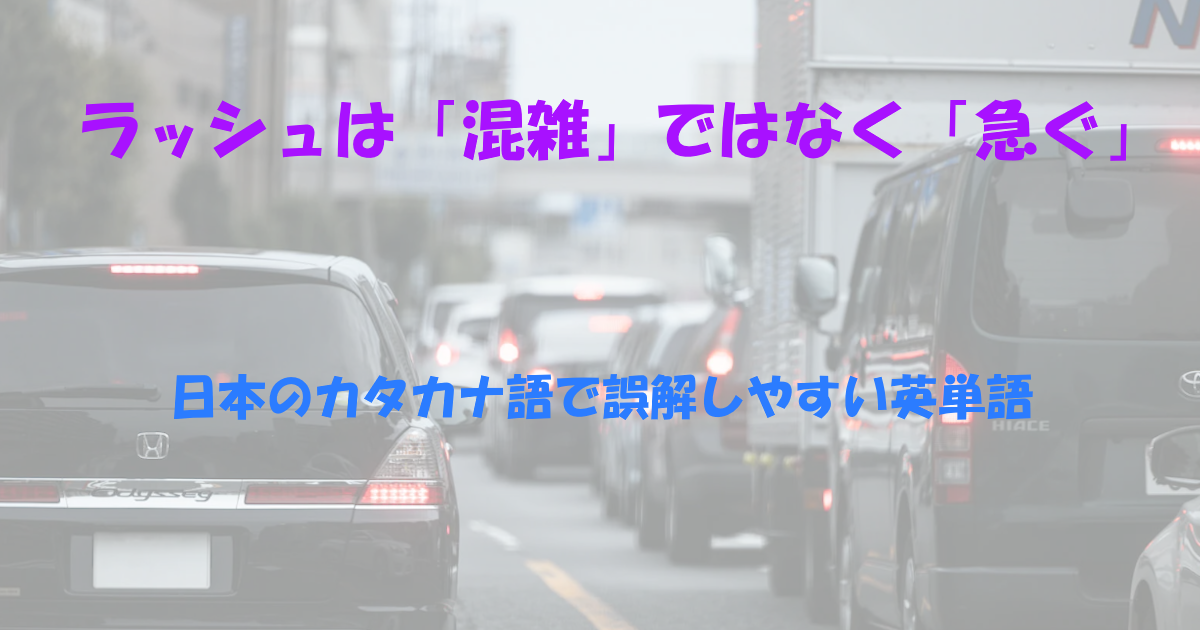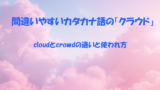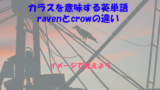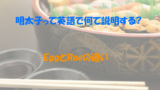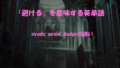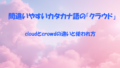日本には、平仮名・片仮名・漢字という3種類の文字システムが備わっていて、その中でもカタカナは外来語や擬音語など、非常に汎用性の高い表記方法です。しかし、外国語の音からカタカナ表記にして日本語に取り込んだものの中には、歴史の中で徐々に外国語本来の意味から遠ざかってしまい、違う意味の言葉として使われるようになっているものもあります。
日本では車の渋滞などの事を「ラッシュ」と呼びますが、これは英単語のrushが基になっている外来語です。「ラッシュ」は「混雑」や「殺到」という意味で使われるますが、英単語としてのrushは少し意味が違っています。今回は、rushとラッシュの違いについて紹介しています。
日本語の「ラッシュ」と英語の「rush」
日本語のラッシュは外来語(カタカナ語)で、元の言葉は英語のrushです。しかしこの両者には意味合いの違いがあり、外国語を話す際などには日本語の意味に惑わされないように注意が必要です。
日本語のラッシュを「混雑」と思っているとイメージしにくいかもしれませんが、英語のrushは「急ぐ」という意味の言葉です。
交通渋滞のラッシュは、本来は「急いでいる人・車が多い」というニュアンスの言葉です。
「ラッシュ」と「rush」について、それぞれ確認してみましょう。
日本語のラッシュ – 「混雑」の意味で使われる
日本では、交通渋滞の事を「ラッシュ」というカタカナ語で表現されます。また、車や人が多い際などには、「混雑」の意味でラッシュという言葉を使用することもあります。

英語のrush – 「急ぐ」という意味
カタカナ語の「ラッシュ」の基になっている英単語は「rush」です。
rushの「発音」
発音はカタカナのラッシュに似てはいますが、最初の子音は日本人が苦手なr音となっています。また、最後の音にも母音のu音(ウ)がない点にも注意が必要でしょう。

発音記号はGoogle 翻訳で表示されるものを引用しています。
rushの「動詞」としての意味
rushという英単語には、動詞として次のような意味があります。
- (自動詞) 急ぐ
- (自動詞) 急いで~する
- (他動詞) 急がせる
- (他動詞) 押し寄せる
rushは自動詞としても他動詞としても使う英単語で、どちらも「急いで何かをする」イメージです。良く耳にする表現として、ひとつ例を紹介します。
例文 : Don’t rush.
和訳 : ゆっくり or 慎重に。(急がないで)
日常会話から映画やアニメなどでも耳にする機会が本当に多い表現です。変化形で「Don’t rush to ~.」という言い回しも良く使われます。スポーツなどでも、有利な状況で「落ち着いていこう」といったニュアンスでも使える言葉です。
rushの「名詞」としての意味
英単語のrushは名詞としても使われます。
- 突進・突撃
- 多忙
- 殺到
日本でも、スポーツやゲームなどにおいて「相手(敵)にラッシュをかける」のように、名詞としてのrushの意味で使われることがあります。
動詞の方は意味合いが変化してしまっていますが、名詞の方は元の意味合いのまま使われていると言えるでしょう。
rush hour(ラッシュアワー)の英語と日本語の違い
カタカナ語のラッシュアワーは、英語でもrush hourと表現します。日本語のラッシュアワーは、交通渋滞が起こる時間帯の事を指します。
rush hourを英語の辞書で調べると以下のように説明されています。
英語 : a time during each day when traffic is at its heaviest.
和訳 : 一日のうちで最も交通量が多くなる時間帯。
ラッシュアワーとrush hourは同じで、日本語と英語で意味に違いはありません。
日本語では、言葉を簡略化したり短縮化することが頻繁に行われるため、交通渋滞を意味するラッシュアワーがラッシュと短縮化されてしまっているとも考えられます。
rushと合わせてまとめると以下の表のようになります。
| – | ラッシュ / rush | ラッシュアワー / rush hour |
|---|---|---|
| 日本語の意味 | 交通渋滞 | 交通渋滞の時間帯 |
| 英語の意味 | 急ぐ | 交通渋滞の時間帯 |
日本語ではラッシュでも交通渋滞の事を意味しますが、英語ではrush単体では「急ぐ」という意味以上にはならず、交通渋滞の事を示す場合には別の表現が必要となります。
「混雑する」を意味する英単語
英語でも混雑する時間帯の事は「rush hour」と表現しますが、「交通渋滞」の事や「混雑する」という意味ではrushは使われません。それぞれは以下のように表現することが多いです。
交通渋滞 – traffic jam
日本では交通渋滞の事を「ラッシュ」と呼ぶことが多いですが、英語での交通渋滞は「traffic jam」と表現します。カタカナで表すと「トラフィック ジャム」となります。
trafficは「交通」の事で、jamは「詰まる」ことを意味します。交通状況が詰まっている状況なので、「交通渋滞」という意味になります。
海外の人に「交通渋滞」を伝えようとした際に、英語だと勘違いしてラッシュと言っても、相手には意味が伝わらないため注意しましょう。
混雑した – crowded
また、カタカナ語のラッシュを「混雑している」という意味で使っている人も多いように思います。

英語で「混雑している」状況を表現する場合には、「crowded」が使われることが多いです。カタカナで無理やり表すとすると「クラウディッド」となります。
原型のcrowdは、名詞だと群衆・大衆といった意味で、動詞だと群がるといった意味の英単語です。過去分詞系になると、形容詞として「混雑した」という意味になります。
近年では、インターネット上で大衆から資金を集める「クラウドファウンディング」が注目を集めています。この言葉は英語では「crowdfunding」で、crowd(大衆)とfunding(資金調達)から成る造語です。
「急ぐ」を意味する英単語 – 「rush」と「hurry」の違い
rushは「急ぐ」という意味の英単語ですが、日本の英語教育では「急ぐ = hurry」と習います。映画などでは「急いで!」という場面で「Hurry up!」という台詞を見た事がある人は多いでしょう。
rushとhurryは、どちらも同じ「急ぐ」という意味ですが、その大きな違いは以下の点です。
rushは、hurryよりも「緊急性が高い」
rushの意味を紹介する際にもあったように、rushには「突撃する」といった意味合いがあります。rushは、大急ぎで何かをしなければならない緊急性がある場合に使われる単語です。
一方hurryは、「普段よりも急ぎで」何かをする場合に使われる、一般的な英単語です。
rushとhurryを使った例文
同じ「急ぐ」という動詞なので、言い換えることも可能です。
例文 1 : I need to rush to the office.
例文 2 : I need to hurry to the office.
和訳 : 急いで事務所に向かわなければ
和訳としては同じでも、意味合いは異なっています。rushの方は日本語の「大至急」といったニュアンスになります。「(全ての事を投げ捨てて)急ぐ」という意味合いです。
hurryの方は、無駄な寄り道などせず、素早い動作などで「急ぐ」という意味合いなので、日本語的には「迅速に」とか「なるはやで」といったニュアンスが近いでしょう。
本サイトでは、このような類義語を扱った記事が他にも色々ありますので、興味のある方はそちらも是非ご覧ください。以下はカラスを意味するcrow(クロウ)とraven(レイブン)の違いについて紹介した記事になります。
「lash」と「rash」の違い
カタカナ語では同じなのに、基となる英単語が異なることはよくあります。日本語と英語が、異なる発音(母音・子音)を持つことにより起こっている現象で、英語のRとLが日本では同じラ行に分類されるなどがその典型です。
日本では急ぐという意味の「rush」だけでなく、「lash」もアイラッシュ等のカタカナ語の一部で使われることがあります。
アイラッシュは英語ではeyelashまたはeyelashesとなります。eyelashはまつ毛の事で、以下のように使われます。
英文 : An eyelash is fell into my eye.
和訳 : まつげが目に入ってしまいました。
日本では、アイラッシュは「まつげに関するおしゃれ」全般の言葉として使われていますが、元々の英単語としては「まつげ」自体を指す単語です。
英単語lashの意味
eyelash(まつげ)に含まれているeyeは、目を表す英単語です。それではlashはどういった意味なのでしょうか。
lashは、名詞としては「鞭打ち・鞭ひも」、動詞としては「鞭で打つ」や「非難する」といった意味の英単語です。
「まつげ」なのに、関係のなさそうな鞭打ちという単語が使われていることを不思議に思う人もいるでしょう。
eyelash, まつげの語源 – 日本語と英語の違い
英語では、「目をゴミなどから守る」という「まつげ」の機能から、「目に備わった鞭」という意味合いが語源となって、eyelashと呼ぶようになったようです。
一方日本語では、「ま」は目の事で、「つ」は助詞の「の」の意味。「げ」は睫(けつ : すれすれに接する)から「ギリギリに生えた毛」で、「まつげ」となっているようです。要は「目の毛」という事です。
異なる言語には異なる歴史があり、同じ意味の単語でもその語源や形成されてきた経緯が異なっていて、非常に興味深いものです。語源や類義語に関する面白い雑学の記事を一つ紹介しますので、よかったら以下の記事もご覧ください。
カタカナ語に興味を持ってみよう
日本語には外国の単語を、音で表記することで簡単に取り込むことが出来るカタカナがあり、現代でも様々な外来語(カタカナ語)が使われています。英語だけでなく、ドイツ語やフランス語など様々な言語から日本語に取り込まれていて、単語を使っている日本人は、それらが元々何の言語の言葉であるかを知る必要もありません。
日常生活をする上では、外来語(カタカナ語)の基になっている言語を改めて学ぶ必要はありませんが、外国の人たちとの交流をする機会がある場合には、今回の様に「日本語で意味が変わっている単語」について知っておきたいものです。通じると思ってカタカナ語の意味で単語を使うと、思わぬ恥をかいてしまうことになるかもしれません。
言語の学習をする過程では、日常に馴染んでいるカタカナ語が言語の理解を助ける場面も多くありますが、逆にカタカナ語の意味に引っ張られて間違ってしまうこともあります。言語を学んでいる人は、身近なカタカナ語を誤って使ってしまわないように、元の言語や意味などにも興味を持ってみるといいかもしれません。