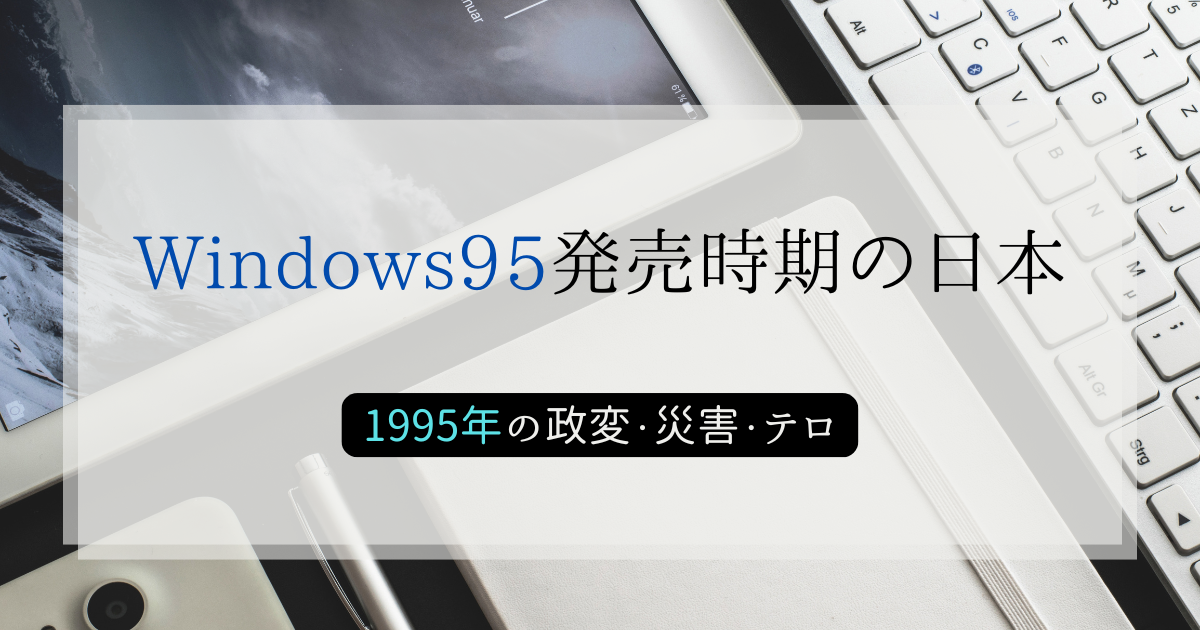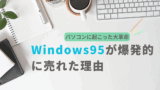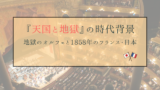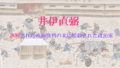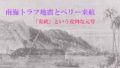1995年にWindows95が発売されたことにより、急速にパソコンやインターネットが普及しました。
今となってはネットもパソコンもない生活は想像が難しいですが、1995年という年は、まさにその境目の年だったといえます。1995年はWindows95の発売以外にも大変な事がたくさん起こった「激動の一年」でした。今回は、1995年の日本でどのようなことが起きていたのかをまとめてみます。
Windows95発売時期 – 1995年の日本
1995年という年は、Microsoft社からWindows95が発売された年で、以降急速にパソコン・インターネットの普及が進んだことから「時代の転換期」ともいえる年です。
世間では、個人や企業がパソコンの利用や導入を検討しはじめると同時に、急激な変化に対する揺り戻しで、パソコンやWindowsを批判したり否定するような声も聞かれました。
そんな1995年という年に起きた出来事を振り返ってみましょう。
村山内閣 – 自民与党で唯一の自民党「以外」の総理大臣
日本の政治は、Windows95が発売される少し前、1993年から不安定な状況が続いていました。
1993年8月の細川内閣発足により、1955年の結党以降、38年間政権与党を維持してきた自由民主党(自民党)の政治に終止符が打たれました。
しかし、細川内閣は多くの政党の連立だったため政権運営は安定せず、羽田内閣発足直後には連立内の最大政党だった日本社会党が離脱します。その後、長く与野党で対立していた日本社会党と自由民主党が手を組む大連立が成され、村山内閣が発足(1994年6月)します。
| 内閣総理大臣 | 与党 |
|---|---|
| 第78代 宮澤喜一 (自由民主党) | 自由民主党 |
| 第79代 細川護熙 (日本新党) | 非自民連立 (8政党) |
| 第80代 羽田孜 (新生党) | 非自民連立 (11政党) |
| 第81代 村山富市 (日本社会党) | 自由民主党、日本社会党、新党さきがけ |
村山内閣は1994年6月に発足し、1995年8月に改造内閣、1996年1月に総辞職しているため、1995年は、一年を通して「村山富市」が内閣総理大臣を務めています。
1995年は戦後50年の節目の年でもあり、村山富市内閣が発表した村山談話は、以降歴代内閣の基本方針として現在まで受け継がれています。
自民党が政権与党でありながら、自民党以外から内閣総理大臣になっているのは、2025年現在までに村山富市だけです。
(1955年の自民党結党以降、自民党外の総理大臣は以下の6名で、残りの5名は自民党下野時)
細川護熙、羽田孜、村山富市、鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彦
阪神淡路大震災 (1995年 1月) – 戦後最大被害の自然災害
1995年の1月17日の午前6時少し前というまだ多くの人が寝ている早朝の時間に、兵庫県淡路島近辺を震源とする大きな地震が発生しました。
阪神淡路大震災は、地震の規模を示すマグニチュードは7.3を記録し、6000人を超える犠牲が出る大災害となりました。
日本としては、当時戦後最大の被害をもたらした自然災害であり、まさに未曽有の大惨事という状況でした。

特に「経験したことのない大災害」であったことで「杜撰な体制」が浮き彫りとなり、逆にこの災害の後から本格的に「近代的な災害対策」がとられるようになったともいえるでしょう。
災害発生時の総理大臣であった村山富市が、自衛隊派遣が遅れたことに対して「なにぶんにも初めてのことですので」と答弁したことは強く非難され、内閣支持率を急速に下落させました。
緊急時の対処「トリアージ」の始まり
阪神淡路大震災時に現場の医療従事者が「トリアージ」を行った事も話題になりました。
傷病の症状から患者の緊急度や優先度を決めるトリアージは日本ではほとんど行われていませんでいたが、阪神淡路大震災発生後に、可能な限り多くの方を救うために現場の判断で行ったとされています。
以降トリアージは、緊急時の対処として国内では周知されるようになり、その後震災の際などには行われるようになっています。
地下鉄サリン事件 (1995年 3月) – オウム真理教による大規模テロ
海外の人が「日本は安全な国」と好意的な評価をしてくれる昨今ですが、1995年にはそんな安全を脅かす事件が起きました。
1995年3月に起きた地下鉄サリン事件は、日本の首都東京で起こった大規模なテロ事件です。
地下鉄サリン事件は、オウム真理教の信者が東京の地下鉄内で神経ガスであるサリンをバラまいた同時多発テロ事件です。
朝8時頃の通勤時間帯を狙った犯行だったため、地下鉄を利用する多くの人たちが被害にあいました。地下鉄駅周辺の道路に倒れ込んで苦しむ大勢の人や、救護・警察関係の人や車両がごった返している大変な状況が、連日テレビなどで報じられました。

事件後にはオウム真理教の犯行が明らかになっていき、最終的には教祖の麻原彰晃や大勢の幹部が逮捕されました。麻原氏や事件に深く関わった数名は死刑が確定し、既に刑は執行されています。
一方でメディアの対応を担当していた上祐史浩氏は、公的文書に関する罪を問われて服役していましたが地下鉄サリン事件等の凶悪犯罪には関与していないとされ、現在は出所して「ひかりの輪」という宗教団体の代表を務めています。
オウム真理教は地下鉄サリン事件が有名ではありますが、その他にも多くの犯罪行為も行っていたり、選挙にも出馬するなど、多くの話題が日々報道され続けていました。特に衝撃だったのが、テレビの生放送での直撃インタビューの最中に、オウム真理教の幹部一名が刺される瞬間が報道されたことです。その後の対応も含めて、今以上にメディアの行動が非常識すぎたのがとても印象に残っています。
1995年の情報収集はテレビが主流
1995年には阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件のような日本を揺るがす大きな出来事がありましたが、当時スマートフォンはまだなく、ポケベルから携帯電話やPHSといった移動体通信機への移行が急速に進んでいるといった時代です。
2020年代からすると、1995年はたった30年ほど前の時代ではありますが、パソコンもインターネットも普及していない時代で、新聞やテレビなどしか情報収集する方法がなかったということに、改めて驚かされます。本当に便利になりました。

ネットが「無い世界」から「有る世界」へ
当時は、新聞やテレビしかないのが普通で特に不便だとは感じていませんでしたが、今は逆に新聞・テレビを全く見ることが無くなり、すべてネットの情報だけで済むようになってしまっています。
当時はテレビの番組中はテレビの前に長い時間拘束されていましたが、今は隙間時間に効率よく情報収集することが出来ており、より人生の貴重な時間を有効活用できていると感じます。
これからのメディアの在り方や、私たちの情報リテラシーの行く末はまだ分かりませんが、間違いなく言えるのは「大きな変革の時期」であるという事でしょう。特にこの20年くらいのITに関する変化は大きく、私たちはまだその変革の途上にあるのです。
多角的にみる歴史
政治の話題をしている場合などでは、政局や政党、総理大臣などの話に集中してしまいがちですが、「その当時どのような状況であったか」を考えてみると、改めて見えてくる「景色」があるのではないでしょうか。
歴史の出来事として、阪神大震災や地下鉄サリン事件を考える場合に、1995年と言えば「パソコンやネットが無かった時代」であることを思い出すことが出来れば、当時の災害や事件への対処がどれだけ大変で、当時の国民がどれほど不安に思っていたのかも想像することができるでしょう。
ひとつの分野に集中して学ぶことは専門性を高めますが、多角的な視野を失わないように注意しなければなりません。分野を超えて見渡すことで初めて気付くことというものはあるものです。