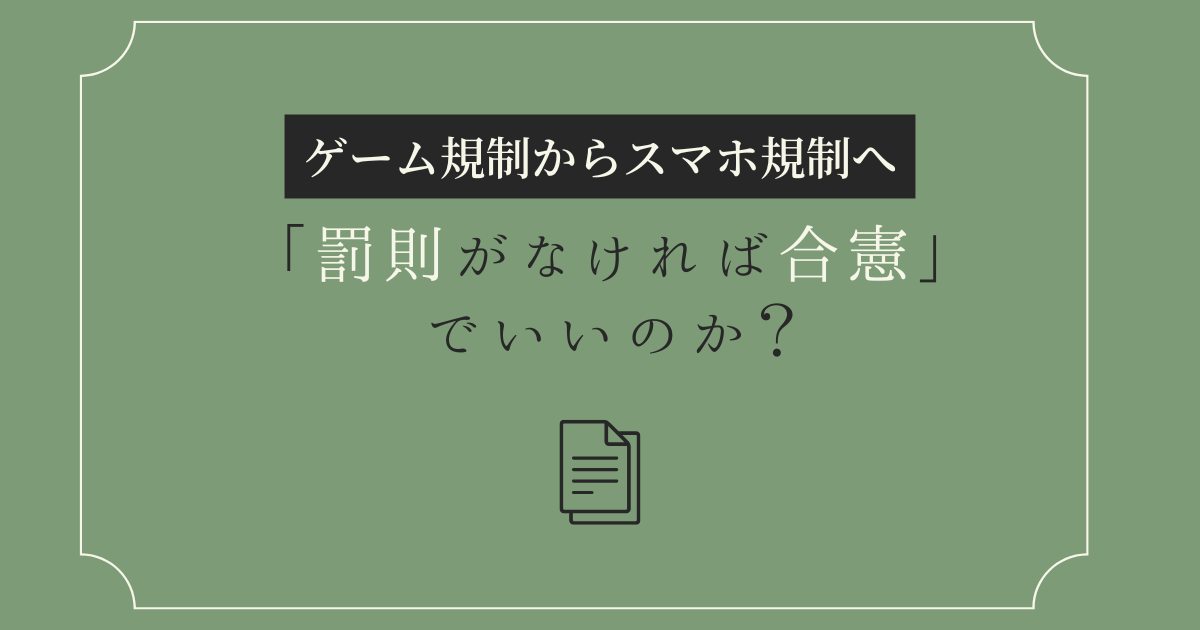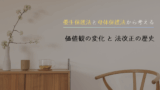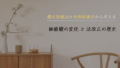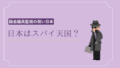罰則がなければ自由を制限してもいいのか。
香川県のゲーム規制条例をめぐる裁判は「合憲」と結論づけました。今回、豊明市が提出した「スマホ使用2時間」条例案は、その延長線上にあります。私たちは、このまま自由の制約を受け入れてよいのでしょうか。
愛知県「スマホ2時間」条例案とその反応
2025年8月、愛知県豊明市が「子どものスマートフォン使用は1日2時間以内を目安」とする条例案を市議会に提出するというニュースが報じられました。
小学生は夜9時まで、中高生は夜10時までの利用を目安とし、施行は同年10月を予定。罰則はなく、あくまで「理念条例」として家庭や学校でのルールづくりを促す内容とされています。
SNS上の反応
SNS上では「子どもの依存症を防ぐために必要」と賛同する声がある一方で、「自由を奪う発想だ」「教育機会の損失になる」といった批判も数多く見られます。
2025年8月21日時点で、同内容を伝えるYahooニュースのSNS投稿に対しての反応は、Grokで定量分析を掛けてみると、賛成は2%程度の圧倒的反対多数という状況のようです。
| 分類 | 割合 |
|---|---|
| 賛成 | 2.44% |
| 反対 | 73.17% |
| 中立 | 24.39% |
- 賛成の例: 「子供の学力低下がやばそうだしいいと思う… 中学までスマホ禁止にすべき」
(学力向上の観点で支持)。 - 反対の例: 「バカじゃないの」「意味無い条例 アホか」「老害共が」
(明確な否定や批判)。 - 中立の例: 「条例違反したらどうなるの?」 (質問)、「これはタブレットが売れる予感。」
(皮肉や代替案)。
果たしてこのような条例は、憲法や自由の観点からどう評価すべきなのでしょうか。
条例案の対象はスマホだけではない
また、Yahooニュースの記事によると、条例案は、睡眠時間確保のため、子どものスマホの使用を小学生までは午後9時、中学生以上は午後10時までを目安とすることが盛り込まれているとのことです。スマホだけでなく、タブレットの他、ゲーム機器やパソコンなども対象となります。
市によると、時間を明示した「スマホ使用条例」は全国初とされています。
前例としての「香川県ゲーム規制条例」
思い出されるのは、2020年に施行された香川県の「ネット・ゲーム依存症対策条例」です。
この条例も「18歳未満はゲームは平日60分・休日90分を目安」と定め、保護者には子どもの利用を管理する努力義務を課していました。
この条例に対しては「幸福追求権(憲法13条)や表現の自由(21条)を侵害する」として訴訟が提起されました。
- 高松地裁(2022年8月):「努力目標にとどまり、法的拘束力はない」→違憲ではない
- 高松高裁(2023年4月):控訴を棄却 → 「条例は合憲」
- 最高裁:上告を受理せず → 判決確定
つまり、司法は「罰則のない理念条例は合憲」と判断したのです。
裁判所の論理 ― 「罰則がないなら自由侵害ではない」
香川の判決のポイントはシンプルです。
- 条例はあくまで「努力義務」や「目安」である
- 罰則も行政処分もない
- したがって、基本的人権を直接的に侵害するとは言えない
この論理によって、原告の「自由侵害」主張は退けられました。
しかし、この考え方には大きな疑問が残ります。
罰則がなければ「憲法審査から免責」の危うさ
罰則がないことを理由に、香川判決は違憲性を否定しました。
しかしこの論理は「罰則さえ設けなければ、条例の内容がどれほど自由を制限するものであっても違憲にならない」という危うさを含んでいます。
たとえば、もし政治的発言の抑制を努力義務として定める条例が作られた場合、形式上は「合憲」とされてしまう恐れがあるのです。
理念条例がもたらす「事実上の強制」
法律上の強制がなくても、条例という「自治体のお墨付き」があるだけで、社会的圧力が生まれます。
実際に考えてみれば、こんな場面が想定されます。
- 学校での強制的な運用
「条例に基づき、スマホは1日2時間まで」と学校が指導すれば、宿題やオンライン授業に必要な時間まで制限され、学習機会が狭められる。 - 家庭での親子関係への圧力
親が「条例だから」と子どもを一律に縛れば、本来家庭ごとに考えられる柔軟な教育方針が失われる。 - 地域社会でのレッテル貼り
「あの家は条例を守っていない」と噂になり、子どもが仲間外れにされるなど、社会的な排除につながる。 - 文化活動への萎縮
eスポーツや動画配信など新しい文化活動が「条例違反」とされ、若者の表現や将来の可能性を萎縮させる。
このように、理念条例であっても「社会的圧力」を通じて事実上の強制が生まれ、自由を制限する危険性は小さくありません。
合理性は本当にあるのか?
条例が合憲とされたとしても、個人が他者に対して自由を制限する行動を起こした場合、それは個人の権利の侵害に問われないのでしょうか?
「自由を奪う権利は誰にもない」というのが大原則です。
憲法学では、自由を制約するなら「合理的根拠」と「必要最小限」が求められます。
ところが現状、スマホ使用時間と健康被害の因果関係は明確ではなく、「長時間=害」とは立証されていません。むしろ使い方次第で学びや社会参加に役立つケースが多いことは、教育現場でも日々確認されています。
「スマホ=害」という前提自体が科学的に脆弱である以上、一律の時間制限を設ける合理性は乏しいと言えるでしょう。
条例制定で変わる司法判断
理念条例であっても、制定されれば司法の判断が左右されやすくなる懸念があります。
「スマホの害がまだ立証されていないのに“一律に制限を迫る”こと」は教育や文化の自由を狭める不当な行為と考える余地が十分あります。
しかし条例が制定されると、市民同士がスマホ制限を迫る行為は“条例に基づく正当な主張”として扱われやすくなります。そのため、自由侵害と訴えても違法性が認められにくくなる可能性があります。ただし、行政や学校が過度に強制した場合には、将来的に「憲法上の権利侵害」として問題化する余地は残っています。
スマホ条例案と香川ゲーム条例の比較
豊明市のスマホ条例案は、香川のゲーム条例と驚くほど似ています。
- 目的:依存症防止、健康維持
- 方法:使用時間を「目安」とする
- 性質:理念条例、罰則なし
香川判決の論理を前提とすれば、仮に憲法訴訟になっても「合憲」とされる可能性が高いでしょう。
しかし、スマホはゲーム以上に 教育・情報収集・交流・文化活動 の手段として不可欠です。
- 学校のオンライン教材や学習アプリ
- 調べ学習やニュースの閲覧
- SNSでの人間関係や文化活動
これらも「使用時間」に含まれてしまいます。
学びの可能性と教育機会の損失
ここで少し個人的な見解を述べさせていただきます。
「学び」というものは、教科書や授業だけから得られるのではなく、生活のあらゆる場面に潜んでいるものだと思います。私自身も、アニメやゲームを通じて知らない英単語に出会ったり、物語の背景から歴史の疑問に興味を持ったりする経験をしてきました。
そうした「偶然の学び」は、若い世代にとって大きな財産になる可能性があります。
一律に「ゲームは1時間まで」「スマホは2時間まで」と区切ることで、こうした学びの芽を摘んでしまうとすれば、それは単なる依存防止を超えて 教育機会の喪失 に直結するのではないでしょうか。
自由を守るために必要な視点
豊明市の条例案は、香川県のゲーム条例の流れを引き継ぐものです。
そして香川判決は「罰則がなければ合憲」とする司法判断を確定させました。
しかし、罰則がなくても理念条例は社会的圧力を通じて事実上の自由制限を生み出します。
もし「罰則がないから問題ない」とされ続ければ、憲法が保障する自由は骨抜きになりかねません。
依存症対策は確かに大事です。しかし一律の使用時間規制という短絡的な方法が、教育や自由を奪い、かえって社会を貧しくする危険性は見過ごせません。
「罰則がなければ合憲」という論理で本当にいいのか――
この問いを今、私たちが考え直す必要があるのではないでしょうか。
関連記事 : 価値観の変化と法改正の歴史
そもそも法律は社会の価値観にどう影響されてきたのでしょうか?
以下の記事では、価値観の変化に伴った法改正の歴史を紐解きながら、「法と価値観の関係性」について考えています。歴史と共に、現代議論されている事例を改めて見つめ直すと、新しい視点から物事を判断できるようになるのではないでしょうか?