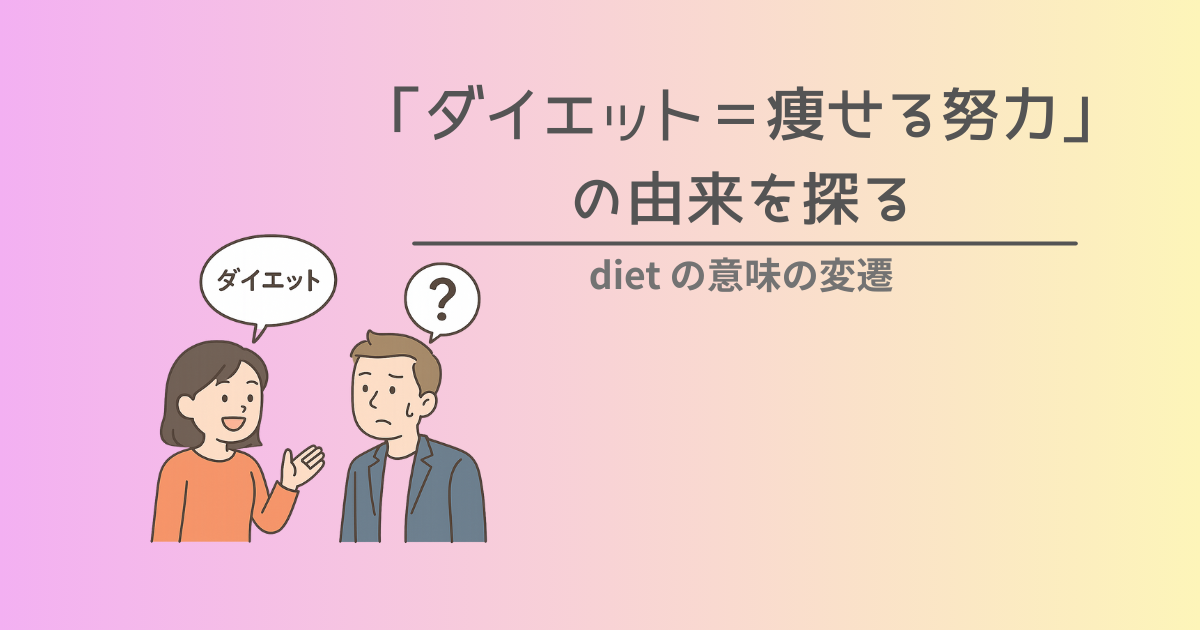日本語で「ダイエット」と言えば、痩せるための食事制限や運動を指すのが当たり前になっています。しかし英語の diet は「日常的な食習慣」という意味が基本で、必ずしも減量や美容を意識した言葉ではありません。
なぜ日本語の「ダイエット」は、英語本来の意味から離れてしまったのでしょうか?
この記事では、diet の語源や日本語での意味変化の歴史を追いながら、正しい英会話での使い方や注意点も解説します。
日本語と英語の「ダイエット」の違い
まずは現代の使い方を比べて、どのような意味のずれがあるのかを確認しましょう。
日本語での「ダイエット」
現代の日本語で「ダイエット」というと、減量や美容目的の努力全般を意味します。

食事制限だけでなく、エクササイズやサプリメントの摂取、専用の器具やプログラムまで含まれるのが一般的です。また、「ダイエット食品」や「ダイエット器具」といった商品名にも頻繁に使われており、「体重を減らすための何か」というイメージが強く根付いています。
英語での diet
英語の diet は基本的に日常の食習慣を意味します。「a healthy diet(健康的な食事)」「a vegetarian diet(ベジタリアンの食生活)」のように、日々の食事の傾向や習慣を指す言葉です。

減量目的の食事制限は to go on a diet という表現で表され、単語一つで「痩せる」という意味は持ちません。つまり、日本語の「ダイエット」は、英語の一部の使い方を切り取って広まった言葉だといえます。
英単語 diet の発音
dietは、英語でもカタカナの「ダイエット」とほぼ同じ感覚で発音できます。ただし英語では母音が弱くなるので、特に「エ」の部分が軽くなり、全体的にさらっとした響きになります。
- IPA:/ˈdaɪ.ət/ または /ˈdaɪ.ɪt/
- 読み方の目安:「ダイエット」(「ダイ」+「エット」の2音節)
- ポイント:
- di- の部分は「ダイ」に近い /daɪ/
- -et は軽く弱く /ət/
動物の「食性」としての diet
diet は人間だけでなく、動物の食性(何を常食とするか)を表すためにも使われます。
図鑑や博物館の展示、生物学の分野では以下のように使うのが一般的です。
- Lion – Diet: Carnivore
(ライオン ― 食性:肉食) - Koala – Diet: Herbivore, primarily eucalyptus leaves
(コアラ ― 食性:草食、主にユーカリの葉) - Bear – Diet: Omnivore
(クマ ― 食性:雑食)
Diet の語源と本来の意味
そもそも diet という言葉自体は、古代の思想や生活文化に根ざしています。
古代ギリシャ語 (diaita) → ラテン語 (diaeta) → 英語 (diet)
古代ギリシャ語「diaita」が語源
diet の語源は古代ギリシャ語の diaita(生活様式・生き方の規律) にさかのぼります。
当時の「diaita」は、食事だけでなく、睡眠や運動など生活全般のリズムを整えることを指していました。
医学の父ヒポクラテスの時代には、病気の治療も「生活習慣の調整」と捉えられており、その思想が「ダイエット」という概念の出発点になったのです。
ラテン語・中世ヨーロッパでの使われ方
ギリシャ語からラテン語「diaeta」に受け継がれ、中世ヨーロッパでは主に医学用語として使われました。
特別な食事療法や、患者ごとの食事制限を示す専門的な言葉として扱われ、そこから英語圏に「diet」が定着しました。この背景から、英語では今でも「治療食」「特別食」の意味を持つ場面が多く見られます。
日本語での意味変化の経緯
日本語で「ダイエット=痩せる努力」となったのには、医学とメディアの影響があります。
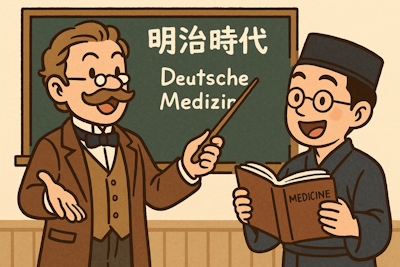
明治期~昭和初期:医学用語としての定着
明治時代、西洋医学が本格的に導入されると、diet は食餌療法(しょくじりょうほう:病気に応じた食事管理)を指す専門用語として日本に入ってきました。
| 用語 | ニュアンス・使用場面 |
|---|---|
| 食餌療法 | 専門書や学術論文で使われる古典的表現。「食餌制限」「食餌指導」など。 |
| 食事療法 | 一般的・平易な表現。患者向け説明や健康記事で使われる。 |
この頃はまだ一般の人が使う言葉ではなく、医師や看護師の世界でのみ通用する専門語でした。
明治日本の医学は「ドイツ語」
明治政府は、近代国家建設のモデルとしてプロイセン(ドイツ帝国)を参考にし、医学教育もドイツ式を導入しました。
当時の日本の医学校や教科書はほぼドイツ語ベースで、diet に相当するドイツ語 Diät(ディエート) が使われていました。この言葉は英語と同じくギリシャ語 diaita に由来し、「食事療法」「患者のための特別食」を意味します。
戦前までは、学術書には「ディエート」「食餌療法」という表現が多く登場しました。
江戸時代、日本で唯一のヨーロッパ言語だったオランダ語と近いドイツ語は、明治日本での学習を容易にしました。以下の記事では、その経緯や日本に入ってきた外来語などをまとめています。
💡関連記事:オランダ語からドイツ語へ – 明治日本の言語学習の変化
戦後~高度経済成長期:美容・体型志向の広がり
戦後の日本では、ハリウッド映画やファッション雑誌の影響で「スリムな体型」が理想像となり、女性誌やテレビで「ダイエット」が美容の代名詞として広がりました。

昭和のダイエットブーム
この時代、「食餌療法」という医学用語的なイメージ(ドイツ語 Diät)から、英語の diet に基づく表記が広まり、雑誌や広告の影響で「体型を整えるための努力」という日本独自のニュアンスに変化していきます。
現代:減量・美容・運動まで含む広義の言葉に
現在の日本語では、ダイエットは「痩せるための行動」全般を指す総称に進化しました。
食品、器具、エステ、アプリなど多様な商品・サービスのマーケティングにも使われることで、英語の diet とはさらに乖離しています。
英会話で注意したい「diet」の使い方:例文
日本語の「ダイエット」をそのまま diet と言うと、意味が通じなかったり不自然になることがあります。
ここでは、よくある間違いと自然な英語表現、そしてdiet本来の使い方を紹介します。
ダイエットの間違いやすい表現
日本語の「ダイエット」は「痩せるための努力」「痩せること」を意味しますが、英語では diet にその意味はありません。直訳すると不自然になったり誤解されることがあります。
以下はよくある表現の「悪い例」と「自然な言い方」の比較です。
- ダイエット中です。
- ❌I’m doing a diet.
- ✅I’m on a diet.
- ダイエットに成功した。
- ❌ I succeeded in dieting.
- ✅ I reached my weight loss goal.
このように「on a diet」「lose weight」といった表現を使うのが自然です。
diet本来の使い方(痩せる努力以外)
I eat a balanced diet.
バランスの良い食生活をしています。
My doctor recommended a low-salt diet.
医者に減塩食を勧められました。
The panda’s diet consists mainly of bamboo.
パンダの食性は主に竹です。
ポイントまとめ
- diet は本来「食習慣・食生活」「特別食・治療食」「動物の食性」を表す言葉
- 日本語の「ダイエット」のように「痩せること」を直接意味しない
- 「減量」に関連する英語表現 (日本語のダイエットの言い換え)
- lose weight(体重を減らす)
- weight loss (減量)
- slimming(体を引き締める:美容)
意味が変わった外来語は他にもある
日本語のダイエットの意味の変化は、言葉の輸入と文化の影響がいかに密接であるかを示す良い例でした。こうした意味の変化は文化背景の違いを映し出しており、日本語の面白さの一面でもあります。
この記事をきっかけに、日常的に使う外来語をもう一度見直してみると、言葉の背景や歴史の面白さがより深く感じられるはずです。
和製英語や意味変化の例
意味が変わって日本に根付いた外来語は、「ダイエット」の他にもたくさんあります。
代表的な言葉としては、以下のようなものが挙げられます。
- コンパニオン:英語の companion(仲間)とは異なり、接客やイベントスタッフの意味に
- サラリーマン:英語では通じず、日本特有の職業観を示す言葉
- マンション:英語圏では「豪邸」の意味、日本語では集合住宅
以下の記事では、コンパニオンの日本語と英語の違いをまとめ、同じように歴史的背景や例文を紹介しています。是非あわせてご覧ください。