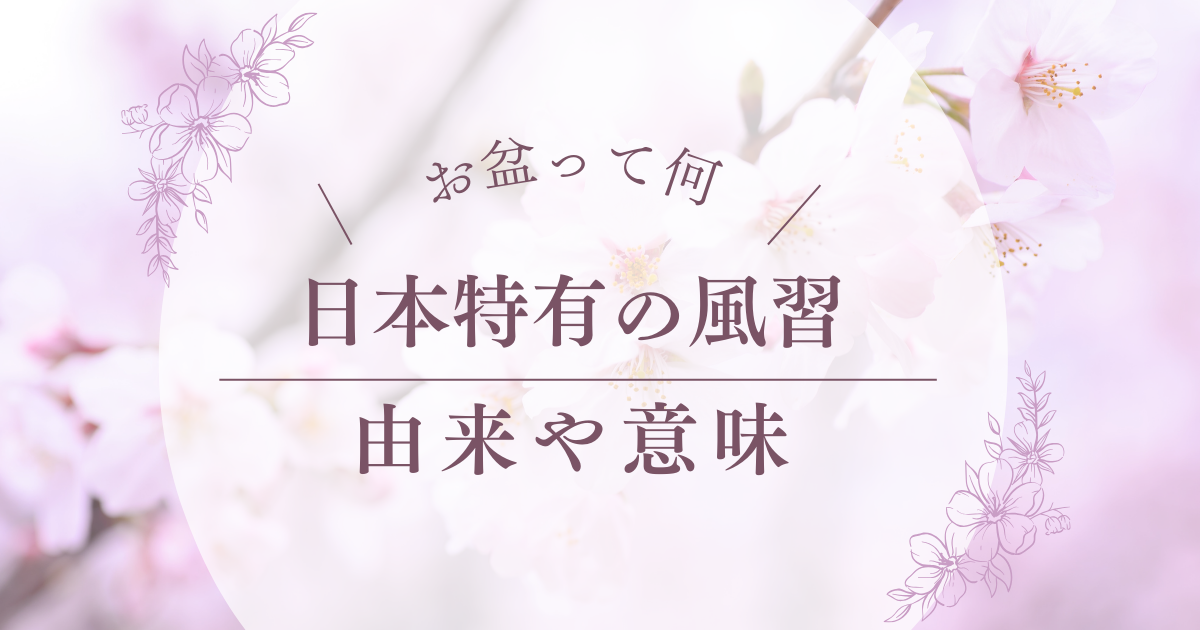日本には四季があり、年間を通して自然の様々な表情を楽しむことが出来ます。しかし近年(特に2020年以降)の日本の夏は毎日が猛暑のような状況です。高い湿度が不快で夜は寝苦しく、エアコンなしでは命の危険すら感じます。
日本の暑い夏の真っ盛り、8月になると「お盆」と呼ばれる年間行事がやってきます。しかし、私たちは意外と「お盆」の事を知らず、「仏教に関連した行事」くらいの認識な人が多いのではないでしょうか。今回は、そんな「お盆」について、由来や意味などを確認していってみます。
令和時代の「お盆」
お盆の由来などのお話をする前に、この記事が作られている「令和時代のお盆」について、イメージをまとめておきます。
宗教的な行事や風習などは時間とともに変化するもので、年月が経つと「当時どの様に考えられていたのか」が分からなくなることも多いためです。
「お盆休み」と「帰省ラッシュ」
令和時代である2020年代のお盆というと、社会人は「お盆休み」という会社の特別な休暇が与えられる期間であることも多く、その期間を夏休みのような長期休暇的な過ごし方をするのが一般的でしょう。
お盆休みは会社によって異なりますが、概ね8月の13日から15日を中心に付与されることが多いようでう。土日や有給休暇と組み合わせて長期の休暇にすることで、遠方のお墓参りや実家への帰省などを行う人も多く、この時期になると「帰省ラッシュ」という交通渋滞が発生したり、新幹線などの公共交通機関の乗車率が平時よりも高くなることが知られています。

「お墓参り」に対するイメージ
「お盆」なので「墓参りをする」という考え方の人もいれば、そもそもお墓参りをする習慣のない人もいて、それぞれが自由に過ごすというのが、令和時代の一般的なお盆のようにも感じます。こういった習慣は親の影響も強いでしょう。先祖代々お墓参りを続けている家の場合は、子は親に連れられてその習慣を学ぶことになります。
親がお墓参りをしない家に生まれると、その子もお墓参りをする習慣が定着せず、そういった人たちにとってのお盆は「ただの長期休暇」と同じでしょう。そういった人たちも、「お盆」は「お墓参りをするもの」だと漠然としたイメージはあるものです。
「お墓の風習」の広まり
お盆というと古くから続いてきている風習のように思う人も多いかもしれませんが、実際に今のように人々がお墓参りを盛んにするようになったのは、江戸時代以降と比較的最近です。江戸時代というと凄い昔のように感じるかもしれませんが、昭和初期までで2~3世代、明治まで遡っても5~6世代くらいなので、日本にある一般的なお墓やそのお参りする風習は、10世代も歴史がないことが多いでしょう。
実は歴史が浅い「弔う」風習
そもそもの話ですが、一般の人が今のように「お墓を立てて親族や先祖を弔う」ということを行い始めたのも江戸時代くらいの話なので、せいぜい200~300年くらいと歴史の短い比較的新しい習慣です。日本の歴史が2700年と言われていることから考えると、どのくらい最近の事か想像しやすいかもしれません。
元々は、一部の高貴な人や皇族などが行っていた「先祖を弔う」という風習が、江戸時代になって「ろうそく」などが大量に生産されるようになったことで一般にも広まったと言われています。一説によると、資金難だった寺社が資金調達のために広く一般にも広め、葬儀や墓所の建立を今のように仏教的に行うことを推し進めたともいわれています。
近代宗教は複雑 – 「神仏分離令」や「国家神道」など
江戸時代は儒教・仏教の教えが広められましたが、明治に入ると日本古来の宗教観と仏教を合わせた神仏習合を否定するようになります。1868年には「神仏分離令」が出され、仏教と神道を分ける政策が推し進められました。
この頃は、儒教・仏教など外来の宗教を排除し、天皇を中心とした日本古来の宗教観を大事にする「国学」や「国家神道」と呼ばれる宗教観が広まった時代でもあり、宗教的やそれに基づく人々の倫理観はとても複雑です。
「お盆」の由来
お盆に墓参りをする風習が一般的になったのは江戸時代くらいで、200年前後の歴史がある事が分かりましたが、そもそも「お盆」という行事はどこから始まったのでしょうか。基になる風習がなければ、一般の人たちに伝えられて広まることもありません。
日本で最初のお盆は推古天皇の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」
日本で最初にお盆を行ったのは、606年に推古天皇が行った「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と言われています。
盂蘭盆会というのは聞きなれない言葉ですが、元々はサンスクリット語のウランバナという言葉だったものを音訳したそうです。ウランバナの意味は「逆さ吊り」で、逆さに吊るされた先祖(母親)を救うために、供物をささげて供養すれば、極楽浄土に行けるという話から来ているとのことです。
個人的にはこの逸話には違和感があります。仏教を始めとした一般的な宗教は、「現世に生きる人を導く教え」であるはずですが、ウランバナの教えは現世にいる人に供養という行動を強制し、苦しめているようにも感じます。仏教的には、人は亡くなると仏になって極楽浄土に旅立つとされているため、遺された人も安心できる教えですが、逆さ吊りになって苦しむようなお話は現世に生きる人に対して苦痛でしかありません。
お盆の本来の意味 – 先祖を救うことで自分も救われる
盂蘭盆会の逸話は、「先祖が苦しんでいる」と考えてしまい、思い悩む現世の人々を救うという意味では、とても仏教らしい教えではあります。
現代では、亡くなった人が死後苦しんでいると考える人は少ないかもしれませんが、お盆の風習の根源は、先祖を救うことで自分も救われるという発想から来ています。
現在の「お盆」の宗教的な位置づけ
日本の宗教観は非常に独特です。仏教的な行事の中にも日本古来の宗教観が混ざってしまっていることがよくあります。これは先にも少し触れた「神仏習合」の影響も多くあります。
お盆は「宗教の混ぜ物」
仏教の浄土真宗などでは、人は極楽浄土に行って仏になった後、現世に舞い戻ったりすることはありませんが、日本のお盆のお墓参りなどでは、お墓に向かって先祖の霊に挨拶したり報告するといった風習があったりもします。この辺りは、祖霊信仰ともいわれる日本古来の先祖の霊を信じる風習が影響しているようです。
「お盆にお墓参りをする」のは仏教行事のようにも思われますが、実際には仏教と神道、その他日本古来の風習などが織り交ざった、不思議な風習と言えるでしょう。
仏教で「お墓に手を合わせる」意味
少なくとも仏教では、お墓に手を合わせてお参りをするという行動は、先祖のためではなく自分のためであり、「貴方がいない日々が辛い私をお救いください」と仏様にお願いする意味を持ちます。また、私もあなたと同じように「極楽浄土に導かれることを希望する」という意思表示でもあります。
「今年も来たよ」は仏教ではなく祖霊信仰
しかし、今のお墓参りでは、「今年も来たよ」と話しかけたり、「今年一年はこんなことがあったよ」と話しかける人も多いようです。これは仏教でも神道でもなく、先祖が霊的な何かになっていると信じる日本人古来の信仰によるものです。とても複雑ですが、現代の日本人にとってはこの「混ぜ物宗教」が一般的な社会通念と言えるほどに定着しています。
以下の記事でもこのあたりの違和感について言及していますので、興味のある方は是非ご覧ください。
宗教は自由でいい – 他人に押し付けないことが大事
「お墓参りは仏教」と考えがちですが、宗教は人それぞれです。結局のところ、仏教も神道も関係なく、自身が納得できるようにすればよいだけの事です。
ただ、他人に自分の宗教観を押し付ける事だけは避けるべきでしょう。これには当然家族も含まれます。子供の頃に、親に強制されて宗教信者にされてしまうという話は、ニュースなどで見かけることがありますが、そういった新興宗教のようなものだけでなく、仏教やキリスト教のような世界的な宗教でも同じことです。
憲法で認められた「信教の自由」
親は親、子は子で別の人間であり、日本では国民一人一人に「信教の自由」が認められています。
(日本国憲法 第20条)
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する
親がお墓参りするからといって、子もお墓参りをしなければならないものでもありません。宗教の解釈が違っていたり、他の宗教と混同してしまっていたとしても、本人が良いならそれでいいのです。
もちろん、他の宗教への敬意や配慮が足りない行動をしていた場合は、気づいた人が正してあげた方がよい場合もあるでしょう。
変化する「お墓」事情
私は人生の中であまり「お墓参り」ということをしてこなかった人間の一人です。今は宗教を学ぶことは好きですが、神様とか霊とかそういったものを全く信じていない類の人間です。
日本人の中には、神様も仏様も信じてはいないけれど、周囲に合わせて行事に参加するといった人もいるでしょう。私も典型的な日本人なので、何度かお墓参りをしたこともありますし、その都度過去の事を思い出したり、色々な事を考えたりもして、それなりに有意義だったと思います。
「お墓」は徐々に「自然葬」へと移行
今は先祖を弔うために「お墓を立てる」ということも行われなくなっているような時代です。
確かにお墓を立て続けてしまうと、日本の国土はお墓だらけになってしまうため、とてもではないですが持続可能な風習ではありません。
今は、樹木層のような「自然葬」と呼ばれる持続可能な埋葬方法が広まっていっていて、「お墓を立てる」人の割合は30%くらいまで低下しています。
不要となった「墓石」の処分問題
別の記事でも引用しましたが、日本各地で不要となった墓石の処分に窮している現状を表す以下のような光景は、さすがに目を疑いたくなります。
「気持ち」と「合理性」を追求する現代
一方で、一年の中でお墓へお参りすることがある人は60%を超えています。これは非常に興味深い傾向だと感じます。人々は昔からの風習を嫌ってお墓を立てなくなっているのではなく、先祖を大切にする気持ちを大切にしながら持続可能で合理的な方法を模索していると捉えられるからです。
特にこの令和日本では、物事の不条理や合理性の欠如を正していこうという動きはとても活発だと感じ、男女の雇用や結婚感などを含めて、「常識の変化」を日々の生活の中で感じることも多いです。
墓参りの目的やメリットについて
令和日本は本当に世知辛い世の中です。人を思いやる日本古来の風習などが次々に失われていっているようにも感じます。検索エンジンに「お墓参り」と入力すると、キーワードの候補に「目的」とか「メリット」といった言葉が表示されると、何というか「人の信心よりも合理性が重視される」時代なのだと感じずにはいられません。
私は無神論者で無宗教な人間ですが、人々は宗教から様々な道徳や倫理観を学んでいて、それらは人の社会生活において大きな役目を担っていると考えています。そういった視点から、墓参りの目的やメリットについて少しだけ考えてみます。
故人を供養して「安心する」
検索エンジンなどで墓参りの目的やメリットを調べると「供養する」と表示されることでしょう。しかし、目的やメリットを調べている人にとって、供養することは何のメリットもない事でしょう。
宗教というのは現世の人のためにこそあるものです。供養することは、当然行った人にも強力なメリットがあります。それが「安心感」です。
大事な人が亡くなって時が経つと、段々その人の事を忘れてしまいそうになってしまいます。お墓参りで供養をすることで、「貴方の事を忘れていません」と自分に言い聞かせて安心させることができます。これは、自分の中でのモヤモヤを解消するために行う重要な宗教的な儀式と言えるでしょう。
親戚や親しい人と「再会する機会を得る」
仏教の説法などで語られることもあるお話ですが、人が亡くなって仏になったことは、現世に生きる人にとっては悲しい事であり、辛い別れではありますが、故人が「親戚や親しい人と再会する機会を与えてくれた」と表現されることがあります。
お墓参りのような宗教行事で、親戚や兄弟・姉妹などと再会することもあるでしょう。これは、「故人を供養する」という行動があって初めて訪れる機会であり、亡くなられた人が与えてくれた貴重な場です。
普段疎遠になってしまっている人との再会の場として、お墓参りやお盆の帰省を利用するというのは、宗教的な合理性に富んでいて、まさに故人のおかげであり、メリットの一つと言えるでしょう。
「意味を理解しておく」ことは大事
お盆にお墓参りをする人もいれば、お墓参りはせずに自分の余暇を楽しむ人もいるでしょう。人の人生はもちろん自由で強制されるものでもないですし、何より日本は信教の自由が認められている国です。お墓参りをしないことを後ろめたく思う必要もありませんし、お墓参りしない人を非難するべきではありません。
宗教は「自分のため」にある – 個人的な見解
個人的には先祖への感謝は大切にしたいと思う人間ですが、墓参りという行動には否定的でもあります。宗教とは「先祖のため」ではなく「自分のため」にあるものという考えるからです。
墓参りをせずとも、自分は「先祖に感謝する気持ちを持っている」と自信をもっています。また、超常的な存在である祖霊を信じる宗教観は持ち合わせていないため、言葉は悪いかもしれませんが、「故人に語り掛けるという一種オカルトのような行為」には意味を見出せないのです。これは私の個人的な宗教観であり、人に押し付けたい訳ではありません。
危険な「普通」という概念
そもそも日本は古くから祖霊を信じる国で、江戸時代以降は仏教的な儀式が広まった社会なので、お盆にお墓参りして手を合わせ、故人に語り掛けるのは「普通」のことです。そういう意味では、私は普通ではないのでしょう。ただ、「普通」という概念は脆く危険なので、その行動の意味や本質をしっかり認識しておくことこそ大事だと思うのです。