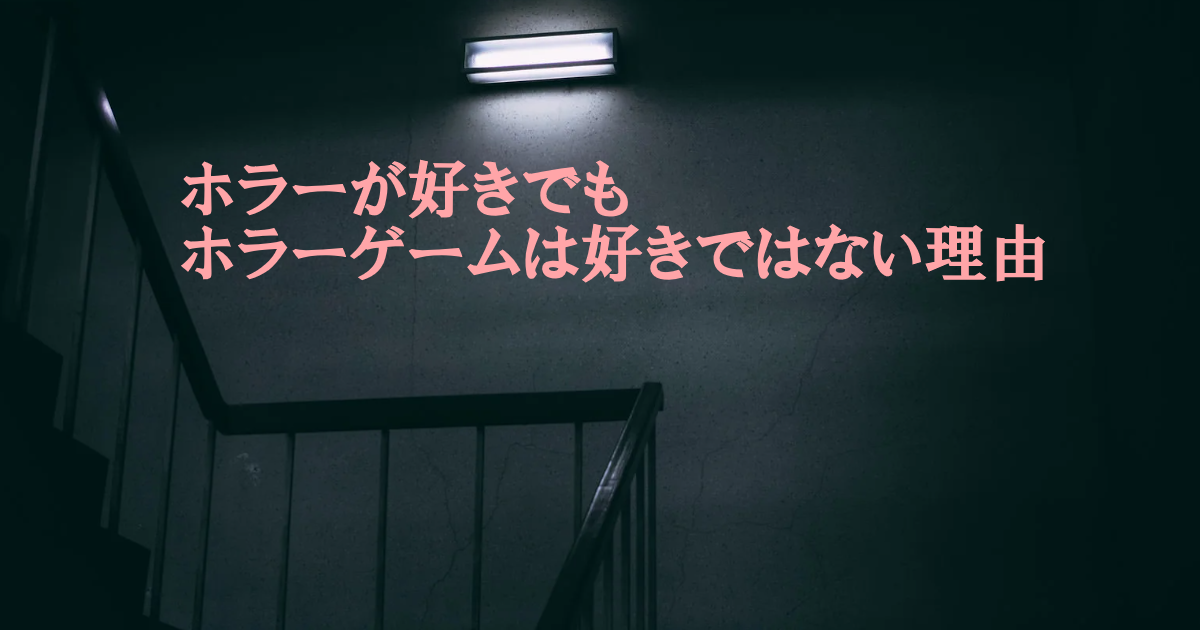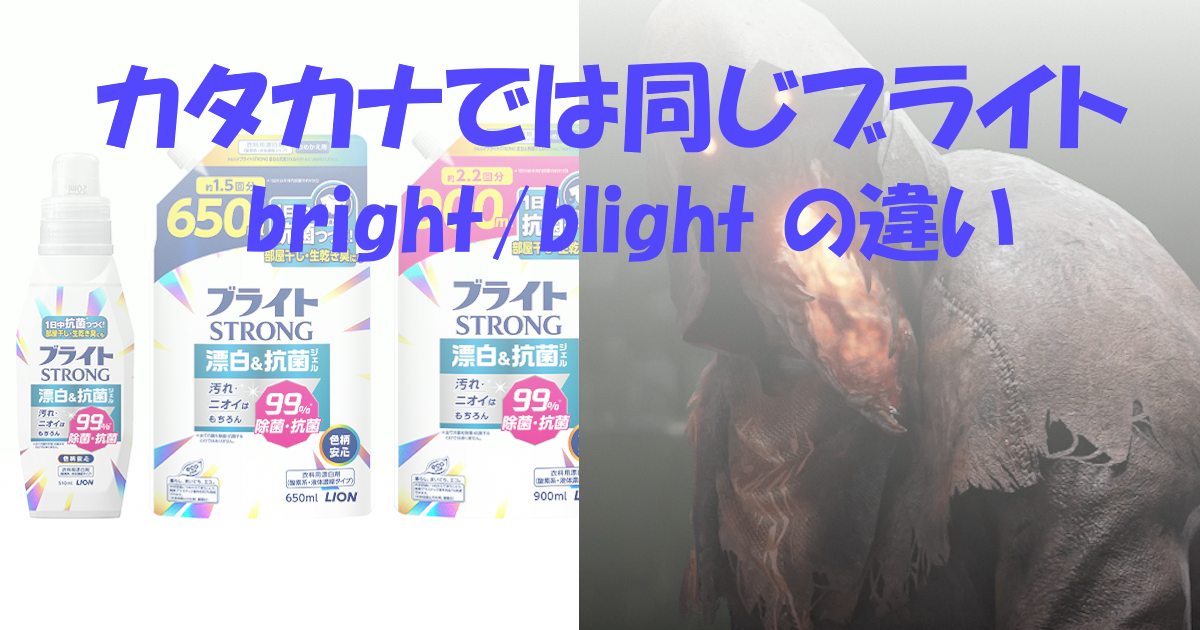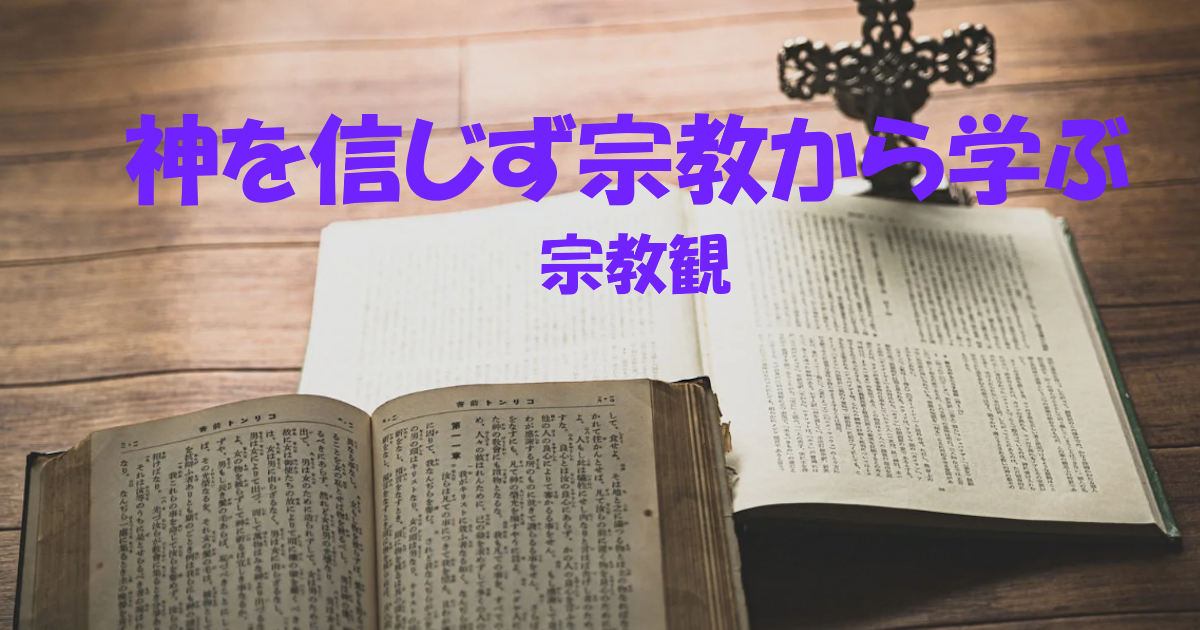最近はあまり観る機会がありませんが、私は元々映画が大好きで、特に大学生頃から20代の間くらいには、家ではDVDで映画を観て、外では映画館にちょくちょく足を運ぶくらい、日々の生活の中で映画は大きな割合を占めていました。映画をよく観ていた父の影響もあって、観るのは洋画が中心で必ず字幕で観るという習慣があり、邦画はあまり観てきませんでした。アクションやサスペンス、そしてホラーといったジャンルが好きで、ゾンビパニック映画等も好んで視聴します。
映画が好きな私ですが、ゲームも楽しみます。好きなゲームがあると、休みの日の前などは朝まで没頭してしまうくらいにはハマり症です。「ホラー映画が好きならホラーゲームも好きそう」だと言われることがありますが、一般的にホラーゲームと呼ばれるジャンルの中には好きな作品は思い浮かびません。今回は、好きなホラーゲームがないどころか、むしろ敬遠している理由について、個人的な考えをまとめて紹介してみます。
「驚き」と「恐怖」の違い – 日本語の「怖い」
最近のゲームはテクノロジーの発展に伴って、現実と見分けがつかないくらいの美しい表現ができるようになりました。人間や風景がよりリアルに描かれることで、プレイヤーはより深い没入感を得ることができます。
リアルになった世界に没入してプレイするホラーゲームは、より身近に恐怖を感じることができてとても楽しそうだと思うのですが、個人的には「俗にいうホラーゲーム」というジャンルの作品には全く興味が湧きません。
JumpScareは「怖さ」なのか
ホラーゲームのPVなど宣伝映像では、急に化け物が飛び出してきたりするシーンがあることは多いです。ストリーマーや実況者の人が、それらのシーンで分かりやすく怖がったり驚いたりしたり、その状況見た視聴者が喜んでいる様子からは、ホラーとは何なのかと考えさせられてしまいます。

日本語では、びっくりする「驚き」も、背筋が凍るような「恐怖」も、同じように「怖い」という言葉で表現されることが多いです。
ホラージャンルの映画等の演出において、急な場面変化などと共に大きな音量で視聴者を驚かせることを英語ではJumpScare(ジャンプスケアー:飛び上がる怖さ)と呼びます。特に日本のホラーゲームの「怖い」という演出には、このJumpScareが多用されているように感じています。日本語としてはどちらも「怖い」という表現になってしまうのですが、個人的には「恐さ」と「驚き」はまったく異なるものだと感じるのです。
私の場合、JumpScareには驚きはしますが、そこに「コンテンツとしての楽しさ」を感じるのは難しいのです。ホラーゲームと冠するのであれば、本当に心の底から恐怖を感じたり、目をそむけたくなるようなおぞましい光景で、トラウマになるような印象的なコンテンツが欲しいものです。そういう意味では、表現的な部分で年齢制限があっても構わないとも思います。もしかしたら本当の「怖さ」を表現すると、自然とそういった制限が必要になるのかもしれません。
近年のホラーゲームというジャンルのゲームは、そもそも「怖さ」を追求していないように思います。
「ホラーテイスト」のアクションゲーム
シリーズ化された人気の「ホラーゲーム」と称された作品の中には、シリーズを重ねるたびに徐々にホラー要素が損なわれて、最近では「ホラーテイストのカジュアルなゲーム」になっていると感じるものもあります。
人気が出たゲームや映画が「続編を出してファンに失望される」という話はよくある話ですが、ゲームの中には「内容が変化しているにも関わらず売り上げが好調」なシリーズというものも存在します。そういったゲームはある意味「進化」していると言えるのかもしれません。
しかし、進化してゲームの内容が変化しているにもかかわらず、ゲームのジャンル分けが変わることはほとんどないのが現状です。第一作目がホラーゲームであった場合、続編がアクションに重点を置いていたとしてもそれはホラーゲームなのです。そういった作品は、ホラーゲームだった時の世界観を踏襲しており、ゲーム全体を通しての雰囲気はまるでホラーゲームのように仕上がっているため、多くのファンたちはそれがホラーゲームであることを受け入れています。
しかし、ファンでもなくシリーズを追っているわけでもない一般のゲームプレイヤーからすると、そういった作品はただの「化け物と戦うホラーテイストのアクションゲーム」にしか感じないこともあるのです。
「海が怖い」と感じたゲーム – Subnautica
ホラーゲームというジャンルに失望している私でも、ゲームで恐怖心を覚えたこともあります。
そのひとつが、「Subnautica」というSteamで販売されている海洋サバイバルゲームです。
このゲームは、人はおろか登場人物や生物が死ぬこともないような平和な世界で、グロテスクな描写があるわけでもありません。私もそのゲームをプレイする際に、まさか恐怖を感じることになるなんて想像もしていませんでした。
今は製品版が発売され、さらに続編Below Zeroもリリースされている本作ですが、私がプレイした時はまだアーリーアクセスで、ゲームの結末までは描かれていない未完成状態のものでした。
製品化された後は一躍有名となって、今はYouTubeなどで多くのプレイ動画が公開されてはいますが、知らない方のために簡単に内容を紹介しておきます。
- 主人公は宇宙船から見知らぬ海洋惑星に不時着する
- 脱出ポッドを仮の拠点としてサバイバル生活する
- 海を探索しながら道具・拠点・船など文明を進化させていく
- 謎の多い海と生態系についてより深く調査していく
「海を怖い」と思う人は「プレイするのが苦痛」と感じる程に、作品全体が海の表現で染まっていて、一部陸の部分もありますが、基本的にはずっと海中です。時間の概念もあり、朝や夜もやってきます。夜の海はもちろん暗くなるので、より恐ろしく、探索するのは難しくなります。
海に感じる恐怖 – 底の見えない暗闇と生物の影
私が強烈に覚えている「恐怖を感じた場面」は、底の見えない真っ暗闇の海の深さと、その下に感じる知らない大きな生物の影を目にした瞬間です。吸い込まれて何処までも落ちていってしまいそうな暗闇にめまいがしそうなのに、そこに得体のしれない白くて大きな何かが泳いでいるのを観てしまうと、呼吸が荒くなって、本当に心の底から「進みたくない」という恐怖に駆られました。
また、同作品の中では水没している宇宙船の中を探索するといった場面があるのですが、その中でも恐怖を感じたことを覚えています。日常生活の中では、「天井は上にあって、床は下にあるもの」という感覚が染み付いていて、意識することはありません。しかし、沈没している船の中での天井は、上ではなく右や下にある事も多く、上下感覚が失われます。酸素ボンベの残量が少なくなってきて外に出たいと思った時に、この失われた上下感覚の中で上へ浮上したいという本能が働き混乱して、本当に息苦しくなってしまいます。
幸いゲームなので命を落としたとしてもセーブした場所からやり直せるのですが、現実世界で海の中の船などには絶対に入りたくないと、トラウマを植え付けられました。
結局のところ、私が怖いと感じるのは、化け物のような架空の存在などではなく、自然のような身近な所にある恐怖や恐れといった物のようです。
2025年にはシリーズの続編 – Subnautica2
紹介したSubnauticaは続編が発表されています。2024年10月に何とSubnautica2のリリースがアナウンスされました。YouTubeにてTeaser Trailerが公開されていましたので、以下に合わせて紹介しておきます。
シリーズ化することでSubnauticaからも「怖い海」が無くなってしまうのではないかと不安になりながらTeaser Trailerを視聴してみましたが、もうこの動画だけで怖いと感じてしまいます。やっぱり光の届かない暗闇の海中は、純粋に「怖い」です。まだゲームのシステムやストーリーなどは謎の部分も多いですが、前作が好きだった人は今後の動きに是非注目してみてください。
Early Access in 2025となっているので、2025年内には触り始めることができるようです。Below Zeroはかなりスピーディーにリリースされたこともありますし、早い時期にアーリーアクセスが開始されたら、Subnautica2の正規版も2025年内という可能性もありそうです。
ホラーが「幸せ」を引き立たせる
異常事態における人間の究極の状況を描いたような作品は多く、私はそれらを純粋に娯楽として楽しみます。追い詰められた人間の異常な選択に驚いたり、主人公たちの活躍に一喜一憂するという面ではアクション映画に通じるものもあるかもしれませんが、ホラーというジャンルには、コンテンツの中に恐怖という感情が含まれるかどうかの違い程度に感じています。
私はホラー映画の熱心なファンという訳ではありませんが、演出に「恐怖」の要素がないアクション映画などでは「物足りない」と感じることがあります。それは、恋愛映画で男女の関係が描かれずモヤモヤする感じや、お寿司にワサビがないという物足りなさに近いかもしれません。
恐怖があるからこそ幸せが引き立つ感覚とでもいうのでしょうか。怖い場面がある作品の方が、全体としても「面白い」と感じているように思います。
ホラー映画を嫌いな人というのは、この恐怖の演出が苦手だったり、グロテスクな表現などが苦手という人が多いのではないでしょうか。正直に言って、私は現実世界では他人の出血を目にすると、それだけで気が遠くなるのを感じるくらいのヘタレですが、映画やゲームに登場する過激なシーンを見ても、基本的には何とも思いません。特に意識しているわけではないですが、きっと心の中で非現実であると切り分けて視聴しているのでしょう。
そのせいか、強大な化け物やおぞましいゾンビのような架空の存在自体に恐怖を感じることは少なくて、それら架空の生物がとる行動だったり、人々に対して与える影響の方に恐怖を感じることがあるように思います。
特に「怖い印象」が残っている映画作品
個人的にホラー映画を視聴しても「怖かった」という印象を抱くことは少ないのですが、沢山視聴した映画の中で特に印象に残っている「怖いシーン」のある映画を思い出しながら少し紹介してみます。
以下に紹介する作品は、怖い作品を探している人の場合は既に視聴されているであろう有名作品ですし、怖い作品に興味のない人にとってはそもそも不要な情報なのかもしれませんが、参考程度に置いておきますので、もし興味があれば是非観てみてください。
冒頭のグロテスクシーンが有名な「プライベートライアン」
映画の中で残酷なシーンがあっても、私は平気で観ながら食事を楽しめます。仕事終わりにお酒と共に食事をしつつ映画を観るなんて、個人的には最高の贅沢だと思うのです。いつものように仕事を終えて帰ってから、食事をしながら映画を観はじめた時に、グロテスクな表現過ぎて流石に気持ち悪くなった衝撃のシーンがあります。
それは「プライベートライアン」という映画です。公式PVの動画を張りたかったのですが、古すぎるせいか見当たらなかったのでYouTube Movies & TVの動画となっています。ご容赦ください。
私は後で知ったのですが、どうやらこの作品は冒頭の数分間の過激な演出が有名な作品だったようです。そのことを知らずに「食事をしながら見始めて後悔した」という話を、会社の同僚などにして大笑いされたところまでがセットで記憶に焼き付けられています。
同映画は第二次世界大戦の転換期となったノルマンディー上陸作戦を背景にした戦争映画で、冒頭はその過酷な上陸の模様が描かれているため、ホラー映画顔負けの血と肉が飛び交うおぞましい映像となっています。全体を通しては、ライアンという兵士を探しながら、上陸後の戦場の中を人探ししていく任務が描かれている作品なので、戦争映画と言っても大きな戦闘が描かれているのは冒頭と終盤程度で、どちらかというと人情や家族、戦争での犠牲といった事について考えさせられる作品と言えるのではないでしょうか。
残酷すぎて目をそらす怖さ「テキサス・チェーンソー ビギニング」
ホラー映画としては、もう何年も前に観た「テキサス・チェーンソー ビギニング」という作品が印象深く、今も忘れることが出来ずにいます。登場人物が殺人鬼に襲われるという定番のシーンが印象に残っているのですが、あまりに残酷なシーンなので細かく書くことはやめておきます。
ホラーというよりもスプラッター寄りのエグイ描写に、ホラー特有の奥歯が震えるような恐怖が合わさった演出が、とにかく凄かったとだけお伝えしておきます。
本作品は、邦題「悪魔のいけにえ」として有名なホラー映画のリメイク作品で、大ヒット映画の「パールハーバー」などの映画の監督としても有名なマイケル・ベイが制作したことでも話題になりました。私はリメイク元も含め、類似したホラー映画も沢山視聴してそれぞれ楽しんでいましたが、特にビギニングの残酷シーンは本当に息をのんで目をそらすような演出が多く、心の底から「怖かった」という印象が強い映画です。
私の場合は、好んで何度も観たいと思うような映画ではないですし、この映画が好きで何度も観ているというような人は、さすがにちょっと怖いかもしれません。
テキサスチェーンソーの原題は「The Texas Chainsaw Massacre」で、私の周辺でこの話題が出た時には、その発音が「テキサスチェーンソー マサコー」と、まるで日本人女性の名前のように聞こえることから、ちょっとした笑い話になっていたことも懐かしく思います。
レザーフェイスがゲームに実装 : Dead By Daylight「カニバル」
「悪魔のいけにえ」シリーズのレザーフェイスは、最近ではDead By Daylightというゲームのカニバルとしても有名となっています。
Dead By Daylightはジャンルとしてはホラーゲームとされていますが、ホラーテイストの強いアクションゲームの部類なので、比較的万人受けしているようですが、元ネタの「テキサス・チェーンソー」シリーズは本気のホラーで、ビギニングは更にスプラッター寄りなので、ゲームが好きでもホラー耐性のない人は視聴を控えておいた方が良いかもしれません。

本サイトでは、Dead by Daylightを引き合いに出して紹介や解説をした記事が他にもあります。以下の記事は英単語の「brihgtとblight」の解説記事ですが、同作品に登場する「ブライト」というキラーがどちらで、どういった意味なのかも紹介しています。興味のある方は是非ご覧ください。
「怖さ成分」を摂取できるコンテンツ
最近はホラー映画も長らく見ていない気がするし、ホラーゲームにはまったく惹かれないため、日々の生活の中に「怖い」という要素が足りていないような気がしてきました。人生の中であまりに多くの怖いコンテンツを摂取しすぎて麻痺してしまったのかもしれませんが、そんなことがあるのでしょうか。
今回は「ホラーが好きな人でもホラーゲームを好きではないこともある」ということについて、長々と記事にまとめてきましたが、懐かしい映画やゲームの事を思い出しながら、まとめて紹介することができました。興味が湧いた方は、ある程度覚悟して挑戦してみてください。
現在流通しているホラーゲームを楽しんでいる人たちの多くは、ホラー映画などに「本当の怖さ」を追求していないのかもしれません。逆に、本当にホラーが好きな人は、ホラーゲームをしていないのではないかとさえ思ってしまいます。そういった人たちは、最近何処で「怖さ成分」を摂取しているのでしょうか。
私は怖い作品を好んで楽しんでいる人間ではありますが、同じくらい可愛いものも大好きです。私が人生の中で企画して世に送り出したゲーム作品の殆どは、特に子供や女性をターゲットにした可愛いキャラクターものばかりです。企画を制作する過程でも、怖い作品を作ろうという発想はありませんでした。怖い作品を生み出しているクリエイターの方々は、どういった心境や利益計画で製作していっているのか、興味深いところです。怖い物好きな私としては、これからも良質なホラーコンテンツが生まれ続けることを願って止みません。