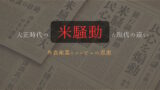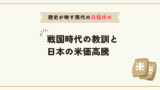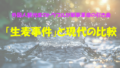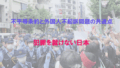2025年(令和7年)は、2024年からの米の価格高騰が続いていて、1年前と比較して倍近い値段で販売されています。(1gあたり約1円)
今回は、米の高騰と関連した歴史上の事件「大塩平八郎の乱」を振り返りながら、令和のコメ騒動といわれる現状を比較してみます。
学校の授業で習った大塩平八郎の乱がどういった事件で、なぜ起きたのかを確認すると、現代との共通点を見出したり、私たちがとるべき行動の参考になることもあるのではないでしょうか。
米価格が高騰する令和時代
令和の現代では、高騰を続けている米の価格が国民生活を圧迫しており、政府も備蓄米の放出を行うなどの対策を行っていますが、2025年の段階では期待した効果が得られておらず、1年前と比較して倍近い価格で高止まりしている状況となっています。備蓄米のほとんどをJA(農業協同組合)が落札していたことから、JAに対する不信感も高まっているようです。
政府の対応と国民の反応
日本国民の米需要は、戦後から減少を続けていたため、政府は日本の農家を守るために海外への輸出を強化したり、国内の生産量を抑えるといった活動(減反政策)を行ってきていました。しかし、米の価格で苦しんでいる国民からは、これらの政策に対する批判も聞こえてきます。特に、国内が苦しい状況にも関わらず、国外への輸出量を増やす政策が継続している政府に対しては、失望よりも怒りといった感情が見受けられます。
「米騒動」は、大正時代に起きた全国的な暴動が有名です。
以下の記事では、当時の状況を振り返り、なぜ抗議が暴動に発展したのか、現代と比較しながら解説しています。興味のある方は是非ご覧ください。
米の価格が1年で倍にまで跳ね上がっているこの状況は、何か事件が起きてもおかしくない程の異常事態といえるでしょう。歴史的にみると、日本では米の価格高騰と政治への不信によって起こった様々な事件があります。
大塩平八郎の乱とは
大塩平八郎の乱は、米の高騰に起因して江戸時代に起きた事件です。
日本では、義務教育で習う程に有名で重要な事件として扱われており、学生時代には試験対策などで覚えた人も少なくないでしょう。具体的な内容について、念のため少し確認しておきましょう。
事件の概要
大塩平八郎の乱は、江戸時代後期に起きた反乱です。餓死者が大勢出る程の酷い状態だった大阪で、人々の救済のために立ち上がり、奉行所や豪商を攻撃しました。
背景 – 大塩平八郎が行動を起こした理由
1836年(天保7年)は天保の大飢饉の最中で、米価格は高騰しており、人数は明らかになっていませんが、多くの餓死者が出る程の酷い状態であったとされています。
日本の開国は1853年のペリー来航以降なので、大塩平八郎の乱当時はまだ海外との貿易は限定的で、国内の食料は国内で生産する時代といえます。米の生産高が、生き残れる日本人の人数とも言える程に重要だったと言えるでしょう。
奉行所の人間(与力)でもあった大塩平八郎は、救済策を上申しましたが受け入れられず、豪商たちも義捐金(義援金)などの拠出を拒否しました。
大塩平八郎が蜂起を決断した背景については、以下の記事で詳しく解説しています。
幕末の志士達の行動力にも通じる「陽明学」を知ると、江戸時代の変革の原動力の理解が深まりますので、是非あわせてご覧ください。
反乱 – 実際に取った行動
1837年(天保8年)の2月19日に、自分の屋敷に火を放ち、私塾(洗心洞)の門弟らと挙兵しました。民衆も含んだ、およそ300人ほどの反乱であったとされています。
洗心洞は、与力を止めた後に大塩平八郎が開いた塾で、陽明学(儒教の一派)を教えていました。塾の名前は、「自利私欲を洗い去る」という意味から付けられ、陽明学は「知行合一(ちこうごういつ) : 言葉だけでなく行動すること」を重視します。
旗印に「救民」を掲げ、奉行所の役人と豪商を攻撃して、飢餓に苦しむ人々に米やお金を分け与えようとしました。
結果と影響 – 乱の顛末とその後の動き
大塩平八郎の乱は一日で鎮圧され、大塩平八郎と息子は自害しました。乱の処罰者は750名にも及び、重罪とされた31人は処刑されました。また、この乱によって大阪市中の約5分の1(家屋1万戸)が焼け、家を失った人も多かったようです。
この乱を受けて、幕府は天保の改革に取り組みを開始します。
また、全国各地で大塩平八郎の乱と同じような反乱(生田万の乱など)が起きており、首謀者は「大塩残党」や「大塩門弟」などと称しました。
天保の改革は、贅沢の制限(倹約令)、農村の復興(人返しの令)、物価の引き下げ(株仲間の解散など)といった内容で、米の収穫量や価格の高騰への対策といえます。同じ商品を扱う商人が共謀(株仲間)して値段を吊り上げるという当時の常識を変えることは難しく、混乱によって物価は逆に少し上がってしまったとされています。
「乱」と「変」の違い
大塩平八郎の反乱は、失敗したため「乱」と呼ばれます。成功して事態に変化が起きた場合は、乱と区別して「変」と呼ばれます。(例 : 本能寺の変)
また類似したものには「役 : えき」というものもあり、これは組織や制度上の役割として行われた場合に付けられ、これらは歴史の事象を正確に伝えるために使い分けられています。
大塩平八郎の乱と令和時代の比較
大塩平八郎の乱について、過去にNHKが特集を組んだ際には、大塩平八郎が反乱を起こした原因や当時の状況を以下のようにまとめていました。
- 役人の贈収賄
- 縁故による出世
- 重い課税
- 貧民救済の放棄
- 金持ちの贅沢な生活
これらの項目について、令和時代と比較して考えてみるとどうでしょうか。
現代の「政治とカネ」問題や財務省デモ
まず最初に、政治とカネの問題や財務省デモといった点が思いかびます。減税を求める声に対して財源論で慎重な姿勢を示したことで、政府与党である自民党は支持率を下げ続けています。
それどころか(通称)独身税の導入や退職金・交通費への課税も議論されており、大塩平八郎の乱がおきた当時の状況と似通っている部分があると言えるのではないでしょうか。
政府対応に求められる「誠実さ」
ただ米が不作で値段が高騰しているのであれば、大塩平八郎も現代の国民もそれほど大きな不満にはつながらなかったと考えることもできます。乱の背景や現代の政府への不満には、一部の政治家(役人)の不正や生活を圧迫する増税などが大きく影響しているといえるでしょう。
大塩平八郎に対策を上申された奉行所が真摯な対応していれば、乱は防げたかもしれません。現代の政府は、国民の声に対して誠実な対応ができているでしょうか。自民党への支持率が低下していることから、少なくとも有権者には評価されていない状況のようです。
令和の時代は、日本の政治に見え隠れする不審な「お金」について、国民の関心が非常に高まっている時代ともいえるでしょう。一部の政治家が、国民の税金で裕福な暮らしをしており、国民は貧困に苦しんでいるという状況であれば、国民の不満は高まるばかりでしょう。
貧民救済すらも批判される政治への不信
貧民救済については、現在の政府は対応を放棄しているようには見えません。住民税非課税世帯などの低所得者を対象とした給付金など、貧困層への支援は行われています。
しかし、この対応についても批判が多く寄せられています。
政府への信頼が低下したことで、こういった対応策についても「利権」や「キックバック」のような贈収賄が疑われていたり、そもそも国民全体の生活が苦しい状況なので、対象者を限定することへの不平等感が生まれているようです。
以下の記事では、歴史上の兵糧攻めで発生した「高直し : 米価高騰」と、令和の米価高騰を比較しながら、政府の機能や私たちの役割について再確認していますので、是非ご覧ください。
政治への関心が腐敗を抑止する
政治だけに限らず、権力というものは腐敗しやすいものです。有権者に監視をされていることが分かれば政治家は襟を正しますが、監視が無ければ人は簡単に堕落してしまうものです。政治への関心が政治の腐敗を抑制するのです。
国民生活の苦しい令和時代では、SNSなどで「現代の大塩平八郎」の登場を望む声も少なからず聞こえてきます。問題を暴力で解決するしかないと思う程に追い詰められている人もいると考えると、餓死者こそでていませんが、日本国内の状況はかなり切迫していると見られます。
政府には、少しでも国民に評価される行動を取ってほしいと願って止みません。また、有権者は次の選挙に向けて、冷静に情報を収集して備えましょう。