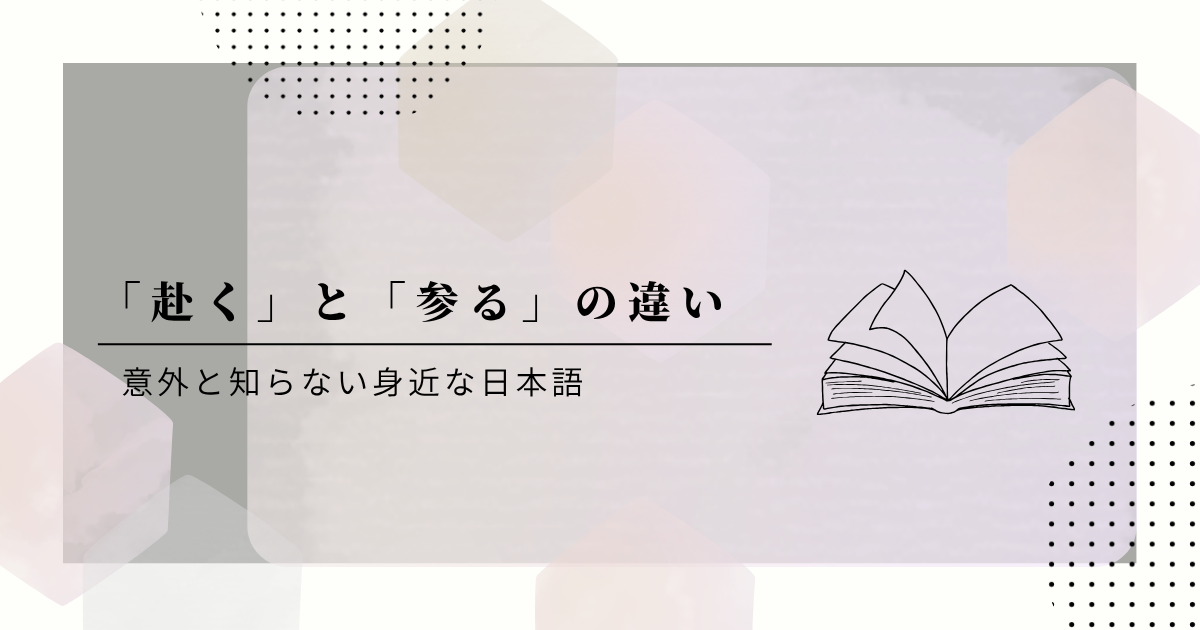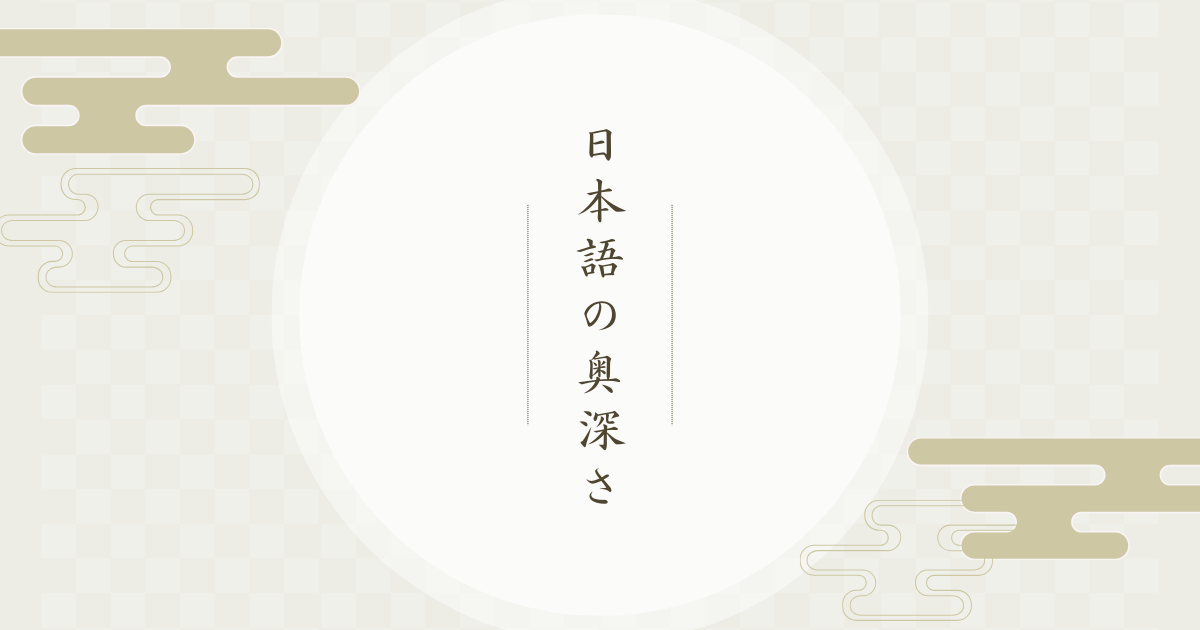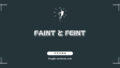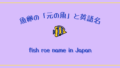日本語には「敬語表現」があるため、同じ意味でも状況によって様々な言葉が使い分けられます。今回は「行く」の敬語表現と共に「赴く」という言葉について確認した上で、英語に訳すことが難しい「伺う」と「参る」という日本語についてまとめています。
日本語の「行く」の敬語表現
日本語の言葉は、相手や状況によって様々な形に変化します。「行く」という言葉の変化について確認していってみましょう。
「行く」の敬語表現
日本語には「敬語」と呼ばれる表現があります。敬語のニュアンスは外国人には理解が難しいようで、インターネット上でもよく話題になっています。
「行く」の敬語表現には以下のようなものがあります。
| 敬語表現 | 分類 |
|---|---|
| 行かれる いらっしゃる おいでになる お越しになる | 尊敬語 |
| 伺う 参る | 謙譲語 |
| 行きます | 丁寧語 |
敬語の分類
日本語の敬語には、大きく分けて「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」の3種類があります。
- 尊敬語 : 相手を高めて敬意を表す言葉
- 謙譲語 : 相手への敬意を表すために自分をへりくだって表現する言葉
- 丁寧語 : 聞き手に敬意を表すための丁寧な言葉
日本人は日常的に使う敬語ではありますが、英語など敬語のない(表現が少ない)言語も多く、日本のコンテンツを外国語へ翻訳した場合、そのニュアンスが失われることも多いです。
「赴く」と「参る」の違い
日本語では、「行く」という意味合いで「赴く : おもむく」という表現も使われます。
「赴く」という言葉は、畏まった(かしこまった)場などで聞くことが多い言葉のため、敬語の一種だと考えてしまいがちです。
「赴く」は「改まった表現」ではありますが、言葉自体に敬意は含まれておらず、敬語ではありません。
「赴く」は、「面」が「向く」が変化して「おもむく」となった経緯があります。その方向を向くという言葉から、「行く」という意味の言葉として使われるようになりました。
「参る」という言葉が自身がへりくだって相手への敬意を表した「敬語 / 謙譲語」であるのに対し、「赴く」は形式的に改まった言い方に変わっただけの言葉であり、使う際には注意が必要です。
「行く」の敬語や「赴く」を使った例文
「行く」の敬語を使った例文をいくつか見てみましょう。
「行く」の「尊敬語」を使った例文
(軽い敬意)
明日、東京に行かれるそうです。
(丁寧な尊敬語)
お客様はどちらにおいでになりますか。
「行かれる」という表現は、日常的なビジネスシーンなどで、上司や先輩のような目上の人の行動に言及する際に、軽い敬意を含めて使われることが多いです。
一方、「おいでになる」という表現は非常に強い敬意を持った表現であり、例文のような客やゲストを丁重に扱う際など、「最大限の敬意」を表現する必要がある場合に使われます。日常会話で使うと少し堅苦しく感じるでしょう。
「行く」の「謙譲語」を使った例文
明日、御社に伺います。
明日、御社に参ります。
「伺う」と「参る」は、同じように使うことが出来る謙譲語です。ビジネスシーンなどでは、「伺う」の方が「より丁寧な」印象を与えることがあります。
以下は、どれもビジネスシーンでよく耳にする表現です。日本人であってもどれが正しい敬語表現なのか判断が難しいかもしれません。
改めて伺わせていただきます。
改めてお伺いいたします。
改めてお伺いします。
改めて伺います。
上記例文の正解(正しい敬語表現)は、最後の「改めて伺います。」だけです。
それ以外の表現は、二重敬語表現と呼ばれるものですが、実際の会話表現としては日常的に使われています。二重敬語は相手への過剰な敬語表現であり、「かえって失礼」とされる場合があります。
特に近年では、最初の例の「させていただく」を含んだ表現についてインターネット上で話題となることも多く、「不快と感じる」といった声も多くあるようです。
「赴く」を使った例文
「赴く」は敬語表現ではありませんが、ここで合わせて例文を紹介します。
戦場に赴くカメラマンは、事前の研修が必要だ。
韓国の後は中国に赴く予定だ。
どちらの例文も非常に畏まった(かしこまった)表現であり、話し言葉と言うよりも書き言葉の印象が強く、報告書などの改まった文章が必要な場面で使われることが多いです。
日本語にも「同じ意味で違う言葉 : 類義語」は多くありますが、英語にも似たように類義語が多くあります。以下の記事などで紹介していますので、興味のある方はご覧ください。
「伺う」「参る」の英訳の難しさ
日本語の「伺う」「参る」は「行く」の敬語表現でもありますが、それぞれ異なった意味も持っています。英語など他の言語に翻訳する場合には、前後の文脈などを考慮した、適切な表現となるように注意しなければなりません。
ここでは「伺う」や「参る」という言葉が持っている、「行く」の敬語以外の意味とその英訳の例を紹介します。
「伺う」の意味と英訳の例
「伺う」という日本語は、「行く」の敬語表現以外に以下のような意味合いで使われます。
| 「伺う」の意味 | 英訳の例 |
|---|---|
| 聞く | hear |
| 訪れる | visit |
| 尋ねる | ask |
意外なことに、Google翻訳など一部の和英辞書では、「伺う」は「行く : go」とは翻訳されていません。類似した表現として「訪れる : visit」が挙げられており、日本語の敬語のニュアンスを汲み取った結果とも考えられます。
「参る」の意味と英訳の例
「参る」と言う日本語の言葉は「行く」という意味でも使われますが、日常会話で多く使われるのは、神社やお墓などを「お参りする」という言葉かもしれません。
| 「参る」の意味 | 英訳の例 |
|---|---|
| 行く | go |
| 来る | come |
| 訪れる | visit |
| (神社やお墓を) 参る | visit a shrine |
「お参りする」という言葉は、「参拝する」という意味で使われていて、表現としては「参る」と「お~する」という二重敬語ではありますが、口語表現として広く使われています。
言葉の中に目的語を含んだような「お参りする」という言葉は特殊で、英語では適切な表現が存在しません。そのため上表の様に、visit a shrine(神社を訪れる)といった表現にしなければ、元の言葉のニュアンスを伝えることができないでしょう。
誤りを認める謙虚さ
正しい敬語を使うことは、日本人であっても難しい事です。また、状況によって使い分けられる言葉の細かな意味やニュアンスは、日本人でも完全に理解することは困難です。
できるだけ正しい日本語を使いたいという気持ちは大事にしたいものですが、言語というものは変化もするもので、今日正しい言葉が明日も正しいとは限りません。正しい言葉を知っていると、間違った日本語を使っている人の事が気になるものです。
間違っている言葉であっても、社会通念上「正しい」となっている言葉は受け入れてしまい、流れに身を任せるくらいの方が「気が楽」なのかもしれません。
また、間違いを指摘された際には、自分を向上させるためにも、謙虚に受け入れられる人でありたいものです。この世界には、自分が知っている事よりも、自分が知らない事の方が圧倒的に多いのです。