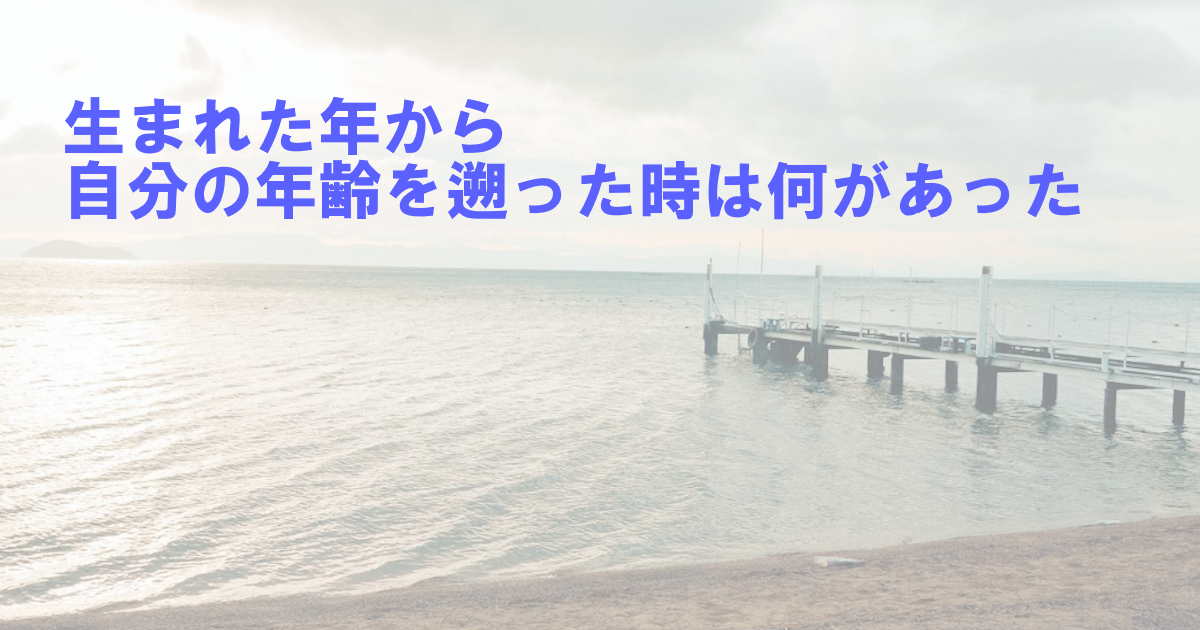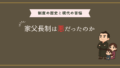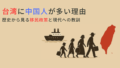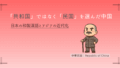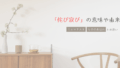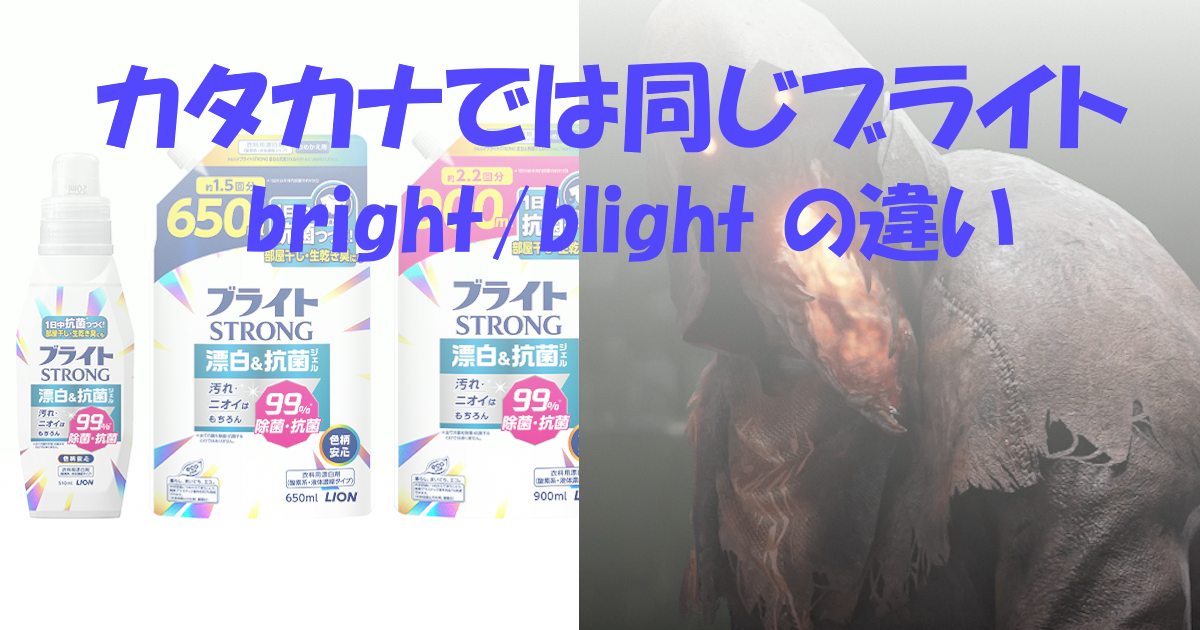40代半ばを過ぎた私は1970年代後半の生まれで、生まれたころの日本は今と違ってインターネットや携帯電話などはありませんでした。今と比べると穏やかで平和な、それなりに豊かな時代だったと思います。ちょうどバブルの時代でもあり、華やかで豪華な生活を夢見ている人が多いような、そんなキラキラした時代だったようにも思います。
最近になって、歴史を学んでいる際に「期間」や「年数」の捉え方が変わっていることに気づきました。同じ年数であっても、幼い頃には遠い昔の事と感じていたことを「短い」とか「たったの」といった風に感じてしまうのです。今回は年齢と歴史の時間認識との関係性について考えてみます。
年齢と共に変わる時間の認識
日本人であれば誰でも、義務教育過程における社会科の授業で、日本や世界の歴史を学びます。主に小学生高学年から中学生にかけて学ぶことが多いため、年齢は10代前半といったところでしょうか。私が中学生の頃には、社会科の授業は地理・歴史・公民のような分類に分けられていて、それぞれに教科書と授業があったように記憶しています。
私も他の人たちと同じように授業で歴史を学びましたが、当時は歴史にあまり興味がなく、ただテストの点数を獲得するためだけに、年号や人名を暗記していたことを記憶しています。本当にあったことである事は理解していても、本当の意味で現実世界で起きたことという認識がなく、どこか架空の世界の出来事のように感じていたようにも思います。
10歳と40歳で異なる「40年という年月」
学校で歴史を学んでいる10代の少年少女にとっては、40年という年数は非常に長く感じるものです。10代の40年は「遠い昔」の歴史ですが、40代では「たったの」と感じるようになり、人や出来事によっては最近と感じる事もあるのです。
人にもよりますが、40歳を超えていても、20年以上前に行っていた就職活動の事や、30年以上前の学生時代の出来事などを鮮明に思い出すことができる人は多いでしょう。
そんなことを考えながら、歴史を振り返って考えてみると、幼い頃には「遠い昔」の出来事と感じていた事が、驚くほど身近な事だったのだと感じてしまうのです。
令和時代に生きる40代 – 生まれる40年前は戦時
執筆時点は令和7年(2025年)になったばかりです。この時代に生きている人たちにも、必ず生まれた年というものが存在します。この時代に生きている40代や50代の人は、生まれた年が1970年代~1980年代といったところです。1975年生まれの人が2025年に50歳を迎えることになります。
年齢と共に長くなった時間の認識は、自分の年齢くらいの期間を「たったの」と短く感じるようです。50代の人にとっての50年は、自分の人生で観測した「短い期間」という事です。
40~50代の人の「生年(生まれた年)」から、短いと感じる期間の「年齢」分だけ歴史を遡って考えてみます。
| 現在の年齢 | 生年 | 年齢分遡った年 |
|---|---|---|
| 50歳 | 1975 | 1925 (大正14年) |
| 45歳 | 1980 | 1935 (昭和10年) |
| 40歳 | 1985 | 1945 (昭和20年) |
50歳の人が生まれた年(1975年)の50年前は、大正最後の年となっていることにも驚きますが、40代の人は遡ると1940年代の戦時中になっている事には一層驚かされます。
50代の人は昭和の人ではありますが、年齢と共に伸びた時間の認識によって、生年の50年前である大正は、今や「身近な事」のように感じる人もいるでしょう。
幼いころに学校で習った日本の戦争の歴史は、当時があまりにも平和で戦争とは無縁な日常だったこともあって「遠い昔」と感じていたものですが、40代となった今から考えると、当時は戦後「たったの」30年~40年しか経っていなかったのです。

歴史ドキュメンタリーなどの映像で見るような、焼け野原となってしまった日本の国土に、たったの30年という期間で豊かな国を築き上げた結果からは、日本の戦後復旧のエネルギーが尋常ではなかったことが想像できます。
戦争の歴史も日本の戦後復旧も遠い昔の歴史の出来事ではなく、自分が生まれる少し前の出来事であったことを考えると、生まれたころの父母を含めた大人達が当時どのような思いで生きていたのかとか、現在どのように日本をみているのかなど、改めて気になりはじめました。
45歳の人が生まれた年に生きていた「大人」
終戦前の生まれという事であれば80代の方も含まれますが、戦争を経験して戦後復旧に携わった人ともなると令和7年の現在では90歳を超えていることになってしまうでしょう。戦後復旧が盛んだったころを仮に1950~1960年代頃として、その頃に働き盛りの30代だった人は、1920~1930年生まれということになります。そういった人たちも、現在では95~105歳ということになります。
令和の時代に45歳の人が生まれた(1980年)ころ、そういった戦後復旧に貢献した大人たちが何歳くらいの人だったのか、考えてみることにします。
戦後復旧に貢献した人たちの年齢は以下のようになります。(条件 : 戦後復旧は1950年当時30歳が行った場合)
| 西暦 | 戦後復旧した大人 |
|---|---|
| 1920 | 0歳 |
| 1950 | 30歳 (戦後復旧当時) |
| 1980 | 60歳 (45歳の人の生年当時) |
45歳の人の生まれた年には、戦後復旧の立役者達は当時60代の人たちだったことが分かります。

実際には、親が生まれた時期が終戦前後の場合もあるでしょう。いずれにしても、父母が生まれたころの日本は焼け野原状態で、父母が物心つく頃は、当時の大人達が全力で戦後復旧に勤しんでいた結果が実り始めていた時期ということになります。そういった日本を再び立ち上がらせるのだというエネルギーに溢れた人たちが作り上げた「新しい日本」社会の中に飛び込んだのが、令和の40代の親世代ということになります。
令和の40代が生まれた頃に60代の高齢者だった人たちは、そういった何もない時代から近代的で豊かな日本を作り上げた人たちであったことを、幼い時分は知る由もありませんでした。
令和の高齢者 – 生まれる80年前は明治維新
今度は令和の40代の親世代、つまり現代の高齢者についても考えてみることにします。
令和7年(2025年)現在80代の高齢者が生まれた年と、そこから生まれた年数を遡って時代を見つめ直してみます。
| 年代 | 西暦 |
|---|---|
| 現在 (80歳) | 2025 |
| 生まれた年 | 1945 |
| 年齢分遡った年 | 1865 |
私はまだ40代の人間なので、80年という年数は非常に長く感じてしまう訳ですが、80代の人たちにとっては自分の人生の時間で、おそらく私とは異なった感じ方をするでしょう。私がそうであるように、80代の人にとっても就職活動の事や子供時代の出来事などを鮮明に思い出すことができ、それらは60年~70年も前の事なのです。

上表にまとめた結果を見ると、80代の人が生まれた年から年齢分遡ると、驚くべきことに江戸時代のしかも幕末真っただ中ということになります。
明治維新頃(幕末当時)の状況
この記事を読んでいる人の中には歴史にあまり詳しくない人もいるだろうと思いますので、参考までにその頃何があったのかをまとめてみます。
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1853 | ペリー来航 |
| 1854 | 日米和親条約 |
| 1858 | 日米修好通商条約 |
| 1865 | 80歳の人が生まれた年齢分遡った年 |
| 1867 | 王政復古の大号令 |
| 1868 | 明治元年 |
もう少し書くと、1863年から1864年の頃は薩英戦争・下関戦争が起きていて、長州・薩摩がイギリスと個別に軍事衝突したことで近代兵器の恐ろしさを味わい、尊王攘夷論から倒幕しての近代化革命へ傾倒し始めた時期です。刀を持った人が普通に歩いていた時代で、ペリー来航以降大勢来日してくるようになった外国人が多くみられるようになっていた時代でもあります。様々な文化が流入して栄えることがある一方で、外国人による治安の悪化やトラブルなども発生しており、刀を持った日本人が主君を守るために外国人を切り捨てたことで戦争にまで発展してしまったのが薩英戦争です。(生麦事件)
令和の高齢者の生まれた時代 – 家電製品のない世界
80歳の人が生まれた年から年齢分遡ると、今とはあまりにも異なる世界に辿り着いてしまいましたが、令和の高齢者の人たちの生まれた頃の段階で、既に現代とは大きく生活環境が異なっていたことを忘れてはいけません。
当時は、電気は辛うじてあるものの家電製品はほとんどない時代で、ようやく大人になったころに「昭和の三種の神器」と言われる洗濯機・冷蔵庫・テレビなどが普及し始めています。冷蔵庫のない時代に生きたことが無い人間としては、「どうやってご飯食べてたのか」すら想像することが難しいでしょう。
この世代の人にとっては、親は大正時代の生まれで、祖父母は明治の人という世代です。令和の40代にとって江戸時代は遠い歴史の事と感じますが、令和の高齢者にとっては幕末は意外と身近に感じられているのかもしれません。
ペリー来航から「15年」で政府を武力制圧した明治維新
少し余談ではありますが、15年という歳月は40代からすると「短い」と感じる年数です。
上で少し触れた幕末の時代は、ペリー来航以降急速に時代が変化していった時期です。幼いころは単純に年号と出来事を覚えただけで意識したことはありませんでしたが、ペリー来航から明治時代に突入するまでの期間はたったの15年しかないことを改めて考えると、時代の変化が如何に急速であったかを思い知らされます。(1853年~1868年)
政府のやり方に反対し、外国勢力の強大な軍事力に恐怖し、政府を武力で打倒してでも生き残る道を見出さなければと決心して行動して成し遂げるまで、かかった時間が15年。この期間で国を作り替えた明治維新という革命は、あまりに準備や実行にかかっている期間が短いように思えてなりません。
学校教育の影響か、ペリーという人がいい人だったのではないかと考えてしまう人もいるようで、私も驚いたことがあります。このあたりの歴史については、以下の記事でもう少し詳しくまとめてありますので、興味のある方はご覧ください。
人の中にある歴史に学ぶ
私は何度も記事に書いてきていますが、儒教的的な思想に嫌悪感があり、年齢の多寡だけで人物の優劣が決められるべきではないと思っていますし、重要な役職は、年齢も性別も関係なくただ能力が優れた優秀な人がやるべきだと思っています。
そんな私は、今回の記事をまとめながら、年長者への敬意について改めて気を付けなければならないと思いました。
自分より年長者の人が体験してきた日々は、間違いなく自分よりも長い期間があり、その日々の中には歴史的に見て貴重で重要な情報が多く含まれているのです。今の私たちの世代はコンピューターやインターネットなどのテクノロジーによって、こうしてデジタルの形で情報を記録して構成に遺していくことが容易にできるようになっています。しかし、現在の高齢者や後期高齢者といった人たちの時代にはそういったものが無かった時代で、情報を残すためには本を執筆するくらいしかなかったのです。
謙虚に学び、恵まれた現代に感謝
年齢に依らず、人が体験してきた様々な経験は、それ自体も一つの歴史の一頁であり、他にも類似した例がある事柄があったとしても完全に一致することはありえず、私たちはその一つ一つの話からも学べるものがあるのです。長い時間を生きてきた年長者には、それだけ長い歴史が刻まれており、そこから学べることも多いでしょう。
組織の運営や役職という話とは別に、その人が経験してきた様々な人生の出来事には敬意と興味を持って、学ぶ姿勢で相対することができれば、人間関係の構築だけでなく自身の知識や能力の向上にもきっと良い効果があるでしょう。

年長者たちが体験した貴重な日々を知ると、昭和から令和にかけての異常なまでの社会の変化のありように改めて驚き、こういった変化が後の世の中においてどのように語られることになるのかワクワクしてしまうのです。たった数十年という年数で、ファミコンがネット・スマホゲームへと変化してきましたが、それよりも前の世代はそもそも水くみとか薪拾い、かまどで炊飯といったことに追われ、今ほど遊ぶ時間がなかった時代なのです。
そんなことを考えると、自分が生きる現代の豊かさ便利さに感謝し、恵まれた環境に生まれることができて良かったと思わずにはいられません。