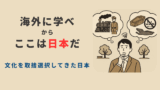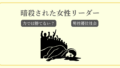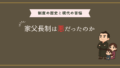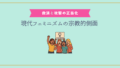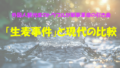「もののあはれ」とは、日本文化を代表する美的理念のひとつです。しみじみとした情緒を表す言葉として知られていますが、本居宣長が説いたその本質を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。なお、現代仮名遣いでは「もののあわれ」とも表記されますが、本記事では本来の表記である「もののあはれ」を用います。
本記事では、江戸時代に生まれたこの思想の意味や背景を解説し、さらに現代にも通じる感性としての意義を考えます。
「もののあはれ」とは何か
日本の文化や美意識を語るうえで欠かせない言葉の一つに「もののあはれ」があります。しかし、その意味を正しく理解している人は少なく、単に「しみじみとした感情」とだけ捉えられてしまうことも少なくありません。
ここでは「もののあはれ」とは何かを、わかりやすくかみ砕きながらその核心に迫ってみましょう。
「もののあはれ」の意味:本居宣長の定義
江戸時代中期の国学者・本居宣長は、『源氏物語玉の小櫛』において「もののあはれ」という概念を強調しました。
それは、目の前の出来事や人の感情の移ろいに素直に心を動かされる感性のことを指します。
論理や理屈ではなく、自然な心の反応を受け止める姿勢が大切だと説かれました。
あはれの語源
「あはれ」という言葉自体は、もともと平安時代の文学でよく用いられていました。語源的には、感動や驚きを表す感嘆詞「あは」に、名詞化の接尾語「れ」が付いたものとされます。
もともとは「わあ!」といった感嘆の響きに近く、そこから「心を動かされること」「しみじみとした感情」を表す言葉へと発展しました。
宣長が用いた「もののあはれ」は、この古くからの言葉を理論的に整理し、日本文化を象徴する美的理念へと高めたものといえます。
哲学的な背景
当時の思想界では、儒教が重んじる「理」や仏教が説く「無常」が主流でした。しかし本居宣長は、これら外来の思想が日本人の心を縛っていると批判し、日本古来の感性を重視すべきだと主張しました。
その中で宣長は「感情」を積極的に肯定し、人生の豊かさは涙や喜びといった心の動きにこそあると説いたのです。
こうした姿勢は、合理性を重んじる西洋哲学とも異なり、日本独自の感性として注目されます。
国学と「もののあはれ」
「もののあはれ」の思想は、江戸時代の学問的潮流である国学の中から生まれました。
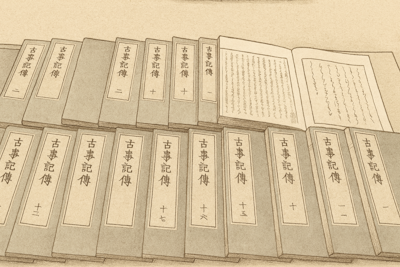
江戸中期の国学の台頭
本居宣長は先人である賀茂真淵の教えを受け、古典を研究しました。特に『古事記伝』や和歌研究を通じて、中国思想からの独立を模索し、日本固有の感性を取り戻そうとしました。
その中で「もののあはれ」が重要な理念として形づくられたのです。
国学思想における位置づけ
荻生徂徠や真淵が理論や古典文法に焦点を当てたのに対し、宣長は「情緒」そのものに光を当てました。この姿勢が、後の文学研究や日本文化論に大きな影響を与えていきます。
関連記事:国学から帝国主義へ
本居宣長が古典を研究し、『古事記』を解読したことは、「日本民族とは何か」「天皇とは何か」といった問いを明らかにする大きな契機となりました。
こうした国学思想は、その後の尊王攘夷運動へと受け継がれ、最終的には明治維新から大東亜戦争に至るまで、日本の政治思想に大きな影響を与えています。
宣長自身が帝国主義を唱えたわけではありませんが、その思想の流れが後世で利用されていったことは否定できません。
詳しくは以下の記事で解説していますので、関心のある方はぜひご覧ください。
💡関連記事:本居宣長の思想と大東亜戦争の奇妙な繋がり
現代人が「もののあはれ」を知らない理由:排除された「国学」
私たち現代人は、「国学」という学問を学校教育で学ぶ機会がありません。しかし戦前の日本では、国学の思想を取り入れた「修身」や「国語」「歴史」の授業を通じて、天皇中心の歴史観や古典尊重の精神が子どもたちに教え込まれていました。実際に、当時の小学生が歴代天皇の名前を順に暗唱させられていたという証言も残っています。
敗戦後、GHQは「神道指令」を出し、国家神道と教育の分離を徹底しました。その過程で、国学に由来する思想や日本神話、天皇中心の歴史観は学校教育から排除されました。
このため、戦後の日本人は「日本の創世神話」や「もののあはれ」といった国学的な美意識に触れる機会をほとんど失い、一般的な知識としては次第に忘れられていったのです。
国学や修身の教育は、ときに「正義」の名のもとで暴力を正当化する大義名分として利用されることもありました。以下の記事では、幕末の桜田門外の変における「天誅」、そして昭和の二・二六事件で叫ばれた「尊王斬奸」について、その思想的な源泉や違い・共通点を解説しています。興味のある方はぜひご覧ください。
💡関連記事:天誅と尊王斬奸の違いと共通点 ― 歴史に見る政治テロの思想
他の美意識との比較
「もののあはれ」は、同じく日本文化を代表する「侘び寂び」と混同されがちです。
違いを整理してみましょう。
「もののあはれ」と「侘び寂び」
「侘び寂び」は、茶道や禅の思想を背景とした「簡素さ」「不完全さ」の美を指します。一方で「もののあはれ」は、文学や日常に宿る「感情の動き」そのものを大切にします。
それぞれを一言で表すと以下のようになります。
- 侘び:不完全・不足の中に心の豊かさを見いだす美意識
- 寂び:古びたものや静けさの中に趣を感じる美意識
- 侘び寂び:簡素で不完全、時間の経過を帯びたものに深い味わいを求める美意識
- もののあはれ:人や自然の移ろいに触れて、しみじみと心が動かされる感覚
「もののあはれ」と「侘び寂び」の違い
侘び寂びは、茶の湯や禅の世界に根づいた「感覚的に美を感じる心」を大切にする美意識です。
これに対して、もののあはれは単なる感覚にとどまらず、本居宣長によって言葉にされ、哲学的に整理された点が大きな違いです。
つまり、侘び寂びが無自覚的な美意識であるのに対し、もののあはれはそれを理念として体系化したものといえます。
補足:「侘び寂び」と「もののあはれ」の異なるルーツ
また、「侘び寂び」と「もののあはれ」は「同じ日本的な美意識」という点で並べて語られることが多いものの、直接的に一方から他方が生まれたわけではなく、それぞれ独自のルーツを持ちます。
- 侘び寂び
中世の禅思想や茶道の文化を背景に育まれた美意識であり、日常生活の中に簡素さや古びた味わいを見いだす感覚から発展しました。 - もののあはれ
平安文学に多く見られた「しみじみとした感情表現」を源とし、それを江戸時代の本居宣長が理論として整理したことで確立した美的理念です。
コラム:外国人が知っていた「もののあはれ」
ここで少し視点を変えて、私自身が驚いた体験をご紹介します。
忘れかけていた文化を外国人に気づかされた瞬間
「もののあはれ」を語っていたのは、VSPO(ぶいすぽっ!) EN(English)に所属している美暮ナリン(Narin Mikure)さんという方です。
日本の「儚い」という表現が好きという話から、「もののあはれ」が語られています。

動画:日本語字幕付き YouTube切り抜き (該当箇所8:10)
引用チャンネル:【和訳】ぶいすぽエントランス VSPO!ENTRANS【ぶいすぽ切り抜き】
日本人も忘れかけている美的理念である「もののあはれ」を外国人の方が知っているということは私に衝撃を与え、またそれと同時に自国の文化や歴史の理解が曖昧な自分を恥ずかしく感じたのです。
美暮ナリン(Narin Mikure)さんについて
美暮ナリン(Narin Mikure)さんはVSPO所属のVirtual YouTuberです。EN(English)部門の一人で普段は英語で話されていますが、韓国語や少しの日本語なども話されるようです。
彼女に興味のある方は、是非YouTube Channelを訪れて配信などをご覧ください。
YouTubeチャンネル: 美暮ナリン(Narin Mikure) – YouTube Channel
「もののあはれ」の英語表現
動画内で彼女は、「もののあはれ」の事を英語の“pathos”に近い概念として説明しています。
I think it’s like the pathos of thing or something…
物事の哀愁みたいなものだったと思うけど…
英語の“pathos”は「悲哀」や「情感」を意味するため、大きくは外れていないと言えるでしょう。
英語の pathos は、ギリシャ語由来の言葉で、発音は /ˈpeɪ.θɒs/(ペイソス/ペイサスに近い音)とされます。意味は「悲哀」「情感」「人の心を揺さぶる力」などで、特に文学や修辞学では「感情に訴える要素」として用いられます。
英語の pathos という単語は、辞書では「特に憐みや悲しみ:pity or sorrow」と解説されることが多く、「もののあはれ」の説明としては一面的すぎると言えます。英語に一語で完全に対応する言葉は存在しませんが、pathos の他には以下のような単語が考えられます。
| 英単語 | 発音 | 主な意味・ニュアンス | 「もののあはれ」との近さ |
|---|---|---|---|
| pathos | /ˈpeɪ.θɒs/ | 悲哀、情感、憐み | 「悲しみ」に寄りすぎるが一般的に最もよく引き合いに出される |
| poignancy | /ˈpɔɪ.njən.si/ | 胸を打つ切なさ、しみじみとした感動 | 「心が揺さぶられる感覚」に近いニュアンスを持つ |
| sentiment | /ˈsen.tɪ.mənt/ | 感傷、情緒、感情の傾向 | 幅広くカバーできるが抽象的で深みは弱い |
それぞれ部分的には「もののあはれ」を説明し得ますが、どの語もその全体を言い尽くすわけではありません。むしろ、この多義性こそが「もののあはれ」という日本独自の美的理念の特徴だと言えるでしょう。
現代に生きる「もののあはれ」
古典的な概念に見える「もののあはれ」ですが、現代社会にも通じています。SNSでの共感文化や、アニメや小説で描かれる切なさに心を動かされる経験は、まさに「もののあはれ」の延長線上にあると言えるでしょう。
こうして見ていくと、「もののあはれ」は過去の美意識にとどまらず、現代人の心にも深く息づいていることが分かります。
「日本人らしさ」を考えさせられる現代
近年は外国文化との共生について、推進と反対がよく議論されており、そんな中では「日本人らしさ」とは何かを考えさせられる日も増えました。
以下の記事では、歴史の中で日本が外国から学び、そして外国を拒絶することで発展した文化などをまとめていますので、興味のある方は是非ご覧ください。