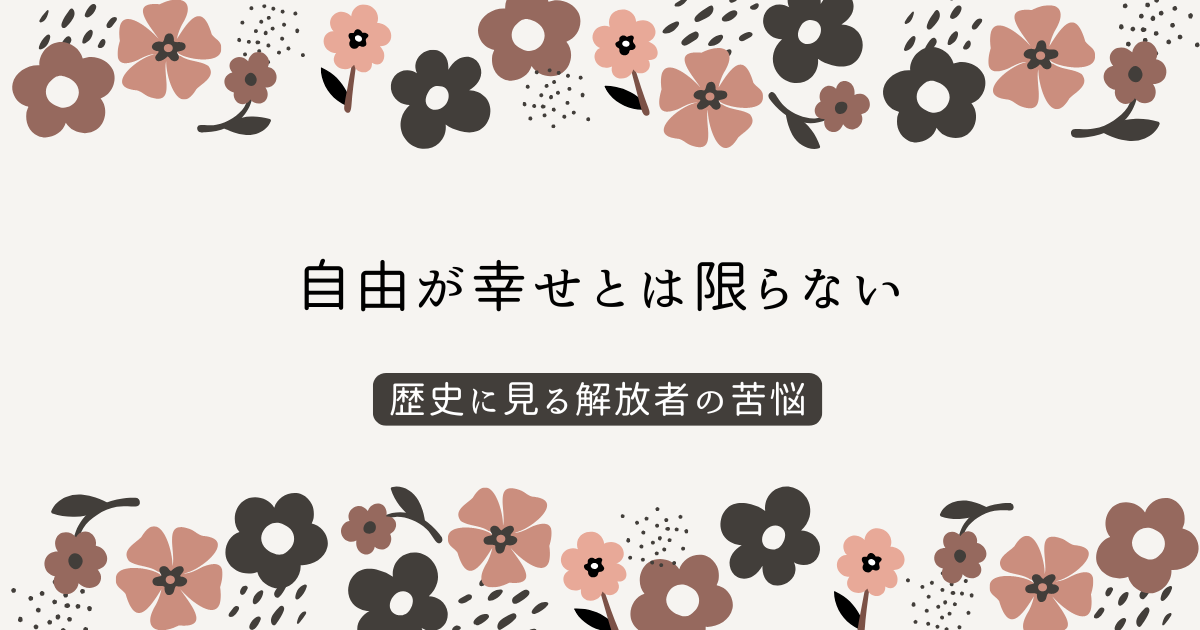「自由になりたい」。
それは多くの人にとって本能的な願いのように思えます。
しかし、歴史を振り返ると、自由を手にした瞬間に幸福を失った人々が少なからず存在します。
古代ローマの解放奴隷たち
古代ローマには、奴隷を解放する「マヌミッシオ」という制度がありました。忠誠心や功績、あるいはお金を払うことで、奴隷は自由を手に入れることができたのです。
しかし、自由は同時に「庇護の喪失」を意味しました。主人のもとでは理不尽ながらも衣食住が保証され、身の安全もある程度守られていたのに、解放された瞬間、競争社会の中で孤立無援となる元奴隷も少なくありません。中には、恨みや嫉妬の対象となり、命を落とす者さえいたと伝えられています。
「自由」とは、選択肢が増える一方で、背負う責任も増えるということ。その現実は、古代ローマでもすでに示されていました。
南北戦争後のアメリカ:自由と差別のはざまで
19世紀のアメリカ南北戦争後、奴隷制は廃止され、多くの黒人が法的な自由を手に入れました。しかし、そこには想像を超える困難が待っていました。
教育や財産を持たないまま社会に放り出され、多くは極度の貧困に苦しみました。さらに、ジム・クロウ法などの差別政策や白人至上主義団体の暴力が彼らを追い詰め、解放の喜びは恐怖と不安にかき消されてしまったのです。
それでも、奴隷制に戻りたいと語る人はほとんどいませんでした。自由には苦難が伴っても、人間としての尊厳を取り戻す価値があったからです。
現代の女性たちの選択
現代の日本でも「自由」と「幸福」の関係に揺れる人々がいます。
女性の社会進出は、フェミニズム運動の成果として権利を広げ、キャリアも自己実現も選べる時代を作りました。しかし、その自由は、育児・家事の負担や社会的期待といった別の重荷を生むことにもつながりました。
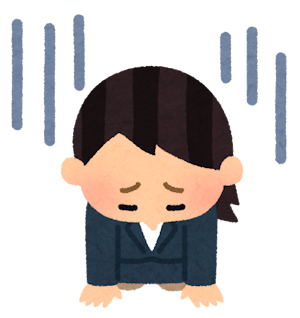
SNSなどでは、専業主婦を希望する女性への批判的な声や、「女性の社会進出」を否定して昔の「家に入る」価値観が良かったという女性の意見さえあるようです。先人たちが勝ち取ってきた女性の自由と権利を否定するようなその意見には、同じ女性からも批判があがっています。
自由と権利には、同時に責任もついてきます。自分で人生を決め、自分で歩んでいくことは、決して楽な道ではないのです。
自由は幸福の保証書ではない
古代ローマの解放奴隷、南北戦争後の元奴隷たち、そして現代の私たち――時代も場所も違う人々の経験には、共通のテーマがあります。
それは「自由は権利として絶対的な価値があるが、幸福とは別問題だ」ということ。自由は選択肢を増やしますが、その分、責任や不安、競争も増やします。
だからといって、昔の庇護や束縛に戻るのが解決策とは限りません。
私たちは「安心と自由の両立」という理想を求め続けていますが、それは簡単には実現しない課題です。親子関係のような無償の庇護以外では、どこかで取捨選択が必要になるのかもしれません。
男性と女性の幸福度
日本は「男性より女性の幸福度が高い国」です。ジェンダーギャップ指数が低いのにと驚く人もいるかもしれませんが、これは発展途上国など男女平等が進んでいない国の傾向でもあります。
男女平等が進んで女性の権利が向上すると、必然的に女性の責任も増えることになります。そのため、女性の幸福度は低くなり、代わりに男性は高くなるという現象が、先進国を中心に多くの国や地域で見られます。
男女は平等であるべきでしょう。女性の権利を向上することは社会の必然です。
しかしそれは、女性に無条件の幸福を保証するものではないのです。
幸福とは何なのか
幸福は人によって異なるものです。
近年SNS等では、自分の幸福を人に当てはめて勝手に判断し、価値観を押し付けるという光景もよく見かけます。中には自分の価値観で相手を蔑んだり、哀れんだりする人もいるようです。
他人を幸せにしたいと思う優しい人もいるでしょう。でもそれが本当に相手の幸せの助けになっているのかは、その相手にしか分からないのです。
ある程度束縛されたとしても、平穏な生活が手に入るなら悪くないかも。
そう思うことがありませんか?