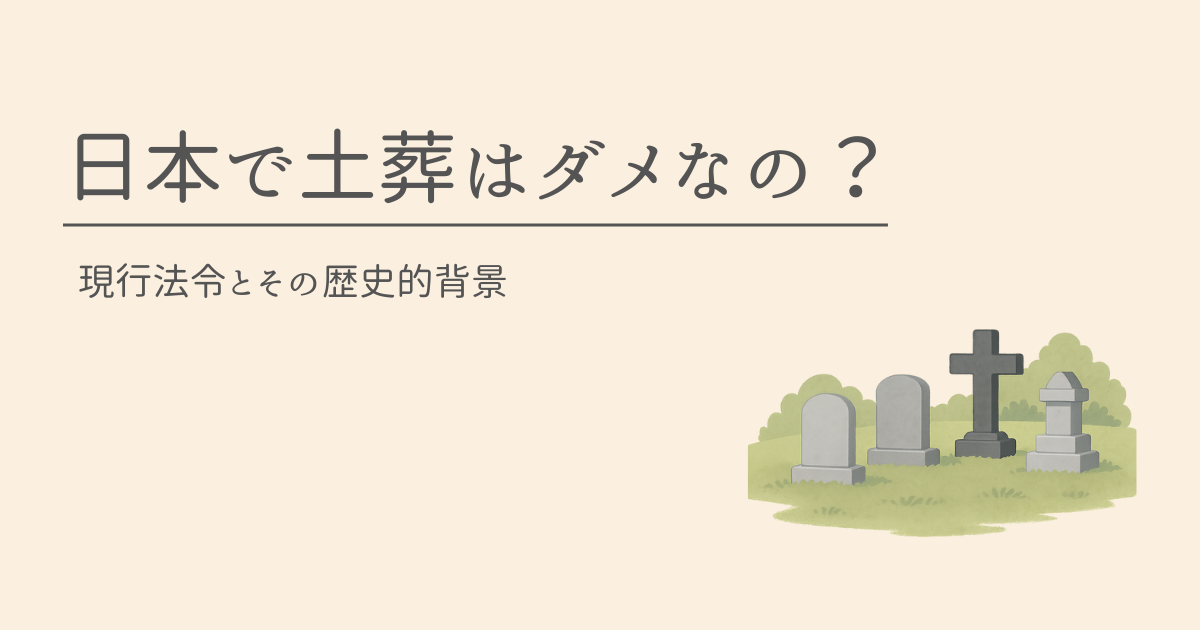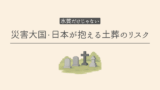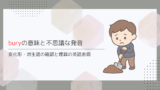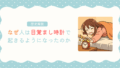「日本では土葬は禁止されていて、火葬しなければならない」
こうした言葉をSNSやネット掲示板で見かけることがあります。
実際、イスラム教徒やユダヤ教徒など土葬を宗教的義務とする人々の話題になると、「日本のやり方に従え」「火葬できないなら帰国すべきだ」という意見が出ることもあります。
しかし、日本の法律は土葬を禁止していません。
火葬が主流になったのは、明治期の衛生思想や都市化といった社会背景によるもので、制度的には今も土葬は可能です。
本記事では、土葬と火葬の歴史や法律、そして現代の状況を整理し、「なぜ火葬が当たり前になったのか」「土葬は本当に危険なのか」をわかりやすく解説します。正しい知識を持つことが、多文化共生や社会の健全な議論に役立つはずです。
日本の法律で土葬は本当に禁止されている?
まずは、現行法の条文を確認しましょう。
「墓地、埋葬等に関する法律」とは
1948年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」では、第3条にこうあります。
死体の埋葬または火葬は、市町村長の許可を受けなければならない。
ここには「火葬が義務」という言葉は一切なく、土葬も火葬も法的には選択可能であることがわかります。
禁止されているのは「許可なしでの埋葬や火葬」であって、土葬そのものではありません。
実務上は火葬が「当たり前」
とはいえ、現代の日本では火葬がほぼ100%の割合で行われています。行政手続きや葬儀業界の運用も火葬を前提に整備されており、土葬に対応できる自治体や霊園はごくわずかです。
この実態が「土葬禁止」という誤解を広めているのです。
日本における土葬と火葬の歴史
法律だけでなく、歴史をたどると火葬が定着した背景が見えてきます。
古代から江戸時代までの埋葬文化
古墳時代には土葬が主流で、古墳そのものがその証です。仏教伝来以降は火葬の文化も広まり、平安時代には貴族や高僧など限られた階層で火葬が一般化しましたが、庶民は江戸時代までほとんど土葬を続けていました。
江戸の町には土葬の墓地が至るところにあり、今も都心の寺院には江戸時代の土葬墓が残っています。
明治期のコレラ流行と衛生思想
火葬が一気に広がったきっかけは、明治期のコレラ流行です。当時の衛生学の知見では、土葬は感染症の原因になりやすいと考えられていました。
このため、明治政府は火葬を推奨し、都市部では火葬場が次々と整備されました。
コレラ対策としての火葬の効果
コレラ菌は糞口感染(飲料水や食物の汚染)が主な経路で、遺体そのものよりも汚染された水源が感染の原因でした。
しかし明治初期(19世紀後半)の日本では細菌学がまだ浸透しておらず、「悪臭や瘴気(ミアズマ)」が病気の原因と考えられていました。土葬は遺体の腐敗臭を出しやすく、感染症の拡散源とみなされたため、火葬が推奨されたのです。
コレラの流行が沈静化した主な要因は、上下水道インフラの整備や衛生環境の改善でした。
火葬による効果は限定的でしたが、当時の井戸や川の水を生活用水として使う環境では、遺体の管理が不適切であれば水源汚染の危険性は確かにありました。そのため、「火葬=感染防止」という考え方は完全な誤解ではなく、火葬の奨励は結果的に衛生観念の向上を促し、感染拡大を防ぐ一助になったと評価できます。
戦後の都市化と土地不足
戦後になると、都市部の人口集中や墓地の土地不足が深刻になりました。火葬は衛生面でも土地の効率利用の面でも有利だったため、全国的に火葬が標準化され、現在では火葬率が99.9%を超える世界でも珍しい国となっています。
日本の近代的なインフラ(電気・水道・ガス)などは、昔からあるようで実はそれほど歴史が長くありません。
SNSなどでは「女性だけの街」の話でよく聞く「インフラ」ですが、以下の記事でどのように整備されていったのかをまとめています。興味のある方は是非ご覧ください。
💡関連記事:「女性だけの街」から考える明治時代 – 近代インフラ整備の歴史
現在の土葬の現実
では、2025年の日本で土葬はどうすればできるのでしょうか?
土葬が可能な墓地の例
日本国内でも、宗教や文化的背景に配慮した土葬専用区画を持つ霊園があります。
たとえば山梨県北杜市の「日本ムスリム協会墓地」は、国内で数少ないイスラム教徒専用の土葬区画として知られています。ほかにも一部の民間霊園や地方自治体で、条件付きで土葬が認められるケースがあります。
手続きや条件
土葬を行うには、まず埋葬先の墓地を確保し、市町村に許可申請を出す必要があります。
ただし、墓地が限られていることや、衛生面・土地利用の制約があるため、手続きや費用のハードルは高いのが現実です。
土葬による感染症のリスク
現代の科学的知見では、適切な衛生管理のもとで行われる土葬は、感染症拡大のリスクが極めて低いとされています。世界保健機関(WHO)は、遺体を地表から1.5〜2メートル以上の深さに埋葬し、水源から十分な距離を確保することを安全基準として示しています。
多くの国ではこのガイドラインを基に墓地の設計や管理が行われており、飲料水や生活環境への影響はほとんどありません。
ただし、この評価は上下水道や衛生インフラが整備されていることが前提です。
井戸水や川の水をそのまま生活用水として利用する地域では、遺体の管理や埋葬が不適切な場合、細菌やウイルスが地下水を通じて広がる危険性があります。実際、19世紀の日本やヨーロッパでは、衛生設備の不備や高い地下水位により、土葬墓地が水源汚染の原因になると考えられてきました。
現代の日本でも、島しょ部や山間部など一部の地域では上下水道が未整備な場合があり、そのような環境では土葬が感染症リスクを伴う可能性があります。
したがって、土葬の安全性は地域のインフラ状況や衛生管理の徹底に左右されるといえるでしょう。
誤解を生む理由
火葬が当たり前になったことで、「土葬は違法」という誤解が生まれやすくなっています。
行政運用の慣習
日本の行政手続きや葬儀業界は火葬を前提に整備されているため、土葬のノウハウを持つ職員や葬儀業者は非常に少なくなっています。このため、役所や葬儀社で「土葬はできません」と言われることもあり、誤解が強まっているのです。
ネット上の誤解
SNSや掲示板では「日本は火葬義務」といった情報が事実のように拡散されます。しかし、これは都市部での慣習を全国一律の法律と誤解しているケースが多いと考えられます。
宗教・多文化共生の視点
イスラム教徒やユダヤ教徒など、土葬が宗教的義務となっている人々が日本でも生活しています。
多文化社会における土葬の意義
外国人労働者や移民が増える中で、埋葬の多様性は重要なテーマです。
日本の国土で土葬が行われることに嫌悪感を抱く人もいるでしょう。しかし、日本の法律では土葬が認められているという事実は、今後の共生社会を考える上で知っておくべき知識です。間違った知識で不当に非難するべきではないでしょう。
本記事では多文化共生の是非は述べません。ただ私たちは、正しい知識を持って議論を深め、正当な手続きで法整備を進めていくべきだと思うのです。
ただ一点、大前提として日本と世界には大きな違いがある事に留意する必要があります。
それが「遺体」に対する価値観の違いです。日本では、「遺体」に対する恐怖感情が強くありますが、世界はそうではありません。
以下の記事では、日本の「遺体=不浄・怖い」という価値観の背景をまとめています。また、日本人の声が外国の宗教よりも軽視される現代の構造も解説しています。是非あわせてご覧ください。
本記事のポイント
- 日本の法律は土葬を禁止していない
- 火葬が主流になったのは衛生思想と都市化のため
- 宗教的理由での土葬も制度的には可能だが、受け入れ先は限られる
- 正しい知識を基に、建設的な議論を
関連記事:日本特有の土葬のリスク
土葬問題の話題では水質を懸念する話題は多いですが、国土占有や水害時の遺体・汚染土壌の流出などは議論されにくいようです。
以下の記事では、土葬の基本的なリスクと共に、災害の多い日本特有のリスクについてもまとめて紹介していますので、是非あわせてご覧ください。
以下の記事では、埋葬するという意味の英単語bury(ベリー)についてまとめています。
外国人に日本の埋葬についての状況を伝えるために役立つ、英語表現についても紹介していますので、是非ご活用ください。