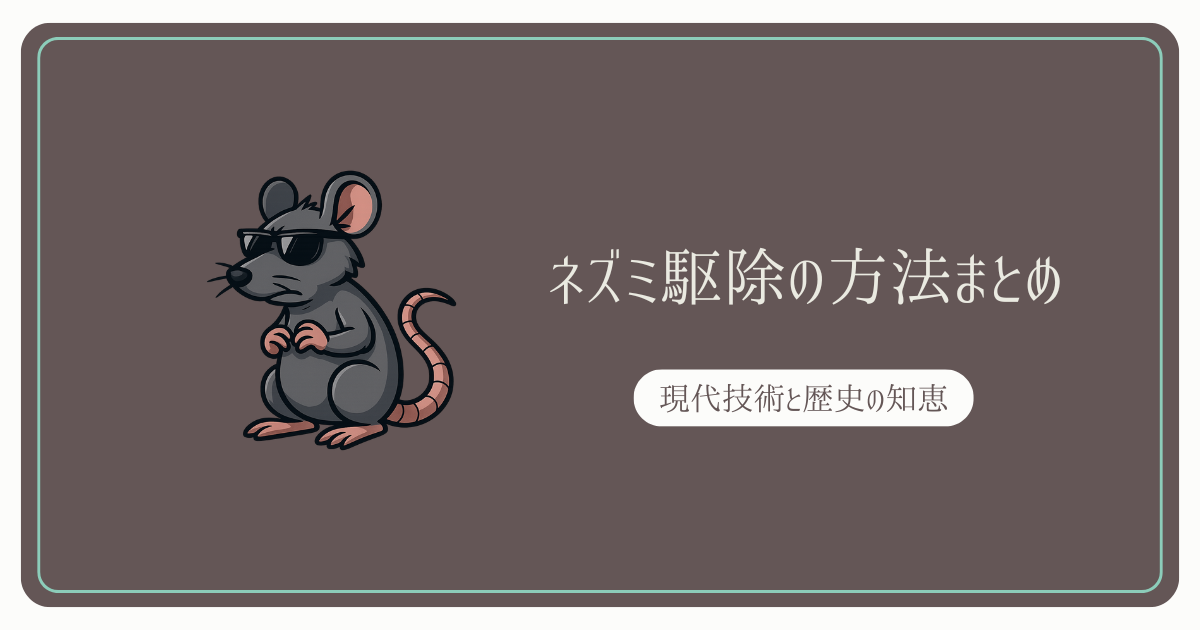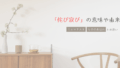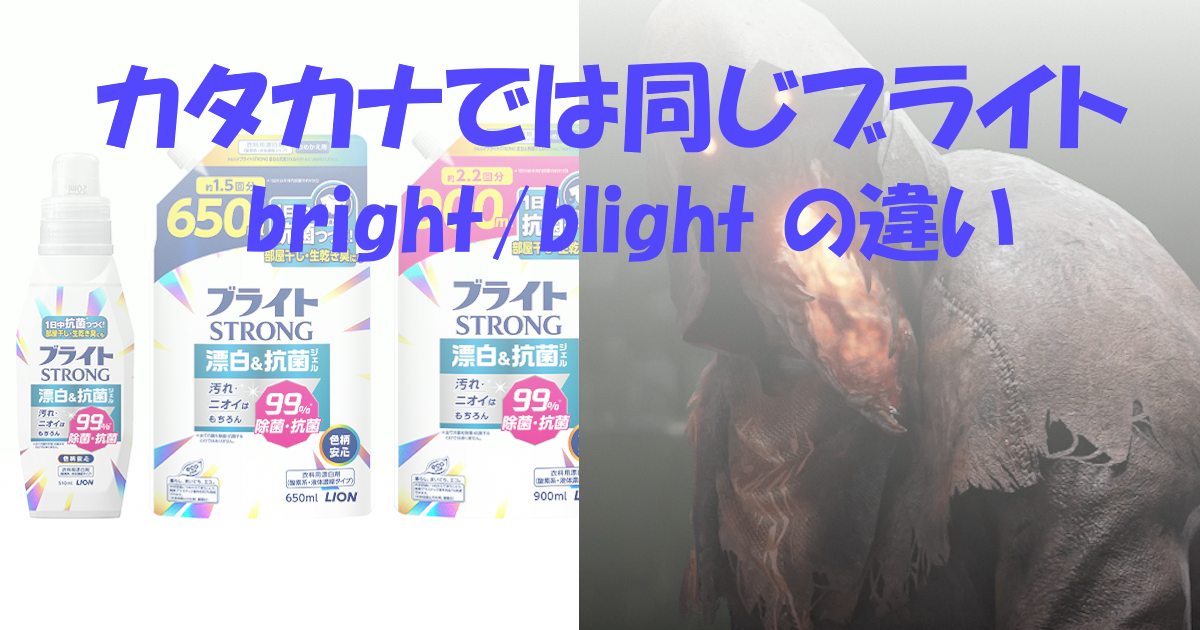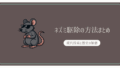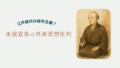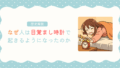現代でも厄介なネズミ被害。この記事では毒餌や防鼠工事など実用的な対策を整理しつつ、費用を抑えたい人のために歴史から学べる工夫も紹介します。
現代社会に残るネズミの問題
ネズミは、都市部ではあまり目にしなくなったとはいえ、現代でも確実に私たちの生活を脅かし続けています。
飲食店や古い住宅では今なお深刻な被害があり、衛生面・経済面ともに看過できない存在です。ここでは、現在どのような方法でネズミに立ち向かっているのかを見てみましょう。
毒餌や粘着シートなどの物理・化学的手段
もっとも一般的で手軽な方法が、毒餌(殺鼠剤:さっそざい)や粘着シートといった物理・化学的な駆除です。古くから使われている基本手段であり、安価で導入しやすいのが利点です。
しかし、一度駆除しても新たに侵入するネズミが現れるため、根絶に至らないという難しさがあります。また、ペットや小さな子どもがいる家庭では、誤食の危険もあり注意が必要です。
100均ショップでも入手可能
ネズミ駆除用の毒餌や粘着シートは、店舗にもよりますが、ダイソーなどの100均ショップでも入手可能です。
- コンパクト耐水ネズミとり – 100均 通販 ダイソーネットストア【公式】
価格:100円(税込110円) - ネズミ駆除(コーンラットα) – 100均 通販 ダイソーネットストア【公式】
価格:100円(税込110円)
専門業者と防鼠工事
被害が深刻な場合、専門業者に依頼するのが一般的です。特に飲食店や倉庫といった施設では、防鼠工事(ぼうそこうじ)と呼ばれる「侵入経路を塞ぐ作業」が欠かせません。

これは単なる駆除ではなく、再発を防ぐための予防型の対策です。現代社会では「ネズミを減らす」だけでなく、「入れない環境を作る」ことが重視されています。
費用について
ネズミ駆除を業者に依頼する場合、依頼内容や家の状態によって大きく異なりますが、1回の駆除で1万円~30万円程度が相場となっています。
防鼠工事の費用は業者や対象の施設にもよりますが、小規模な箇所であれば数万円程度、大規模な工事や広範囲の施工が必要な場合は数十万円、さらには100万円を超えることもあります。
新しい技術の利用
技術革新によって、新しい駆除手段も登場しています。超音波を発してネズミを近寄らせない装置や、IoTセンサーで出没を監視するシステムなどです。また、スマホから駆除業者を呼べるサービスもあり、利便性は格段に向上しました。
それでも、ネズミを完全に克服するには至っていません。彼らの適応力の高さが、いかに強力なものであるかを示しています。
スマホ用 超音波アプリの効果は?
近年では、スマートフォン用のアプリで「ネズミの嫌がる超音波を出す」といったものも存在します。

しかし、ネズミ用の超音波アプリは、一部のユーザーには効果があるかもしれませんが、スマートフォンのスピーカーで再生できる音の周波数には限界があるため、ネズミが嫌がる周波数の超音波を正確に再生できない可能性があります。効果は限定的で、ネズミが音に慣れると効果が薄れることもあります。
アプリに頼るのではなく、ネズミの駆除業者に相談するなど、他の駆除方法も検討するのがおすすめです。
歴史上のネズミ退治 ― 世界と日本の工夫
人とネズミの戦いは、現代に始まったものではありません。古代から近代まで、世界各地で人々は知恵を絞り、さまざまな工夫でネズミに立ち向かってきました。ここでは、いくつか象徴的な事例を振り返ってみます。
ネズミ駆除にお金を掛けたくないといった方は、是非先人たちの知恵を参考にしてみてください。
動物を使ったネズミ対策
人々は、歴史の中で動物の助けを借りて問題に対処していることがあります。
いくつか事例を紹介します。
古代エジプトでは神として崇められた猫:バステト女神
古代エジプトでは、農耕社会を脅かすネズミへの対抗策として、猫が特別な地位を与えられました。バステトと呼ばれる女神は猫の姿で描かれ、家庭と豊穣を守る存在として信仰されたのです。

猫は農作物を守る「聖なる存在」とされ、傷つけることは罪とみなされました。この信仰の背景には、猫が現実にネズミ退治に大きな力を発揮していたという事実があります。
バステト信仰は、動物の実用性と宗教的象徴が結びついた興味深い例であり、人類がネズミとどう向き合ってきたかを物語っています。
日本でもネズミ対策で活躍した「猫」
日本でも江戸時代、米蔵や商家を荒らすネズミに頭を悩ませていました。そこで活躍したのが猫です。猫は「生きたネズミ捕り」として重宝され、家庭や商家で飼われるのが一般的でした。
また、専門のネズミ捕り業者が存在したことも知られています。庶民の暮らしの中に、ネズミ退治を仕事とする人がいたのです。
江戸時代にも愛された猫:招き猫の雑学
猫は時代を超えて、江戸時代にも庶民文化の中で愛されました。
江戸後期には「招き猫」が登場し、商売繁盛の象徴として人気を集めました。また「猫を大切にすると火事にならない」といった俗信もあり、猫は生活を守る存在と考えられました。
浮世絵や文学作品にも猫がしばしば登場し、文化的なアイコンとしての地位を確立していきます。
猛禽類を利用したネズミ対策
ヨーロッパの一部地域では、猫だけでなくフクロウやタカといった猛禽類もネズミ退治に利用されました。田畑や穀倉の周辺に巣箱を設置して猛禽類を呼び込み、自然の捕食者にネズミを減らしてもらう仕組みです。
これは人間が直接駆除するのではなく、生態系を利用した方法であり、現代の「環境に優しい防除」の先駆けともいえます。実際に、今日でも農村地域によってはフクロウの巣箱が設置され、農薬や毒に頼らないネズミ対策として継続されています。
建築の工夫:蔵と鼠返し
建物そのものにも工夫を凝らしてネズミ被害を防ごうとしました。代表的なのが、蔵や米倉に設けられた「鼠返し」です。柱や壁の上部に金属や漆喰で張り出した部分を作り、ネズミがよじ登れないようにした仕掛けです。
さらに、蔵の床を石の上に高く設ける高床式にすることで、地面からの侵入を防ぐ工夫も広まりました。こうした構造的な知恵は、現代の防鼠工事にも通じる発想といえるでしょう。

画像引用:高床式倉庫のねずみ返し@竹取公園古代住居広場 | 奈良の宿大正楼
ちなみに、この鼠返しは蔵などの建築物に限らず船などにも使われる他、後にお城などに付けられた「忍び返し」にも応用されています。
緊急事態には最悪「素手」で捕獲:ペスト奨励金制度
明治時代(19世紀末)に、日本にもペストが持ち込まれると、政府は本格的な対策に乗り出しました。その一つが「ネズミ捕獲奨励金制度」です。捕まえたネズミを役所に持ち込むと金銭が支給され、庶民がこぞってネズミ捕りに参加しました。
捕獲方法にはネズミ捕りカゴや罠なども使われますが、素手でも捕獲が行われます。当時はゴム手袋もビニール袋もない時代だったため、人々は感染のリスクを抱えながら捕獲を行っていました。
日本の対策を含めて、ペストの歴史については以下の記事で詳しく紹介しています。興味のある方は是非ご覧ください。
音でネズミを集める?-ハーメルンの笛吹き男伝説
ドイツに伝わる「ハーメルンの笛吹き男」は、ネズミ退治を請け負った笛吹きが報酬をもらえず、代わりに町の子どもたちを連れ去ってしまうという物語です。

しかし、実際には「ネズミが特定の音に対して集まる習性」は確認されていません。
当時は「笛=魅力や魔力の象徴」と考える文化的背景がありました。また、音に敏感なネズミの習性を誤解して物語に描いてしまった可能性もあるでしょう。
ネズミは人間より高周波(超音波領域)を聞き取る能力を持っていて、人間には聞こえない「20kHz以上」の音を感知できます。不快な超音波はネズミの「忌避行動(逃げる)」を引き起こすことが知られており、現代の「超音波駆除器」はこの性質を利用しています。
歴史は今を映す鏡
ネズミ駆除の歴史を振り返ると、現代の問題が決して特別なものではなく、昔から人々が向き合ってきた課題のひとつであることに気づきます。
そして「なるほど、こんな工夫があったのか」と知ることは、ネズミに限らず、私たちが抱える様々な課題にも応用できる発想のヒントになります。
歴史は遠い過去の物語ではなく、今を照らし出す鏡のような存在なのです。
以下の記事では、現代の科学での最適なお米の保管についてと共に、歴史上の「保管の知恵」を紹介しています。間違いやすい「パンは冷蔵庫?冷凍庫?」といった点も紹介していますので、是非あわせてご覧ください。