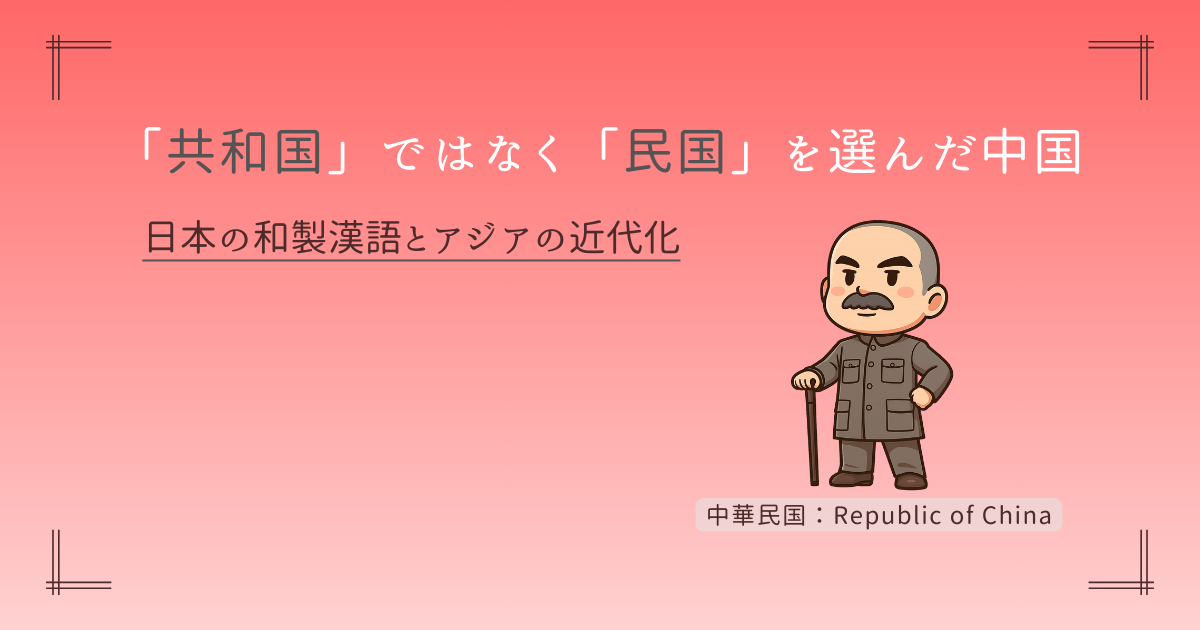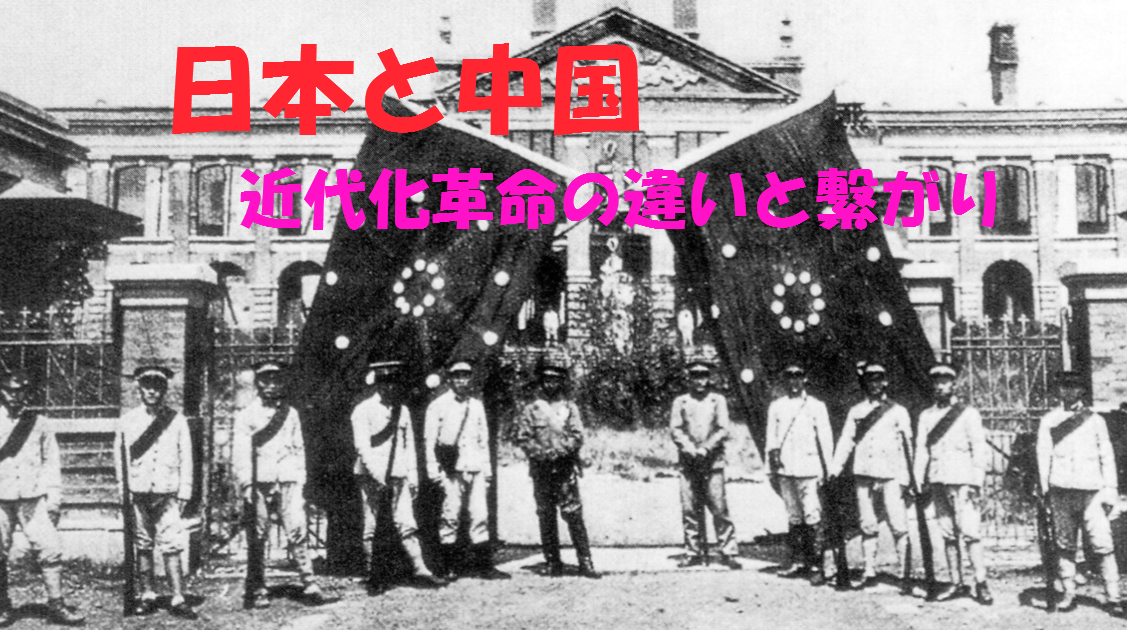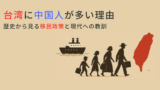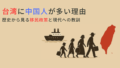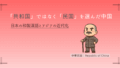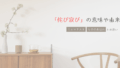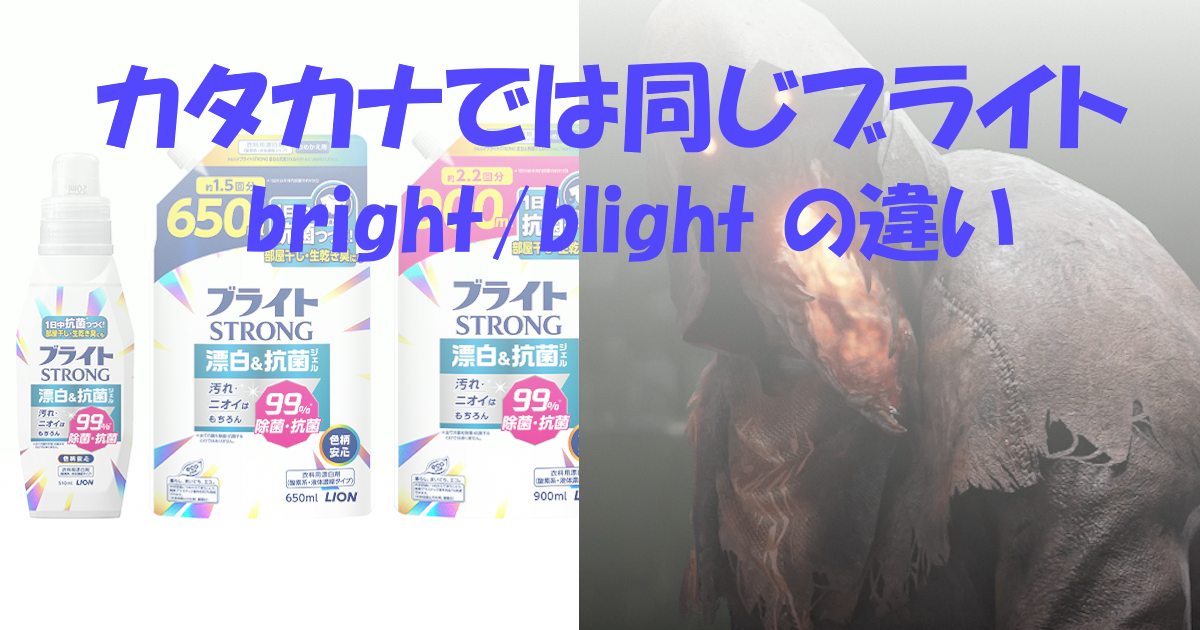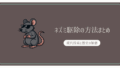英語の Republic という単語は、現代日本語では一般的に「共和国」と訳されます。たとえばフランス共和国やイタリア共和国など、世界の多くの国名に「共和国」という言葉があてられています。
ところが、Republic of China は「中華共和国」ではなく「中華民国」が正式な国号です。
中華民国の建国時、Republicという英単語には既に「共和国」という訳がありましたが、あえて「民国」という言葉を選んだのは何故なのでしょうか。
この不思議な翻訳(Republic = 民国)の背景には、日本で生まれた和製漢語と、中国が自らの伝統を重んじて近代を選び取った歴史が隠されています。
日本で次々と生まれた和製漢語
明治時代、日本は急速に欧米の学問や制度を吸収し、その多くを漢字で翻訳しました。
このとき誕生した新しい言葉は「和製漢語」と呼ばれます。
「人民」「民主主義」「共和国」「自由」「権利」など、現代でも当たり前のように使われている言葉は、この時代に日本で生まれたものです。
| 政治・社会制度 | 思想・学問 | 経済・社会 |
|---|---|---|
| 共和国 民主 自由 権利 社会 国家 | 哲学 科学 宗教 美学 論理 芸術 | 経済 労働 資本 産業 革命 文明 |
日本語に翻訳された概念は、留学生や書籍を通じて中国や朝鮮半島に伝わり、彼らが自国の近代化を考える際の重要な武器となりました。つまり日本は、欧米とアジアをつなぐ「翻訳拠点」として機能し、言葉を通じてアジア全体の近代化を後押ししたのです。
孫文と日本での学び
中国革命の指導者・孫文もまた、日本から大きな影響を受けました。
清朝打倒を掲げて活動していた孫文は、しばしば日本に亡命し、多くの日本人知識人や政治家と交流しました。
この過程で彼は、日本で作られた和製漢語を多数吸収します。
「民主」「自由」「共和国」といった言葉は、孫文にとって中国を変革する際の思想的な武器となったのです。

孫文は当然、Republic の訳語として「共和国」が用意されていることを知っていました。
それでも彼は、最終的に中国の新しい国号として「民国」を選び取ります。
辛亥革命と「中華民国」の建国
1911年、辛亥革命が勃発し、清朝の支配は崩壊しました。
翌1912年、孫文は臨時大総統に就任し、中国は「中華民国」として新たな時代を迎えます。
本記事では辛亥革命の詳細には触れません。辛亥革命について詳しく知りたい方は、是非以下の記事をご覧ください。少し古い記事ですが、日本の明治維新と比較しながら詳しく解説しています。
中華民国は、アジアで初めて共和制を採用した国家でした。
💡政治制度のおさらい
「共和制」:君主(王や皇帝)のいない民主国家
例)フランス共和国、アメリカ合衆国、イタリア共和国など
「立憲君主制」:君主はいるが、憲法の下で権限が制限された民主国家
例)日本、イギリス、オランダなど
これは理念的には「近代化革命」と呼ぶにふさわしい出来事で、国民が政治の主体となる新しい時代の幕開けを示していました。
もっとも実態は理想通りには進まず、軍閥割拠や列強の干渉によって、安定した国民国家の形成は困難を極めました。
それでも「中華民国」という国号は、確かに清朝を倒し、新しい中国が誕生したことを世界に示す旗印となったのです。
なぜ「共和国」ではなく「民国」だったのか
では、なぜ孫文は「共和国」ではなく「民国」という国号を選んだのでしょうか。

その背景には、中国の伝統思想があります。孟子の「民を貴しと為す」という言葉に象徴されるように、中国には古来から「民衆こそ国の基盤」という観念がありました。
「民国」という言葉は、この伝統を直接的に想起させるものだったのです。
一方、「共和国」は西洋の Republic という概念を基に、日本で新たに作られた和製漢語でした。そのため知識人には理解されても、一般大衆には馴染みが薄い言葉だったのです。
革命運動のスローガンとしては、直感的でわかりやすい「民国」の方が圧倒的に有効でした。
つまり「民国」という選択には、単なる翻訳ではなく、中国自身の言葉で近代国家を名乗る という強い誇りと決意が込められていたのです。
💡ポイントまとめ
共和国:西洋概念の「単なる翻訳」
民国:中国の伝統を想起させる「誇り」
捕捉・雑学:大韓民国の「民国」
1919年、朝鮮独立運動の中心となった上海臨時政府は「大韓民国」という国号を採用しました。
これは明らかに「中華民国」に倣ったものであり、帝国からの決別をわかりやすく示すスローガンとしての性格が強いものでした。
中国が自らの伝統から「民国」を選んだのに対し、韓国の場合は外から借りてきたスローガン的な意味合いが大きかったと言えます。
「中華人民共和国」と「中華民国」の国号
1949年に成立した「中華人民共和国」の国号を見てみると、「人民」も「共和国」も日本の和製漢語に由来しています。つまり、新しい中国は日本で作られた外来の概念を、自らの国号に組み込んだのです。
一方で1912年に誕生した「中華民国」は、「民国」という中国伝統の語彙を採用しました。
同じ「中国」でも、外来語を取り入れた「人民共和国」と、伝統を重んじた「民国」とでは、その性格がまったく異なるのです。
この対比を考えるとき、やはり「中華民国」という名前には、外来の概念に依存せず、自らの言葉で近代国家を宣言したという誇り高さが感じられるのではないでしょうか。
参考:国号の比較(漢字表記と英語表記)
| 国号 | 漢字表記 | 英語表記 |
|---|---|---|
| 中華民国 | 中華民國(繁)/中華民国(簡) | Republic of China |
| 中華人民共和国 | 中華人民共和國(繁)/中华人民共和国(簡) | People’s Republic of China |
※「華」の字の変化について
中華人民共和国の建国時には、文字の簡略化(簡体字)運動の影響で「华」の字が一般的になっていました。そのため、中華人民共和国と中華民国では、簡体字表記における「華」の字が異なっています。
日本で使われている「中華人民共和国」の表記は、繁体字・簡体字のどちらの表記とも異なっています。正確性が問われる文書や学術論文などでは、原語表記(中华人民共和国/中華人民共和國)に注意した方がよいでしょう。
コラム:台湾の国号「中華民国」への複雑な思い
今日の台湾においても、正式な国号は「中華民国」です。
しかし、この名称は台湾社会で複雑な感情を呼び起こします。
一部には、「中国伝統を受け継ぐ正統な国家」として「中華民国」に誇りを感じる人々がいます。
とくに国民党系の支持層には、「我々こそ中国の正統」という思いが根強く残っています。
一方で、台湾人としての独自アイデンティティを重視する層にとって、「中華民国」という名前は「中国の影」を引きずるものであり、違和感を伴うものです。
実際、台湾の政治家は国際舞台では「台湾」を強調し、国内制度上は「中華民国」を使うという二重性の中で活動しています。
つまり「中華民国」という国号は、台湾にとって 誇りでもあり、制約でもある。その板挟みの感覚こそが、現代台湾の政治とアイデンティティを映し出していると言えるでしょう。
関連記事:台湾と中国
台湾は、中国や日本と歴史的に深い関係があります。
以下の記事では、台湾に中国人(漢民族系の人)が多い理由について、歴史を紐解いて解説しています。オランダの植民地時代から、明→清→日本、そして中華民国政府が入ってくるまでの過程を、人口や文化の変化、出来事などを中心にまとめています。
また、日本では中国の人と台湾の人の間に、文化や価値観の違いがあることが知られています。
以下の記事では、同じ漢民族系でありながら、台湾の人たちが中国の人たちと異なる価値観を持つことになった背景について、歴史や現代の教育制度の観点からまとめています。