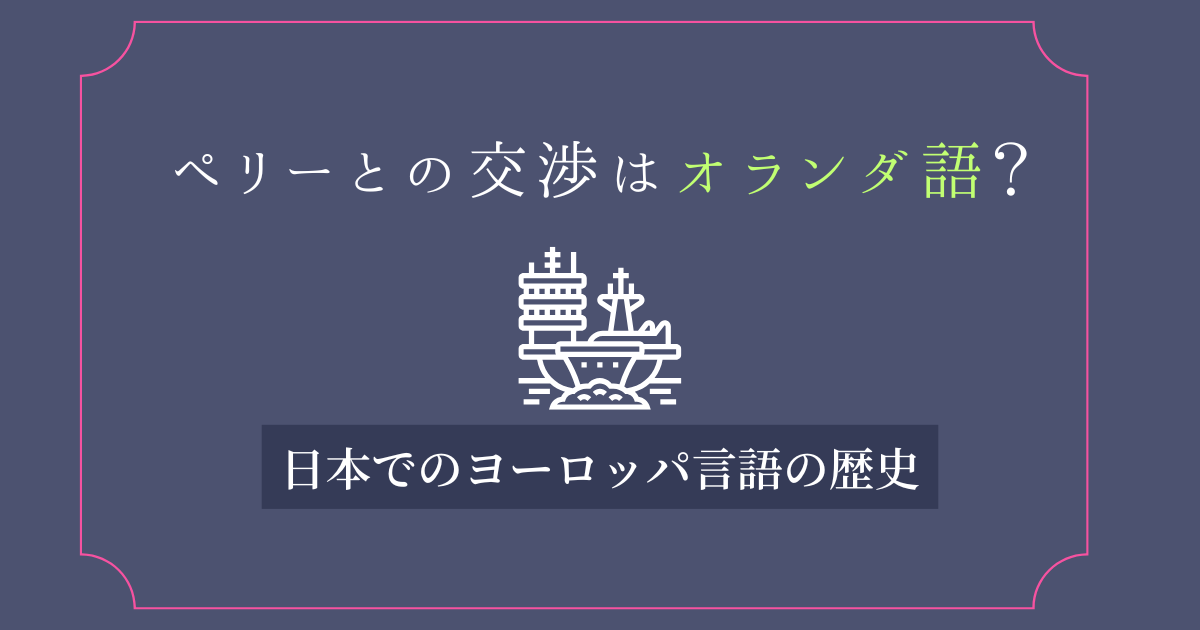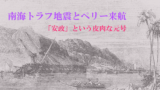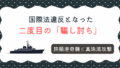1853年のペリー来航は、歴史の大転換点として今なお語り継がれています。しかし、その外交の場で使われていた「言語」が何だったか、ご存じでしょうか?本記事では、その謎を入り口に、日本で使われてきたヨーロッパ言語の歴史を紐解きます。
日本で使われたヨーロッパ言語の歴史
日本に最初にヨーロッパ人がやって来たのは1543年の種子島ー鉄砲伝来のポルトガル人です。その後1549年のフランシスコ=ザビエル(スペイン人)、1600年には三浦按針(ウィリアム・アダムス – イギリス人)がオランダの船に乗って日本に辿り着きます。
19世紀中ごろになってアメリカからやって来たペリーとは、一体何語で交渉したのでしょうか。
順番に見ていきましょう。
はじめに ― 意外な交渉言語
1853年、浦賀沖に突如現れた黒船。その黒い艦隊の中心にいたのが、アメリカのマシュー・ペリー提督です。彼は日本に開国を迫るべく、アメリカ大統領の親書を携えてやって来ました。この歴史的事件は誰もが知るところですが、交渉の場で使われた「言語」については、意外と知られていません。
アメリカ人であるペリー。ならば当然、英語で交渉が行われた――と思いきや、実は交渉の中心となった言語は「オランダ語」だったのです。
なぜ英語ではなく、オランダ語だったのでしょうか? この小さな「なぜ?」を入り口に、日本とヨーロッパ言語の長い交流の歴史をたどってみましょう。
鎖国とオランダ語 ― 唯一の西洋言語として
江戸時代、日本は200年以上にわたって「鎖国」体制を敷いていました。とはいえ、完全な孤立ではなく、長崎・出島を通じてオランダとは交易を続けていたのです。
キリスト教布教を目的としたポルトガルやスペインとの交流は禁じられましたが、宗教に関心を持たなかったオランダだけは例外的に認められていたという事情があります。
このため、江戸期の日本にとって西洋=オランダであり、西洋の言葉=オランダ語という認識が定着しました。医学・天文学・物理学といった西洋知識は、すべてオランダ語を通じて学ばれました。この学問的潮流は「蘭学」と呼ばれ、杉田玄白や前野良沢らの『解体新書』も、オランダ語原書の翻訳として生まれたものです。
通詞(つうじ)と呼ばれるオランダ語の通訳者も育成され、幕府の中には専門の通訳部門が存在していました。
ペリーが日本にやって来た19世紀半ばの時点で、日本にとって「オランダ語は唯一実務で使える西洋言語」だったのです。
ペリー来航と交渉の言語事情
1853年、ペリー提督が日本にやって来ます。彼が差し出したアメリカ大統領フィルモアの親書には、英語に加えてオランダ語・中国語訳が添えられていました。アメリカ側は、日本人が英語を理解できないことを予想して、あらかじめ多言語対応を準備していたのです。
実際の交渉でも、ペリー側は英語を使いましたが、日本側は英語を直接理解できません。そこで、ペリー艦隊の中にいたオランダ語を話せる通訳者が、英語をオランダ語に訳し、それを日本の通詞が日本語に訳す、という三段階の通訳体制が敷かれました。
| 幕府 | 幕府通訳 | ペリー通訳 | ペリー |
|---|---|---|---|
| 日本語 | 日本語 ← オランダ語 | オランダ語 ← 英語 | 英語 |
| 日本語 | 日本語 → オランダ語 | オランダ語 → 英語 | 英語 |
このとき活躍した日本人通詞の一人が堀達之助(ほり・たつのすけ)です。長崎の出身でオランダ語に堪能だった彼は、ペリーとの折衝を成功裏に導く上で欠かせない存在でした。
つまり、「ペリーとの交渉はオランダ語で行われた」というのは、厳密に言えばオランダ語を媒介とした間接的な英語交渉だったのです。
明治維新と英語・ドイツ語の時代へ
やがて開国の流れは止まらず、1868年の明治維新を迎えた日本は、急速な近代化へと舵を切ります。ここで主役の座に躍り出るのが英語とドイツ語です。
英語は、外交・法制度・教育・経済といった広い分野で活用され、政府は英語教師を海外から招聘し、翻訳事業に力を入れました。一方、医学や軍事の分野ではドイツ語が主に使用され、陸軍の医師はドイツ語で論文を読んだり、カルテをつけたりしていたほどです。
こうした中、オランダ語は急速に影をひそめていきます。明治10年代には「蘭学」という言葉自体がすでに古めかしいものとなり、やがて教育課程からも姿を消しました。オランダ語は、「最初の西洋語」として日本に知識の扉を開いたものの、英独語にその役割を譲っていったのです。
ヨーロッパ言語と日本の「知」のかたち
オランダ語、英語、ドイツ語――これらのヨーロッパ言語は、単に外国語として日本に持ち込まれたのではありません。それぞれの言語を通じて、日本人は「世界をどう見るか」「知識をどう理解するか」という枠組みをつくっていったのです。
たとえば、民主主義(democracy)や科学(science)といった言葉は、明治時代に英語からの翻訳語=和製漢語として生まれました。そしてそれらは、現代の日本語の基本語彙となり、さらには中国・韓国など東アジア諸国にも影響を与えました。
言語はただの道具ではなく、文化の「型」をつくる存在でもあります。ヨーロッパ言語を受け入れることで、日本は“日本語のまま”近代化を果たす道を選んだのです。
おわりに ― 言語から歴史を読む
「ペリーとの交渉は何語だったのか?」という素朴な疑問から始まった話が、こうして日本の近代史全体につながっていくのは不思議なことのように思えるかもしれません。しかし実は、言語の歴史は、常に人と人の出会いや、国家の方向性の変化と深く結びついているのです。
英語に囲まれた現代の私たちも、かつてオランダ語で世界と対話していた先人たちの足跡の上に立っています。言語を通じて歴史を紐解くことは、今を生きるための教養であり、未来へつなぐ視点でもあるのです。
🔹コラム:日本語に残るオランダ語
江戸時代にオランダ語から入った言葉の一部は、現代の日本語にも残っています。
- ビロード(velours:起毛布地)
- ガラス(glas:硝子)
- ランドセル(ransel:背負いカバン)
- コーヒー(koffie)
これらの言葉に触れるたび、私たちは知らず知らずのうちに「蘭学の記憶」と共に生きているのかもしれません。
ペリー来航と南海トラフ地震
本サイトには他にもペリー来航に関連した記事が多くあります。以下はその中の一つで、ペリー来航の時期に起きた「南海トラフ地震」と、その後の交渉の間に起きていた「余震」について多角的にまとめています。興味のある方は是非ご覧ください。