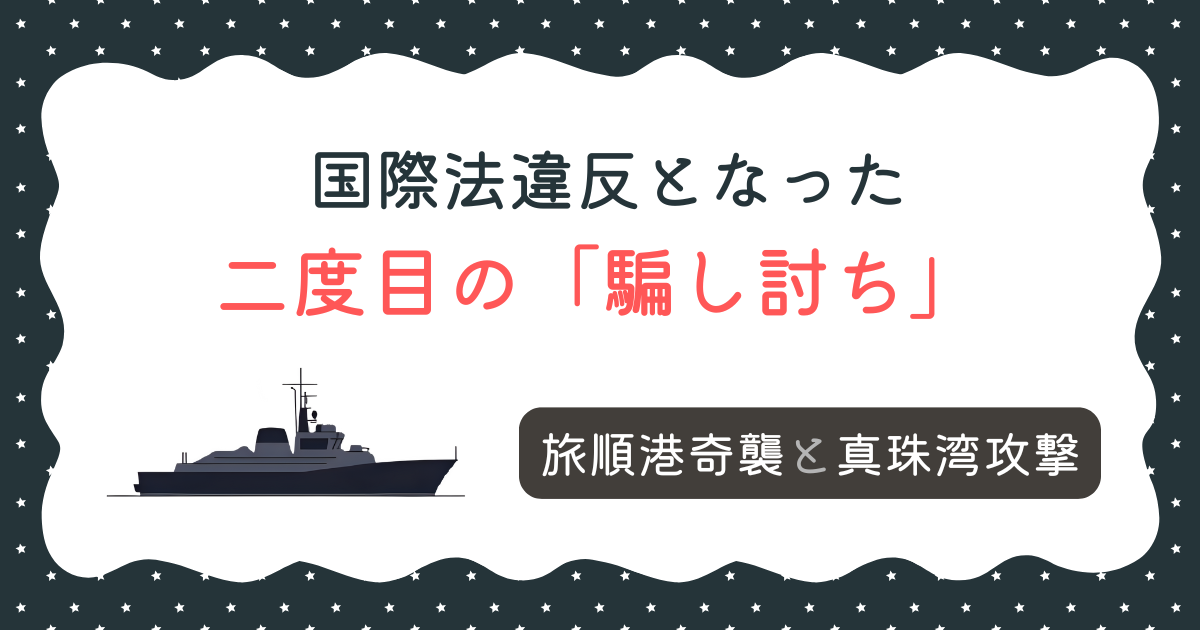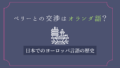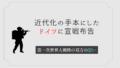日本が行った二つの奇襲――1904年の日露戦争・旅順港奇襲と、1941年の太平洋戦争・真珠湾攻撃。
37年の時を隔てた二つの行為は、戦略的には似ていながらも国際法上の評価は大きく異なります。
なぜ真珠湾は「卑劣」と非難され、旅順港はグレーゾーンとされたのか。その経緯と国際法の変遷を解説します。
二つの「騙し討ち」が残した影
1941年12月8日(米国時間7日)、ハワイ・オアフ島にある米海軍真珠湾基地は、日本海軍機動部隊による奇襲を受けました。戦艦アリゾナをはじめ多くの艦船や航空機が破壊され、死者2400名以上。アメリカ国民は激怒し、この攻撃は瞬く間に「卑劣な騙し討ち」として世界に知れ渡ります。
しかし、この評価にはもう一つ背景がありました。
37年前の1904年、日露戦争の開戦直前、日本はロシアの旅順港を奇襲しています。奇妙なことに、真珠湾を批判した国際世論は、この旅順港奇襲を「前例」として持ち出すことが多かったのです。
では、この二つの奇襲はどのように似ていて、何が違法とされたのでしょうか。
1904年 旅順港奇襲
20世紀初頭、朝鮮半島と満州をめぐる権益争いで、日本とロシアの関係は悪化の一途をたどっていました。外交交渉は行き詰まり、ついに日本は開戦を決意します。
1904年2月8日深夜、日本海軍はロシア艦隊が停泊する遼東半島・旅順港を奇襲しました。魚雷攻撃により戦艦2隻などが損傷し、ロシア艦隊は行動不能に。奇襲の2日後、日本は正式に宣戦布告を行いました。
- 1904年2月6日
日本、ロシアとの交渉を打ち切る(開戦決定は2月4日)。 - 2月8日夜
旅順港に停泊中のロシア太平洋艦隊へ日本海軍が夜間魚雷攻撃(いわゆる旅順港奇襲)。 - 2月9日朝
仁川沖海戦(韓国・仁川港付近でロシア艦隊撃破)。 - 2月10日
日本がロシアに対し正式に宣戦布告を通告(奇襲から2日後)。
この時点での国際法、特に1899年のハーグ陸戦条約には、「宣戦布告前に攻撃してはならない」という明確な条文はありませんでした。
そのため、旅順港奇襲は「違法」と断じられることはなく、むしろ日本の機動力を評価する声も一部にありました。
しかし、ロシアや一部欧米諸国はこの行動を「卑劣」と批判。国際世論は賛否に分かれ、外交的な議論が巻き起こります。
国際法の改正と旅順港の教訓
旅順港奇襲を受け、国際社会では「戦争開始の手続き」を明文化すべきだとの声が高まりました。
そして1907年、第2回ハーグ平和会議で「開戦に関する条約」が採択されます。そこには、「戦争は、理由を付した最後通牒、または宣戦布告を事前に相手国に通告した上で開始しなければならない」と明記されました。
この改正により、旅順港奇襲のような宣戦布告なしの奇襲は、明確に国際法違反となったのです。
1941年 真珠湾攻撃
そして37年後の1941年、日本とアメリカは中国・東南アジア情勢や経済制裁をめぐって緊張を高めていました。外交交渉は続けられていましたが、日本政府は水面下で開戦準備を進め、ハワイの真珠湾を最初の攻撃目標に定めます。
日本側は攻撃開始前に宣戦布告文書(通告文)を米国に手交する予定でした。しかし、大使館内での暗号解読やタイプ作業が遅れ、米国政府が文書を受け取ったのは、真珠湾がすでに攻撃を受けてから約1時間後でした。
この結果、米国は真珠湾攻撃を「意図的な騙し討ち」と断定。ルーズベルト大統領は議会演説で「これは不名誉の日である(Day of Infamy)」と述べ、米国民の怒りは頂点に達しました。
国際法から見た二つの奇襲
ここで、二つの奇襲を国際法の観点から整理してみましょう。
| 項目 | 旅順港奇襲(1904) | 真珠湾攻撃(1941) |
|---|---|---|
| 当時の国際法 | 明確規定なし(グレー) | 1907年ハーグ条約で明確に禁止 |
| 宣戦布告 | 攻撃の2日後 | 攻撃後に到達(遅延) |
| 国際世論 | 賛否両論 | ほぼ全面的非難 |
| 戦略効果 | ロシア艦隊の行動制限 | 米国の戦意激化・長期戦化 |
旅順港奇襲は国際法の隙間を突いた行動でしたが、その行為が国際法の厳格化を招きました。真珠湾攻撃は、その強化された国際法に違反する形で行われたため、「二度目の騙し討ち」として強く非難されたのです。
歴史が作った「二度目の汚名」
真珠湾攻撃が特に悪名高く語られたのは、単に米国を不意打ちしたからではありません。
すでに日本は「宣戦布告なしの攻撃」という前例を持っており、その結果生まれた国際法を破ったという歴史的経緯があったのです。
旅順港奇襲は、当時の日本にとって戦略的成功でしたが、国際法上のグレーな行動として批判も受けました。その経験から国際法は改正され、真珠湾攻撃の時代には「違法」と明言できる枠組みが存在していたのです。
現代の国連憲章の下では、先制攻撃は原則禁止であり、自衛権行使も「武力攻撃を受けた場合」に限定されます。つまり、旅順港奇襲や真珠湾攻撃のような行為は、今やほぼ例外なく国際社会から厳しく糾弾されることになります。
この二つの奇襲は、日本外交史における光と影を象徴しています。歴史の中で生まれた「前例」が、次の時代に重くのしかかる──その典型例といえるでしょう。
(参考資料)
1899年・1907年ハーグ条約
米国議会記録「Day of Infamy」演説
『日露戦争史』中央公論社
Foreign Relations of the United States (FRUS) 文書集