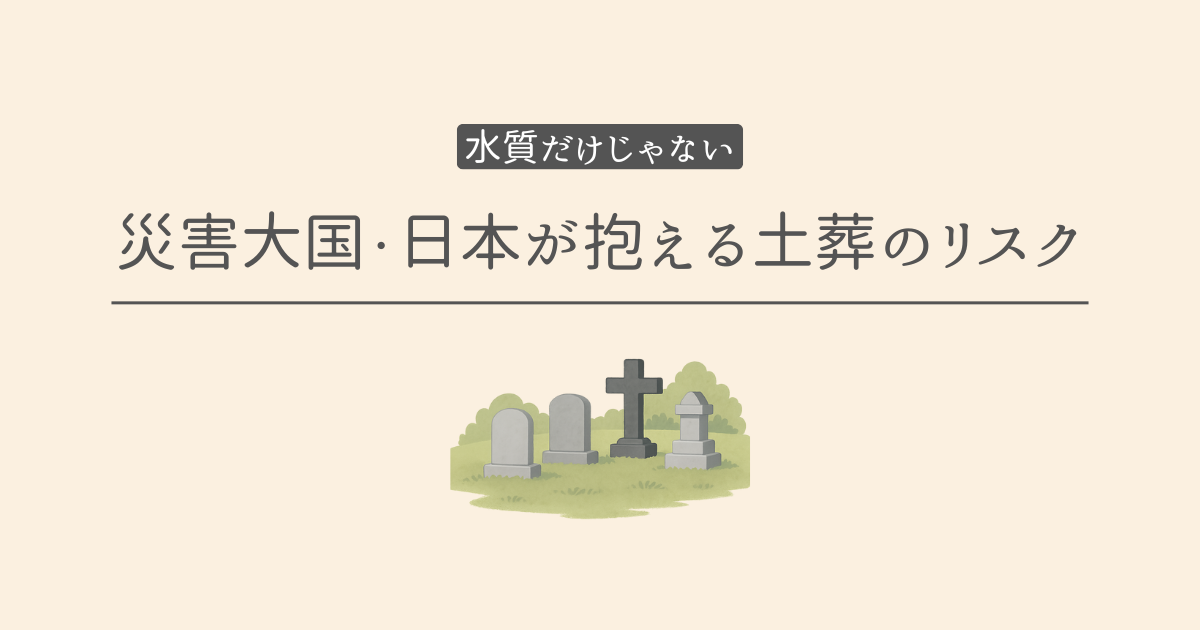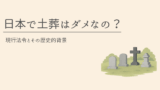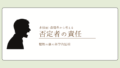土葬のリスクは水質汚染だけではありません。
土地利用の問題に加え、災害大国・日本では地震や豪雨による墓地被害といった特有のリスクも存在します。本記事ではその両面を整理します。
土葬に伴う基本的なリスク
土葬というと「衛生面の問題」として語られることが多いですが、実際にはそれ以外にも多くのリスクが存在します。まずは一般的に知られている代表的な影響を整理します。
土葬の汚染と臭気 ― WHOが認めている内容
世界保健機関(WHO)は、大規模災害時の遺体処理指針において、土葬そのものは必ずしも感染症拡大の原因にはならないと示しています。
ただしそれは適切な条件を守った場合に限られます。
- 水質汚染:地下水と近い場所に埋葬されると、遺体の分解に伴って窒素・リン・微生物が水系に流入する恐れがあります。
- 土壌汚染:遺体から放出される栄養塩に加え、棺の防腐剤や医療由来の重金属が土壌に蓄積することがあります。
- 臭気の発生:分解過程ではアンモニアや硫化水素などが発生し、覆土が浅ければ地表に漏れ出す可能性もあります。
つまり衛生リスクが「ゼロ」ではなく、条件を誤れば周辺環境を汚染し、生活環境に影響を及ぼす可能性があるのです。
土地の持続可能性の問題
土葬は「1人につき1区画」を必要とするため、土地の占有が大きくなります。
欧州ではその不便を解消するために「20〜30年で区画を返還」「共同納骨堂へ改葬」といった期限付き利用が制度化されています。
また土葬は、火葬に比べて専有面積が広いため、実質的な追加コスト(区画更新料・管理料・改葬費用等)が課される傾向があります。これは、「自由はあるがコストを伴う」制度設計によって、土地負担を減らす方向に誘導しているともいえます。
永続利用が前提 ― 日本の特殊な事情
墓地の土地占有を一定程度に抑えるために、欧州だけでなくシンガポールや韓国のように「使用期限」を設けている国が多くあります。一定期間が経過すると、追加料金を課し、払えなければ強制的に改葬するなどの措置がとられます。
一方で日本では、墓地の使用は“永続利用”が前提の制度設計です。
区画の「再利用の期間制(20年・30年…)」といった全国ルールは存在しません。日本での無縁墳墓は、官報公告と現地掲示を1年間実施(「縁故者は申し出を」)して、申し出が無ければ改葬許可がおりる仕組みです。
世界的には、自然葬(森林葬や樹木葬など)が選択肢の一つとして広がりつつあり、持続可能性の観点から注目されています。多文化共生の観点から進められる土葬墓地拡大は、必要な事とはいえ、持続可能性の観点からは課題が残ります。
日本で土葬墓地が認められる理由
土葬には多くのリスクが指摘されます。それでも日本の制度で全面禁止になっていないのは何故でしょうか。
そこには法制度と基本的人権の観点があります。
- 法的な位置づけ:1948年の「墓地、埋葬等に関する法律」により、許可された墓地であれば土葬も埋葬方法として認められています。
- 衛生基準:WHOが示す条件を満たす限り、公衆衛生上の大きな影響はないとされます。
- 個人の自由:憲法20条で保障された信教の自由や、人格権の一部としての埋葬選択権が尊重されるべきと考えられています。
つまり、法的にも倫理的にも「土葬を認める余地」が残されているのです。
現行法令の仕組みや、コレラ流行をきっかけに火葬が普及した経緯については、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
議論されない日本特有の土葬リスク
世界的には少数派の宗教的要望に配慮し、土葬を一定程度認める流れが広がっています。韓国や欧州の都市部では、イスラム教徒のために専用墓地が整備される事例もあります。
しかし日本は事情が異なります。
災害が多発する国土では、土葬は他国以上に深刻なリスクを抱えています。土葬が広がった場合、日本特有の自然災害によって墓地が被害を受けるリスクが想定されます。
代表的な例を整理すると以下のとおりです。
| 災害の種類 | 想定されるリスク |
|---|---|
| 地震(液状化・崩壊) | 墓地の地盤が崩れ、棺や土壌が露出する恐れ |
| 豪雨・洪水 | 河川沿い墓地が冠水し、遺体や汚染土壌が水系に流入する可能性 |
| 土砂災害 | 斜面墓地が崩落し、遺体を含む土壌が集落に流れ込む危険 |
いくつか具体的に掘り下げ確認してみましょう。
水害での遺体・汚染土壌の流出
近年は線状降水帯の発生に伴う局地的な大雨(いわゆるゲリラ豪雨)も頻繁に見られるようになりました。一時間に120ミリを超える雨が降り、地下商業施設が水没するなどの被害も報告されています。
こうした水害では、生活排水や下水が混じった水が流れ込むため、衛生上の危険が大きいのですが、もし土葬が広がれば、そこに遺体や汚染された土壌も加わる可能性があります。
水害がもたらす影響
WHOや国際赤十字の指針では、遺体は感染症の主な原因にはならないとされています。ただし、コレラやエボラのような一部の感染症では死後も一定期間は高い感染性を維持し、危険性は数日から1〜2週間程度続くとされています。
水害で遺体や汚染土壌が流れ出た場合、腐敗に伴う有機物やアンモニア・硫化物が局所的に水質を悪化させる可能性はありますが、実際の衛生リスクとしては生活排水・下水・工場排水の混入がはるかに大きな要因です。
しかし、遺体や骨が水害で流出・露出することは、遺族や地域社会に大きな精神的ショックを与えます。「不衛生」「不潔」といった文化的価値観からの嫌悪感も強く、住民トラブルや二次的被害(偏見・風評)につながる可能性もあります。
WHOや赤十字も精神的な面を完全に無視しているわけではありませんが、主要な論点は公衆衛生リスクであり、精神的負担は補足的に触れられる程度にとどまっています。
日本は世界とは異なり、遺体を強く「忌諱」する文化があります。これについては、後述の[文化による遺体の捉え方の違い]で簡単に触れています。
大災害時に発生する追加コスト
災害時に大量の遺体が発生すると、火葬と土葬の違いは社会に大きな負担の差を生みます。
火葬遺骨であれば再埋葬で済むケースが多いのに対し、土葬の場合は掘削や再埋葬、衛生処理などの大規模な作業が必要になります。そのため、遺体の尊厳を守るために追加のコストや人員を投入せざるを得ず、社会全体の負担が増大します。
関東大震災後に火葬が加速した理由
1923年の関東大震災では、10万人以上の犠牲者が発生し、当時の東京の火葬能力を大きく超えました。仮埋葬も行われましたが、遺体の露出や衛生不安が高まり、火葬の合理性が社会に強く認識されました。その後、火葬場の増設が進み、土葬から火葬への転換が一気に加速しました。
東日本大震災での墓地被害
2011年の東日本大震災では、津波によって福島県浪江町の共同墓地が被災し、墓石や遺骨が流出しました。火葬済みの遺骨であっても被害は深刻でしたが、もし土葬墓地であったなら、汚染土壌や遺体の流出を伴い、復旧コストや社会的影響はさらに大きくなっていた可能性があります。
土葬を認めるべきなのか
多文化共生の観点から、少数派の声に応える形で一定の土葬を認めることは世界的な潮流です。
しかし、日本の国土条件や災害リスクを踏まえると、衛生面以外の議論が不足している現状があります。
- 自由の尊重と公共の安全のバランス
- 認める場合の追加コスト負担や制度設計
- 災害大国としての特有のリスク
これらを議論した上で、日本にとって望ましい埋葬のあり方を考える必要があります。
「世界がそうしているから」ではなく、「日本の国土に適した選択か」という視点を持つことが求められています。
文化による遺体の捉え方の違い – 恐怖と尊重
日本では古来より「死=穢れ」と捉える文化が強く、遺体を日常空間から遠ざける傾向があります。これは欧米やイスラム圏で遺体を尊重し直接触れる習慣とは対照的です。
遺体が水害で流れてきた際、日本人は恐怖にも似た「忌諱」を強く感じますが、世界的には「悲しみ」や「悼む気持ち」として受け止められることが多いのです。
イスラム文化で火葬が禁止されているのと同じように、日本では遺体の存在そのものが強く忌避される対象です。こうした文化的背景もまた、日本で土葬が受け入れられにくい一因となっていると考えられます。
日本と世界の遺体観の違いと、日本人の声が軽視される構造的な問題については、以下にまとめてありますので、是非あわせてご覧ください。