💡この記事は、日本の伝統宗教「神道」特集の一部です。
神道では「死」は特別な穢れとされてきました。
本記事では、古代の制度から近代の皇室儀礼、そして現代の感覚まで、日本人の死生観を支えた「死穢観」の歴史をたどります。
神道における「穢れ」とは何か
死を穢れとする背景を知るために、まずは神道における「穢れ」概念そのものを確認しておきましょう。
穢れは「罪」ではない
神道における「穢れ」は、キリスト教のような「罪」とは異なります。穢れは人が悪事を働いた結果ではなく、自然の循環の中で一時的に生じる「不調和」の状態と考えられました。
そのため、祓えや清めの儀式を行えば回復できるものです。血や出産、そして死もまた「特別な穢れ」とされ、神に仕える場からは慎重に遠ざけられました。
生命観と死の対比
神道は、豊作・健康・子孫繁栄といった「生きることの力強さ」を尊ぶ宗教です。その対極にある「死」は、生命の流れを断ち切る異常な出来事と受け止められました。
こうして死は自然秩序から外れた存在とされ、穢れとして避けられるようになったのです。
雑学:神社の手水と清めの作法
神社に参拝するとき、手水舎(ちょうずや、てみずや)で手や口を清めるのは当たり前の風習とされています。

これは、死や血といった「穢れ」を神域に持ち込まないための行為です。単なる衛生習慣ではなく、「神に近づく前に身も心も清浄にする」という宗教的な意味を持っています。
古代の死と忌避の制度
古代では、死の穢れを社会制度として明確に管理していました。
忌服令と日数の決まり – 「忌引き休暇」の由来
『延喜式』には、死者が出た際に親族が何日間「忌服:きふく」に入るかが定められていました。父母の死で50日、兄弟姉妹で30日など、親等によって細かく規定されています。
忌服の間は政務や神事から外れ、共同体に死穢(しえ)が及ぶのを防ぐ意味がありました。
現代の「忌引き休暇」の制度は、この古代の仕組みに由来しています。
斎宮と死の隔絶
伊勢神宮に仕える斎宮(内親王)は、死や出産といった穢れから徹底的に隔絶されていました。近親者が亡くなっても、斎宮はそのまま仕えることが許されず、退任を余儀なくされます。
制度そのものが「死を避ける思想」に貫かれており、死穢観念が皇室のあり方に深く影響していたことが分かります。
雑学:現代の「神職は葬儀に関わらない」慣習
現代の神社で神職が葬儀に関わらないことが多いのも、古代の「死を神前から遠ざける」考え方の延長線上にあります。
中世の変化「祭りは神道、葬りは仏教」
武士の時代になると、死は避けられる存在でありながらも、「祀る」対象として別の形を与えられていきました。
御霊信仰と怨霊の神格化
菅原道真や崇徳上皇のように、無念の死を遂げた人物は怨霊となり恐れられました。そのため彼らを神として祀り上げ、鎮める「御霊信仰」が広まりました。
例:菅原道真(天満宮)、崇徳上皇(白峯神宮)
死は穢れであると同時に、強大な霊力の源泉でもあると意識されるようになったのです。
仏教による葬送の独占 – 神道と仏教の役割分担
中世以降、葬儀はほぼ仏教寺院が担うようになりました。
神社は死を扱えないため、生活の中で「祭りは神道、葬りは仏教」という住み分けが成立しました。
この役割分担は今日まで続いています。
近世における死と差別構造
江戸社会では、死を扱う人々が「制度的に」差別されるようになりました。
触穢と穢多・非人
死体の処理やと畜(屠殺:とさつ)、刑場の後始末といった仕事に従事する人々は、「穢れ」に触れる存在(触穢:しょくえ)とされました。彼らは「穢多(えた)」「非人(ひにん)」と呼ばれ、社会の周縁に追いやられていきました。
屠殺が入っていることからも分かるように、「死=穢れ」という概念は人間だけでなく動物にも及びました。神道は仏教のように「殺生そのものを罪」とはせず、肉食も原則的に禁じてはいません。
けれども死や血は「穢れ」と見なされ、神事や日常生活の中で特別に忌避されました。
死穢観念は単なる宗教的感覚にとどまらず、差別構造を生み出す要因ともなったのです。
雑学:動物肉の不思議な名前
日本では長く「肉食は禁止」という建前がありましたが、実際には人々は獣肉を口にしていました。ただしその際、直接「肉」とは言わず、婉曲的な呼び名でごまかす工夫がされました。
代表的なのは、イノシシを「山鯨(やまくじら)」と呼ぶ例です。海に棲む鯨なら食べてもよいという発想にかけて、イノシシを「山の鯨」と言い換えたのです。また、シカは赤い肉の色から「もみじ」、ウサギは羽で数えることにして「鳥」とみなすなど、ユニークな呼称が広まりました。
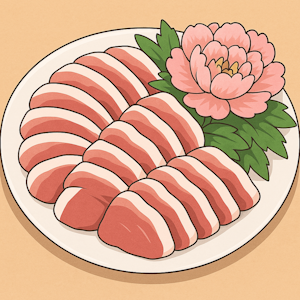
盛り付けが牡丹の花に見えることに由来
こうした隠語は、仏教がもたらした「四足食禁止」の禁忌を避ける方便であると同時に、神道における「血や死=穢れ」という感覚をやわらげる働きもありました。言葉をすり替えることで、肉食をしながらも「禁忌や穢れに正面から触れていない」という心理的な納得を得ていたのです。
| 動物 | 婉曲名 | 由来・イメージ |
|---|---|---|
| 鹿 | もみじ | 毛色や肉の赤さを紅葉にたとえた |
| 猪 | ぼたん | 皿に盛った肉が牡丹の花に似る |
| 馬 | さくら | 肉の色が桜色に似る |
| 鶏 | かしわ | 焼いた肉の色が柏の葉の色に似る |
※ いずれも「死の穢れ」を避けるための婉曲表現であり、直接「肉」と呼ぶのを避ける文化的な工夫でした。こうした名称は、色や形の連想から植物に例えられることが多いのが特徴です。
雑学:刑場跡地に残る痕跡
江戸時代の刑場は町の境界に置かれることが多く、その痕跡は今も地名や史跡に残っています。
例えば、東京・南千住の「小塚原刑場跡(こづかっぱらけいじょう)」には供養塔があり、吉田松陰らが処刑された場所として知られます。
小塚原(南千住)は、死刑場跡や「穢多・非人」と結びついた歴史から、長らく土地評価が低く見られる傾向がありました。現代では再開発なども進み、昔ほどの忌避感は薄れていますが、古い世代ではなお「縁起が悪い場所」という認識が残ることがあります。
こうした土地に漂う「忌避の空気」こそ、死を穢れとする感覚の歴史的な証といえるでしょう。
近代以降の皇室と死の儀礼
近代以降の「死の穢れ」を考える上で欠かせないのが皇室です。
そもそも天皇は神道の中心的存在であり、祭祀を通じて神道そのものを体現してきました。そのため、皇室の死に関する作法は、神道的な死穢観がどのように近代へ継承されたかを示す重要な手がかりとなります。
宮中の死の回避作法
宮中では、誰かが亡くなるとその部屋に新聞紙を敷く慣習がありました。これは「穢れが床に残らないように」という実務的な意味合いを持ちます。また、宮中三殿では死者を祀らず、葬送は「大喪儀」という国家儀礼として別枠で執り行われました。
平成天皇による国際親善の重視
昭和までは皇室が外国の葬儀に参列することはほとんどありませんでした。しかし平成天皇(上皇明仁)は、海外の国王や大統領の葬儀に積極的に参列しました。
これは「死の穢れ」という伝統観念を超えて国際親善を優先する姿勢であり、日本の皇室が現代外交に対応した象徴的な出来事でした。
結論 ― 死穢観が示す日本的宗教観
神道における「死=穢れ」は、単なる迷信ではなく、
・生命を尊ぶ価値観
・共同体の安全保障
・宗教儀礼の純粋性
を守るための合理的な仕組みでした。
古代の忌服令から江戸の差別構造、皇室の死に関する作法、そして現代の外交における変化まで、この観念は形を変えながらも日本社会に深く影響を与えてきました。
死を穢れとする感覚は、今なお神社の葬儀回避や日常の慣習に息づいており、日本人の死生観を理解するうえで欠かせない要素といえるでしょう。
関連記事:神道特集
本記事は、以下の「神道」特集の一部です。
神道全般に関心のある方は、是非以下もあわせてご覧ください。
関連記事:日本と世界の遺体観
日本では、死を穢れとする神道の価値観に加え、近代に流行した疫病の記憶から「遺体」に対する恐怖感情が強く根づいています。
以下の記事では、近年話題となることが多い土葬問題を切り口に、日本と海外の「遺体観」の違いを比較しました。日本で「恐怖の対象」となりがちな遺体は、世界ではどのように捉えられているのか。ぜひ本記事とあわせてご覧ください。
とする神道2.png)
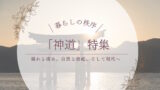

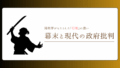
とする神道2-120x68.png)