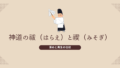死と並んで「血」もまた、神道では大きな穢れとされてきました。ここでは、血の穢れがどのように認識され、時代ごとにどのように扱われてきたかを見ていきます。
古代神話と血の穢れ
血の概念は古代神話の段階からすでに重要な役割を果たしていました。
古事記・日本書紀に見る「血」
古事記や日本書紀には、血がもたらす吉凶両面の象徴性が描かれています。
たとえば、イザナギが火の神カグツチを斬ったとき、その血から多くの神々が生まれたと記されています。血は「生命を生む力」として描かれる一方で、同時に災厄や死を連想させる危険な存在でもありました。
この二重性こそが、神道における「血の穢れ」の原点といえるでしょう。
出血=出産との両義性
出産の際の出血も、同じく穢れと見なされました。
当時の人々にとって出産は、血による穢れを伴う忌むべき出来事であると同時に、新しい命を迎える喜ばしい出来事でもありました。この相反する二面性が、出産に関する儀礼や隔離の風習を生んだと考えられます。
古代~律令期の社会制度
神話的観念は次第に、具体的な生活規範や制度へと組み込まれていきました。
産忌(うぶいみ)と血の忌避
出産に伴う血は強い穢れとされ、母子を一定期間共同体から隔離する「産忌」という習俗が存在しました。これにより、母子は産屋や産小屋と呼ばれる別棟に籠るのが一般的でした。
律令制下でまとめられた『延喜式』にも、出血にまつわる忌み事が条文化されており、国家的な規範としても扱われていたことが分かります。
産屋の独立構造
古代から中世にかけては、出産のために家屋から離れた場所に産屋を設ける風習が広く見られました。これも「血の穢れ」を共同体から切り離すための仕組みと理解できます。
中世・近世の慣習
血の穢れは、共同体の生活や宗教儀礼に深く関わっていきました。

月経と女性の「不浄」観
月経の血も忌避の対象とされ、女性はその期間、神事や祭祀から距離を置くのが通例でした。
また、中世以降には仏教由来の「血盆経(けつぼんきょう)」が広まり、女性が血の罪を背負うといった観念が浸透しました。
こうした思想は、女性差別的な価値観を補強する要因のひとつともなりました。
血の池地獄という名称
大分県別府市の「血の池地獄」は、赤い熱泥が湧き出す温泉として知られています。
その名は、仏教に伝わる「血盆池(けつぼんち)」の観念と重ねられたものです。血盆池(別名:血の池地獄)は、女性が出産や月経で流す血によって罪を背負い、死後に落ちるとされた地獄です。
中世中国で成立した『血盆経』では、僧侶が経を唱えたり、生前に信仰することで、この血盆池から救われると説かれました。こうした信仰は日本にも伝わり、女性の供養や安心を支える重要な役割を果たしました。
中世以降に広まったこうした仏教的女性観が、自然現象と結びついて「血の池地獄」という名を生んだのです。神道の「血の穢れ」とは直接の関係はありませんが、血を不浄とみなす価値観が広く人々の意識に根づいていたことを示す興味深い事例といえるでしょう。
月経小屋と女性の隔離
中世から近世にかけて、日本各地では月経や出産に伴う「血」を穢れとみなし、女性を一時的に隔離する風習が存在しました。農村部では「籠屋」「産屋」などと呼ばれる小屋が設けられ、女性はそこで数日を過ごしました。
これは宗教的な「清浄観」に基づくと同時に、当時は適切な生理用品がなく、共同生活の場を衛生的に保つための実際的な配慮でもあったと考えられます。世界的にも月経小屋はアジアやアフリカ、南米に広く見られる慣習であり、日本独自の現象ではありません。
近代以降、衛生環境の改善や生理用品の普及によって急速に廃れていきましたが、血の穢れという観念は、神道的な清浄思想と結びつき、長らく人々の生活に影響を与え続けていたのです。
月経小屋の評価と指摘
月経小屋は「血の穢れ」という価値観に基づく隔離の場であり、現代から見れば女性差別的な風習とみなされます。
しかし同時に、当時の女性にとっては家事や農作業から解放される休息の場であり、近代以降に整備された「生理休暇」と通じる部分があります。また、女性同士の交流や知恵の共有が行われる大切なコミュニティーでもあったと指摘されています。
武士社会と流血
一方で武士の社会では、戦いや刑罰などによる流血が日常的に伴いました。
しかし、それでも神社参拝や婚礼といった清浄を重んじる場面では、血穢れは明確な禁忌とされていました。
血の存在は「日常」と「祭祀」の境界を強く分ける要素だったのです。
流血後の「禊」
戦や狩猟で流血を伴った後には、川や海で身を清める「禊(みそぎ)」が行われました。血の穢れを水で洗い流すという発想は、現代の神道儀礼にも受け継がれています。

山岳信仰と女人禁制
中世に入ると、修験道や仏教の影響を受けて、山岳信仰の聖地には女人禁制の習慣が広がりました。
奈良県の大峰山や富山県の立山、さらには富士山も古くは女性の立ち入りが制限されていた場所です。背景には、神道的な「血の穢れ」の観念に加え、仏教が強めた「女人不浄観」がありました。
山は修行と神の宿る場とされ、清浄さを守るために女性が遠ざけられたのです。こうした慣習は地域差はあれど全国的に見られ、近世に至るまで長く続きました。
近代における変化
明治維新によって日本社会は大きな変革を迎え、女人禁制の慣習も例外ではありませんでした。
伝統として守られてきた山岳の禁制は、近代国家建設の流れの中で見直されていきます。
明治政府による女人禁制の廃止
1872年、明治政府は太政官布告によって全国の霊山における女人禁制を廃止する方針を示しました。これは、神仏分離や修験道廃止と並んで、近代国家としての合理性や国民平等を打ち出す政策の一環でした。
伊勢神宮や熊野三山、大峰山など古くから女人禁制を守ってきた霊場も対象となり、女性の参拝が可能になりました。布告は「封建的で迷信的な慣習の打破」を目指したものであり、神聖な領域への女性立ち入りが制度的に認められる大きな転換点となりました。
例外として残る女人禁制
しかし、布告が出されたからといって、すべての地域で即座に慣習が消えたわけではありません。信徒や地元の強い反発もあり、特に修験道の聖地である奈良県の大峰山山上ヶ岳(おおみねさん さんじょうがたけ)は、今も女人禁制を厳格に守り続けています。また、福岡県の沖ノ島(宗像大社の神領)も「神宿る島」として古代祭祀の伝統を保持しており、女性は一切立ち入ることができません。
関連サイト:世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
こうした例は世界遺産登録の際に「女性差別ではないか」と国際的に議論されましたが、日本側は「宗教的伝統の尊重」と説明し、最終的には文化的多様性の一例として容認されました。
つまり、明治以降に多くの禁制は解かれたものの、今も少数ながら女人禁制を守る聖域が存在し、伝統と現代的価値観の間で揺れ続けているのです。
現代社会における影響
現代においても、一部の神社では出産や喪明け後に一定期間の参拝自粛を求める習わしが残っています。
また、月経と参拝をめぐる議論は、相撲の女人禁制などの問題とも重なり、現代社会のジェンダー論ともつながっています。血の穢れ観は形を変えつつも、文化的記憶として息づいているのです。
相撲と女人禁制 ー 神聖な土俵
相撲の土俵もまた「女人禁制」が維持されてきた場のひとつです。近世までは祭礼の余興として女性が相撲を取る「女相撲」も存在しましたが、明治期に相撲が「国技」として制度化される過程で、土俵は神聖な神事の場と位置づけられ、女性の立ち入りが禁止されました。背景には、神道的な「血の穢れ」の観念と、近代国家が強めた男性中心的な社会規範が重なっています。
この伝統は戦後も続き、2018年には京都府舞鶴市で市長が土俵上で倒れた際、救命のため駆け寄った女性に対して「女性は土俵から降りてください」と場内放送が流れ、大きな批判を呼びました。日本相撲協会は「伝統」を理由に女人禁制を維持する姿勢を示しましたが、「人命より伝統を優先するのか」という社会的議論に発展しました。
相撲の女人禁制は、宗教的起源を持ちながらも、近代以降の「国技」としての権威付けや男性優位社会の構造の中で強化されたものです。そのため現代では「伝統文化の尊重」と「ジェンダー平等」の間で揺れ動く象徴的な事例となっています。
関連記事:命よりも大事なものはあるのか?
歴史の中では、「命よりも大事」とされたものがいくつもあります。
以下の記事では、歴史の中の事例を紹介するとともに、現代も議論が行われている「人の尊厳」について考えています。興味のある方は是非ご覧ください。
皇室の慣習
皇室では現在も出産に関連した伝統的な儀礼が続けられています。これは「血の穢れ」を避ける古代的な思想が、現代にまで連続している事例のひとつです。
日々の生活と日本の伝統
血の穢れは、死の穢れと並んで神道における重要な観念でした。血は生命を生むものであると同時に、死や不浄をもたらすものとして恐れられてきました。
科学的理解が進んだ現代においても、祭祀や文化的習俗の中に血の忌避は姿を変えて残っており、日本人の精神文化を考えるうえで欠かせない要素といえるでしょう。
伝統か合理性か
現代では合理性や個人の価値観が重視され、神社への参拝は誰にでも開かれています。日本人だけでなく、神道をよく知らない外国人観光客も数多く訪れています。
そのため、ときには日本人から見ると驚くような行動がとられることもあり、SNS上では批判の声があがることもあります。こうした摩擦をなくすためにも、日本人自身が神道の伝統を学び直すことには大きな意義があるでしょう。
一方で、神道の教えの中には、すでに合理性を失った概念も少なくありません。かつての女人禁制が時代の中で見直されていったように、社会に合わせて変えていく必要があるのかもしれません。伝統と合理性の狭間で、私たちがどう向き合うのか――それは現代社会に課せられた大きな課題の一つなのではないでしょうか。
関連記事:死を穢れ(けがれ)とする神道
今回の記事では、神道の「血の穢れ」を扱いましたが、以下の記事では「死の穢れ」をまとめています。
歴史の中で行われた差別や、現代の忌引き休暇の由来なども紹介しています。土葬問題などで、日本人は遺体を強く忌避しますが、これには日本の宗教や歴史が影響しています。是非合わせてご覧ください。
とする神道.png)

とする神道-160x90.png)