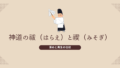神道は「死」を穢れ(けがれ)とみなし、忌避してきました。しかし明治以降、日本国家は「死」を「英霊」として祀る方向へと転換します。その象徴が靖国神社です。
本記事では、神道における「死」と、国家神道による「英霊」の違いを宗教的な観点から整理します。その上で、「尊崇の念」という言葉にも見られる「日本人の複雑な宗教観」を考えます。
神道における死の穢れ
まずは神道における伝統的な死生観を確認します。

死の忌避と神域の原理
神道では、死は穢れ(けがれ)とされました。
生命力を奪うものとして恐れられ、神域に近づけてはならないものだったのです。神体や神域は「清浄」であることが求められ、死者の存在はその秩序を乱すものと考えられました。
穢れ(けがれ)という概念
神道における「穢れ」という概念自体も、そもそもどのようなものか議論が続いています。
神道において「死」と「血」は代表的な穢れとされ、特に強く忌避されてきました。
死は「生命力の欠如=気枯れ」と捉えられ、血は「物質的な汚れ」と結びつけられることがありますが、実際には両者が入り混じり、独特な「穢れ」観念が形成されたと考えられています。
葬送が仏教に委ねられた理由
こうした考えから、神道には体系的な葬送儀礼は整いませんでした。日本では古代から仏教が葬式や供養を担い、死者の魂を慰める枠組みを提供してきました。
人々の死生観の実務部分は、事実上仏教に依存していたのです。
補足:怨霊を祀る神社の存在
神道では本来、死は神域から遠ざけられる存在です。
しかし例外的に、菅原道真を祀る天満宮、崇徳上皇を祀る白峯神宮、平将門を祀る将門神社など、怨霊と恐れられた人物を鎮めるために創建された神社もあります。
これは「死を穢れ」とする神道において、祟りを避けるために死を祀った特異な事例といえます。
招魂祭から靖国神社へ
近代国家は、戦没者の扱いを新たに制度化する必要に直面しました。
招魂の系譜
戊辰戦争では多くの戦死者が出ました。これを慰霊するために行われたのが「招魂祭」です。御霊信仰など前近代の鎮魂観に由来しながらも、戦没者を顕彰する新しい儀式として発展しました。
| 用語 | 読み | 意味 |
|---|---|---|
| 招魂 | しょうこん | 霊を呼び戻して祀る行為。主に戦没者や先人の霊を対象とする。 |
| 御霊 | みたま | 亡くなった人の霊を指す言葉。怨霊を祀ることで御霊となり、 さらに神として崇敬の対象になると考えられた。 |
| 鎮魂 | ちんこん | 霊を慰め、落ち着かせる行為。怨霊を鎮める儀礼としても行われた。 |
| 顕彰 | けんしょう | その人物の功績や徳を明らかにし、広く称えること。 国家神道では英霊を讃える形で用いられた。 |
| 合祀 | ごうし | 複数の霊を同じ祭祀対象にまとめること。 |
靖国神社の創設
靖国神社は、明治2年(1869年)に明治天皇の勅命によって「東京招魂社」として創建されました。創建の直接の契機は、戊辰戦争で新政府側(官軍)として戦い、命を落とした兵士たちを祀ることにありました。当初は、明治維新を支えた戦没者の慰霊と顕彰を目的としていたのです。

その後、西南戦争や日清戦争、日露戦争といった国内外の戦争・事変のたびに、戦没者の霊が次々と合祀されました。昭和期には第一次世界大戦、日中戦争、さらに太平洋戦争(大東亜戦争)へと対象が広がり、現在ではおよそ246万6千柱もの「英霊」が祀られています。
明治12年(1879年)には「靖国神社」と改称されました。
靖国とは「国を靖(やす)んずる」、すなわち「国の平安と安寧を祈る」という意味であり、国家のために殉じた人々を神として祀る国家的施設としての性格が明確化されました。こうして靖国神社は、戊辰戦争を起点としつつ、近代日本の歩みとともに「国家に殉じた英霊」を祀る場として拡大していったのです。
国家神道と「英霊」観の形成
国家は「死」を穢れから栄誉へと転換する物語を作り上げました。
「英霊」という意味付け
靖国に祀られる戦没者は「英霊」と呼ばれました。
彼らは国家の守護神とされ、その死は「栄誉」と位置づけられました。この意味付けは教育や儀礼を通じて国民に浸透し、忠誠と献身を支える道徳規範として機能しました。
死を穢れとする「神社」で祀られる理由
英霊は「単なる死者」ではなく、「神格化された存在」として位置付けられました。そのため、死を穢れとして遠ざける神社でも祀られているのです。
一方、例外的に神社で扱われる「怨霊」は、まず「死者」として恐れられました。祀られることによって「御霊(みたま)」、さらに「神」へと変化したと考えられています。
伝統神道とのズレと接合
この英霊の意味付けは、死を忌避する神道の伝統とは相反します。しかし明治政府は、神道の枠組みを政治的に転用し、死者を祀る仕組みを制度化しました。
神道本来の「穢れ」観は逆転され、国家に殉じた死が「神聖なもの」とされたのです。
補足:国家神道のハイブリッド性 (神道+儒教+仏教)
国家神道は、純粋な神道の延長ではありませんでした。
- 神道の要素:天皇祭祀や清浄観を基盤とする。
- 儒教の要素:教育勅語に代表される忠孝・道徳秩序。
- 仏教の要素:本来神道にない「慰霊」「供養」の観念を取り込み。
これらを融合したハイブリッドなイデオロギー体系こそが、国家神道だったのです。
靖国神社の特異性
靖国神社は神社でありながら、他の神社と大きく異なります。
対象選別と包摂/排除
靖国で祀られるのは「国家に殉じた者」に限定されます。氏神信仰や自然神を祀る神社とは、対象の論理がまったく異なります。
宗教性と政治性の結合
靖国は慰霊と顕彰にとどまらず、戦意高揚の役割も果たしました。儀礼は宗教行為であると同時に、政治的なメッセージを帯びていたのです。
靖国神社への参拝では、通常の神社と同じように鳥居をくぐって神域に入り、手水や鈴などを通じて身を清め、神(英霊)と向き合います。この作法は紛れもなく神道のものです。しかし、参拝の心持ちは神への畏敬だけでなく、追悼や敬意といった感情が込められることも多い点に特徴があります。(後述:「尊崇の念」という言葉)
補足:地方版靖国としての護国神社
各都道府県に設置された護国神社は、地域出身の戦没者を祀る場です。
靖国を中央とすれば、護国は地方の補完的存在でした。祀られる対象はいずれも「英霊」であり、昭和14年(1939年)に「護国神社」の名称で統一されました。
戦後と現代の論点
敗戦後、靖国神社は新たな争点となりました。
政教分離と公私の境界
国家神道は解体され、靖国は宗教法人となりました。しかし首相や閣僚の参拝をめぐり、それが「公的」か「私的」かは常に議論の的となっています。

中国・韓国など近隣諸国との外交問題にも発展しました。国内でも靖国参拝は賛否を分けるテーマであり、歴史認識や政治姿勢を映す鏡となっています。
「尊崇の念」という言葉
靖国参拝をめぐる発言の中で、しばしば「英霊に対し尊崇の念を表する」という表現が使われます。この言葉は、一見すると先人に敬意を払うシンプルな言葉に思えます。
しかしその由来をたどると、単なる敬意の表現以上の背景が見えてきます。
- 神道との関係
神道の伝統的語彙には「崇敬」「畏敬」などがあります。「尊崇」も近代以降に神社界で用いられるようになりましたが、古来からの言葉というよりは、近代神道の制度化の中で整備された表現です。 - 仏教との関係
仏教では「供養」「敬虔」「帰依」といった言葉が中心で、「尊崇」という語はあまり一般的ではありません。 - 儒教との関係
「尊」や「崇」は儒教的な徳目表現でもあり、忠孝や敬意を表す言葉として古来から用いられてきました。「尊崇」という熟語は、むしろ儒教的な影響が色濃いと考えられます。 - 国家神道における定着
明治以降、国家は戦没者を「英霊」と呼び、その顕彰を制度化しました。
その際に「尊崇の念」という表現が、宗教的色合いを抑えつつ「敬意」を表現する公式用語として広く使われるようになったのです。
このため「尊崇の念」という言葉は、単に美しい日本語表現であると同時に、国家神道的な背景を持つ言葉でもあります。慰霊でも畏敬でも感謝でもない、神道・儒教・仏教が入り混じったハイブリッドな用語であることが、日本人の宗教観の複雑さを象徴しているといえるでしょう。
日本人の宗教観
靖国神社は、国家神道により神格化された「英霊」を祀る場所です。英霊は神道における「死の穢れ」としては扱われず、むしろ顕彰と守護の対象として祀られてきました。そのため、靖国参拝には「慰霊」や「畏敬」「感謝」など、さまざまな心情が重なり合っています。この複雑な感情を表す言葉としてよく用いられるのが「尊崇の念」であり、それは神道・儒教・仏教が混ざり合った国家神道的な精神性を色濃く映し出しています。
日本の宗教観は非常に柔軟で、外来の価値観を取り込みつつ、新しい宗教やイデオロギーを生み出してきました。明治以降に西洋文化を積極的に受け入れられたのも、この柔軟さの一つの表れといえるでしょう。
柔軟な日本宗教と厳格な外国宗教
ただし、宗教に対する姿勢は国や文化によって異なります。日本の宗教は時代や状況に応じて形を変える柔軟さを持ちますが、他方で、経典や戒律を絶対視し厳格に守ることを重んじる宗教も少なくありません。
この違いは、ときに価値観の摩擦を生みます。
神道が「死を穢れ」としながらも、怨霊鎮めや仏教・儒教との融合を通じて「英霊」という概念を生み出したのは、妥協と調和の一つの形でした。しかし、他の宗教では「火葬はできない」「特定の食材は口にできない」など、揺るがせない規範が存在することもあります。
日本的な柔軟さが必ずしも通用しない場面があるのです。
宗教を理解する大切さ
日本では、仏式の墓前では「慰霊」、神社での参拝では「畏敬や感謝」という心持ちが求められるはずですが、しばしば両者を曖昧に混同して行動してしまうことがあります。これは日本の宗教観の柔軟さの表れである一方、対象に対する理解が浅いと「無意識に失礼になってしまう」危険も含んでいます。
先人に対して「礼を失する」ことを避けるためにも、まずは身近な宗教について「どのような心持ちで臨むべきか」を理解することは大切です。
それは結果的に、他宗教や異なる文化を理解する姿勢にもつながるのではないでしょうか。
靖国神社は、その複雑な宗教観や歴史を通じて、現代の私たちに「宗教をどう理解するか」という問いを投げかけているのかもしれません。
関連記事:死を穢れ(けがれ)とする神道
死を穢れとする神道からすると、靖国神社で戦没者を英霊として祀るのは例外的な位置づけです。以下の記事では、忌引き休暇の起源や江戸時代の差別など、日本の歴史の中で「死」がどのように遠ざけられてきたのか、古代から近代まで紐解いて解説しています。
靖国神社や国家神道の独自性について理解を深めたい方は、是非あわせてご覧ください。

とする神道-160x90.png)