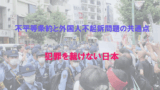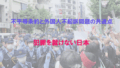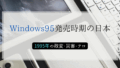令和時代の現代では、政治を批判する声が毎日のように聞かれます。特にSNSなどでは現在の政府である石破内閣や、政府与党の自民党・公明党への攻撃的な発言もみられ、国内ではデモ活動も行われるほどの状況になっています。
歴史の中にも、政治への批判が過熱していた時期というのがいくつかありますが、今回はその中から井伊直弼(いいなおすけ)の時代を紐解いてみることにします。
現代と似た状況ともいえる幕末の時期に、外交交渉の最前線にいた井伊直弼は、批判する人たちの手によって暗殺されました。井伊直弼の事件は、政治的に国民の誤解を解くことができない状況下で起きた悲劇という側面があり、この事件から「政治批判に求められる冷静さ」を改めて考えてみます。
井伊直弼の政治と暗殺
日本の義務教育課程では、井伊直弼(いいなおすけ)という政治家を必ず習います。江戸時代末期に大老という役職にあった井伊直弼は、ペリー来航以降の激動の時代で難しい判断を迫られます。
彼については、現代の日本では「欧米列強に日本を売り渡した売国奴」といった認識が多いように感じられますが、実際にはどのような人物であったのか確認してみましょう。
不平等条約(日米修好通商条約)の締結
江戸幕府末期の日本は、ペリー来航以降諸外国との外交交渉に苦戦します。絶大な軍事力を背景にした威圧的な外交を仕掛けてくる欧米列強に対抗することが難しく、日本は相手国の要求をのまざるを得ない状況でした。
歴史的に、大きな流れは以下のようになっています。
| 西暦 (年) | 出来事 | 井伊直弼 |
|---|---|---|
| 1853 | ペリー来航 | – |
| 1854 | 日米和親条約 | – |
| 1857 | 日米追加条約 | – |
| 1858 | 日米修好通商条約 (6月) | 大老就任 (4月) |
| 1860 | 桜田門外の変 | 暗殺 |
日米追加条約は、下田協定(協約)とも呼ばれる、日米和親条約の補足条約です。治外法権を含んだ不平等条約でもあり、その後の日米修好通商条約の土台となりました。以下の記事でも触れていますので、詳しく知りたい方は是非ご覧ください。
鎖国派でありながら開国を主張した井伊直弼
よく勘違いされがちですが、井伊直弼は元々は鎖国派の人間です。ペリー来航以降には、鎖国継続を主張する書状なども送っていますが、その後すぐに考えを転換して開国を主張するようになっています。
井伊直弼は「攘夷は無謀」と考えるようになり、外国から技術を学ぶことで力を付けて、改めて鎖国体制へ戻すという戦略を考えていました。1853年8月に送られた井伊直弼の意見書には、以下のように記されています。
海軍力を整備し、遠洋を航海できる技術を得れば、時宜を得て鎖国に戻すことも可能
日米修好通商条約とアロー戦争
1858年の4月に大老になった井伊直弼は、6月には窮地に立たされます。
日本がアメリカから通商条約を持ちかけられたのは1857年の12月でしたが、日本は調印に消極的でした。しかし、1858年の6月に入ってから、清国で軍事衝突(アロー戦争)しているイギリス・フランスが侵略に押し寄せてくる前に、日本に友好的なアメリカと結ぶべきと指摘を受けて、条約締結の判断をすることになります。
調印に対する姿勢 – 天皇の許可
ほとんどの幕僚は開国派で条約締結に天皇の勅許は必要ないと考えていましたが、井伊直弼(と他1名)は条約締結には天皇の勅許を得るべきと主張していました。井伊直弼は急ぎ天皇の許可を得るために奔走し始めます。
待機しているアメリカに対しては「時間がない場合はやむなし。できるだけ時間稼ぎを」という姿勢でしたが、この方針を「調印の承諾」を得たと判断した開国派が、アメリカと早々に調印してしまいます。これが「日米修好通商条約」です。
違勅調印を巡る幕府批判
条約調印の経緯について、朝廷から幕府に「御三家か大老」へ説明を要求しますが、大老の井伊直弼は多忙を理由に上京せず、代わりに老中を派遣します。この対応に不満を持った薩摩藩や水戸藩は、朝廷に働きかけて幕府の体制を改める密勅を得ます。
この密勅は戊午の密勅(ぼごのみっちょく)と呼ばれ、その後国内を揺るがすことになります。
幕府体制を批判する朝廷からの言葉は重く、朝廷が幕府を経由せず諸藩と繋がる構造は、政治体制の崩壊を意味していました。
安政の大獄 – 朝廷を担いだクーデターを処罰
朝廷に掛け合って戊午の密勅を得て、幕府体制の崩壊を画策した犯人らは、井伊直弼ら幕府側に調べられて捕縛・処罰されることになります。このクーデター未遂に加担した人間は次々と処罰され、最終的には100名を超える人が投獄や処刑されることになりました。(安政の大獄 1858-1859年)
それと同時に、朝廷にも条約調印の経緯を説明して、幕府と朝廷の関係は修復されます。
朝廷にも、「条約は一時的な物で鎖国に戻す」ということで納得してもらいましたが、この政治的な裏事情が知られると諸外国の反発を招き、場合によっては軍事衝突も誘発させかねないため、公表することはできませんでした。
戊午の密勅の返還要求
関係を修復した幕府は、朝廷から「戊午の密勅の返納」という勅書を得ます。つまり、先の密勅は無かった事にするので返す様にという命令が出されたわけです。返納の勅書を得た幕府は、水戸藩へ密勅返納を要求し、水戸藩はそれを直ぐに承諾する決断をします。しかし、水戸藩内の尊王攘夷を訴える一部の過激派はこれに反対します。
幕府から「返還しなかった場合に重い罰則(改易)を与える」という脅しを提示されたことで、過激派たちは井伊直弼の暗殺を決意し、計画を具体的に詰め始めます。
| 年月 | 出来事 | 朝廷と幕府 |
|---|---|---|
| 1858年 6月 | 日米修好通商条約 | |
| 1858年 8月 | 戊午の密勅 | 朝廷の幕府批判 |
| 1859年 2月 | 密勅返納の勅書 | 関係修復 |
| 1860年 1月 | 「戊午の密勅」の返納要求 水戸藩で返納を決定 | |
| 1860年 2月 | 密勅返納の催促 暗殺を決意 | |
| 1860年 3月 | 桜田門外の変 |
桜田門外の変
違勅調印と将軍継嗣問題などによって幕府との関係が悪化していた水戸藩を中心として、倒幕の計画が進められていましたが、計画の一端を担っていた薩摩藩が踏みとどまったために、大規模なクーデター作戦は諦められ、井伊直弼の暗殺計画だけが進められることになりました。
井伊直弼の暗殺は、1860年の2月に決意され、3月には実行されました。
早朝、江戸城に向かう籠に載った井伊直弼に、直訴状を渡す振りをして近づいた元水戸藩氏達は、警護の者を切りつけ、籠を銃で撃ち、それを合図に一斉に襲い掛かりました。井伊直弼は致命傷のまま籠から引きずり出され、首を切り落とされます。(桜田門外の変)
誤解されたまま暗殺された政治家
井伊直弼は、日本の将来を考えて現実的な外交交渉を進めていた人間とも言えるでしょう。日本の軍事力は欧米列強に対して圧倒的に劣勢で、攘夷が無謀という井伊直弼の主張は、その後の歴史が証明してもいます。(1863年の下関戦争や薩英戦争など)
また、朝廷や天皇に対しても、十分配慮したバランスの良い政治を行おうと努めていたように見えます。
井伊直弼の政治的な判断を公にしてしまうことはできず、不平等条約締結について知った国民は、井伊直弼について誤解したまま批判を続けることになります。水戸藩のような関係者は、朝廷からの「密勅の返納」で天皇の意思を知ることができていたにも関わらず、一部の過激派は行動を起こしてしまいます。
短すぎる就任から暗殺の期間
井伊直弼が大老に就任したのは1858年の4月、桜田門で暗殺されたのが1860年の3月で、大老職として政治活動を行っていたのは約2年程しかありません。
その間に、日米修好通商条約の締結、クーデター計画(と安政の大獄)があり、後始末の最中に桜田門で襲撃され命を落とします。長い間の政治活動を批判されたのでもなく、国家転覆計画を処罰したことをまるで「独裁や横暴」のように批判する声もあったようです。
勝手に調印された条約について批判され、誤解を解くこともできずに暗殺された井伊直弼の無念さは計り知れません。
令和の外交に対する批判
令和の現代では、政治に対する批判が多く聞かれます。物価高で苦しい国民生活が経済政策の批判を呼び、外国人による国内犯罪などが対外政策に関する批判に繋がっているようです。
その中でも特に大きな批判の対象となっている政治家を挙げてみます。
岩屋毅 – 中国にすり寄る外務大臣
令和の石破政権で外務大臣を担う岩屋毅氏は、親中の国会議員として国民から批判されることが多く、大阪カジノ誘致に関連して中国からの不正なお金を受け取っているとして、アメリカには入国できない州もあるという話も聞こえてきます。

国会においても、「尖閣諸島は日本の領土か」と問われた際に明言を避けたことも話題となり、SNSなどでは国民の敵とまで言われています。#岩屋毅外務大臣の更迭を求めますという署名活動も行われ、多くの賛同者がいる状況が日刊ゲンダイなどでも報じられました。
石破茂 – 関税交渉や米輸出で批判される
アメリカでトランプ大統領が誕生してから、日本も高い関税を掛けられることとなりました。日本の産業を守るためにもアメリカとの交渉を望む声が多く聞かれましたが、石破政権は「お願い」するだけで、何の成果もあげられず国民からは大きな失望が感じられます。

また、国内で米価格が高騰しているにも関わらず、米の輸出強化政策を進めていることも、内閣総理大臣の石破茂氏への批判に繋がっているようです。
関税自主権を失い、治外法権を認めさせられていた不平等条約下の日本と、現代の石破政権下の日本では、似ている事象が多く見受けられます。
見えていない事にも注意しよう
井伊直弼は日本を欧米列強に売り渡した売国奴・国賊といった認識が広まっていますが、実際には危機にある日本の未来のために必死に動いていた一人の政治家という側面もあります。また、天皇と幕府は違勅調印についても和解していましたが、政治的に公表することが難しい内容であったために、国内の誤解は解消せず、過激な思想の人が誤解したまま行動を起こしてしまうことになりました。
現代においては、政治に関心を持った国民が、インターネットなどの技術の普及に伴って、政治家や政策などを監視することが容易な時代になりました。政治家の言動が良いことも悪いことも直ぐに周知され、話題となります。広まった言動には動画や音声など具体的な証拠が付いていることも多く、国民が信じるに足りる情報であり、真実でもあります。
大前提としては、国民を裏切るような政治は「批判されてしかるべき」です。
ただし、冷静に考える必要はあるでしょう。政治の駆け引きがすべて公開されていては、諸外国との交渉にも影響がある事が容易に想像できます。自分の知っている情報が「すべて」と考えず、冷静に情報を収集して分析した上で、最終的な判断をするべきだと、歴史が教えてくれています。