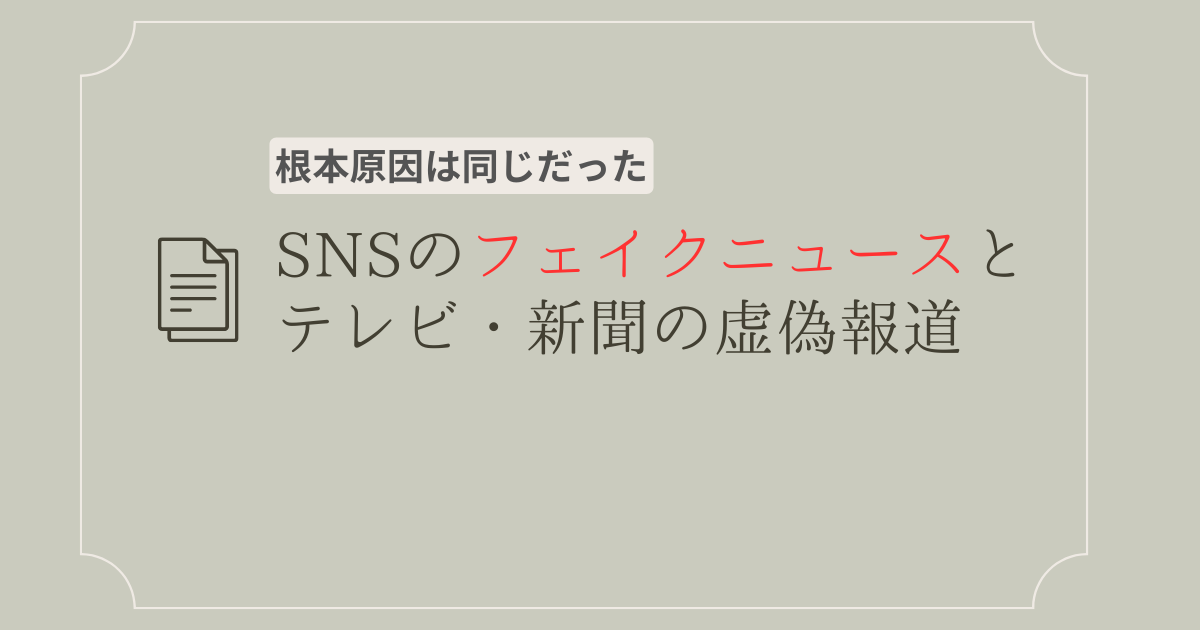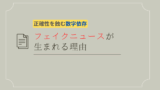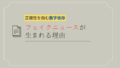SNSのフェイクニュースは現代社会の大きな課題として語られますが、テレビや新聞といったマスメディアも過去に数多くの虚偽報道や誤報を起こしてきました。
本記事では、両者の事例を比較しながら、発生の背景や共通する原因についてまとめています。その上で、「情報の速度を落とさず正確性を高めるための改善策」を提案しています。情報の受け手・発信者双方に役立つ、実践的な内容となっています。
テレビ・新聞における虚偽報道の事例と特徴
まず最初に、これまでのメディアの中心にあったテレビや新聞といったマスメディアについて確認してみましょう。
公正な報道を行う機関であると信じられているマスメディアですが、過去には虚偽報道が問題となった事例もあります。ここではその代表例を紹介しながら、構造的な要因について考えます。
過去の代表的な事例
マスメディアが虚偽や捏造で民事訴訟になった事例の中から、Wikipediaにも載っているほどの事件になったものを2点だけ紹介します。
- 朝日新聞「サンゴ損傷事件」(1989年)
概要:西表島サンゴの写真に「落書き被害」と報道 → 実は記者自ら傷をつけて撮影
結果:関係者解雇・謝罪広告、数百万円の慰謝料支払い
出典 : 朝日新聞珊瑚記事捏造事件 (Wikipedia) - フジテレビ「あるある大事典II」捏造問題(2007年)
概要:「納豆で痩せる」特集で実験データを捏造
結果:消費者や企業から損害賠償請求(複数和解)
出典 : 発掘!あるある大事典 – データ捏造問題 (Wikipedia)
その他、雑誌などでは「噂」を記事にしたために名誉棄損で訴えられたという事例は数多く存在しています。
誤報に関する法律・刑事罰
日本では「誤報そのもの」を直接的に刑事罰で処罰する法律はありません。刑事責任が問われるのは、主に報道によって特定の法益(名誉、信用、秩序など)を侵害した場合に限られます。
刑事上の責任(刑法など)が問われる罪としては、以下のようなものが挙げられます。
- 名誉毀損罪(刑法230条)
- 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)
- 虚偽報道による選挙妨害(公職選挙法235条など)
また、民事においても名誉や信用の棄損の他、精神的苦痛などで訴えられる可能性もあります。
- 損害賠償責任(民法709条 不法行為)
- 慰謝料請求
放送法においても、放送事業者は「事実をまげないですること」(第4条)を義務付けられています。
しかし、誤報が「単純な取材ミス」や「事実誤認」で、悪意や重大な過失が認められない場合には刑事罰が認められにくく、その場合は民事賠償や訂正報道での対応する形が一般的です。
法的視点:真実相当性という考え方
虚偽報道と聞くと、ただちに違法や不法行為と感じがちです。
しかし、日本の判例では、公共性・公益性を満たし、かつ取材時点で真実と信じる相当の理由(真実相当性)があれば、違法性が阻却(そきゃく)される場合があります。
つまり、結果的に誤報となっても、当時の取材が十分であったなら法的責任を免れる可能性があるのです。
逆に、裏付けが不十分であったり、意図的に事実を歪めた場合は真実相当性が認められず、責任を問われやすくなります。
発生する構造的な要因
- 速報性を優先する取材文化
- 事実確認の工程不足
- 経営・編集の独立性が弱く、外部圧力に左右されやすい
訂正・謝罪の限界
新聞は紙面の片隅、テレビは短時間の謝罪コメントで訂正されることが多く、誤情報の方が記憶に残りやすいという問題があります。
SNSにおけるフェイクニュースの事例と特徴
YouTubeやX(旧Twitter)などには、有用な情報がある一方で、単純な間違いやアクセス数を稼ぐ目的等で作られた虚偽情報も存在しています。
拡散の速度と規模
SNSは誰でも瞬時に発信でき、投稿は数分で数万人に届くことがあります。情報の真偽が検証される前に拡散が進むのが最大の特徴です。
主な事例
- 災害時のデマ(「○○ダム決壊」など)
- 著名人の死亡デマ
- 選挙前の候補者に関する虚偽情報
日本でもフェイクニュースが問題となっていますが、韓国でもAIを使って作成されたフェイク動画などが拡散し、社会問題となっているようです。
出典 : ウソの訃報も…韓国で「フェイク」動画急拡大で社会問題に
李在明大統領が“規制強化”指示…過激YouTuberの行動抑制する狙いか
(FNNプライムオンライン)
訂正が困難な理由
- 発信者が匿名・偽名で特定困難
- アルゴリズムによる再拡散で古い誤情報が何度も浮上
- 出典や一次情報が不明なまま引用が繰り返される
虚偽報道とフェイクニュースの比較分析
マスメディアの虚偽報道とSNSのフェイクニュースは、真実ではない情報が流布されるという点では同じです。誤情報により以下のような危険性があります。
- 個人や団体の名誉・信用を傷つける
- 世論や選挙の結果に影響を与える
- 社会的混乱を招く
マスメディアとSNSの特徴比較
その上で、マスメディア(虚偽報道)とSNS(フェイクニュース)の違いをまとめてみましょう。
| 項目 | マスメディア (テレビ・新聞) | SNS |
|---|---|---|
| 発信者特定 | 容易 | 困難(匿名多い) |
| 事実確認体制 | 編集部によるチェックあり(不完全) | 原則なし |
| 拡散速度 | 限定的(放送・紙面) | 爆発的(リアルタイム) |
| 訂正手段 | 紙面・番組内で告知 | 各ユーザーへの到達は困難 |
| 主な影響 | 世論形成、経済、選挙 | 感情的反応、社会混乱 |
マスメディアには編集者やデスク、内部の監査機関などの「精査する体制」があるのが一般的ですが、緊急性の高い情報などではチェックが甘くなることもあります。また、独立性が低い問題を解決するために設けられた第三者機関などは、実効力がなく、勧告を出す程度しかできないといった問題もあります。
マスメディアでは訂正報道が形式的で、SNSではそもそも誰が責任を持つか不明確。結果として、誤情報が半永久的に残り、人々の認識をゆがめ続けます。
どちらも確認体制の不足、訂正の脆弱さがあることが分かります。
なぜSNSだけが批判されるのか
テレビや新聞、そして行政も盛んに「SNSのフェイクニュースに気を付けろ」といった趣旨の警鐘をならしていますが、それは一体なぜなのでしょうか。
SNSを問題視する理由には以下のようなものが考えられます。
- 拡散力が桁違い
→ 個人の投稿が短時間で数百万人に届く - 責任所在の不透明さ
→ 誰が発信源か特定しにくく、訂正も困難 - 検証機能の欠如
→ 情報の裏付けがないまま感情的に拡散されやすい
→ マスメディアは不完全であっても努力はされている - 報道機関の信頼低下リスク
→ SNS発のフェイクニュースが「テレビで見た」「新聞に載っていた」と誤解され、マスメディアへの信頼も巻き添えで下がる
築いてこなかった虚偽情報の防止体制
フェイクニュース(SNS)と虚偽報道(マスメディア)は「事実と異なる情報による社会的影響」という意味で本質的に同じです。
歴史的にはマスメディアの誤報・虚偽報道は多数存在しており、現状は「テレビや新聞でできなかったことをSNSに求めている」状況と捉えることができます。
「まだ拡散速度が比較的遅い時代」に虚偽情報の防止体制を徹底しなかったことが、現在のSNS時代のフェイクニュース問題を深刻化させる土壌になったともいえるでしょう。
虚偽情報の防止と情報の訂正について、これまでマスメディアの陰で有耶無耶にしてきた課題が、情報の速度と量が爆発的に増えた現代になって、無視できない状況になっているのです。
現代に生きる私たちは、マスメディア・SNSに限らず、正確な情報を共有する仕組みを考えなければなりません。
今後の改善策:速度を落とさず精度を上げるには
SNSのフェイクニュースは大きな問題ではありますが、その一方で情報の量や速度を格段に向上させることに役立ってもいます。
そのため、改善策には虚偽情報を抑えながらも、全体の情報量や速度を落とさない精度が求められます。
現段階で考えられる改善策
現段階の改善策としては以下のようなものが考えられます。
- AIによるリアルタイムファクトチェック
投稿直後に公的データや信頼できる報道と照合し、信頼度スコアを表示。 - 出典明示義務化
医療・政治・災害など重要分野では一次情報の提示を必須に。 - コミュニティ型検証ネットワーク
ユーザー参加型で訂正情報を拡散し、誤情報と同じ速度で広げる。 - メディアリテラシー教育
「シェア前に確認する」習慣を学校教育で定着させる。
進む改善と変わらない体制
X(旧Twitter)などでは、コミュニティーノートやGrok(AI)などの機能的な対策が進められ、利用者の間でも「情報の精度」を気にする情報リテラシーが備わりつつあるようです。
その一方で、情報リテラシーの高いネットユーザーがマスメディアの報道に対しても同じように接するようになったことで、テレビ番組のやらせ(仕込み)インタビューが暴かれて炎上するといったことも起きるようになっています。
今後の改善策を考える上での大事な視点は、「SNSだけ」「マスメディアだけ」ではなく、情報を提供するメディア全てにおいて対策していかなければならないということでしょう。
おわりに:SNS時代の情報との付き合い方
私たちは今、発信者であり受信者でもある時代に生きています。「どこから来た情報か」「裏付けはあるか」という基本的な視点を持ち、誤情報を広げない意識が不可欠です。
SNSのフェイクニュースも、テレビ・新聞の虚偽報道も、本質は同じです。
この欠陥を埋める努力を社会全体で進めることが、情報時代を健全に生きるための第一歩となるのです。
フェイクニュースについては、今回まとめた内容以外にも、虚偽情報の流布が収益につながるという「構造的な問題」もあります。是非以下の記事もあわせてご覧ください。