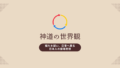💡この記事は、日本の伝統宗教「神道」特集の一部です。
巫(かんなぎ)とは、本来は神と人のあいだを取り持つ存在を意味します。その一部が神社に取り込まれ、巫女として定着しました。
古代から現代までの系譜をたどり、巫女の役割と神道における位置づけを解説します。
巫(かんなぎ)とは
まず最初に、巫(かんなぎ)という言葉の意味を押さえておきましょう。
「巫」という珍しい漢字
「巫」という字は、現代では「巫女」の語でしか目にすることがほとんどない珍しい漢字です。しかしその形と意味には、古代の宗教観が凝縮されています。
字の成り立ち
「巫」は会意文字で、両手を広げて天と地を結ぶ人の姿をかたどったものとされています。
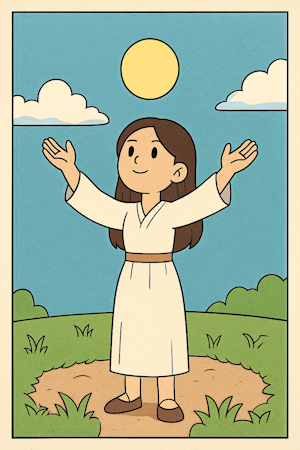
古代中国の甲骨文や金文では、舞をして神を呼び降ろす人物の姿が描かれており、神と人を媒介する存在を示しました。
本来の意味
本来の「巫」は、神に仕えて神託を伝えるシャーマンのことを指します。『説文解字』には「能以舞降神者也(舞によって神を降ろす者)」とあり、舞によって神を招き降ろす存在と説明されています。
中国では男性の巫を「覡(げき)」、女性を「巫(ふ)」と区別する場合もありました。
日本での用法
日本に伝わると、巫は神懸かりの人を広く指し、その中で特に女性を「巫女(みこ)」と呼ぶようになりました。「巫女」という熟語は日本独自に定着したもので、中国には存在しません。
巫の意味
「巫」とは、神と人間のあいだを仲立ちする存在を指します。
神懸かりして神の言葉を告げる者や、祈祷・祭祀を行う者を広く含む言葉でした。古代日本では男女を問わず存在し、政治や社会に大きな影響を及ぼしたと考えられています。
ここで注意すべきなのは、「巫」は必ずしも神道だけに属するものではない、という点です。
巫は東アジア全域に見られるシャーマン的存在であり、日本でも神道の枠組みに入らない民間信仰や地域の祭祀で活動していました。その一部が神社制度に取り込まれ、「巫女」として神道の役割に組み込まれていったのです。
巫と神薙の違い
「かんなぎ」という読みは「巫」にも「神薙」にもあてられます。両者は似ていますが、意味には違いがあります。
- 巫(ふ/かんなぎ):神に憑かれ、神託を伝える者。神懸かりの側面が強い。
- 神薙(かんなぎ):神を祀り、場を整える者。祭祀執行や祓いに重きがある。「薙(なぎ)」は「鎮める」「清める」の意。
古代には明確な区別がなく混同されることも多かったのですが、のちに「憑かれる者」と「祀る者」という役割の違いが意識されるようになりました。
巫の多様な役割
巫といっても、その役割は一つではありません。広義の巫はさまざまな姿に分かれており、それぞれに社会的な役割を担っていました。
神託を伝える者
神に憑かれ、神の言葉を語るのが最も典型的な巫の姿でした。古代の政治においても神託は重要視され、王権を支える根拠となることもありました。
その代表的な例が、3世紀に倭を治めたとされる女王・卑弥呼です。

『魏志倭人伝』によれば、卑弥呼は「鬼道に事え、能く衆を惑わす」と記され、神秘的な祭祀を通じて人々を導いたとされます。彼女自身は表に姿を見せず、神託を通じて政治を行い、弟が実務を補佐しました。
卑弥呼はまさに「巫的支配者」の典型であり、神託を媒介に国を統治した存在だったといえます。
祓いや鎮魂を行う者
病や災厄を祓う祈祷師的な存在も巫に含まれます。神の力を借りて禍を退ける役割を担い、のちには修験者や陰陽師の系譜とも重なっていきました。
芸能・舞を奉じる者
神楽や舞を奉納して神を楽しませる役割も巫の大事な職能です。これが後世、神楽巫女や神社の舞姫につながっていきます。
口寄せ・霊媒
死者や精霊の声を伝える「口寄せ」も巫の仕事でした。東北のイタコ、沖縄のユタなどはその代表例です。神社制度には組み込まれず、民間信仰の中でシャーマン的役割を果たしました。
遊行する巫女
中世以降には、神社に属さず各地を渡り歩き、芸能や祈祷を行う「遊行巫女(ゆぎょうみこ)」も登場しました。中には遊女的役割を担うこともあり、社会的評価は必ずしも高くありませんでした。
巫女の歴史的変遷
広義の巫の中から、神社に仕える女性を中心に「巫女」という存在が形作られていきました。その歴史的変化を時代ごとに見ていきましょう。
古代 ― 神聖な未婚女性としての巫女
古代には、伊勢神宮の斎王のように、天皇の血筋から選ばれた女性が神に仕える制度がありました。
巫女は神懸かりして神託を伝える存在とされ、特に未婚女性がその役割を担いました。
未婚であることは、俗世の性から離れた「清浄な存在」と見なされ、また女性は新しい命を生む力を持つため「神秘的で神聖」と考えられました。
こうした理由から、古代において女性は神と強く結びつく存在とされたのです。
中世 ― 巫女像の多様化
中世には巫女の役割が広がり、神楽を舞う巫女、口寄せを行う巫女、各地を渡り歩く遊行巫女などが登場しました。世襲制や職業化も進み、地域社会の中でさまざまな形で活動しました。
江戸時代 ― 神社と庶民信仰の中の巫女
江戸期には、神社に属して代々務める社家巫女(しゃけみこ)が存在しました。
一方で、庶民の信仰を支える口寄せ巫女や神楽巫女も活動しており、時に遊女的役割と混ざり合って社会的評価が揺らぐこともありました。
| 種類 | 読み方 | 特徴・役割 | 社会的位置づけ |
|---|---|---|---|
| 社家巫女 | しゃけみこ | 神社に属し、世襲的に務める常勤の巫女。 祭祀補助や神楽を担当。 | 神社組織の一員として比較的安定 |
| 口寄せ巫女 | くちよせみこ | 霊を憑依させ、死者や神の言葉を伝える。 イタコ的要素を持つ。 | 民間信仰で需要がありつつも、 迷信視されることも |
| 神楽巫女 | かぐらみこ | 神楽舞を舞い、祭礼を華やかにする役割。 芸能性が強い。 | 神聖性と芸能性を兼ね、 庶民にも人気 |
| 遊行巫女 | ゆぎょうみこ | 各地を渡り歩き、祈祷・舞・口寄せを行う。 遊女的要素と結びつく場合も。 | 社会的には低く見られることが多い |
近代 ― 国家神道下での再編
明治期に神社制度が整備されると、巫女は「神職の補助」として制度化されました。国家神道のもとで役割が整理され、神社に仕える女性は統一された形で位置づけられるようになります。
- 口寄せ巫女 → 「迷信・非科学的」とされ、国家神道では排除。
以降は民間信仰の中に残存(例:イタコ)。 - 遊行巫女 → 流浪・芸能・遊女的要素が問題視され、制度的には消滅。
- 神楽巫女 → 芸能性の強い要素は切り分けられ、神社神楽の一部に吸収。
独立した巫女像としては衰退。
こうして、神社に所属し、儀礼を補助する「社家巫女」系統が制度化され、現代の巫女につながっています。
現代の巫女像
近代から続く制度を背景に、現代の巫女像が形作られています。
白衣と赤袴
現代の巫女といえば「白衣と赤袴」が定番です。
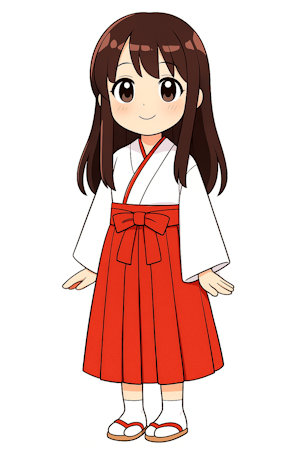
白は清浄、赤は魔除けと生命力を象徴する色で、古代からの未婚女性に結びつくイメージとも重なります。この配色は江戸から明治にかけて定着しました。
鳥居の朱色と巫女の赤袴は、どちらも魔除け・生命の色として共通した意味を持ちます。
現代の役割
今日の巫女は、神社祭祀の補助者として舞を舞い、御守りを授与し、儀礼を整える役割を担っています。古代のように神託を伝える神秘性は薄れましたが、神社の祭祀を支える重要な存在であることに変わりはありません。
現代の巫女の実態
現代の巫女は、古代の神懸かり的な存在とは大きく姿を変えています。
- 神社数と運営
日本には約8万の神社がありますが、その多くは神職のみで運営され、常勤の巫女がいるのは大規模な神社に限られます。 - 助勤・アルバイトとしての巫女
多くの神社で見られる巫女は、正月や祭礼シーズンに活躍する助勤巫女やアルバイト巫女です。特に初詣の時期には、若い女性が白衣と赤袴をまとい、お守りや御札の授与、参拝者の案内などを担います。 - 常勤巫女の役割
大きな神社では常勤の巫女も存在し、日常的な社務や儀礼補助、神楽舞を務めます。ただし人数は限られており、全国的にはごく少数です。
こうした実態から、現代の巫女は「日常的に出会う存在」ではなく、正月や祭礼で象徴的に姿を見せる存在となっています。赤袴の巫女を見かけると特別な雰囲気を感じるのは、まさにその希少性ゆえともいえるでしょう。
巫女の歴史が示すもの
巫とは、神と人間のあいだを取り持つ存在の総称でした。その中から、神社に仕える女性が「巫女」として定着していったのです。
現代においては、実際の巫女さんを見かけるよりも、漫画やアニメに登場する巫女キャラクターを目にする機会の方が多いかもしれません。それだけに、巫女や神道の歴史を知っていると、その姿の見え方もまた違ったものになるでしょう。
歴史を学んだからといって明日の生活が劇的に変わるわけではありません。しかし、身近な存在をより深く理解できることで、世界の見え方が少し広がるはずです。学ぶことは楽しいだけでなく、視野を養うことにもつながりますので、ぜひ日常の中で気になるテーマの歴史にも目を向けてみてください。
関連記事:歴史に見る「化粧」
巫女の歴史が「女性と神聖性」の問題と深く結びついていたように、化粧の歴史もまた「女性と社会の関係」を映し出してきました。ジェンダー観の見直しが進んだ現代では、すっぴんの女性は失礼といった風潮は薄れつつあり、最近では自己表現の手段として、男性も女性も化粧を楽しむ文化が芽生えています。
以下の記事では、化粧の歴史を解説しています。化粧は本来どういう意味で、いつの時代から「女性は化粧をするのがマナー」となったのかなどを紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください。
また、本記事は以下の「神道特集」に含まれています。
現代にも繋がる伝統的な宗教である神道について関心のある方は、是非こちらもご覧ください。


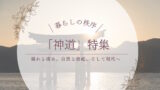
-120x68.png)