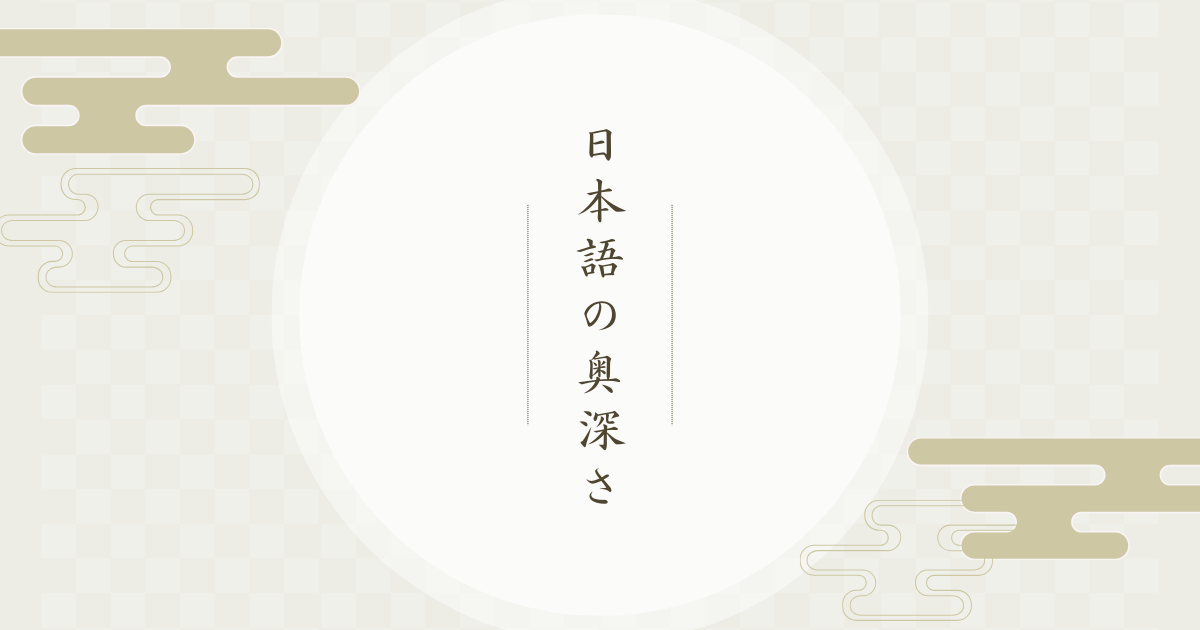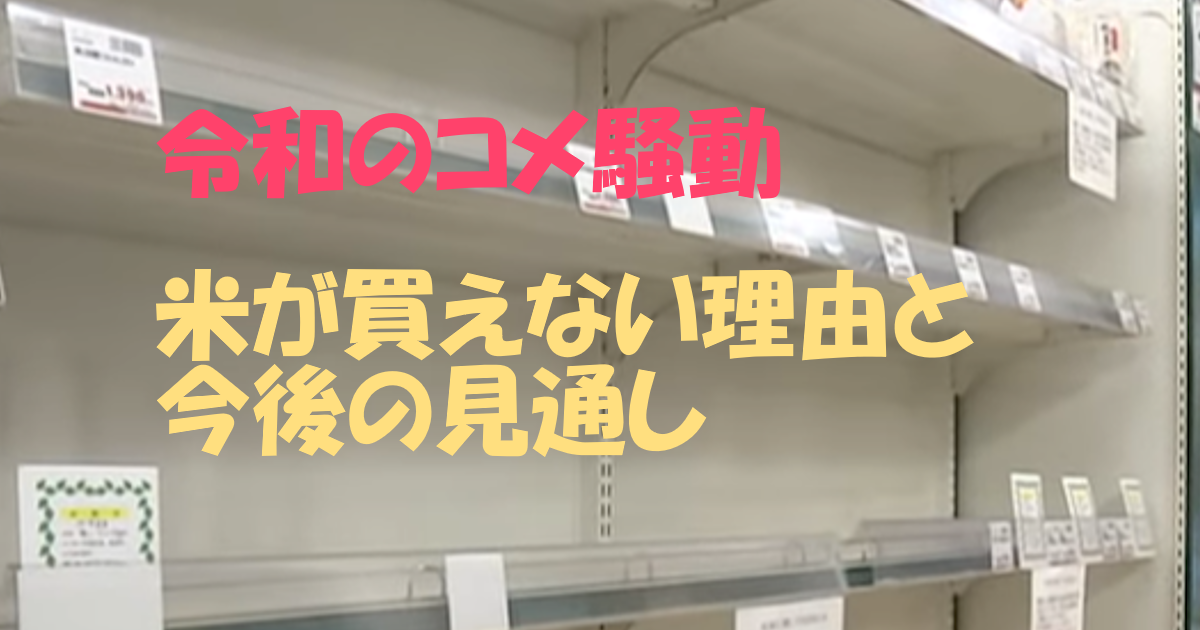近年はインターネットを通じて、英語の会話を聞くことがとても身近になっています。日本語字幕を付けてくれている動画なども多くあり、言語学習の教材には困らない時代と言えるでしょう。
日本語を英語に翻訳した際に、元の日本語に存在していたニュアンスが翻訳語の文章から欠落してしまうことがあります。今回は、翻訳で失われるニュアンスと共に、日本語の奥深さについてまとめてみます。
日本語の「奥深さ」と言語の違い
近年では、英語学習に便利な動画コンテンツをYouTube等で簡単に視聴することができるようになっています。

それらのコンテンツのほとんどを無料で体験することができるため、言語学習はとても身近で取り組みやすいものになっているといえます。
英語へ翻訳した際の「情報欠落」
YouTube等には、海外の人が「日本語の動画」を日本語音声・英語字幕で視聴して、そのリアクション自体をコンテンツとして公開している動画が多くあります。こういった動画からは、言語の学びを得られるだけでなく、海外の文化圏での捉え方(文化の違い)も見ることができ、得られる学びは多いです。
しかし、日本語の音声と英語の字幕は違う言語であり、双方にはニュアンスの違いがあることも珍しくありません。
具体的に、英語で情報が欠落してしまう代表的なパターンをいくつか紹介します。
キャラクターの個性が欠落する「一人称」
日本語の一人称が多いことは、多くの日本語学習者を驚かせているようです。日本語では多様な一人称があってそれぞれとても個性に溢れていますが、英語の一人称は’I’ か、頑張っても’me’くらいです。
Wikipediaによると、日本語の一人称の数は現在でも分かっていないそうです。方言や文学作品などでも新しい表現が生み出され続けているからか、定量的な計測が難しいのかもしれません。
以下の画像はSNSに投稿された「一人称の違い」をまとめたもので、世界中の言語学習者の間で注目され、話題になりました。

海外でも好評な日本のアニメなどだと、「キャラクターの個性」を表現するために、「僕」や「オレ」といった表現が使い分けられます。これらの英字幕では、当然「I」と翻訳されて、キャラクターの個性を表現するニュアンスは欠落することになります。
海外向けのコンテンツを作成する場合などは、一人称で個性を表現する日本語的な手法は、翻訳で苦労することになるので注意が必要でしょう。
関係性が失われる「敬語、謙譲語、丁寧語」
日本語は「相手との関係性」を言葉に込める表現が豊富です。
言葉遣いでお互いの関係性が表現される日本語では、敬意を持っている、遠慮しているといったニュアンスが言葉・台詞から感じられますが、英語の字幕になるとそういった情報が失われることが多いです。
一例を挙げると、「言う」という動詞の敬語表現は、英語ではいずれも「say : 言う」となってしまうという事です。
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 言う | say |
| 仰る | say |
| 申し上げる | say |
動詞の「言う」という言葉は、英語では「say」と表現できます。日本語の尊敬語の「仰る」や謙譲語の「申し上げる」という敬語表現は、英語では該当する言葉がないので翻訳すると同じ「say」になってしまいます。
英語に敬語はない?
英語には「敬語」に該当する表現はありません。
ただし、英語にも「丁寧な表現」は存在し、ビジネスシーンなどでは日常会話と違った言い回しが使われます。
以下は英語の代表的な「丁寧な表現」の一部です。
- フォーマルな単語を使う (buy → purchaseなど)
- would, couldを使う
- appriciateを使う (日本語の「~して頂く」に相当)
- mindを使う (気に障りませんか? という伺い)
言葉選びに気を遣うという点では日本語も英語も同じです。ただ、日本語は「相手との関係性」、特に上下関係を大事にした表現なのに対して、英語は単純に口語ではなく文語的な言い回しを選んでいるだけともいえます。
先輩も同級生も「タメ口」な英語字幕
特にこの丁寧さについて残念に感じるのは、複数人で会話をしているような状況です。
例えば、主人公が「同級生」と「先輩」と3人で話しているような状況の場合、「同級生」については普通の話し方で、「先輩」に対しては丁寧な口調で会話するといった表現がされることが多いですが、英語にすると敬意や丁寧さが欠落し、「タメ口」になってしまっていることが多いです。
敬語が入った日本語を英語に翻訳すると、「敬語のニュアンス」は欠けてしまうことがよくあります。更にその英語表現を日本語に直すと、敬意が失われた日本語となります。「丁寧さ」を表現する語尾の「…です」なども、日本語から英語にすると欠落します。
奥ゆかしい時代劇の表現
2024年に世界的に大ヒットしたDisney+のShogunは、Hollywood作品なのに台詞の7割が日本語で英語字幕という思い切った構成も話題になりました。
Shogunは時代劇なので、現代の日本語よりも一層奥ゆかしい表現が盛りだくさんです。一人称以外も含めて、英語字幕では日本語の豊かなニュアンスは表現しきれるものではありません。
所有格「your」の翻訳でも欠落する「関係性」
一人称だけでなく、所有格の翻訳時にも情報の欠落が起こります。
上に紹介したTrailer動画の中にも、日本語台詞で英字幕という場面がありますので、ひとつだけ引用して紹介します。(長い動画ではありませんが、2:14あたりの台詞です)
[台詞]
己の務めを果たす覚悟はできておるか?
覚悟はできておりまする。
[英字幕]
Are you ready to do your part?
I’m ready.
日本語の「己(おのれ)」という表現からは、上下関係(格下に対する)も感じる事ができますが、英語のyourにはそのニュアンスはなく、英字幕で視聴している人の中には「対等の関係」と感じる人もいるでしょう。
「当たり前」に「感謝」を
当たり前になっていることに感謝を感じることは難しい事です。
日本だと当たり前となっているものが、一歩外に出ると当たり前ではないことは沢山あるものです。海外の言語や文化の学習を通して、身近な当たり前の事が「ありがたい」事である事に気付くことも多いです。
狭い視野で感謝の気持ちを持てないよりも、広い視野で感謝の心を持って過ごせた方が、素敵な事だと思うのです。