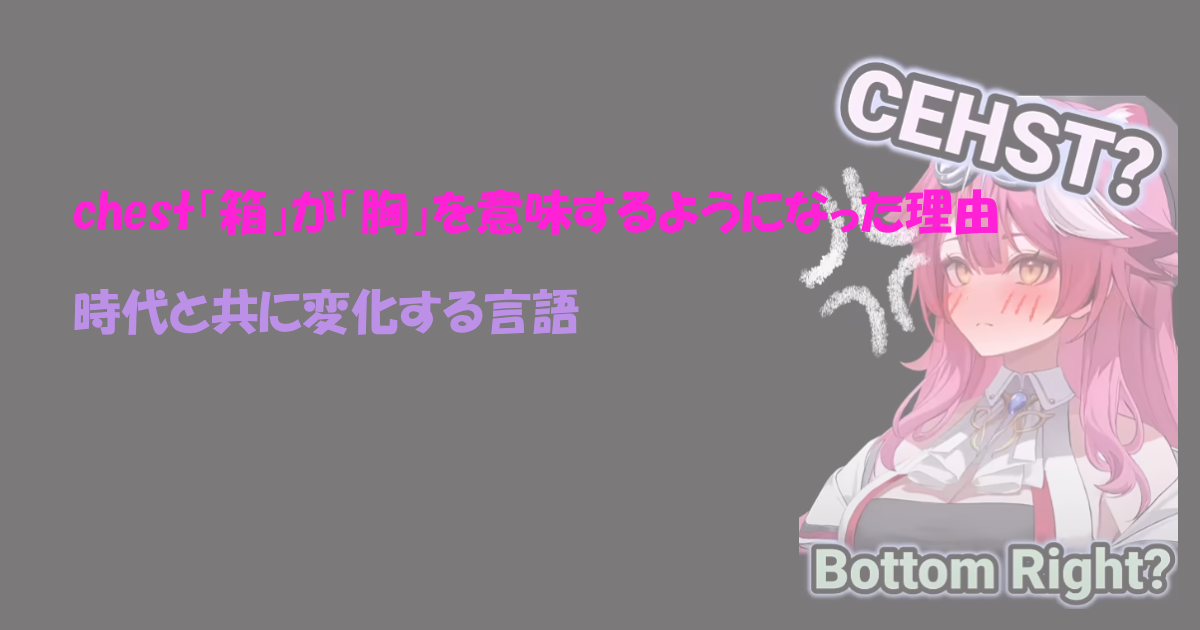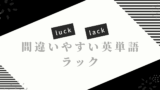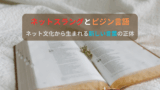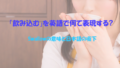言語を学習していると、一つの単語の中にまったく異なる意味が含まれていて不思議に思うことがあります。現代においては、複数の意味を巧みに使ってジョークにされることもあったりしますが、日本人としては「何故そんな複雑なことになったのか」と由来が気になったりするものです。
言語というものは、人々の生活と共に長い時間をかけて徐々に変化していくものです。今回は、ゲーム配信などでよく耳にすることがあるchest(チェスト)という英単語が、「箱」という意味から「胸」の意味を持つようになった由来や、その他の似た様な事例をまとめています。
chest(箱)が「胸」を意味する理由
英単語のchestは、日本ではカタカナでそのまま「チェスト」と表現されることも多く、とても馴染みのある外来語の一つでしょう。
「箱」の意味で使われることが多いですが、特にゲームなどでは宝箱のような「アイテムが入っている箱」を指してチェストと呼ぶことが多いようです。
「胸」は心臓や肺などが入った大事な「箱」
元々は医学などの分野で人体の重要な器官が収まっている「箱」という意味合いで、胸の部位をchestと表現するようになりました。

重要器官が入っているchest「箱」だった胸が、徐々に広い意味で「胸」を指す言葉へと変化していき、現代の様に「表面的な胸」のことも指す言葉になっていったようです。
使っているうちに、徐々に意味が広がったり、発音が言いやすい形に変化するということが、長い言語の歴史の中ではよく見られます。
chestとbreastの違い – チェスト、ブレスト、バスト
「chest」と「breast」はどちらも日本語の「胸」を意味する英単語ですが、意味合いは異なります。
- 「chest」 – 胸部全体を指す一般的な言葉で、男性にも女性にも使えます。
- 「breast」 – 主に女性の乳房を指す言葉。料理の文脈では鶏の胸肉を指します。
また、日本語のカタカナ語(外来語)で使われる「バスト : bust」は、英語では「胸囲」や「胸像」を表す単語で、主にファッション関係の分野で使われます。
rack(ラック : 棚)を使った女性の胸の表現
スラング的な少し変わった表現として、「棚 : rack」を使って女性の胸部を表現することがあります。「棚 : rack」に女性の所有格が付くと、文脈にもよりますが、女性の胸を意図した表現として扱われます。
huge rack : 巨大な棚
her huge rack : 彼女の大きな胸
ラックというカタカナ語は、英語で似た発音の単語が多いため注意が必要です。以下の記事詳しく扱っていますので、興味のある方は是非ご覧ください。
箱(chest)と胸(chest)を掛けた言葉遊び
英単語のchestには、「箱」という意味の他に「胸」の意味もあり、海外の女性ゲーム配信などでは、視聴者がそれらを掛けたセクハラ紛いのコメントをするということも珍しくありません。
上のショート動画は、マインクラフトというゲームにて、配信者(VTuber)がchest(箱)を置くという話をすると、視聴者が「chest(胸)は右下にある」と、画面右下のキャラクターの胸部を指すセクハラ的なコメントをしています。
ショート動画としては、そのコメントに対しての配信者の対応が素晴らしいという趣旨となっています。
引用動画チェンネル : HoloShortChips – YouTube
出演者チェンネル: Raora Panthera Ch. hololive-EN – YouTube
organ(臓器)が「オルガン(楽器)」を意味する理由
chestと似た様な変化をしている単語に、「臓器」を表す英単語のorganがあります。
organは、元々体内の臓器を表す英単語ですが、不思議なことに、現代では楽器の「オルガン」のことを指す英単語でもあります。
「臓器のようなパーツ」を組み合わせた「楽器」
オルガンと一言だけ聞くと、私たち日本人としては幼稚園や保育園に置いてある簡素な鍵盤楽器を思い出しますが、本来オルガンというのは大聖堂などにおいてあるような巨大なパイプオルガンのような楽器でした。
パイプオルガンは、様々な大きな部品を組み合わせて作る楽器で、その部品や組みあがった楽器の事を、臓器に例えてorganと呼び始めたようです。

同じ作品やゲームなどの中に、臓器も楽器も登場するような場合は、文脈からどちらの事を意味しているのかを考えなければならないことになります。
chestやorganは、本来の意味とは違う分野で単語が使われるようになり、その使われ方が変化していっています。その変化は現代まで続いており、現代では小型のオルガンの事もorganと呼ぶようになっています。
日本語で「意味が変化」している言葉の例
日本語でも、言葉の意味が変化する現象は起きています。いくつか例を挙げてみてみましょう。
ありがたい = めったにない
「ありがたい」という言葉の意味が、昔と今では異なっている話は有名です。
元々は漢字で書くと「有難い」で、「めったにないこと」といった意味でしたが、現代では「感謝する」意味に変化しています。
お礼の言葉としても一般的で、現代では「ありがとう」という言葉が日常的に使われるようになっています。この変化に伴って、現代では「めったにない」という意味では「ありがたい」を使うことはなくなってしまいました。
破天荒 = 前例のないこと
「破天荒」な偉業を成し遂げたなどという表現が現代でも使われますが、この言葉は「豪快で大胆」といった意味で使われることも多くなっています。
元々の破天荒にはそのような意味はなく、本来は「前例のないこと」「今までだれもしなかったような事をすること」といった意味です。四文字熟語での「前代未聞」と近い意味でした。
「破天荒」の由来
この言葉は、中国の故事に由来しています。
中国の官吏(科挙)に100年以上合格者がいない「天荒」と呼ばれる状態を「破って」合格した偉業のことを、「破天荒」と呼び称えました。
興味深い「言語の世界」
インターネット時代の現代では、世界中の人たちがオンラインで繋がって、お互いに言語学習をしやすい環境になりました。そういった人たちの話を聞くと、各国で学習に対する姿勢に違いがあるようで、私たち日本人には「由来」や「理由」を気にする傾向があるという話を聞くことがあります。
私個人は長い歴史を持つものが好きで、宗教・文化・言語など関連した事柄全域に興味の分野が広がってしまっていますが、もしかしたら日本人全体に、そういった物事の心理を探求する性質が備わっているのかもしれません。先祖の話に興味を持ったり、食品の原産地や製造国などが気になるという人は、日本人には比較的多いような気もします。分からないもの = 怖い・怪しいといった感覚があるのかもしれません。
生き物のように変化する言語
言語というのは、長い時間をかけて変化していくものです。現代の私たちも、比較的安易に省略形の単語などを生み出して使っていたりしますが、中には本来の意味とはかけ離れた誤用のようなものも存在していたりもします。言葉が創り出された瞬間は、誤りだと指摘される声があったとしても、それが定着してしまうと誤用が正解となることさえもあったりします。
知識が多くなればなるほど、そのような言語の変化を受け入れることが難しくなったりもします。美しい日本語を守りたいという言語に対する愛もあるでしょう。正しい言語を後世に伝えていきたい気持ちが強くなると、誤った言語を流布する人を叱責してしまうこともあるかもしれません。言語は変化していくものだということを念頭に、すこし距離をとって冷静に時代の流れを楽しみましょう。
利便性で生み出される「ピジン言語」
言語の歴史の中では、利便性だけを考えて、複数の言語をごちゃ混ぜにして使うという荒業が定着して、新しい言語体系を生み出すということもあります。言語愛のある人も、きっと呆れ果てて逆に冷静になる事間違いないでしょう。興味のある方は是非以下の記事もご覧ください。