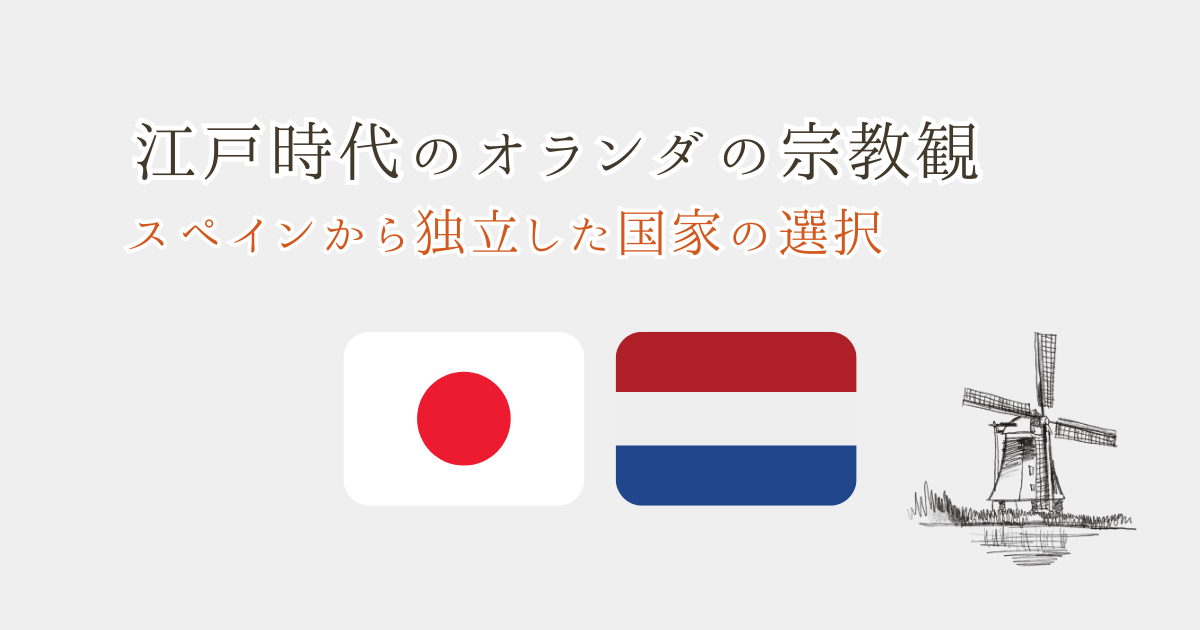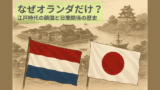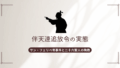💡この記事は、「日本とオランダ特集」の一部です。
江戸時代、日本がキリスト教を禁じていたにもかかわらず、オランダとの交易だけは例外として続けられていました。なぜオランダだけが許されたのでしょうか。
オランダは同じキリスト教の国ではなかったのでしょうか。
その答えは、オランダという国がどのような歴史を経て生まれたのか――つまり、「スペインからの独立」と「宗教改革」という二つの流れにあります。
江戸時代、日本とオランダが出会ったとき
1600年、オランダ船リーフデ号が嵐に遭い、九州の豊後(現在の大分県臼杵市付近)に漂着しました。この船には、イギリス人航海士ウィリアム・アダムス(三浦按針)や、オランダ人ヤン・ヨーステン(八重洲の語源とされる人物)らが乗っていました。
彼らは航海術や地理の知識を持ち、家康の前で世界の情勢を語ったといわれています。
この出来事が、日本とオランダの最初の接点でした。
当時の日本は、すでにポルトガル人の来航でキリスト教が広まりつつありましたが、家康はその勢力を完全に拒んではいませんでした。外国の知識や技術を利用しようとする段階であり、禁教政策が制度として整うのは、まだ後のことです。
(詳しくは「江戸幕府初期のキリスト教禁止の背景 ― 家康とプロテスタント」をご覧下さい)
そんな中で、布教を目的としないオランダ人たちは、他の「南蛮」勢力とは少し違う印象を与えたことでしょう。
この小さな出会いから、後に二百年以上にわたって続く日蘭関係が始まります。
では、そのオランダとはどのような国だったのでしょうか。
日本ではあまり知られていませんが、当時のオランダは、スペインの支配を脱したばかりの「新生国家」でした。宗教に寛容で、利益を優先する商業国家がどのように生まれたのか、その背景を振り返ってみましょう。
スペインからの独立 ― 宗教改革の時代
1600年に日本へ漂着したリーフデ号が出航したのは、オランダがまさに独立を目指して戦っていた時代でした。
この新しい国が「宗教に寛容な商業国家」として生まれるまでには、激しい弾圧と信仰の闘いがありました。
宗教改革とカルヴァン派の広がり
16世紀のヨーロッパでは、ドイツの神学者マルティン・ルターによる宗教改革が大きな波を起こしていました。「信仰は神と個人との間にある」という新しい考え方は、ローマ教会の権威に疑問を投げかけ、多くの人々に支持されます。
この流れの中で、スイスの神学者ジャン・カルヴァンが登場します。
彼は「神の定め(予定説)」を説き、同時に倹約や勤勉を重んじる生き方を信仰の証としました。
| 出来事 | 西暦 | 江戸日本との距離感 |
|---|---|---|
| ルターの宗教改革開始 | 1517年 | 家康誕生(1543年)の約25年前 |
| カルヴァンの活動期 | 1536〜1555年頃 | 戦国時代真っ只中(織田信長が青年期) |
このカルヴァン派の教えは、商人や職人が多く住むオランダの都市社会に強い影響を与えます。
ルターやカルヴァンが中心となって始まった宗教改革は、カトリックに対抗する新しい信仰――のちに「プロテスタント」と呼ばれる流れを生み出しました。
スペイン支配と異端審問の弾圧
当時のオランダ(ネーデルラント地方)は、ハプスブルク家の支配下にありました。
神聖ローマ皇帝カール5世、そしてその子であるスペイン王フェリペ2世が統治しており、両者とも熱心なカトリック信者でした。
フェリペ2世はプロテスタントの広がりを危険視し、異端審問を導入して厳しい弾圧を行いました。
カトリック以外の信仰を持つ者は「異端」とされ、投獄や処刑の対象となります。
さらに、戦争と支配維持のための重税が課され、都市の商人や職人たちは強い不満を抱きます。
聖像破壊運動と血の評議会
1566年、民衆の怒りが爆発し、カトリック教会の聖像を破壊する「聖像破壊運動」が起こりました。
スペイン王フェリペ2世は、これを「信仰への反逆」と見なし、武力による鎮圧を命令しました。翌1567年、将軍フェルナンド・アルバ公をオランダに派遣。
アルバは強硬策をとり、反乱分子を裁く「血の評議会(Council of Blood)」を設置します。
数千人が処刑され、貴族や市民の間に恐怖と怒りが広がりました。
スペインからの独立をかけた「八十年戦争」のはじまり
アルバ公の弾圧に耐えかねたオラニエ公ウィレム(後のウィリアム1世)は、国外へ逃れながらも、スペインの圧政に抗する決意を固めます。
1568年に、ドイツ方面から軍を率いてオランダへ侵攻し、スペイン支配に抗う独立戦争――八十年戦争が始まりました。
この戦争は単なる政治的独立の戦いではなく、「宗教の自由」と「自治の確立」を求める闘いでもありました。
オランダ共和国の独立宣言(1581年)
1581年、北部7州がスペイン王への忠誠を放棄し、「オランダ共和国」の独立を宣言します。
| 出来事 | 西暦 | 江戸日本との距離感 |
|---|---|---|
| 八十年戦争のはじまり | 1568年 | 織田信長が足利義昭を奉じて京都へ上洛 |
| オランダの独立宣言 | 1581年 | 信長の最盛期(御馬揃え) |
| 1582年 | 本能寺の変 |
正式にスペインが「オランダの独立」を認めるのはずっと後のことです。
最終的に1648年、八十年戦争を終結させたウェストファリア条約によって、オランダの独立はようやく国際的に承認されました。
この長い戦いの中で、オランダは宗教よりも現実的な利益を重んじる国へと変わっていきます。
「宗教は個人の信念、国家は商業で栄える」――
その考え方が、後のオランダ社会の基礎となりました。
オランダとイギリスの軍事同盟
イギリスはエリザベス1世の時代に入り、プロテスタント国家としてカトリックの脅威に直面していました。イギリスにとって「スペインは宗教的にも軍事的にも最大の敵」でした。
1581年にオランダが独立宣言を出すと、イギリスは外交的に支援する姿勢を強めました。
1585年「ノンスチュ条約」により正式な軍事同盟を締結し、事実上の英蘭同盟が成立します。
指揮権や目的の違いで摩擦はありながらも、イギリス海軍の存在はスペインの戦力を分散し、オランダ独立を後押しします。
オランダとイギリスは、カトリック勢力のスペインと対抗するプロテスタント国ではありますが、厳密には宗派は異なっています。
(オランダ:カルヴァン派、イギリス:イングランド国教会)
宗教が不安定だったイギリスは、最終的には日本に拒絶されることになります。
💡関連記事:禁教下の日本とイギリス ― 江戸幕府の外交と通商の行方
戦乱の最中に出航するリーフデ号
こうした時代背景の中、1598年にはオランダの東インド遠征艦隊が出航します。
独立戦争の最中でありながら、人々は新しい貿易の道を切り開こうとしていたのです。
その艦隊の一隻こそが、後に日本へ漂着するリーフデ号でした。
この艦隊にはオランダ人とイギリス人が共に乗り組んでおり、両国が当時スペインと対立する「同じ陣営」にあったことが、その背景にありました。
つまり、日本にたどり着いたオランダ人たちは、宗教の自由と商業の発展を信じて海へ出た「新しい国家の民」だったのです。
宗教の自由から商業国家へ
長い戦争の果てに誕生した新しい国は、信仰の違いで人を裁くことをやめ、商業と知を重んじる国家へと歩み出しました。
宗教よりも「商業」を重んじる国へ
宗教戦争の反動として、オランダでは「信仰は個人の問題」という考え方が広まりました。
ユダヤ人やカトリック、プロテスタントなど、宗派を超えて共存する都市社会が形成され、宗教的寛容が国の根幹となります。
宗教の束縛から解放されたオランダは、学問と思想の自由を重んじました。アムステルダムは「ヨーロッパで最も自由な都市」と呼ばれ、哲学者スピノザやデカルトらが活動しました。
1602年には東インド会社(VOC)が設立され、布教ではなく貿易を通じた経済的発展が国策として進められました。
東インド会社(VOC)は、国家から独立した営利企業として活動していました。
宣教師の派遣は禁止され、商人が国家の代表として海外に渡るという形が取られます。
オランダ商人の江戸幕府(禁教体制)への理解
オランダ人は、日本の禁教体制を理解し、宗教的な象徴をいっさい持ち込みませんでした。
出島では礼拝や十字架の掲示も行わず、信仰を表に出すことはなかったといわれます。将軍への謁見の際にも、日本の礼儀作法に従い、贈り物や所作の一つひとつにまで慎重な配慮を見せました。
こうした姿勢は、単なる迎合ではありません。宗教を個人の問題とするオランダの思想が、そのまま外交の形となって現れていたのです。
信仰を語らず、交易をもって誠意を示す――それが、
江戸幕府の信頼を得た唯一の西洋国家・オランダの在り方でした。
独立から黄金期へ ― 世界商業国家への成長
正式に独立を果たしたオランダは、宗教よりも商業を軸にした国家として、17世紀に黄金期を迎えます。
ウェストファリア条約と正式独立(1648)
八十年戦争の終結を定めたウェストファリア条約により、オランダ共和国の独立が正式に承認されました。
このとき、日本ではすでに幕府体制が安定し、出島でのオランダ貿易が始まっていました。
いわば両国は、同時期に「安定と秩序の確立」という節目を迎えていたのです。
島原の乱での日本とオランダ
島原の乱(1637-1638年)という激震の最中も、オランダ商館は交易を維持するために幕府と慎重な関係を続けていました。
商館長報告によれば、乱鎮圧の折に幕府から武器支援を求められたものの、オランダ側は「交易の継続」が最優先であることを明確にしつつ協力しています。オランダ側の記録は「商業・交易記録」といった実用的な物が中心で、感情的な記録は少なく、島原の乱については「幕府の求めに応じて交易環境を守るための協力」という側面が強調されています。
こうした姿勢も、オランダが「宗教より商業を優先する国家」であるという幕府の信頼をさらに確固たるものにしました。
島原の乱については以下の記事で詳しく解説しています。
💡関連記事:島原の乱の背景と影響 ― キリスト教を掲げた日本の民衆蜂起
世界の交易網と「オランダ黄金期」
17世紀のオランダは、東インド会社を中心にアジア・アフリカ・南米へと交易を拡大しました。
アムステルダムは世界の商業中心地となり、芸術・科学・金融の分野でも大きく発展します。
この黄金期の影響は、やがて日本にも波及し、出島経由で伝わった西洋学問――すなわち蘭学の発展へとつながっていきました。
関連記事:オランダ黄金期に訪れる「世界初のバブル」
この時代、オランダはスペインやポルトガルを凌ぎ、世界貿易の覇者となりました。そんな中で、富裕層の間では珍しいチューリップへの投資が流行します。
世界初の投機バブルと言われる「オランダのチューリップ」については、以下の記事で詳しく紹介しています。
現代日本にも通じるオランダの選択
オランダはカトリックによる弾圧を経験したからこそ、宗教を国家の中心に据えませんでした。
「信仰を押しつけない国家」という選択が、江戸幕府にとって唯一の“信頼できる西洋”となり、出島の灯を照らし続けたのです。布教をしないという選択は、宗教を否定したのではなく、「宗教を個人の自由に委ねる」という考えの結果でした。
約400年前にオランダが辿り着いた「自由」と「現実主義」は、どこか現代の日本にも通じるものがあります。今のオランダも、日本と同じように無宗教が多数派で、宗教に寛容な社会です。
関連年表:
【年表】江戸時代のオランダの宗教観 ― 独立戦争期の日本
宗教改革から独立、日本との交流までの流れを時系列で整理しています。
関連記事:オランダと日本のその後の関係
幕末期には、友好的な関係を築いたオランダとも不平等条約を結ぶことになります。
江戸時代の日本とオランダの関係については、以下の記事で詳しく解説していますので、関心のある方は是非こちらもご覧ください。