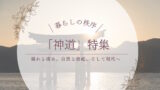💡この記事は、日本の伝統宗教「神道」特集の一部です。
「死」や「血」に触れると、それだけで周囲にまで「穢れ」が移ると考えられていた――。神道の中で重要な観念のひとつが「触穢(しょくえ)」です。
本記事では、神道における触穢が歴史の中でどのように扱われていたのかを解説し、世界との違いや現代に残る風習(子供の遊び「えんがちょ」など)についても紹介します。
触穢(しょくえ)とは
神道における「穢れ」とは、死や血といった出来事に触れることで人が清浄さを失うと考えられた状態を指します。
「触穢(しょくえ)」とは、穢れそのものに触れた人だけでなく、その人に「接した者までもが新たに穢れる」とされる考え方です。
穢れは人から人へ「移っていく」と捉えられたのです。
ここで言う「移る」とは、病気や感染のことではなく、社会的・宗教的な忌避観念を意味します。
触穢の具体例
この触穢の発想は、古代から中世にかけて社会制度の中に強く組み込まれていました。
喪中と社会的隔離
親族の死に接した者は一定期間「忌中」とされ、神事や社会生活から外れることが求められました。これは触穢を避け、共同体全体の清浄を守るための仕組みでした。
律令制の時代には、この考えは延喜式に定められた「忌服令」として法制化されます。
忌服令では、亡くなった人との続柄に応じて、忌(神事に関わることを避ける期間)と服(喪に服す期間)の日数が細かく規定されていました。たとえば父母を亡くした場合は1年、祖父母や兄弟姉妹の場合は150日など、親族関係に応じて厳格な期間が定められていたのです。
この「死者に接した者は一定期間を隔離する」制度は、現代にも「忌引き休暇」としてその名残を見つけることができます。現代では宗教的な意味合いは薄れているものの、死に向き合うための時間を社会的に保障する仕組みとして残されているのです。
出産や死に関わる人々
出産の場に立ち会った助産者も「血の穢れ」に触れたとされ、隔離される対象でした。また、葬送に関わる人々も同様で、穢れが共同体に広がらないよう一定期間「物忌み」が必要とされました。
江戸時代に入ると、こうした「穢れに触れる役割」を担う人々は制度的に区分され、「穢多(えた)」と呼ばれて差別的に扱われるようになりました。
彼らは動物の解体や皮革加工、刑場での死刑執行や死体処理、産婆などに従事し、社会に不可欠な役割を担いながらも「穢れに常に触れる存在」として蔑視されました。
また、触穢の観念は「穢れは移る」という考え方を強め、穢多とされた人々だけでなく、その子孫までもが差別的に扱われる要因となりました。
遠ざけられた出産と月経
触穢の観念は、死だけでなく「血」にも強く結びついていました。特に出産や月経は、生の営みの証であると同時に「血の穢れ」とされ、共同体から隔離される対象となったのです。
出産の場合、母親や出産に立ち会った助産者は「産忌(さんき)」と呼ばれる期間を経なければならず、その間は神事や社会的な役割から外されました。母子は家から離れた「産屋」や別棟にこもることが多く、共同体から血の穢れを遠ざけると同時に、母子を守る役割も果たしていました。
月経に関しても、血は「不浄」と見なされました。平安時代の宮中儀礼では、月経中の女性は御簾の内に入ることが禁じられ、神事への奉仕もできませんでした。地域によっては、月経中の女性が過ごす「月経小屋」が設けられ、一定期間は家族からも距離を置く習慣がありました。
血の穢れについては、以下の記事で歴史的な扱いから現代に残る風習まで詳しく紹介していますので、関心のある方は是非こちらもあわせてご覧ください。
社会秩序としての触穢
触穢の思想は、単なる迷信ではなく社会の秩序を守るための仕組みでもありました。
隔離と共同体の安全
死や出産といった大きな出来事を「特別な状態」として区別し、その影響を共同体から切り離す。触穢による隔離は、共同体全体の「清浄」を保つための社会的装置として機能しました。
権力と触穢
また「穢れに触れないこと」自体が聖性の証明となり、天皇や斎王の権威を支える仕組みでもありました。触穢を避けることで「人ならざる存在」としての象徴性を強調したのです。
捕捉:世界における触穢観念
触穢の考えは日本だけのものではありません。
聖書にも「不浄なものに触れた者もまた不浄とされる」という規定があり、インドのカースト制度にも「触れてはならない人々(アンタッチャブル)」が存在しました。神道の触穢もまた、人間社会に普遍的な「伝染する不浄」という感覚の一形態といえるでしょう。
触穢観念の「公衆衛生」効果
宗教的な触穢の観念は、単なる迷信にとどまらず、結果的に人々の命を守る役割も果たしていたと考えられます。
死体や血液は感染症や腐敗の原因となりやすく、出産の場も当時は衛生的に危険を伴いました。触穢によってこうした人々を一時的に隔離したことは、結果的に病気の蔓延や疫病の拡散を防ぐ効果を持っていた可能性があります。
科学や医学が発達する以前、人々は宗教的な物語や禁忌を通じて、結果的に公衆衛生を維持する工夫をしていたのだと理解することもできます。
えんがちょ ― 子供文化に残る触穢
触穢の発想は、やがて子供の遊びにまで形を変えて残りました。それが「えんがちょ」です。
えんがちょのルール
遊びの中では「汚いものに触れた」とされると、その穢れが他人に移ると考えられました。
そして、指で「切る」動作をして「えんがちょ切った!」と唱えることで、その移動を断ち切ることができるとされました。まさに触穢の縮図といえます。
「えんがちょ」の語源は、「縁を切る」「縁を切除(ちょ)」が縮まって「えんがちょ」になった、という説が有力です。(「ちょ」は「切る」の擬音、あるいは「ちょん切る」の「ちょ」)
現代人への示唆
えんがちょは子供の遊びですが、その背後には「穢れは移る」という古い観念が生き続けています。これは科学的な病気の伝染とは異なり、社会的に「不浄」とされるものが人から人へ波及するという思想でした。
現代に残る神道の価値観
触穢とは「穢れは移る」とする神道の重要な観念でした。これは死や出産に関わる人を隔離し、共同体の清浄を守るための仕組みでもありました。
「えんがちょ」は子供の遊びに過ぎませんが、現代の私たちが当然のように抱いている「常識」の中には、神道に由来する価値観がいまも数多く息づいています。
関連記事:日本と世界の「遺体観」の違い
その代表例が「遺体を強く忌避する」価値観です。これは神道の「死の穢れ」や近代の疫病の記憶が折り重なって形成されたと考えられます。遺体を「恐怖」の対象とするほど強く忌避する日本人の感覚は、世界の多くの地域とは異なり、文化的摩擦を生む要因の一つにもなっています。
以下の記事では、土葬問題をめぐって日本人と世界の遺体観を比較するとともに、現代社会の制度において日本人の声がどのように扱われているのかをまとめています。興味のある方は是非あわせてご覧ください。
また、本記事は「神道特集」に含まれています。
神道全般に興味のある方は、是非以下の特集もご覧ください。
.png)
とする神道2-160x90.png)