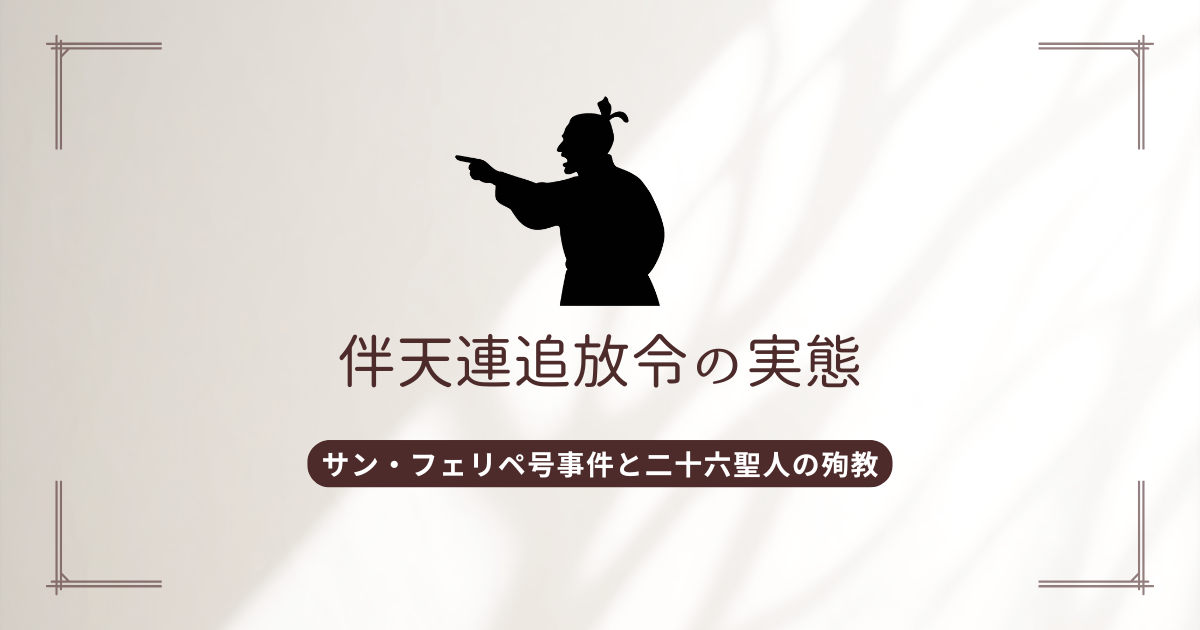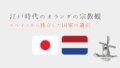💡この記事は、「日本のキリスト教禁教史特集」の一部です。
豊臣秀吉の伴天連追放令は、当初は警告にとどまるものでした。
しかし、サン・フェリペ号事件をきっかけに方針は一変し、二十六人のキリスト教徒が処刑されます。日本の禁教政策が「実行」に移された最初の出来事です。
伴天連追放令の限定的な効果 ― 事件前の状況
1587年、豊臣秀吉は宣教師に国外退去を命じる伴天連追放令を発令しました。キリスト教を完全に禁じるものではありませんでしたが、宗教勢力を政治から切り離すという明確な方針が示されました。
この命令は一定の効果を持ちながらも、地域や大名の対応に差があり、全国的な統制には至りませんでした。
伴天連追放令での取り締まり
発令直後、京都や大坂の教会は破却され、宣教師には退去命令が出されました。
九州では高山右近などのキリシタン大名が領地を失い、改宗を迫られるなど、一定の取締りは実施されています。しかし、南蛮貿易の利益を重視する大名も多く、貿易港や地方では布教活動が黙認される例もありました。
こうして追放令は、「完全な排除」ではなく「地域ごとの裁量での対応」という不均衡な形で運用されていきます。
潜伏して活動する宣教師
宣教師たちは退去命令を受けても、日本国内にとどまりました。
一部は農民や商人に身を変えて潜伏し、密かに信者と連絡を取り続けます。彼らは信者の家で礼拝を行い、キリシタンの子どもたちに教義を伝えるなど、形を変えた布教を続けました。
黙認的な行政措置 ― 追放令と国益の狭間で
追放令の前年(1586年)、長崎はイエズス会の管理下から秀吉の直轄地に編入されました。
しかし、その後も教会活動はしばらく続き、1590年代初頭まで宣教師が滞在していた記録があります。また、秀吉が派遣した天正遣欧少年使節(1582〜1590)の帰国時には、彼らを迎えたのがイエズス会士たちでした。
これらの事実は、秀吉自身が宣教師の存在を十分に把握していたことを示しています。
それでも、秀吉は彼らを直ちに排除しませんでした。その背景には、南蛮貿易によって得られる経済的利益や、海外との情報・外交ルートを維持するという国益上の判断がありました。
つまり、伴天連追放令は「徹底的な禁教」ではなく、状況に応じた「柔軟な行政措置」として運用されていたのです。
しかし、この黙認的な体制を一変させる出来事が起こります。
サン・フェリペ号事件 ― 警戒から禁教強化へ
追放令から約10年後の1596年、土佐沖に漂着したスペイン船「サン・フェリペ号」の一件が、秀吉の疑念を決定的にしました。
宗教・外交・経済が入り混じったこの事件は、伴天連追放令の方針を「実際の取締り」へと押し上げるきっかけとなります。
座礁の救助と積み荷没収
サン・フェリペ号はメキシコからフィリピンへ向かう途中、暴風雨に遭って土佐に漂着しました。
漂着したサン・フェリペ号を保護したのは、土佐の領主・長宗我部元親でした。
元親は船員を救助し、積み荷を検分のうえ秀吉に報告しています。
文禄五年(1596)八月、異国船一艘、土佐国浦戸沖に漂着す。
元親これを救い、兵をもって守らしむ。船中に金銀珍宝多く、太閤のもとへ上聞に及ぶ。
太閤、これを召し上げ、京へ運ばしむ。
―― 土佐藩関係の地方史料『南路志』の要約
サン・フェリペ号には銀や絹、香料など高価な物資が積まれていました。
秀吉はこれを「漂着物」として接収し、京都に送らせます。
一方、スペイン側は「略奪行為」として強く抗議し、これが事件の発端となりました。
抗議での誤訳の可能性 ― 「征服発言」
抗議の場で、スペイン人船長が「宣教師は征服の先兵である」と発言したと伝えられています。
しかし、現代の研究ではこれは通訳による誤訳や誇張であった可能性が高いと考えられています。
実際の意図は、南米やフィリピンなど他地域の事例を説明したもので、日本を征服するという意味ではなかったとみられています。
そもそも押収された物資は、スペインが東南アジア方面で進めていた植民地経営のために運ばれていたもので、日本を征服するための軍需品ではありません。
秀吉の受け止め方
たとえ誤訳であったとしても、秀吉にとっては「外国勢力が日本近海に物資を運び、宣教師を通じて内側から影響を広げている」という事実が脅威に映りました。
この事件を通して、秀吉はキリスト教を単なる信仰ではなく、外国による支配の手段として捉えるようになります。
そして、これを機に「国外追放」という建前を超えた、実際の取り締まりに踏み切ることになりました。
外交と体面の問題
秀吉は天下統一を果たしたばかりで、自らを「日本国王」に準ずる存在と見せたい立場にありました。
物資没収への抗議は、秀吉にとって単なる経済問題ではなく、自らの権威を否定する言葉として響きました。
その怒りは警戒心を再燃させ、禁教強化の決断へとつながったのです。
サン・フェリペ号事件は、外交上の体面と政治的主権を守るための行動を決定づけた事件でもありました。
なお、船の乗組員たちは一時的に拘束されたものの、処刑されることはなく、のちにルソン(フィリピン)方面へ帰還したと記録されています。
二十六聖人の殉教 ― 追放令の“実行”としての処刑
サン・フェリペ号事件は、秀吉にとって外国勢力の脅威を現実のものとして意識させる出来事となりました。
そのわずか数か月後、京都や大阪で宣教師や信徒が逮捕され、長崎まで引き回されて磔刑に処されます。「二十六聖人の殉教」として知られるこの事件は、伴天連追放令の方針が初めて“実際の制裁”として現れた瞬間でした。
| 年 | 月 | 出来事 | 関連人物 |
|---|---|---|---|
| 1596年 | 10月 | スペイン船サン・フェリペ号、土佐沖で座礁(浦戸沖)。 長宗我部元親が救助・報告。 | 長宗我部元親 |
| 11月頃 | 秀吉、積み荷を接収。スペイン船長の発言を聞き激怒。 | 豊臣秀吉 | |
| 12月 | 京都・大阪の宣教師・信徒を次々逮捕。 | フランシスコ会士、信徒 | |
| 1597年 | 2月 | 捕縛された26人を長崎で磔刑(西坂)。 | 二十六聖人の殉教 |
見せしめとしての処刑
フランシスコ会の宣教師、日本人信徒、そして子供を含む26人が捕らえられ、京都から長崎まで約1000kmの道を歩かされました。
長崎・西坂の丘で行われた公開処刑は、民衆に対する見せしめの意味を持っていました。
この出来事は、後にカトリック教会で「二十六聖人の殉教」として記憶されることになります。
処刑が行われた「西坂の丘」という場所
公開処刑が行われた長崎の西坂の丘は、日本の禁教史における象徴的な場所となりました。

画像引用:西坂公園|ながさき市お出かけ公園ナビ
江戸時代、禁教政策と弾圧が激化した時期には、同じ場所で多数の宣教師や日本人信徒が処刑されています。(1622年:長崎大殉教)
関連記事:「日本の法」より「神の法」 ― 異教徒を処刑した日本の歴史
さらに、幕末期に日本が不平等条約によって教会の建設を拒めなくなると、西坂の丘を望む地に「日本二十六聖人殉教者」に捧げられた大浦天主堂が建てられました。
関連記事:幕末のキリスト教弾圧 ― 教会に現れた隠れキリシタンの行く末(浦上事件)
秀吉の意図とヨーロッパの反応
秀吉にとっては、国外勢力に対して「日本の主権を侵す行為は許さない」という姿勢を示す政治的行為でした。
一方、ヨーロッパではこの事件が「信仰を貫いた殉教」として伝えられ、カトリック世界で大きな反響を呼びました。
同じ出来事が、国家の防衛と信仰の象徴という二つの全く異なる意味を持ったのです。
「二十六聖人」という呼称の由来
「二十六聖人」という呼び名は、1862年にローマ教皇ピウス9世が彼らを正式に列聖した際に付けられたものです。
当時の日本では宗教的な称号ではなく、単に「キリシタン磔事件」として記録されていました。
後世の教会による列聖が、事件の記憶を宗教的な「殉教」へと昇華させたのです。
まとめ ― 警告から制裁へ舵を切る為政者
秀吉の伴天連追放令は、もともと「宣教師の国外退去」を命じるだけの警告でした。
しかし、サン・フェリペ号事件によって外国の脅威を実感した秀吉は、その方針を実際の処罰へと転じました。二十六聖人の殉教は、その転換点に位置する象徴的な出来事です。
この禁教政策は単なる信仰弾圧ではなく、国家の主権と秩序を守るための政治的決断でもあったのです。
関連年表:
【年表】伴天連追放令の背景と実態 ― ザビエルから秀吉の死まで
ザビエルの来日から秀吉の死までの流れを、時系列で整理しています。
性質の異なる禁教政策 ― 秀吉と家康の違い
秀吉も家康もキリスト教や宣教師の活動に対して、最初は融和的な方針で進め、後に禁止・弾圧へと舵を切っています。
しかし、両者の禁教政策の性質は、以下のような点で異なっています。
- 秀吉:政治秩序の誇示、外交的体面の維持としての禁教。
- 家康:国際関係(貿易・宣教師・海禁)を総合的に観察した結果としての禁教。
権威を示すための行動だった秀吉に対して、家康は外交を通じて慎重に決断・制度化しています。
キリスト教や南蛮貿易を再評価した家康
秀吉も家康もキリスト教を禁止したことで知られていますが、両者の政策方針は連続していません。
家康は、秀吉の禁教政策をそのまま引き継ぐことなく、自らの判断で南蛮貿易やキリスト教の影響を見直し、改めて禁教の決断を下します。
江戸時代初期におけるキリスト教禁止の背景については、以下の記事で詳しく解説しています。
また本記事は、以下の「日本のキリスト教禁教史」特集の一部です。
日本のキリスト教禁教の背景や実態を詳しく知りたい方は、是非こちらもご覧ください。