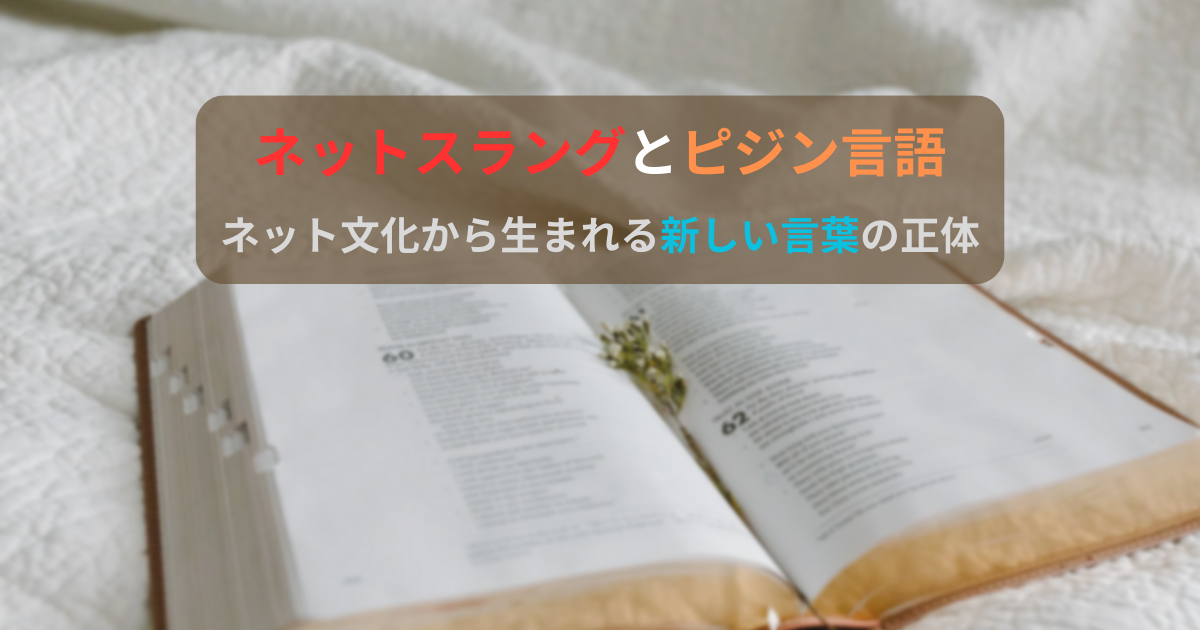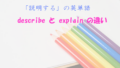近年発達したインターネット上の様々なサービスによって、今は国や言語を超えて様々な人々が交流することが日常的になりました。
異なる言語の人たちの交流の中では、複数の言語が混ざったような「新しい言葉」が次々と生み出されていますが、こういった現象は言語学の中では珍しいことではありません。この記事では、専門用語を交えながら、言葉の不思議な成り立ちについて考えてみます。
言語が混ざる「ネットスラング」や「若者言葉」
現代のネット社会においては、日本語の中に英語など外国語の表現を取り込んだような「新しい言葉」が次々に生み出されています。中には、ゲームやSNSなど特定のコミュニティーだけで使われるものもあります。
これらの言葉は、複雑な文法や活用形を避け、単純な形で表現されることが多く、「ネットスラング」や「若者言葉」と呼ばれます。
現代の「ネットスラング」「若者言葉」の例
現代で使われている「ネットスラング」や「若者言葉」の例をいくつか紹介します。
- 「〜ニキ」「〜ネキ」
- 使われる場所 : ネットの掲示板やSNS
意味合い : 特定の行動や特徴を持つ人物を指す言葉。
語源 : 兄貴(ニキ)、姉貴(ネキ) - 特定の語彙(ニキ、ネキ)が、文法的に独立した接尾辞のように使われる。
元の意味(実の兄弟)から離れ、「〜する人」「〜に詳しい人」といった、単純化された意味を持つ。(「ポケモンニキ」「有能ネキ」など、英語のBroに近い使われ方)
- 使われる場所 : ネットの掲示板やSNS
- 「やばいンデ」
- 使われる場所 : K-POPファンなどのコミュニティ
意味合い : 「やばいんだけど」「やばいね」
語源 : 韓国語の「ンデ」(語尾に付く「〜だが」や「〜だよ」といった意味) - 驚きや困惑、感動などを表す際に使われます。
- 使われる場所 : K-POPファンなどのコミュニティ
- 「バズる」
- 使われる場所 : SNSやインターネット上
意味合い : ある投稿や情報が急速に広まり、多くの人々の注目を集める状態を指す
語源 : 英語の「buzz」(ざわめき)に日本語の動詞「る」をつけた言葉。 - 英語と日本語の語彙が融合し、元の言語にはない新しい意味「口コミのように情報が広がる様子」を表すようになりました。
- 使われる場所 : SNSやインターネット上
ピジン言語とクレオール言語
ネットスラングや若者言葉のように、言語が混ざり合って新しい言語が作り出される発想には驚きますが、実はこういった事例は人類の長い歴史の中で何度も見られます。
言語学的には、こういった複数の言語が混ざり合った言語を「ピジン言語」や「クレオール言語」と呼びます。
ピジン言語やクレオール言語は、交易や情報交換等において両者の認識を共通化する際に「便利」で、そういった場合に自然発生するといえます。
ピジン言語
2ヶ国の言語が混ざり合って通用語となった言語をピジン言語と呼びます。
ピジン言語は何度も創り出されてきており、現代でも使われているピジン言語も存在しています。有名なものには、パプアニューギニアやソロモン諸島などで使われている言語があります。
日本に馴染みのあるピジン言語としては、ハワイで使われているピジン イングリッシュと呼ばれる言語があり、英語とハワイ語を中心として、その他ポルトガル語や日本語などが混ざった言語です。その他、満州国では日本語の変種として協和語という言語も使われていたそうです。
クレオール言語
交易や商売のために作られ、話されるようになっていったピジン言語が、その子供の世代に伝わり母語となったものをクレオール言語と呼びます。
ピジン言語が発音や語彙などに個人差があるなど粗削りなのに対し、クレオール言語では言語が体系化(発達・統一)され、複雑な意思疎通が可能になったもので、完成された言語として扱われます。
上記ピジン言語の項で触れたソロモン諸島の共通語は、現代ではクレオール言語として扱われているようです。
現代使われているクレオール言語には様々なものが有りますが、日本に馴染みのある言語としては台湾北東部などで使われている宜蘭(ぎらん)クレオールという言語があります。これはアタヤル語(タイヤル語)に日本語の語彙が混ざった言語となっています。日本統治時代に、台湾の原住民族が使っている言語と日本語が融合して話されるようになった言語です。その他、沖縄県などで話されている言語を、琉球言語と日本語の融合(クレオール)言語として扱う場合もあるようです。
利便性で行われる「言語の融合」
インターネットを通じて、様々な国の人々がコミュニケーションする時代になりました。言語の壁は、多くの場合両者が「英語」を使うことで解消しています。
しかし、英語が第一言語でない場合、どちらかが英語の単語を知らない場合も多く、相変わらず言語がコミュニケーションの障壁となることも多いです。
そんな中で、とある中国人がSNS上に投稿した「気づき」が話題になっているようです。
画期的な日中対話 – 英語文法に漢字の名詞
その中国人は、日本語と中国語には似た名詞が多いため、英語から文法と副詞を借りることで、日本人と中国人が理解することが容易な文章が作れるというのです。
具体的な例をひとつ先に紹介します。(後述の動画内より抜粋)
中国人 can 理解 this 文章?
これは日本人から中国人に向けた質問で、この文章は中国人としては理解に問題がないと返答されていたようです。日本人としても、中学生レベルの英文法の上に日本語の名詞を乗せただけなので、容易に理解できる内容でしょう。
本件について、非常に分かりやすく、そして短くまとめられた素晴らしい動画がYouTube上にあったので、こちらで紹介させていただきます。
引用動画 : 新言語の発明で日本と中国が簡単に交流できるようになった
ネットの反応
言語を習得する際に、大変な労力が必要となる単語(Vocabulary)の記憶・習得を、大幅に軽減できるこの方法は、非常に画期的な手法としてインターネット上の人々に好意的に受け入れられ、話題となっているようです。
上に紹介した動画のコメントでは、日本人と中国人がこの新しい混合言語を使って様々なコミュニケーションを試みていて、非常に興味深いです。こういった言語の構造や他言語話者とのコミュニケーションに興味のある方は是非一度観てみてください。
ちなみに、この新しい混合言語についてもYouTubeは翻訳機能を提供してくれますが、当然未知の言語なので正しく翻訳されなくなっているところも、非常に面白いと感じます。テクノロジーによって支えられるのではなく、人々の知恵で工夫することで新しい文化・文明が築かれていき、人の発展を追いかけてテクノロジーが発展していくものなのでしょう。
単語が思い出せずに起こる「言語の混合」
複数の言語を習得していると、会話の途中で単語が思い出せずに困ってしまうということもあります。
話している言語ではなく、別の言語の単語で補完して話すと、ピジン言語と似た様な構造の文章が出来上がります。
こういった現象は、日常でも起きることがあります。
以下の動画は、母国語の単語が出てこなくなってしまうという、一種のお笑い(funny moment)のコンテンツです。相手に伝えようとして母国語の英語ではなく日本語の単語が発語されています。
引用動画 : Hakos Baelz can’t speak English anymore
同動画内で発話された文章を一部切り出してみてみます。
It’s so 便利.
日本にあるコインロッカーが便利だったという話の流れで、英語の便利(Convenient)が思い出せなくなってしまったので、日本語の「便利」を代用しています。
その結果、先に紹介した事例と同じ「日本語と英語の混成言語」になっています。
インターネットで言語・文化の距離が縮まった現代
私たちが生きている時代は、インターネットの普及が進んだことで、急速に言語や文化の距離が縮まった時代と言えるでしょう。人類の長い歴史の中では、インターネットの登場から現代までは一瞬と言ってもよいほどしか時間が経過していません。まさに歴史的な瞬間の中に、私たちは生きているのです。
インターネットが普及する前は、飛行機や船に乗って海外に行ったり、海外から来日してきた外国人と会話するくらいしか、他言語話者と会話する機会というのは得られないのが普通でした。しかし、現代はパソコンやスマートフォンを使って、気軽に文字や音声による他言語間でのコミュニケーションが可能な時代で、冒頭に紹介したような言語の融合や文化的な変化が起きて行っている最中なのでしょう。
今後、インターネットによって加速した情報交換によって、世界各国で文化的・言語的な融合は加速するのかもしれません。
私たちが生み出す新しい文化
今私たちが話している日本語や英語といった言語は、時間と共に変化していき、ピジン言語のような利便性重視で複数言語が混成したような新しい言語が形成されていくのかもしれません。そして、そういった新しい言語の先には、世界共通言語のような万国共通の便利な言語の誕生が待っているのかもしれません。とても興味深い変化ではありますが、私たち人類の一生は短く、未来の事は想像するしかありません。私たちの世界は、今後どのように変化していくのでしょうか。
いつの時代でも、「より便利に」なるように努力した人たちの手によって、新しい文化や文明が生み出されてきました。世界が劇的に変化している現代に生きる私たちも、そういった文化を生み出す一人の人間であることは間違いないでしょう。