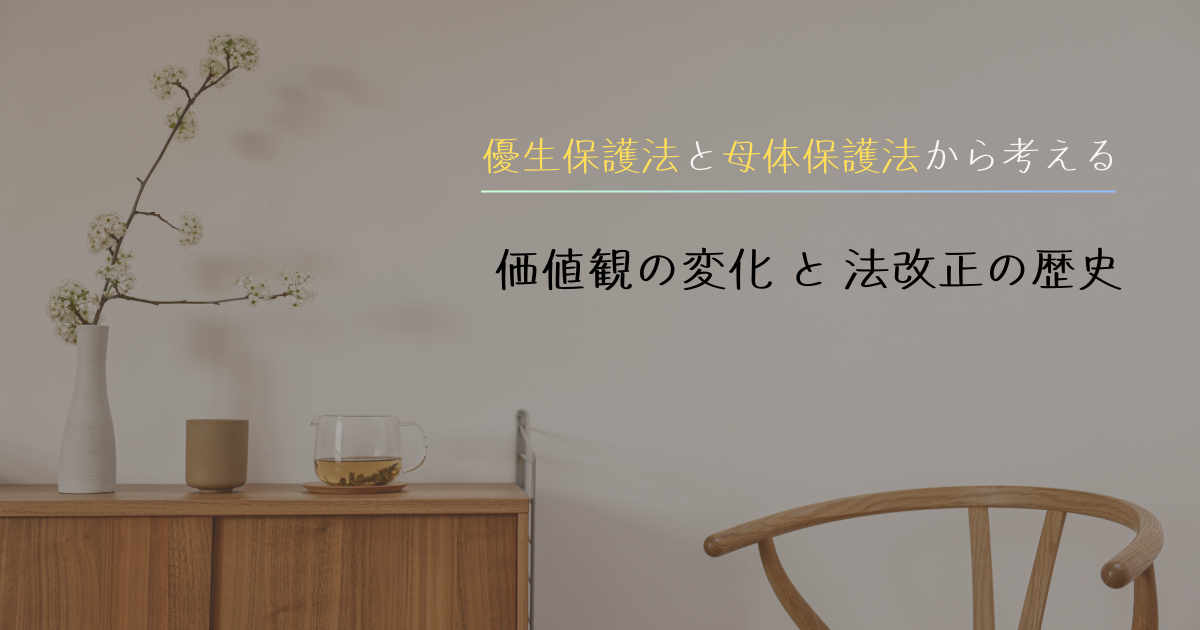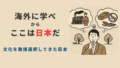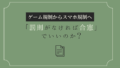「母体保護法」という言葉を聞いて、どんなイメージを持つでしょうか。実はこの法律、かつての「優生保護法」と深い関わりがあります。社会の価値観は移ろい、法律もそれに合わせて姿を変えてきました。その歩みをたどることは、未来の法律を考えるヒントになるはずです。
母体保護法という“あまり知られていない法律”
「母体保護法」という法律の名前を耳にしたことがあるでしょうか。人工妊娠中絶や不妊手術の条件を定めた法律ですが、実際に詳しく内容を知っている人は多くありません。
驚くべきことに、この法律はかつて存在した「優生保護法」の後継として1996年に制定されました。優生保護法といえば、強制不妊手術など深刻な人権侵害をもたらした法律として知られています。その流れを汲む母体保護法は、名称や制度の上で旧来の価値観を残したまま現代に続いているのです。
母体保護法第14条には、「身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがあるとき」に中絶を認める、と定められています。【出典: 厚労省 法令集】
つまり「経済的困窮」も条件に含まれる運用ですが、女性自身の意思だけでの中絶は正面から認められていません。
この“限定的な自己決定権”が、今日も議論の対象となっています。
優生保護法とは何だったのか
戦後の1948年、日本で「優生保護法」が制定されました。背景には二つの要因がありました。
一つは「優生思想」です。遺伝性疾患や精神障害を理由に、子どもを産ませないことが社会全体の利益につながると考えられていました。もう一つは「人口政策」です。戦後の混乱期に人口増加が問題視され、人工妊娠中絶を合法化する必要があったのです。
この法律の下で、約1万6千件以上の強制不妊手術が行われたと推計されています。
本人の同意がないまま手術が実施され、人生を大きく奪われた人々がいました。
優生保護法に関する裁判と賠償
2024年7月3日には、最高裁大法廷が旧優生保護法の規定を「違憲」と判断し、国の賠償責任を認めました【出典: 最高裁判決】。
| 裁判所 | 判断ポイント |
|---|---|
| 第一審(地裁) | 旧優生保護法は憲法違反、除斥期間適用なし、国に賠償命令(原告勝訴) |
| 控訴審(高裁) | 主要多くの高裁がこの判断を支持。 例外的に除斥期間を認めたものもあったが、賠償命令が多数 |
| 最高裁 | 旧法は憲法違反で国の賠償責任あり。 除斥期間の適用は信義則・公平に反する場合は許されないと確定 |
また2019年に成立した一時金支給法では、被害者1人あたり320万円の補償が定められ、2025年1月時点で1,180件が認定されています【出典: 厚労省資料 – 旧優生保護法一時金支給法に係る経緯等, 旧優生保護法補償金等支給法に係る経緯等】。
母体保護法への改正
1996年、国際的な人権意識の高まりや国内の批判を背景に、優生保護法は廃止されました。その代わりに制定されたのが「母体保護法」です。
改正のポイントは、「優生的な条項」を削除したことにあります。つまり「遺伝的に劣っているから産ませない」といった発想は、正式に法から排除されました。
しかし問題は残りました。新しい法律の名前が示すように、「母体保護法」は女性を「母体=胎児を育てる器」として位置づける構造を温存していたのです。女性自身の意思や生き方の選択よりも、「母体を守る」という発想が前面に出ています。
そのため、現代のフェミニズムや人権の観点からは「女性の自己決定権を十分に尊重していない」と批判されています。
法は価値観と共に変わる
「法は社会の価値観に従って変わる」ものです。優生保護法から母体保護法への改正はその典型例といえます。
ここでは、価値観の変化で変化した法の事例と、現代議論されている課題についてまとめます。
歴史的な事例
実際、日本の歴史を振り返ると同じような事例がいくつもあります。
- 家制度の廃止(1947年)
戦前の民法では戸主が家族全員を支配しましたが、戦後の憲法24条「個人の尊厳と両性の平等」を受けて廃止されました。(家父長制の解体) - 治安維持法の廃止(1945年)
言論・思想を弾圧した治安維持法は、敗戦と同時に廃止され、民主化が進められました。 - 公害対策基本法 → 環境基本法(1970年代以降)
高度成長期の「経済優先」から、「環境と健康を守る」価値観への転換が法改正に結びつきました。
これらはすべて、価値観の変化が直接に法制度を変えた事例です。
現代に議論される課題
では、現代の日本において「価値観と法のズレ」が指摘されている事例は何でしょうか。
選択的夫婦別姓
世論調査では「夫婦別姓を選べるようにすべき」とする回答が63%(朝日新聞 2025年2月調査)と多数派になっています【出典: 朝日新聞】。一方で内閣府の調査(2021年実施)では設問文が異なるため「導入賛成28.9%」にとどまりました【出典: 内閣府】。
設問の立て方によって結果が大きく変わるこの問題は、社会の価値観の揺らぎを示しています。
同性婚の承認
同性婚については賛成72%/反対18%(朝日新聞 2023年調査)と、圧倒的に賛成が多くなっています【出典: 朝日新聞】。
自治体によるパートナーシップ制度も2025年時点で530自治体/人口カバー率92.5%に広がり、実質的には社会の承認が進んでいます。
親権制度
2024年5月17日、民法改正により離婚後の共同親権制度が導入されました。
2026年から施行予定で、DVなどの場合は単独親権も選べる「選択制」となります【出典: 法務省・報道】。これも国際基準に合わせる形での制度変化です。
性犯罪規定
長年「暴行・脅迫」が要件だった強姦罪は、2017年に強制性交等罪へと改正され、非親告罪化などが進みました。さらに2023年には不同意性交等罪が新設され、性交同意年齢も13歳から16歳へ引き上げられました【出典: 法務省】。
性犯罪の定義や被害者保護の範囲も、時代の価値観に応じて変化しているのです。
私たちの価値観と法
歴史を振り返ると、法律は常に時代の価値観を反映しながら変化してきました。家制度も、治安維持法も、かつては当然とされていたものが廃止されました。
では現代の私たちはどうでしょうか。
「わたしの体は母体じゃない」訴訟
優生保護法は違憲とされ、既に廃止されています。しかし、母体保護法については未だ議論され続けています。以下に、分かりやすくマンガ形式にまとめられた母体保護法の問題と、その訴訟活動について紹介しますので、是非ご覧ください。
- わたしの体は母体じゃない – マンガで公共訴訟(13) – 公共訴訟のCALL4(コールフォー)
- 「わたしの体は母体じゃない」訴訟 – 公共訴訟のCALL4(コールフォー)
(引用 : 「わたしの体は母体じゃない」訴訟 より)
生殖能力に違和感を覚えたり、子どもをもたない生き方を確信をもって選択した原告らにとって、不妊手術は自分が自分らしく生きるために不可欠な手段です。
しかし母体保護法は医療目的等以外の不妊手術を原則として禁止し、施術する場合にも子を既に出産していることや配偶者の同意を必要としています。
これらの規定が、生殖に関する自己決定権を侵害し、憲法違反であることを訴え、現在のルールを変えたいと考えています。
法は時代と共に変化する
私たちは、法令を守りながら日々の生活を営んでいます。
しかし社会の価値観は時とともに変わり、それにあわせて法律も少しずつ改められてきました。法律は確かに「守るべきもの」ですが、同時に「時代に合わせて直していくもの」でもあります。
大切なのは、法律を盲目的に信じるのではなく、私たち自身の価値観に照らして改善を考え続ける姿勢なのです。
関連記事:価値観の起源を探る
本記事では「価値観と法改正」の関係を見てきましたが、価値観そのものの起源を知ることも大切です。
日本では当たり前と思われている価値観が、実は外から持ち込まれた歴史があります。常識とされる価値観は本当に正しいのか――ぜひあわせてご覧ください。