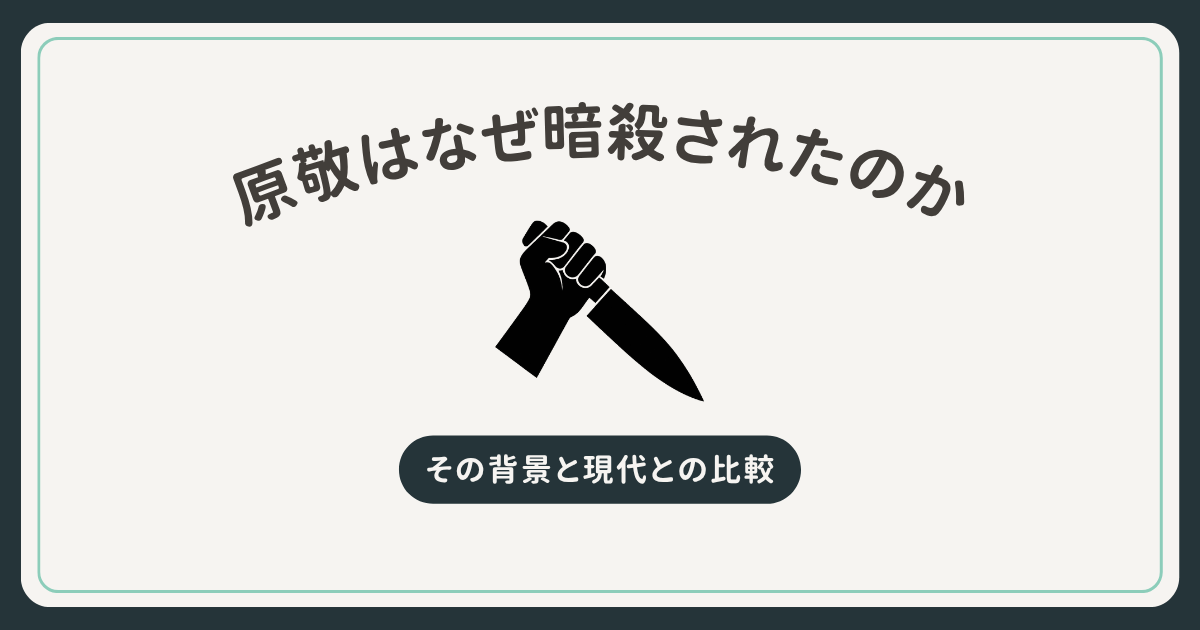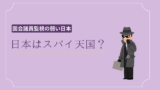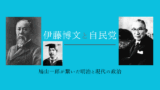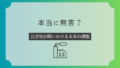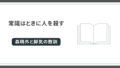1921年11月4日、現職の内閣総理大臣・原敬(はらたかし)が東京駅で刺殺されました。
大正デモクラシーを象徴する「平民宰相」が倒れたこの事件は、日本の政治史に深い影を落とします。100年以上前の出来事ですが、政治不信や社会の閉塞感という背景は、現代とも無縁ではありません。
この記事では、原敬暗殺の詳細をたどり、現代日本との共通点と違いを整理しながら、私たちがこの歴史から何を学べるのかを考えます。
日本初の「現職首相」原敬暗殺 ー 事件概要
1921年(大正10年)11月4日午後7時過ぎ、内閣総理大臣・原敬は東京駅のホームに降り立った直後、青年に短刀で刺され、その場で命を落としました。犯人は元鉄道省職員の中岡艮一(こんいち)、26歳。政治家や政党に強い不満を抱き、「腐敗した政治を正すため」と供述しています。
首相在任期間は1918年(大正7年)9月29日〜1921年11月4日 で、約3年1か月あまりでした。

東京駅 (丸の内南口)
この暗殺は日本史上初の「現職首相暗殺事件」として国民を震撼させ、政治不信を一層深める結果となりました。
原敬の実績と批判
原敬(はら たかし、1856~1921年)は、岩手県盛岡出身の政治家で、日本史上初の「平民宰相」と呼ばれた人物です。
平民宰相とは、華族(元公家や大名)や旧藩閥(薩長土肥)の出身ではなく、庶民から首相に上りつめた政治家を指す呼称です。
原敬(はら たかし)は、日本史上初の「平民宰相」だったのです。

原敬(はらたかし)
画像引用 : 第19代 原 敬 | 歴代内閣 | 首相官邸ホームページ
「平民宰相」と期待され「金権政治家」と批判される
明治時代後半、原は立憲政友会を率い、議会を基盤とした政党政治の確立に尽力しました。
彼の内閣は、鉄道や道路などのインフラ整備、教育予算の増額、外交の安定化など、近代国家としての基盤を整える施策を推進しました。
| 代 | 氏名 | 主な特徴・背景 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤博文 | 明治の元勲・初代首相。(総理在任:明治前期~中期) 薩長藩閥政治からの脱却を目指し、立憲政友会を創設。 |
| 2 | 西園寺公望 | 伊藤の後継。2度の内閣を組閣し、立憲政友会を政権与党に育てる。 穏健派の公家出身。(総理在任:明治後期~大正初期) |
| 3 | 原敬 | 初の「平民宰相」。(総理在任:大正初期~中期) 政党政治を確立。鉄道網整備や選挙制度改革を推進。 |
一方で、理想と現実の間には大きな乖離がありました。
政友会の勢力を維持するために議員や地方有力者との関係を深め、選挙には莫大な資金が投じられました。そのため「平民宰相」という呼び名とは裏腹に、「金権政治家」という批判も多かったのです。
「安定志向」という「弱腰」な外交姿勢
原はまた、内政だけでなく外交にも影響力を発揮しました。
第一次世界大戦後の国際秩序の中で協調外交を進め、国際連盟への加盟を実現。
対米協調を軸とした安定志向の外交は一定の評価を受けますが、その慎重な外交姿勢は一部から「弱腰」とも見られました。
総括:原敬の政治
こうした原の政治スタイルは、一方で近代化と議会政治の象徴でありながら、他方で旧来型の利権政治から脱しきれない矛盾を抱えていました。
その結果、国民の間では尊敬と不信が入り混じった複雑な感情が芽生え、暗殺犯中岡艮一のような青年が「腐敗した政治を正す」という過激な動機を抱く土壌を生むことになります。
事件後の社会と政党政治への影響
原敬の死後、政友会は急速に混乱し、後継として第四代総裁の高橋是清が首相に就任します。(高橋は財政政策で手腕を発揮し、後の世界恐慌時にも経済再建を行いました)
「政党政治こそ近代化の象徴」とされた時代に起きたこの事件は、「政治は金で動く」「選挙は一部の富裕層のためのもの」という国民の不信感を決定づけ、やがて1930年代の軍部台頭や政治の不安定化へとつながる一因になったといわれます。
犯人・中岡艮一は死刑判決を受けましたが、大正天皇の恩赦で無期懲役に減刑され服役中に病死。
社会の一部には同情の声もあり、「腐敗した政治家を討った」という評価さえあったことは、当時の不満の深さを物語っています。
原敬暗殺の背景と現代の共通点
100年前の日本と現代はまったく別の時代のように思えます。
しかし、原敬暗殺の背景を紐解くと、今の社会にも通じる問題が浮かび上がります。

まずは「政治不信」と「お金の問題」という視点から見てみましょう。
「政治とカネ」による政治への不信
原敬の時代、政党政治は確かに近代化の象徴でしたが、同時に「金権政治」の温床でもありました。選挙資金や利益誘導のための政策が横行し、庶民には政治が遠い存在に見えたのです。
現代でも政治資金パーティーや派閥問題、汚職疑惑などが繰り返し報じられ、政治への信頼は決して高いとはいえません。
「結局は既得権益層のための政治」という感覚は、100年前も今も国民の間に存在しています。
貧困・孤立・格差が生む不満の連鎖
犯人・中岡は鉄道省を辞めた後、生活に困窮し、社会から孤立していました。経済格差が広がる中で思想的影響を受け、「一人で政治を正す」という過激な行動に至ったのです。
現代日本でも格差や非正規雇用、孤独死問題などが注目されています。SNSで過激思想や陰謀論が容易に広まり、孤立した個人が短期間で過激化する例も見られます。
社会の閉塞感が個人の絶望を深め、暴力的な行動を正当化してしまう構造は、100年前から変わらず存在しているといえるでしょう。
原敬暗殺と現代の違い
原敬暗殺の背景には現代と重なる課題が多く見られますが、同時に時代は確実に変わっています。
社会の仕組みや情報環境の進歩は、当時とはまったく異なる状況を私たちに与えています。
ここからは、100年前と現代の「違い」に目を向けてみましょう。
新聞・雑誌からインターネットへ
1920年代の情報源は新聞や雑誌に限られ、情報は遅く、限られた人々の手にしか届きませんでした。事件は世論に衝撃を与えましたが、国民の反応は今よりも限定的で、政治的な対話の場も少なかったのです。
現代はインターネットとSNSで誰もが情報を発信でき、事件の背景や政治の問題点が瞬時に共有されます。その一方で、誤情報や偏った意見が拡散しやすく、社会不安や憎悪を増幅させるリスクも高まっています。
情報の即時性は、時代の進化であり同時に新たな課題でもあります。
制限されていた「選挙権」
原敬暗殺が起きた1921年当時、選挙権は納税額によって制限され、国民の多くは政治に直接関与できませんでした。
不満を持っても、投票で意思を示す手段が限られていたのです。
現代では18歳以上のすべての国民が一票を持ち、選挙に参加できます。暴力ではなく言論や投票によって社会を変えられる仕組みは、過去の時代にはなかった大きな進歩です。
歴史を振り返れば、今の私たちがどれほど恵まれた環境にいるかがわかります。
投票で示せる社会の意思
原敬暗殺は、日本政治史に深い爪痕を残しました。腐敗や不平等に対する怒りは理解できても、暴力は何も解決せず、社会を混乱させるだけだったという歴史の教訓がここにはあります。
現代の日本社会にも、政治不信や格差、孤立といった問題は残っています。
だからこそ、私たちには暴力ではなく投票で社会を動かす力が与えられているのです。
100年前の悲劇を繰り返さないために、一票の価値を改めて考えてみませんか。
関連記事:国会議員監視の弱い日本
投票行動をするために、私たちは政治や国会議員の行動をしっかり監視しなければなりません。最近は「スパイ防止法」を巡る議論も活発です。以下の記事では日本の「国会議員監視の弱さ」についてまとめていますので、是非あわせてご覧ください。
関連記事:立憲政友会と自民党の繋がり
原敬は立憲政友会の総裁として、内閣総理大臣に就任します。
立憲政友会は、藩閥政治から政党政治へ舵を切った伊藤博文が作った政党です。その初代幹事長は、戦後の自由民主党(自民党)初代総裁鳩山一郎の父・鳩山和夫です。
以下の記事では、鳩山一郎を中心として、立憲政友会と自民党の繋がりを解説していますので、関心のある方は是非こちらもご覧ください。