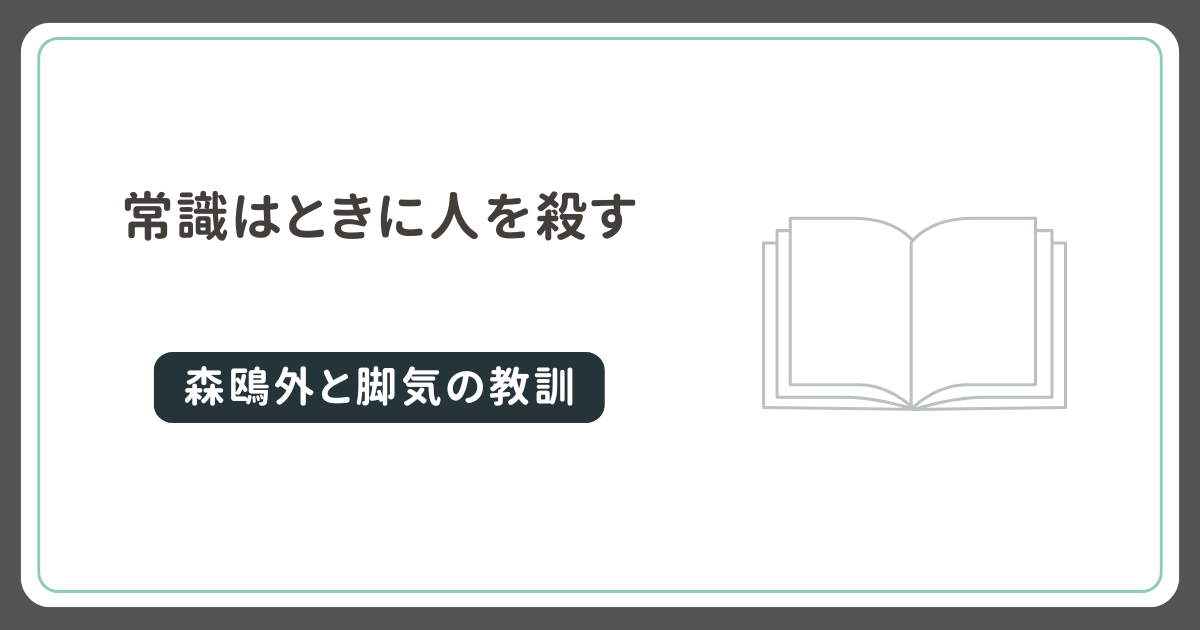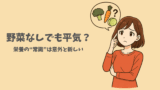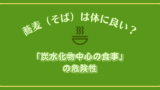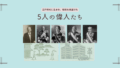「科学的に正しい」という言葉には、どこか安心感があります。
しかし、歴史を振り返ると“科学の常識”が命を奪った事例が数多くあります。
その象徴のひとつが、明治時代の日本陸軍で発生した脚気による大量死です。この悲劇の背景には、森鴎外という一人の軍医の判断がありました。彼は当時の最先端科学を信じた結果、実地での観察や経験則を退け、結果的に数万人の兵士を失いました。
この歴史は、常識や権威を盲信することの危うさを、現代の私たちに強烈に突きつけています。
森鴎外と脚気 ― 戦場で命を奪った病
脚気(かっけ)は、ビタミンB1の欠乏によって神経障害や心不全を引き起こす病気です。江戸時代から日本で広く知られていましたが、当時は原因が分からず「贅沢病」と呼ばれることもありました。

明治時代に入り、軍隊の兵食にも白米が普及しました。清潔で高級感のある白米は、兵士の士気を高める象徴でもありましたが、同時に麦飯に比べてビタミンB1が少ないという欠点もありました。
脚気は、兵士たちの命を奪う深刻な問題へと発展します。
対照的な対応をした陸軍と海軍
明治期の陸軍では、兵士の士気向上や「近代的な軍隊の象徴」として白米中心の食事が採用されました。しかし、白米偏重は脚気を蔓延させ、戦場での兵士の体力を奪いました。
日露戦争時には、脚気対策の方針が陸軍と海軍で異なり、患者数や死者数に大きな違いが生じます。
| 軍種 | 脚気患者数 | 脚気死者数 | 食事方針 |
|---|---|---|---|
| 陸軍 | 約25万人 | 約2万7千人 | 白米中心、対策なし |
| 海軍 | ほぼゼロ | ほぼゼロ | 麦飯の他に、パンなど 近代的な洋食スタイルの食事を導入 |
同じ日本軍でありながら、方針の違いが兵士たちの命運を大きく左右したことが、この数字からも明らかです。
二人の軍医:森鴎外と高木兼寛
この脚気問題の背景には、陸軍と海軍を率いた二人の軍医の対照的な判断がありました。
| 項目 | 森鴎外(もり おうがい) | 高木兼寛(たかぎ かねひろ) |
|---|---|---|
| 軍での立場 | 陸軍軍医総監 (陸軍医療体制の最高責任者) | 海軍軍医総監 (海軍医療体制の最高責任者) |
| 脚気への考え方 | 細菌説を主張、栄養学的原因説を否定 | 統計的分析で麦飯の有効性を証明、食事改革を推進 |
| 評価 | 権威主義的・理論重視。 脚気問題では悲劇を招いた象徴 | 実証主義の象徴。 現場データを尊重し兵士の命を救った |
| —– | —– | —– |
| 生年・出身 | 1862年 島根県 | 1849年 宮崎県 |
| 学歴・留学 | 東京大学医学部卒業後、ドイツ留学(1884–1888) | 長崎で英語・医学を学び、イギリス留学(1870年代) |
| 成果・功績 | 衛生制度、防疫・検疫体制を整備。 文学者としても活躍(舞姫など) | 海軍の脚気根絶に成功。 日本初の近代医学校(慈恵医大)を創設 |
森鴎外は近代衛生制度の整備者としても功績を残しましたが、脚気については細菌説に固執し、現場の観察を軽視しました。対照的に高木兼寛は、海外で得た知識を統計的思考と組み合わせ、観察データに基づく改革を実行しました。
同じ時代に同じ軍医総監の地位にあった二人の判断の違いは、日本軍の歴史に大きな影響を与えました。
森鴎外の信念と判断
森鴎外は陸軍軍医総監として、日本陸軍の衛生政策や医療体制を統括していました。彼は「脚気は細菌感染による病気である」と信じ、白米中心の兵食を改めることをしませんでした。
この判断は、鴎外個人の独断というよりも、当時の世界医学の潮流や知識レベルに深く影響されたものです。

画像引用:森鴎外について – 文京区立森鴎外記念館
森鴎外の決断の背景
鴎外が脚気を細菌説で説明しようとしたのには、当時の医学界の状況と栄養学の未熟さが関係していました。
細菌説が最新医学だった時代背景
19世紀後半の医学界では、ルイ・パスツールやロベルト・コッホの研究によって「病気は細菌が原因である」という学説が強固な支持を得ていました。コッホは炭疽菌や結核菌、コレラ菌などを発見し、感染症対策に革命をもたらしました。
森鴎外はドイツ留学中にこの学説を学び、日本に導入した第一人者の一人です。
そのため脚気も細菌による感染症と考えるのは、当時としては最も科学的で合理的な判断だったのです。
日露戦争前後は、日本でペストが流行していた時期でもあり、森鴎外はペスト防疫でも活躍しています。鴎外の「脚気=細菌」の考えはペスト流行前からではありますが、ペスト対策によっても「細菌対策は役立つ科学」という実績になりました。
日本のペスト対策の歴史については以下の記事で詳しくまとめています。興味のある方は是非ご覧ください。
栄養学が未発達だった現実
森鴎外の時代、栄養学はまだ初歩的な段階にありました。
当時は「ビタミン」という概念すらなく、欠乏症の発想も存在しませんでした。
栄養研究はまだカロリー計算や三大栄養素(炭水化物・タンパク質・脂肪)の理解が始まった段階であり、脚気を「栄養欠乏症」と結びつける科学的根拠はありませんでした。
栄養学的な説明を軽視したのは、科学的証明が不十分だった時代背景も大きな要因でした。
後に明らかになった真実 – オリザニン(ビタミンB1)の発見
1910年、鈴木梅太郎が米ぬかから「オリザニン」(後のビタミンB1)を抽出し、脚気の原因がビタミン欠乏であることが初めて科学的に証明されました。
その後、栄養学は急速に発展し、脚気は「栄養失調の病」として理解されるようになります。
森鴎外の判断は誤りだったとされますが、それは個人の怠慢ではなく、当時の科学知識の限界を象徴した出来事でもあります。
彼の功績は多く、衛生制度や防疫体制の近代化に尽力したことも忘れてはなりません。
脚気論争は、科学の進歩がいかに試行錯誤を伴うかを示す貴重な歴史です。
現代では常識な「ビタミン」、実はまだ発見されて100年程しか経過していません。
歴史の中では脚気以外にも、栄養不足が原因で人々を苦しめた病気は多くあります。以下の記事ではその一部を紹介し、野菜を食べないことのリスクと対策をまとめていますので、興味のある方は是非ご覧ください。
歴史が示す現代への教訓
森鴎外の失敗は、「科学を否定した失敗」ではありません。
むしろ彼は科学を信じた結果、別の視点を軽視してしまったのです。
実測や観察を軽んじることが、いかに命に関わるか。
これは過去の公害問題や、今議論される気候変動対策にも共通する構造です。
科学や常識は常に進化し、時に誤ることもあります。
だからこそ、データや観察を尊重し、柔軟に疑う姿勢を持ち続けなければなりません。
この記事の狙いは、「常識を盲信することの危うさ」を、歴史を通じて再確認してもらうことです。
世間一般では、「常識」や「普通」を重視し、科学的根拠の乏しいものは否定されがちです。しかし、その考え方の行きつく先は、森鴎外の失敗ではないでしょうか。
森鴎外の歴史は、未来の私たちに対する重要な警告として語り継ぐ価値があります。
関連記事:脚気対策には蕎麦もよい
以下の記事では、脚気対策に有効な食べ物の紹介をしています。ビタミンB1の豊富な食材には豚肉など様々なものがあります。物価高騰する現代でも比較安価に購入できる「蕎麦」は、江戸時代には脚気(江戸患い)の対策に有効と噂が広まり、江戸で大流行します。