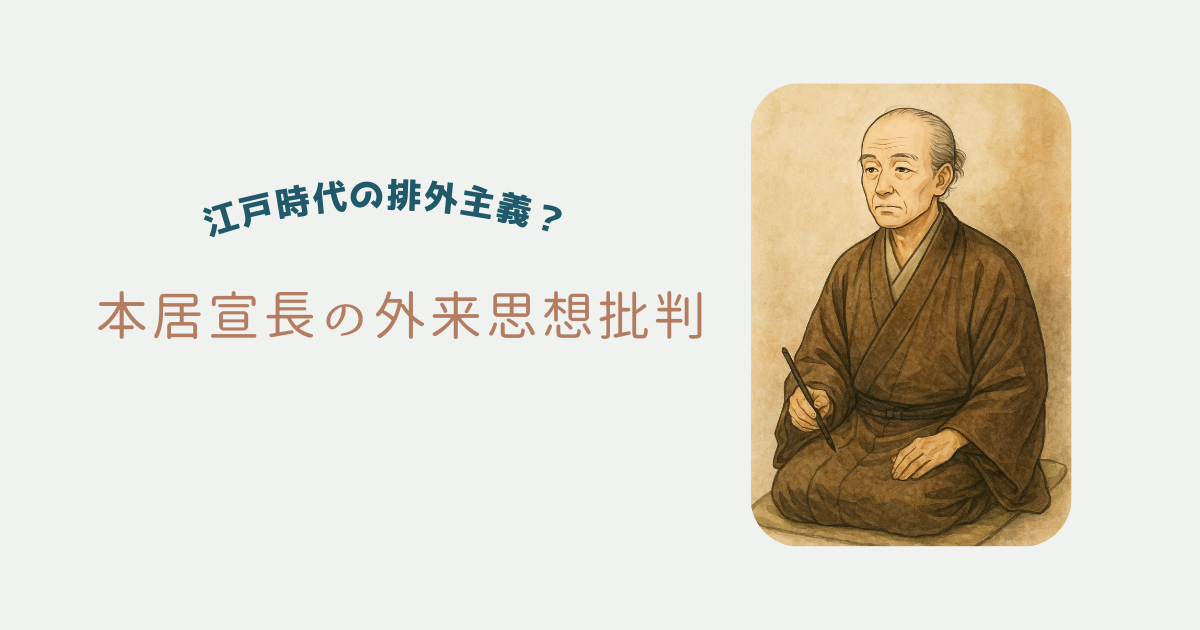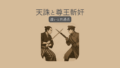現代の日本社会では「日本人ファースト」や「右傾化」といった言葉が飛び交い、外国人受け入れや国際関係をめぐる議論が熱を帯びています。外からの影響に揺さぶられるなかで、「日本らしさ」をどう守るのかという問いは、今や誰にとっても身近なものになっています。
しかし実は、江戸時代にも同じように「外来思想」を警戒し、日本固有のあり方を模索した学者がいました。それが国学者・本居宣長です。彼は儒教や仏教を「からごころ」と呼び、強く批判しました。この姿勢は、現代的な排外主義と重なるのでしょうか。
本居宣長の思想とは
本居宣長が説いたのは、「やまとごころ」と「からごころ」という二つの概念でした。
「やまとごころ」とは
宣長にとって「やまとごころ」とは、日本人が本来もつ素直で自然な心です。喜怒哀楽をそのまま受け止め、歌や物語のなかにあらわれる豊かな情緒を大切にする心のあり方でした。
この「やまとごころ」を最も端的に表す言葉として、宣長は「もののあはれ」を重視しました。自然の移ろいや人の感情に触れたときに生まれる「しみじみとした感受性」こそ、日本人の精神文化の核だとしたのです。
「もののあはれ」という美的理念については、日本古来からの美意識として知られる「侘び寂び」との違いなどを含めて、以下の記事で解説しています。是非合わせてご覧ください。
💡関連記事:もののあはれとは?-侘び寂びとの違いと歴史に与えた影響
「からごころ」とは
その対極にあるのが「からごころ(漢意)」です。
理屈や外来思想に頼り、日本人の素直な心を曇らせてしまう心を指します。宣長は特に、当時幕府に重んじられていた朱子学や、現世を否定する仏教を名指しで批判しました。
江戸時代の外来思想批判が生まれた空気
宣長のことばだけを切り出すと過激に見えますが、当時の「空気」を押さえると、彼の問題意識の輪郭がはっきりします。

政策と学問の枠組み
幕府は朱子学を「正統」とし、昌平坂学問所を中心に官学として整備しました。学問は漢文教養と結びつき、異説は抑制的に扱われがち。寺請制度やキリスト教禁制など宗教統制も広く及び、思想・信仰の「型」は上から固定されていました。
寺請制度は、住民が寺に登録する制度で、戸籍のような役割を果たしていました。
しかし、宗派の自由もなく、強制的に寺へ登録させられた上に、葬式・法事・寄進などで寺にお金を払わざるを得ず、経済的負担として嫌がられていました。
こうした秩序は安定をもたらす一方で、日常の感情や土着の感覚を“理”で包摂する圧力にもなります。
宣長の目には、これが「からごころ」—外から来た理屈が、日本の言葉と感情の手触りを鈍らせる—と映ったわけです。
人々の生活実感
18世紀には享保・天明などの飢饉が相次ぎ、都市では物価高と生活不安、農村では年貢・参勤交代の負担がのしかかりました。百姓一揆や打ちこわしも散発し、町では奢侈禁止令(しゃしきんしれい)や風紀取締りが周期的に強化されます。
奢侈禁止令とは、贅沢品の購入を制限し、質素・倹約を強制する法令の総称です。
儒教では本来、努力して正当に得る贅沢品を禁じる考えはありません。
しかし幕府は「武士が貧しいのに町人が豪奢に暮らすのは『礼』に反する」として、質素倹約を正当化しました。
「上からの型」と「下からの息苦しさ」。そのあいだで、人々は心の居場所を探していました。
宣長の古典回帰(『万葉集』『古事記』)は、理屈ではなく歌や物語に宿る感情の確かさ—すなわち“やまとごころ”—を拠り所にしようとする動きでした。
知のカウンター運動
江戸幕府の公式イデオロギーは朱子学でした。昌平坂学問所を頂点とする学問体系が全国に広まり、武士の教育や官僚登用の基盤となっていたのです。
つまり「学問」といえば朱子学であり、異なる思想や学び方は周縁に追いやられる状況でした。現代のように「好きな学問を自由に選ぶ」環境とはまったく異なり、思想的には朱子学一強の体制が敷かれていたのです。
本居宣長の時代(18世紀後半)、この枠組みの「窮屈さ」に反発するように、多様な知の試みが芽生えます。
- 古学・古文辞学(伊藤仁斎・荻生徂徠):経書を言葉の本来の意味から読み直そうとした。
- 心学(石田梅岩):商人の日常倫理を説き、武士中心の価値観に挑んだ。
- 蘭学(杉田玄白ら):実証的な観察に基づき、西洋医学や自然科学を取り入れた。
- 陽明学(中江藤樹~大塩平八郎):知行合一を掲げ、実践を重んじる儒学批判の流れ。
- 国学(荷田春満—賀茂真淵—本居宣長):中国思想から距離を取り、日本の古典に根ざした「やまとごころ」を再発見した。
宣長はこの潮流の中で、「言葉と心」を徹底的に掘り下げ、やまとごころを「感じ、言いあらわす力」として再建しようとしました。
陽明学は儒学の一派ですが、18世紀以降には朱子学中心の幕府に対抗する学問として広がり、武士や町人の倫理にも影響しました。
その流れを受けた大塩平八郎は、米の高騰や政治の腐敗に対して、学問を実践へと結びつけ、行動によって世に訴えました。詳しくは以下の記事をご覧ください。
💡関連記事:令和のコメ騒動と大塩平八郎の乱 – 政治の腐敗と米の高騰
外圧の前兆と揺れる秩序
18世紀末には北方からの接近(ロシア船来航など)が報じられ、外の存在が具体性を帯び始めます。幕藩体制の統治はなお強固でしたが、「内なる秩序」と「外の気配」が同時に意識される境目の時代。
“外”の影にざわつく心は、宣長の外来思想批判(からごころ)をいっそう切実に響かせました。日本語の古層に潜む感情世界を拠り所にすること—これが宣長の選んだ応答でした。
「やまとごころ」から「もののあはれ」へ
宣長が重視したやまとごころは、感情の豊かさをそのまま受け止める力です。その具体の姿として彼が提示したのが「もののあはれ」でした。自然の移ろい、人の心のふとした震えに「しみじみ」と応じる感受性は、理屈より前にある生活の真実です。
—この視点の詳しい解説は、別記事「もののあはれとは何か」もあわせてどうぞ。
現代の排外主義との比較
ここで現代と比較してみましょう。
- 共通点
外からの思想や文化に揺さぶられる状況に対し、日本らしさを守ろうという意識。 - 違い
現代の排外主義は、移民や国際関係をめぐる政治的・社会的な排除として現れます。
一方、宣長の国学は文化的・精神的な次元で「やまとごころ」を取り戻す営みでした。
本居宣長は排外主義者なのか
宣長の思想を読むと「排外的だ」と感じる人は少なくないでしょう。
実際、彼の言葉は外来思想を徹底的に退け、日本人固有の心を称揚するものだからです。
学問的な評価も分かれています。
多くの研究では、宣長を「現代的な意味での排外主義者」とはみなしていません。彼は政治家ではなく学者であり、外国人排斥や外交政策を唱えたわけではないからです。
ただし同時に、近代日本における国家主義や排外思想の源流のひとつとする見解も存在します。
本居宣長の国学は、その後、水戸学や尊王攘夷思想を通じて受け継がれ、最終的に明治維新の精神的基盤の一つとなっていきました。
やまとごころを思い出そう
外からの思想や文化に揺さぶられることは、昔も今もあります。
本居宣長は『やまとごころ』を見失うなと説きました。
今こそ私たち自身も、自らの心を見つめ直し、「日本人とは何か」を改めて考える時ではないでしょうか。
関連記事:天誅と尊王斬奸
今回紹介した学問の中に、大塩平八郎の学んだ「陽明学」があります。陽明学には「正しいと知れば、たとえ結果が不利でも行うのが本物の知」という考えがあります。(知行合一)
この考えは、後の時代に過激な行動を起こす原動力にもなって今います。
以下の記事では「桜田門外の変」のスローガンとなった「天誅」と、昭和の二・二六事件のスローガンになった「尊王斬奸」について比較しています。両者ともに死を覚悟していても、その死についての考え方には違いがあります。関心のある方は是非ご覧ください。