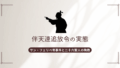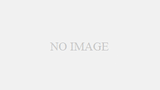日本にキリスト教が伝えられてから半世紀後、豊臣秀吉は「伴天連追放令」を発しました。
それは、信仰の問題にとどまらず、貿易・外交・国家のあり方をめぐる大きな決断でした。
ザビエルの来日から秀吉の死までの流れを、年表で整理します。
年表:日本最初の禁教令 ― 伴天連追放令の歴史
凡例:
赤色背景 ー 「イエズス会」関連
黄色背景 ー 「秀吉」関連
| 年 | 出来事 | 備考 |
|---|---|---|
| 1549年 | フランシスコ・ザビエル、鹿児島に上陸 | 日本にキリスト教が伝来。宣教師はポルトガル船で来航。 |
| 1550年 | ザビエル、山口で布教 | 大内義隆の庇護を受ける。西日本で布教が広がる。 |
| 1551年 | 大内義隆の死 | 西国の布教拠点を失い、ザビエルは失意のうちに日本を離れる。 |
| 1552年 | ザビエル、航海中に病死 | 中国広東島で死去。以後、日本布教はイエズス会士が継承。 |
| 1560年代 | 九州でキリシタン大名が増加 | 大村純忠・大友宗麟・有馬晴信らが改宗。布教と貿易が結びつく。 |
| 1563年 | 大村純忠がキリスト教に改宗 | 日本初のキリシタン大名。領内で教会建設を許可。 |
| 1565年頃 | 平戸・口之津で南蛮貿易が活発化 | ポルトガル商人と宣教師が定期的に来航。 |
| 1570年 | イエズス会、長崎に注目 | 安全な貿易港と布教拠点を求め、港建設を提案。 |
| 1571年 | 大村純忠、長崎港を開港・寄進 | ポルトガル船が初入港。港湾管理権をイエズス会に寄進。 長崎が南蛮貿易の中心に。 |
| 1575年 | 長崎に司教館が設立 | 日本布教の本部として機能。イエズス会の自治が拡大。 |
| 1578年 | 大友宗麟、臼杵で布教を保護 | 豊後がキリシタン文化の拠点に。教会学校や神学校も設立。 |
| 1582年 | 天正遣欧少年使節が出発 | 九州のキリシタン大名のもとからローマ教皇に派遣。 ヨーロッパとの宗教交流の象徴。 |
| 1582年 | 本能寺の変 | 織田信長が倒れ、豊臣秀吉が天下統一へと動き出す。 |
| 1585年 | 秀吉、関白に就任 | 政治権力を確立。全国統一を目前に、宗教勢力への統制を強化。 |
| 1586年 | ガスパル・コエリョ、秀吉と会見 | 宣教師の活動報告を行う。 長崎に砦を築こうとする構想を漏らし、秀吉の不信を招く。 |
| 1587年(天正15年) | 秀吉、九州を平定 | 島津氏を降伏させ、九州全土を支配下に置く。長崎を視察。 |
| 1587年6月 | 伴天連追放令を発布 | 宣教師の国外追放・布教禁止を命じる。 同時に長崎を没収し直轄地化。 |
| 1587年〜1588年 | 秀吉、日本人奴隷貿易に抗議 | ローマ教皇宛に書簡を送り、奴隷売買の禁止を要求。 |
| 1588年 | 秀吉、刀狩令を発布 | 農民・宗教勢力の武装解除を進める。宗教統制政策の一環。 |
| 1590年 | 全国統一がほぼ完了 | 各地の宗教・貿易を豊臣政権の直轄支配に置き、禁教方針を継続。 |
| 1591年 | 千利休が処刑 | 宗教的・思想的権威への抑制を象徴する事件。 |
| 1592年 | 文禄の役(朝鮮出兵)開始 | 海外征服政策に転換。南蛮貿易の利用を継続。 |
| 1596年 | サン・フェリペ号事件 | 土佐に漂着したスペイン船。 再びキリスト教への警戒を高める。 |
| 1597年 | 二十六聖人殉教 | 長崎で宣教師・信徒26名を処刑。禁教の方針が明確化。 |
| 1598年 | 秀吉死去 | 禁教政策はいったん停滞するが、後の徳川政権が継承。 |
関連記事:伴天連追放令の解説記事
この年表に関連した出来事や動きについては、以下の記事で詳しく解説しています。