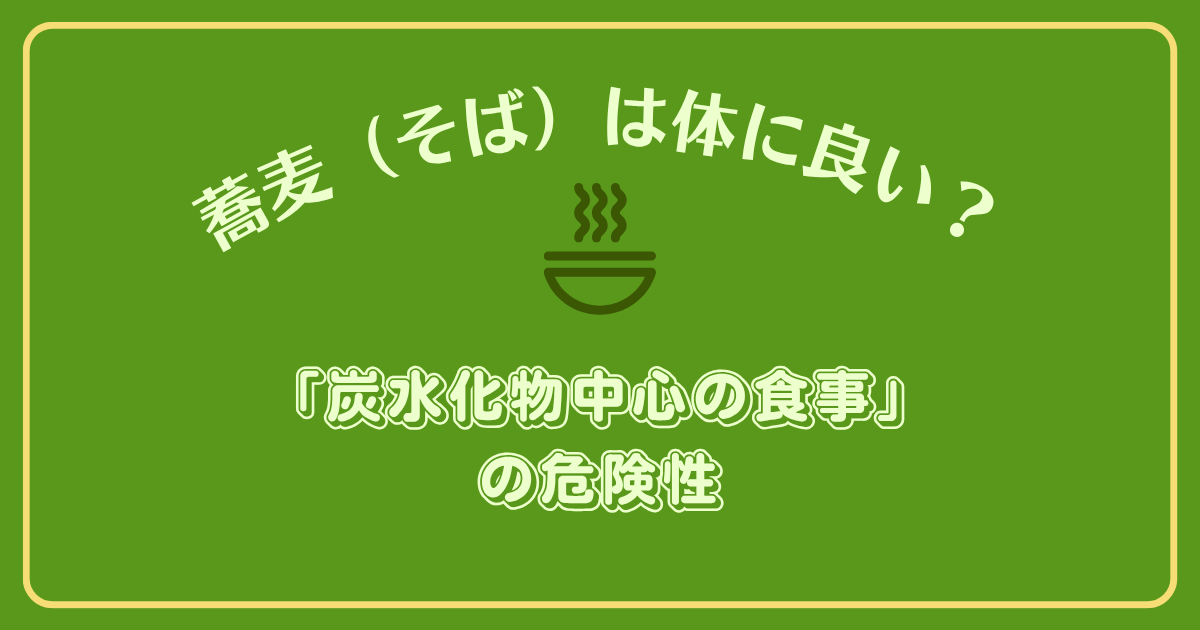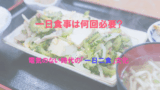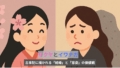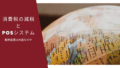近年では、宅配や冷凍食品などで手軽に食事を調達できるようになったこともあり、「野菜を食べない」食生活をしている人も多いようです。
炭水化物を中心とした食生活をしていると、手足が痺れたり、眩暈(めまい)がするといった体の異変を感じる事があります。今回は、この症状の原因や危険性と共に、その対策に蕎麦(そば)が役に立つということを、歴史を交えて紹介しています。
ビタミンB1不足と脚気
野菜をあまり食べず、炭水化物を中心とした食生活を送っていると病気になりやすくなるといった話を聞くこともあります。
炭水化物を中心とした食事を続けると、体にはどのような変化が出てくるのか、歴史を振り返りながら確認してみましょう。
炭水化物が引き起こす病気「脚気 : かっけ」
炭水化物中心の食事によって引き起こされる代表的な病気は「脚気 : かっけ」です。脚気と言えば、膝を叩いて反応するかどうかのテストが有名です。

脚気は、肉や野菜をあまり摂取せず、炭水化物を中心とした食事で引き起こされる病気で、日本では白米を食べるようになった江戸から昭和時期までに多くの国民を苦しめた病気でもあります。
「脚気」の症状
脚気は体全身に問題が発生する病気で、代表的な症状には以下のようなものがあります。
- 全身の倦怠感
- 手足の痺れ
- 食欲不全
- めまい
- 息切れ
日常生活をしていて、足先が痺れたように感じたり、めまいを感じるような体調が続く時は、食生活が原因で「脚気」になりかけている可能性があるため注意が必要です。
症状が悪化すると「心不全」などを引き起こし、死に至ることもある病気です。
「脚気」の原因
「脚気」の原因は、ビタミンB1の不足です。
ビタミンB1は、体内に摂取した糖質(炭水化物等)の分解で消費されます。
米や麺類、インスタントラーメンなどを中心とした食事では、糖質の分解でビタミンB1が消費されるばかりで補給されず、徐々に欠乏していくことになります。また、運動によってエネルギーを消費するとビタミンB1の消費も加速することになるため、運動量の多い人も脚気になりやすい傾向にあります。
脚気の症状が出ている際に激しい運動をしてしまうと、体内のビタミンB1がさらに消費され、症状の緩和どころか逆効果となる可能性があるため注意が必要です。
日本人を苦しめた「脚気」の歴史
日本人は伝統的に「米」を主食としてきました。
日本で肉が食べられるようになったのは明治時代以降です。栄養に関する学術的な研究が進み、国民に周知されていくのも昭和時代に入ってからの事で、それまでの日本人の多くはビタミンB1だけでなく、炭水化物以外の栄養全般が不足していたともいえるでしょう。
江戸時代に流行した「脚気」 – 江戸患い
日本は江戸時代に入ると、裕福な武士階級の人たちを中心に、精米した「白米」が食べられるようになっていきます。
精米する前の玄米にはビタミンB1が多く含まれていますが、白米にしてしまうとビタミンB1の多くは失われてしまいます。
そのため、江戸時代(1700年頃)になると、白米を食べる人が多かった江戸地方では「脚気」が流行し、当時は「江戸患い」と呼ばれて恐れられていました。また、当時の江戸では「うどん」が流行していて多くのお店がありましたが、小麦から作られた「うどん」も白米と同じような栄養しか摂取できず、白米を避けても脚気からは逃れられませんでした。
江戸患いの対策については後述します。(脚気(江戸患い)の救世主 – 蕎麦(そば)の流行)
日露戦争と脚気 – 銃弾よりも多く人の命を奪った病気
日露戦争(1904年)時の陸軍において、脚気の患者数は25万人といわれており、そのうち2万8千人が命を落としています。
日露戦争での戦死者数は4万7千人であり、その半数以上が「銃弾ではなく脚気で」亡くなっていることになります。
その一方で、海軍の脚気死者数は3名に留まっています。この原因は、補給の難しい陸軍が白米を中心とした食事をしていたのに対し、海軍では脚気の対策として洋食を取り入れる等の工夫がされていたこととされています。
栄養学が進んでいなかった当時は、「脚気」は感染症の一部だと考えられていて、軍医であっても食事の改善に否定的な人は多かったようです。(小説家としても有名な森鴎外などが反対していたことが知られています)
脚気の予防
現代に広まっている「バランスの良い食事」をすることは、それだけで脚気予防になっていて、日本国内の脚気患者は戦前の日本と比較すると劇的に少なくなっています。
ここでは、自炊をしてバランスの良い食事を摂ることが難しい方のためにも、脚気を予防するためにはどのような食材を食べればよいのかを、具体的に紹介します。
脚気予防に有効な食材や料理
脚気を予防するためには、ビタミンB1が多く含まれる食材を食べるのが効果的です。
- 豚肉、レバー
- うなぎ、魚卵
- 玄米
- 蕎麦(そば)
- 豆類
- ごま
日々の食事の中で、これらの食材を使った料理を食べていれば、自然と脚気の予防になるでしょう。
独り暮らしで自炊が難しい人などは、豚肉の乗った丼物や、「たらこ」などの魚卵を使ったパスタなどであれば、比較的摂取しやすいのではないでしょうか。
ビタミンB1の吸収を助ける食材 – アリシン
ビタミンB1は体内に吸収されにくいため、一度に大量に摂取してもあまり意味がありません。
吸収を助ける栄養素「アリシン」と一緒に摂取すると高い効果が期待できます。「アリシン」は以下のような食材に多く含まれています。
- にんにく
- たまねぎ
- ニラ
ニラや玉ねぎと一緒に豚肉やレバーなどを組み合わせた料理、例えばレバニラ炒めのような料理は、脚気予防に非常に効果的といえます。
野菜を食べない、自炊もしない人にとっては、どれも少し摂取しずらいかもしれません。ただ、アリシンはビタミンB1の吸収を助けるものであり、脚気予防としてはまずビタミンB1を含んだ食材や料理を選ぶことが重要です。
脚気(江戸患い)の救世主 – 蕎麦(そば)の流行
生鮮食品の流通が盛んとなる昭和時期よりも前は、脚気の予防に効果的な食材を入手することは簡単ではありませんでした。また、栄養に関する知識もなかった時代では、効果がありそうという「噂」で予防法が広まっていました。
蕎麦(そば)は「体に良い」
江戸時代の蕎麦は、現代の様に小麦粉と混ぜるという習慣がなく、「蕎麦粉のみ」で作られていました。脆くて千切れやすい当時の蕎麦は食べづらく、うどんよりも不人気でした。
江戸患いに苦しめられていた江戸の人たちの間で、「蕎麦を食べている人が脚気にならない」という噂が広がりました。
丁度その頃、小麦粉と蕎麦粉を混ぜた現代のような蕎麦が作られるようになったこともあって、瞬く間に江戸中に大流行を巻き起こします。100万人の江戸の人口に対して、蕎麦を提供するお店は3000店舗以上あったともいわれています。
茹で時間が「うどん」よりも短く、手軽に食べられる「蕎麦」は、せっかちな江戸の人たちに好まれ、その上「脚気」の予防にもなるということが大流行の原因と考えられています。
この「うどん」から「そば」への流行の変化は、YouTubeなどでも数多くの動画が公開されています。もっと詳しく知りたい方は是非調べてみてください。ここでは一つだけ動画を紹介いたします。
引用 : 【蕎麦が大人気】江戸で一番多い飲食店は、なぜうどんから蕎麦に変わったのか?
引用動画チャンネル : ずんだちゃん – YouTube
手足の痺れや眩暈の対策に「蕎麦」
日々の生活の中で、手足の痺れを感じたり眩暈がする場合、食生活に問題がある可能性があります。
炭水化物中心の食事だったり、インスタントラーメンのような食事ばかりを食べていると、体内のビタミンB1が不足して「脚気」になる可能性があり、手足の痺れのような症状は、その前兆とも考えられます。
日々の生活が忙しくて自炊が難しい人や、物価高騰の対策で節約した食生活をしている人などが現代には比較的多いため、実は隠れ脚気患者のような人が多いと、医療関係者も警鐘を鳴らしているようです。
蕎麦(そば)はお手軽な「薬効」
蕎麦(そば)は、日本では古くから「薬膳」として食されていたもので、健康には様々な効果が期待できます。脚気以外にも、胃もたれや高血圧などにも効果があります。ただしアレルギーのある人は、アナフィラキシーショックなどを引き起こし、生命の危険があるため、絶対に摂取しないように注意が必要です。
日々の生活で眩暈や痺れで困っていても、忙しくて病院に行くことが難しいという人などは、是非「蕎麦 : そば」を試してみてください。炭水化物中心の食生活で脚気予備軍のような状態になっているのであれば、蕎麦のビタミンB1が体調改善に役立つ可能性があります。
先人たちが作り上げてきた「生活の知恵」という歴史を活用することで、健康な日々を過ごしましょう。