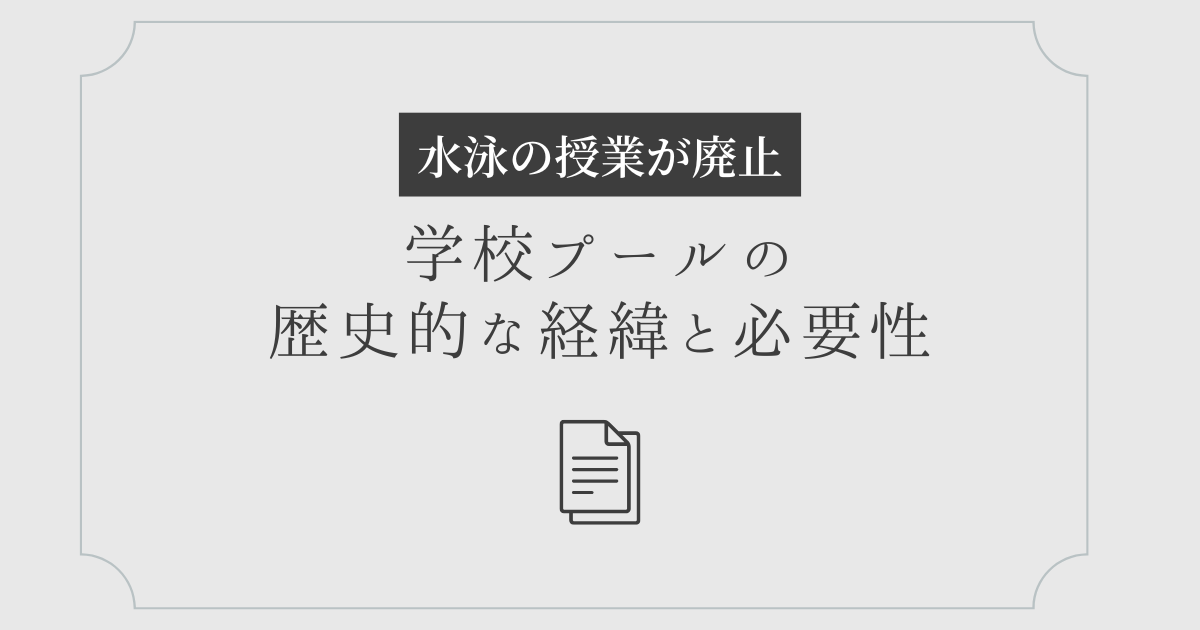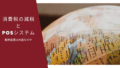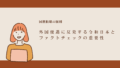令和の現代では、「伝統や慣習に捉われず、物事を合理的に変えていくべき」だという風潮があります。しかし、物事には歴史や経緯があって、結果的に現在の形式になっているものも多くあります。今回は、近年廃止されつつある義務教育での「水泳の授業」について、歴史を紐解きながら必要性を考えてみます。
水泳の授業が廃止 – 令和時代の動き
2025年6月29日、静岡県沼津市の中学校では、今年度から17校全てで「水泳の授業が廃止になる」という報道がありました。
引用動画 (YouTube) : 全国各地で水泳授業が廃止に…なぜなくなる?背景は? 着衣水泳のポイント【ワイド!スクランブル】(2025年6月29日)
引用元YouTubeチャンネル : ANNnewsCH
この動画では、全国の学校で水泳授業が廃止になっていく背景や現状について詳しく紹介されています。
水泳の授業が廃止される「原因」
上記報道でもまとめられていますが、水泳の授業が廃止される原因には以下のようなものが挙げられています。
- 教師の負担
- 老朽化
- 熱中症対策
プールの設備の耐久性は40年程度となっているものが多く、令和の現代では各学校のプール設備が老朽化していっているものの、その改修費用が莫大なため維持が難しいようです。
また、近年の気候変動の影響もあって、熱中症の対策は大きな問題となっているようです。プールサイドで生徒が火傷を負ったというニュースもある程に、プールの内外が高熱化しています。教える教師は全体を見回すためにプール外から監視をする時間も長く、危険な状態のようです。
昭和時期頃は「プールの温度が低くて水泳の授業が中止」することがありましたが、令和の現代では「高温でプールに入れない」という日があるようです。7月の水泳授業は寒くて震えていた記憶がありますが、今は最早「お風呂」に近い温度のようです。
水泳授業廃止の「賛成派」と「反対派」の意見
紹介した動画のコメント欄やSNSでは様々な意見が飛び交っています。またネットメディアのAbemaでも本件は取り扱われており、様々な立場の人が議論をして注目を集めています。
水泳の授業の廃止に賛成派の人と反対派の人、両方の意見にはどのようなものがあるのでしょうか。
| 賛成派 (不要) | 反対派 (必要) |
|---|---|
| 泳ぐ機会なんてない 親が川や海に連れて行かない 教育の優先順位を決めて対応すべき 希望者だけスイミングスクール等を活用 | もしもの時の備え 着衣水泳は必要 日本は島国で水は避けられない 教育にこそ税金を使うべき |
様々な意見がありますが、いずれにしても学校だけで解決するのは難しい問題でしょう。
現場では水泳の授業の廃止や、実技なしで座学だけ、近隣のスイミングスクール等に外部委託をするなど、学校プール設備を使わない方法で対応が図られているのが現状のようです。
プールでの水泳授業 – 歴史的な経緯
令和時代に入り、様々な理由で廃止が検討されている水泳の授業ですが、何事にも始まった経緯があるものです。水泳授業の始まりについて、日本の歴史を紐解いてみましょう。
紫雲丸事故(1955年5月) – 大勢の児童が亡くなった水難事故
1955年(昭和30年)5月11日、旧国鉄の連絡船・紫雲丸が別の連絡船(第三宇高丸)と衝突して沈没するという大きな事故がありました。この事故で、修学旅行中だった小中学生100人が犠牲となっています。
犠牲となった人は168名で、その内訳は以下のようになっています。
- 紫雲丸関係者 (2名)
- 一般乗客 (58名)
- 小中学生 (100名 – 男子19名, 女子81名)
- 引率の先生、父母 (8名)
修学旅行の帰りだったため、大事なお土産を取りに船内に戻り、助からなかった子もいたようです。女子生徒の犠牲者が多い理由としては、男子の多くが甲板にいたため早めに避難できたことなどが挙げられています。
事故現場からの遺体搬出はあまりにも凄惨で、関係者も当時の状況をしばらくは話すことができなかったとされています。
見直される安全基準と教育
同連絡船は何度も事故を起こしており、この1955年の事故は5度目となります。
大勢の死傷者を出した5度目の事故が社会に与えた衝撃は大きく、鉄道連絡船の安全基準の見直しや、瀬戸大橋建設の機運が一気に高まったとされています。(紫雲丸は岡山・香川の間を繋ぐ連絡船だったため)
この事故の2か月後、国会(第22回国会 文教委員会)で水泳授業の必要性や教員の水泳技術の向上などが議論されていることからも、紫雲丸の事故がキッカケで「国内の水泳授業が広まった」ともいわれています。
水泳の授業やプールが無かった時代では泳げない人も多く、特に女生徒は上級生になると川や池での水泳を避ける傾向があったそうです。そのため当時は、女子の方が水泳が苦手な子が多かったようです。
橋北中学校水難事件(1955年7月) – 水泳授業中の事故
橋北(きょうほく)中学校水難事件は、1955年7月(上記紫雲丸事故の2か月後)に三重県津市の津市立橋北中学校の女子生徒36人が、水泳訓練中に溺死した水難事故です。
学校にプールがなかった時代、水泳の授業が海で行われることもありました。この橋北中学校は毎年夏季に同じ海岸で10日間程度の期間で「水泳訓練」を行っていました。泳いだことが無い子や、泳ぐのが苦手な子も多く、参加生徒660名を17組に分けた内、12組が水泳能力のない子供たちでした。(男子3組,女子9組)
最終日に水泳能力テストが行われ、参加した女子生徒は200名でした。女子生徒が海に入った2~5分後には100名ほどが一気におぼれ始め、懸命に救助されましたが36名が助かりませんでした。
この水難事故は業務上過失致死で刑事裁判も行われています。この裁判において、生存者たちの証言から「異常な潮流があった」ことが認められ、最終的には無罪で確定しています。しかし、男子生徒の泳ぐエリアでは問題が確認されておらず、女子生徒の泳ぐエリアの狭い範囲でだけ異常な潮流があったことから、裁判ではその認定が難しかったようです。
学校の水泳授業にはプールが必要
橋北中学校の水難事故は、子供に水泳の教育が必要としながらも、プールのような安全な設備がない事で、「危険な自然の海を利用した」ことが根本的な原因でもあります。事故が起こった場所は水深1mほどで、決して深くはありませんでしたが、突発的な潮流で足元からすくわれて、海に引きずり込まれたと生存者が証言しています。
自然環境では、十分な注意をしていても予測不能な事態が起こり得るものです。
紫雲丸の事故と橋北中学校の水難事故が立て続けてに起きたことで、国会では厳しく国の責任追及が行われ、現在は「学校にプール設備を設けること」が義務付けされています。(例外アリ)
悲惨な事故の経験から学び、国民の命を守るため、安全な環境で最低限の水泳技術を子供たちに教える体制が整えられています。
過ちを繰り返さないために
実際に起きた悲惨な事故であっても、時と共に忘れられていくものです。プールでの水泳授業が始まった経緯や歴史を知らない人が、「プールはレジャーだ」や「水泳は必要ない」という意見がある気持ちも分かります。
この問題は、「家を建ててはいけない場所」に家を建てた結果、洪水などの被害に遭う事例とよく似ているように感じます。先人たちの警告や工夫を無視することで、人は過ちを繰り返します。
常識や慣習に捉われず、より合理的な社会を目指すことは素晴らしい事ではありますが、経緯や歴史をしっかりと確認し、慎重に結論を出す必要があるでしょう。