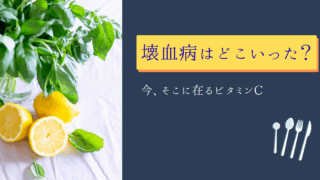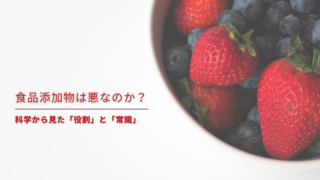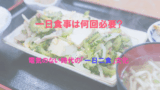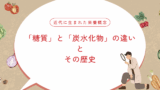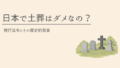最近は「野菜を食べない」食生活を送る人も少なくありません。栄養の知識はあっても、「野菜を食べなくても健康でいられる」という実体験が、その考えを後押ししているのでしょう。
しかし、私たちが信じている「栄養の常識」は意外にもまだ100年ほどの歴史しかなく、誕生の背景には深刻な病気や失敗の歴史があります。この記事では、栄養学の歩みをたどりながら、飽食の現代にも潜む偏食のリスクを考えます。
現代の栄養の常識
まずは、現代の私たちが「当たり前」と感じている栄養の基本を振り返ってみましょう。

三大栄養素やビタミン・ミネラルなど、日々の食生活で耳にする言葉の背景には、科学的な研究の積み重ねがあります。ここで一度、それぞれの役割や代表的な食材を簡単に整理しておきます。
三大栄養素とエネルギーの基礎
現代の栄養学の出発点は「三大栄養素」です。
- 炭水化物:エネルギー源。1gあたり4kcal。
- タンパク質:体をつくる材料。ホルモンや酵素の合成にも不可欠。
- 脂質:効率的なエネルギー源。細胞膜やホルモンの材料にもなる。
三大栄養素のバランスを意識することは、健康維持の基本とされています。
| 栄養素 | 主な働き | 代表的な食材 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | エネルギー源 | 米、パン、うどん、じゃがいも |
| タンパク質 | 筋肉・臓器・酵素など体をつくる材料 | 肉、魚、卵、豆腐、納豆 |
| 脂質 | 高エネルギー源、細胞膜・ホルモンの材料 | バター、オリーブ油、ナッツ、チーズ |
ビタミン・ミネラル・食物繊維
三大栄養素に加えて重要なのがビタミンやミネラルです。
ビタミンは体内で合成できない微量栄養素であり、欠乏すると特定の病気が発症します。ミネラルは骨や血液の材料となり、神経や代謝を支える働きを持ちます。さらに、腸内環境の改善や生活習慣病予防に重要な食物繊維も、近年注目を集めています。
| 栄養素 | 主な働き | 代表的な食材 |
|---|---|---|
| ビタミン | 代謝・免疫・臓器機能を支える | 野菜、果物、レバー、卵黄、魚 |
| ミネラル | 骨・歯の形成、血液や神経機能の調整 | 牛乳、海藻、小魚、ナッツ |
| 食物繊維 | 腸内環境の改善、生活習慣病予防 | 野菜、果物、豆類、全粒穀物 |
食事バランスガイドの普及
日本では厚生労働省や農林水産省が「食事バランスガイド」を提示し、1日に必要な食品の目安をイラストで紹介しています。これは現代人が簡単に栄養の過不足を意識できる仕組みで、戦後の栄養改善政策の延長線上にあるものです。
💡外部リンク:「食事バランスガイド」について|厚生労働省
今や「バランスの取れた食事」という言葉は常識のように使われますが、実はこの「常識」が誕生したのは、ほんの百数十年前に過ぎません。
栄養の常識がなかった時代 ― 偏食が招いた病気
私たちは今や当たり前のように「栄養バランス」という言葉を使いますが、こうした知識がなかった時代には、食生活の偏りが深刻な病気を招くことも珍しくありませんでした。

ここでは、科学的な栄養学がまだ確立していなかった時代に、人々を苦しめた代表的な病気を振り返ります。
脚気 ― 白米偏重が生んだ国民病
明治時代、日本陸軍や一般家庭で脚気(かっけ)が流行しました。脚気はビタミンB1の欠乏症で、神経や心臓に障害をもたらし、重症化すると死に至ります。
当時、白米は豊かさの象徴であり、精米技術の普及によって庶民の食卓にも浸透しました。しかし白米はビタミンB1をほとんど含まず、栄養バランスが崩れた結果、多くの人々が脚気に苦しむことになります。
原因となった栄養素:ビタミンB1(チアミン)
糖質をエネルギーに変える代謝に必須。欠乏すると神経や心臓に障害。
解決に役立つ食品:
豚肉、玄米、胚芽米、豆類(大豆・小豆)、ごま、ナッツ類
森鴎外が陸軍軍医総監として「脚気は細菌が原因」と考えたこともあり、栄養素の欠乏という考え方はなかなか浸透しませんでした。やがて海軍で行われた麦飯導入実験や科学的な研究によって、ビタミンの重要性がようやく認識され、脚気対策は進展します。
壊血病 ― 船乗りを苦しめたビタミンC不足
ヨーロッパの大航海時代、長期間の航海に出た船員たちは壊血病(かいけつびょう)に悩まされました。壊血病はビタミンC不足によって慢性的な疲れやだるさといった症状と共に、歯茎や血管が脆くなり、重症化すると死に至る病気です。
当時は果物や野菜を保存する技術がなく、乾パンや塩漬け肉ばかりの食生活が続いた結果、多くの船員が命を落としました。
18世紀、イギリス海軍がライムやレモンを積極的に支給することで壊血病を克服したのは、科学的発見というより経験則の勝利でした。これが後にビタミンCの重要性を示す重要な事例となります。
原因となった栄養素:ビタミンC(アスコルビン酸)
コラーゲン合成や免疫機能維持に必要。欠乏すると血管や歯茎が脆くなる。
解決に役立つ食品:
柑橘類(レモン・みかん)、イチゴ、キウイ、ピーマン、ブロッコリー、キャベツ
現代において、加工食品などの偏食によるビタミンB1の欠乏は「隠れ脚気」と呼ばれて注意が呼び掛けられているのに対し、壊血病はほとんど耳にしなくなりました。
食品添加物とビタミンCなどの栄養に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
ペラグラ ― 貧困と食文化が招いたナイアシン欠乏症
18世紀から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパやアメリカ南部の農村ではペラグラ(Pellagra)が蔓延しました。主食として広く食べられていたトウモロコシには、ナイアシン(ビタミンB3)が体内で利用しにくい形で含まれており(後述)、タンパク質摂取の不足も重なり、皮膚炎・下痢・認知障害を引き起こす「3D病」と呼ばれる症状が現れました。
3D病:皮膚炎(Dermatitis)、下痢(Diarrhea)、認知症(Dementia)
文化や貧困がもたらした偏った食習慣が、地域社会全体を病気に追い込んだ例です。
ペラグラは歴史上の病気というイメージがありますが、アフリカなどトウモロコシが主食でタンパク質摂取が難しい地域では、今も報告例があり、国際的な栄養支援の対象になっています。
原因となった栄養素:ナイアシン(ビタミンB3)
代謝や神経機能に関与。欠乏すると皮膚炎・下痢・認知障害。
解決に役立つ食品:
鶏肉、魚(カツオ・マグロ)、レバー、落花生、きのこ類、卵
補足:トウモロコシの伝来と「伝わらなかった調理法」
トウモロコシ自体にはナイアシン(ビタミンB3)が含まれています。ただし多くは「結合型ナイアシン(ニコチン酸配糖体など)」として存在しており、ヒトの消化管ではほとんど吸収できません。
中南米では古くから石灰水でトウモロコシを煮る「ニスタマリゼーション」という調理法があり、これによってナイアシンが遊離し、吸収されやすくなっていましたが、新大陸からトウモロコシが伝わった際、この調理法は伝わりませんでした。
そのためヨーロッパや米国では栄養価が低いまま主食となり、ナイアシン欠乏症(ペラグラ)が多発しました。
栄養常識の誕生と科学の進歩
こうした病気の流行は、当時の人々が怠けていたからではなく、食事や健康に関する科学的な知識そのものが未発達だったことが原因でした。では、この「栄養の常識」はどのように誕生し、広まっていったのでしょうか。

ここからは、ビタミンの発見をはじめとした科学の進歩と、社会に根づいた食生活の変化をたどります。
ビタミン発見と欠乏症の克服
20世紀初頭、ビタミンという栄養素が次々と発見され、欠乏症の原因が明らかになりました。脚気、壊血病、ペラグラなど、これまで原因不明だった病気の多くが、特定の栄養素の不足によるものであることが科学的に解明されます。
この発見は公衆衛生や食生活の在り方を大きく変えました。
日本人の世界的発見「オリザニン」ービタミン研究の黄金期
20世紀初頭(明治末期~昭和初期)は「ビタミン研究の黄金期」と呼ばれ、わずか数十年で多くの必須栄養素が発見されました。以下はその主な流れです。
| 年代 | 出来事・人物 | 内容・背景 |
|---|---|---|
| 1880年代 | 脚気の原因研究 | 米ぬかに含まれる成分が脚気を防ぐと提唱 |
| 1897年 | エイクマン | 鶏の脚気実験から、精白米に欠けた成分の重要性を発見 |
| 1910年 | 鈴木梅太郎 | 米ぬかから「オリザニン(ビタミンB1)」抽出 |
| 1912年 | カシミール・フンク | 「ビタミン」の命名 「Vital amine(生命に必須なアミン)」 |
| 1913年 | ビタミンA発見 | 成長に不可欠な脂溶性物質として同定 |
| 1920年代 | ビタミンC分離 | 壊血病を防ぐ成分として特定 |
| 1930年代 | ビタミンD研究 | くる病の原因解明・強化食品の普及 |
| 1940年代 | 他のビタミン群次々発見 | B群やKなど大部分が同定され、栄養学体系が整う |
この研究の進展によって、脚気や壊血病など、長年原因不明だった病気が栄養不足によるものだと解明され、食生活は大きく変わっていきました。
鈴木梅太郎は発見した成分を「オリザニン」と名付けましたが、その後、国際的な栄養学で「ビタミン」という概念が普及したため、「ビタミンB1」という呼称に統一されました。今ではオリザニンという名前は歴史的な用語として語られる程度になっています。
明治後期から昭和にかけての食生活革命
日本では明治後期から栄養学の研究が進み、軍や学校での食事改善が始まりました。
昭和期には一日三食のスタイルが定着し、戦後の学校給食制度などを通じて「栄養バランス」の概念が国民に広まりました。現在の栄養ガイドラインや健康教育は、この時代の科学的進歩の上に成り立っています。
栄養学が社会の常識へ
20世紀後半には冷蔵技術や食品加工技術が発展し、栄養の確保はかつてないほど容易になりました。同時に、カロリー計算や栄養バランスを意識した食事管理が当たり前になり、「野菜を食べよう」「栄養バランスの良い食事を」という言葉は生活の基本となっています。
歴史の教訓を、今日の食卓へ
私たちが日々享受している「栄養の常識」は、たった百年余りの研究と試行錯誤の積み重ねで生まれた新しい価値観です。
しかし、便利なサプリメントや加工食品に頼りすぎたり、極端なダイエットを行ったりすれば、歴史が示した脚気やペラグラ、壊血病のような欠乏症に陥る可能性は今も残っています。
飽食の現代だからこそ、偏った食習慣に陥るリスクはむしろ高まっているともいえるでしょう。
科学が教えてくれた栄養の知識を軽視せず、歴史から学び、バランスの取れた食生活を実践することが、健康を守る第一歩なのです。
📚その症状、実は野菜不足が原因かも!?
風邪をひきやすい、肌が荒れる、疲れが取れない…そんな日常の不調は、もしかすると野菜不足からきているのかもしれません。
代表的な症状と、不足しやすい栄養素、対策に役立つ食材をまとめました。
| 症状 | 原因(不足している栄養素) | 摂取した方がいい食材例 |
|---|---|---|
| 歯茎の出血・あざができやすい | ビタミンC不足 | 柑橘類(みかん・レモン)、いちご、ブロッコリー、キャベツ |
| 慢性的な便秘・腸内環境の悪化 | 食物繊維不足 | きのこ、海藻、豆類、玄米、葉物野菜 |
| 疲れやすい・めまい・顔色が悪い | 鉄・葉酸・ビタミンB群不足 | レバー、ほうれん草、卵、豆類 |
| 肌荒れ・乾燥肌・にきび | ビタミンA・ビタミンC・亜鉛不足 | 人参、かぼちゃ、ピーマン、牡蠣 |
| 風邪をひきやすい・免疫力低下 | ビタミンA・C・Eなど抗酸化ビタミン不足 | 緑黄色野菜、柑橘類、ナッツ |
| 骨が弱い・骨折しやすい | ビタミンK不足 | 小松菜、ほうれん草、納豆、ブロッコリー |
| 高血圧・むくみ | カリウム不足 | バナナ、じゃがいも、アボカド、ほうれん草 |
普段あまり野菜を食べない方で、表にあるような症状に心当たりがあるなら、食事の内容を少し見直すだけで体調が改善するかもしれません。
歴史が教えてくれる“食の大切さ”を現代でも活かしていきたいですね。
以下の記事では、「糖質」と「炭水化物」の違いから、栄養学の歴史を振り返っています。
ビタミンの発見によって、病気を予防する新しい分類として「糖質」が生み出されます。