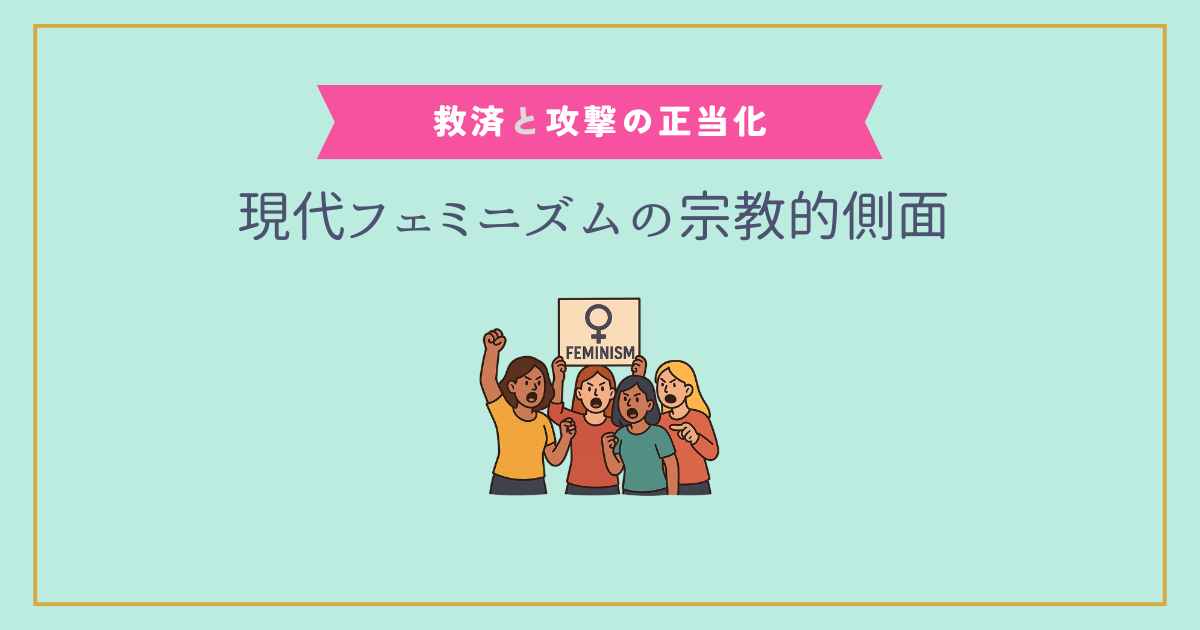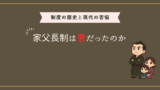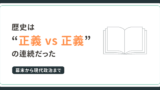現代フェミニズムには「宗教的な側面がある」と言われることがあります。突飛な見方に聞こえるかもしれませんが、よく見ると確かに宗教と似た機能を果たしています。
本稿ではその機能を 救済 と 正当化 という二つの視点から整理し、歴史上の宗教との対比を通じて考えてみます。
救済 ― 孤立する人を包み込む力
フェミニズムも宗教も、人々が社会から孤立したときに「生きる意味」や「居場所」を与えてきました。
ここでは、まず現代のフェミニズムに見られる救済的な役割を確認し、その後に歴史における宗教の事例を振り返ってみましょう。
現代フェミニズムの救済的側面
現代は女性の社会進出が進み、かつてより自分の人生を自由に選択できるようになりました。
しかし依然として、「女性=結婚・出産」と結びつける価値観は社会に深く残っています。キャリアを優先する女性や独身を選ぶ女性は、ときに「不完全」だと見なされたり、孤立感を抱いたりすることもあります。
こうした状況の中で、フェミニズムは「結婚や出産だけが女性の価値ではない」と伝え、孤立しがちな人々に生きる意味を与えてきました。SNSや市民活動を通じた連帯は、共同体の役割を果たし、現代社会における救済の機能を担っています。

フェミニズムによる男性の救済
フェミニズムはしばしば「女性のための思想」と見なされますが、本来は男女を問わず救済の機能を持っています。
男性にとっての大きな重荷は「仕事こそが男の役割」という規範でした。稼ぎ手でなければ一人前ではないという圧力から解放されること、つまり「働かなくても生きていける」という視点が、男性にとっての救済になります。
女性は自由に働いて生き、男性は家族を養う必要もない。そんな各個人が自由に生きられる現代では、「結婚」への意欲は減少し、婚姻数や出産数も年々低下しています。
この背景には、かつて社会を支配していた「家制度=家父長制」の影響も見え隠れします。以下の記事では、その歴史的背景と現代への影響をまとめていますので、興味のある方はぜひご覧ください。
本来のフェミニズムの救済
フェミニズムは本来「ジェンダーによる不平等をなくす」思想です。当たり前だと思ってしまっている固定的なジェンダー役割(Gender Role)そのものを壊し、性別に関係なく個人の自由な人生を肯定します。
その意味で、本来のフェミニズム思想を、救済的側面から整理すると以下のようになります。
- 女性
- 社会規範:女性=結婚・出産
- 救済:結婚しなくても、出産しなくても尊厳がある
- 結果:キャリアを優先する女性や独身を選ぶ女性も、生き方を肯定できる
- 男性
- 社会規範:男性=仕事・稼ぎ手
- 救済:仕事をしなくても尊厳がある
- 結果:仕事から外れた男性も、孤立せず生き方を肯定できる
もっとも、現代のフェミニズムにおいては、男性の救済という観点は十分に語られているとはいえません。
歴史における宗教の救済的側面
同じような「救済の仕組み」は、歴史の中にも存在しました。
現代と違って女性が職業を自由に選べなかった時代、結婚できなかった女性や寡婦は、経済的にも社会的にも弱い立場に置かれました。そんな彼女たちを受け入れ、共同生活や修行を通じて孤立から救ったのが修道院や尼寺だったのです。
ヨーロッパの修道院では、祈りと労働を中心とした共同体生活が営まれ、写本や刺繍、病人の看護などを通じて役割を果たしました。日本や中国の尼寺でも、読経や写経、日々の作務を通じて修行に励み、地域社会に祈祷や供養を提供しました。

修道院や尼寺は、単なる避難所ではなく「祈り・労働・学び・奉仕」を通じて女性に新しい意味を与え、孤立から救済する場だったのです。
宗教による男性の救済
宗教は女性だけでなく、男性にも独自の救済のかたちを与えてきました。
修道院に入った男性は、日々の祈りと労働に加えて、神学や哲学の学習、写本制作といった知的営みに従事しました。これは世俗社会の競争や責任から解放され、学問と信仰に生きることで救済を得る仕組みでした。
同時に、宗教は男性の「死」にも意味を与えました。十字軍の騎士たちは、聖地を奪回するための戦いを「神への奉仕」と位置づけられ、戦死は「殉教」として救済に結びつけられました。日本でも武士は、戦場での死を「忠義」と結びつけ、宗教的な意味づけを伴って美化しました。出家によって俗世を離れることもまた、一つの救済の道とされていました。
女性が奉仕や修行によって「生きること」を救済されたのに対し、男性は戦いや学問を通じて「生きること」だけでなく「死ぬこと」までも救済の対象となったのです。
攻撃の正当化 ― 正義が生む過激さ
一方で、救済と同じくらい「正当化」の機能も宗教にはつきまといます。自分が正義の側にいると信じたとき、人は攻撃的になりやすいのです。
フェミニズムの正当化的側面
本来フェミニズムは弱者を救う理念です。
しかし一部では、「フェミニストだから他者を攻撃してよい」という免罪符のように使われることがあります。自由や平等、多様性など「守るべき価値」が掲げられる場面でも同様で、「自分は正しい」という確信が攻撃を正当化してしまうのです。
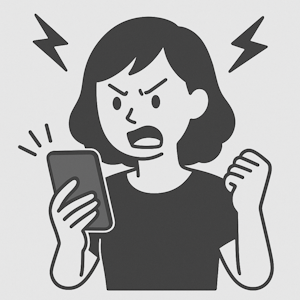
この現象は心理学的には モラル・ライセンシング(善行が悪行の免罪符になる現象)や 道徳的脱却(バンデューラ) として研究されており、「正義の名の下に攻撃性が増す」という傾向は学問的にも裏付けられています。
捕捉:学術的理論
- モラル・ライセンシング:善行によって自分に“免罪符”を与えてしまう心理
- 道徳的脱却(バンデューラ):行為を高尚な目的と結びつけることで、罪悪感を麻痺させる。
- 社会的アイデンティティ理論:自分の集団が「正義の側」だと信じると、外集団への攻撃性が増す。
宗教の正当化的側面(歴史例)
歴史を振り返ると、宗教はしばしば「正義の名の下に」攻撃を正当化してきました。
十字軍では、聖地を奪回するという大義のために戦争が正当化され、殺戮に加わった者には「罪の赦し」が与えられると説かれました。これは信仰が人々を勇気づけただけでなく、暴力の免罪符ともなったのです。
魔女狩りや異端審問も同じ構造でした。異端者を排除することは「共同体を守る正義」とされ、拷問や火刑といった残虐な行為が正当化されました。
救済を生かし、正当化の罠を避ける
救済と正当化は常に表裏一体でした。宗教は人を救うと同時に、暴力を正当化する免罪符にもなり得ました。現代フェミニズムもまた、救済の力を持ちながら、正当化の罠に陥る危うさを抱えています。
大切なのは、救済の理念を生かしつつ、正当化の名の下で攻撃に走らないことです。
歴史の教訓に学び、建設的な議論や制度改革を通じてこそ、フェミニズムは本来の力を発揮できるのではないでしょうか。
関連記事:正義の反対も正義
戦争や紛争は、必ずしも「正義 vs 悪」という単純な構図ではありません。
歴史を振り返れば、正義の名のもとに相手を攻撃し、争いが始まった事例は数多く存在します。
以下の記事では、なぜ正義同士が衝突するのかを解き明かし、幕末から現代政治に至るまでの具体的な事例を紹介しています。「正義の反対も正義」という構造を理解することは、現代の対立や分断を考える上でも大きなヒントになるでしょう。