幕末と現代、日本人はいつの時代も政府への不満を抱いてきました。
しかし幕末には批判が「行動」へと結びつき、現代では言論にとどまります。
本記事では、「陽明学」を中心に幕末と現代を比較して、その違いについて考えてみます。
幕末と現代に共通する「政府批判」
現代と幕末、日本人は権力に対して常に不満や批判を抱いてきました。その点では両者は驚くほど似ています。
幕末と現代の政治批判を整理してみます。
以下のように、時代は違えど似た構図が浮かび上がります。
- 幕末
- 幕府の腐敗
- 飢饉
- 異国船来航
- 現代
- 政治とカネの問題
- 社会格差の増大、貧困率の拡大
- 国際情勢への不安や、移民・外国人をめぐる社会的議論
幕末の政治状況
幕末の日本は、長期にわたる飢饉や財政難、幕府の腐敗に苦しんでいました。
さらに黒船来航に象徴されるように、異国からの圧力も強まり、庶民や下級武士の不満は臨界点に近づいていきます。こうした不安の中から「尊王攘夷」「倒幕」といったスローガンが広がり、幕府批判が一気に高まりました。
現代の政治状況
現代日本もまた、政治とカネの問題、社会格差、国際情勢への不安などが国民の不満を強めています。SNSやメディアを通じて政府批判が広く共有される状況は、幕末の世相とどこか重なって見えます。
ただし大きく異なるのは、その不満が「言論」にとどまっている点です。
行動に結びついた幕末、言論に留まる現代
両者の違いは「批判が行動に発展するか、言論に留まるか」にあります。

幕末における陽明学の役割
幕末の志士たちの背中を押したのが、陽明学でした。
「知行合一」――知って正しいとわかっていることを、実行しなければ本当の知ではない。こうした思想は、批判するだけでは自らが不誠実だと感じさせ、行動を義務とする圧力となりました。
乱を起こしたことで有名な「大塩平八郎」も、陽明学を学び行動に移した人物の一人です。
さらに水戸学と結びつくことで「天誅」「尊王攘夷」といったスローガンが生まれ、過激な行動が正当化されていきます。井伊直弼の暗殺(桜田門外の変)や各地の尊王攘夷運動は、この思想的触媒なしには語れません。
現代に思想的触媒は存在しない
一方の現代には、陽明学のように「知識を行動に直結させる思想」が社会に共有されていません。むしろ「批判は言論で行うもの」という制度的な合意が広くあり、社会制度もその方向で整えられています。そのため、批判や不満はSNSやメディアでの発信にとどまり、大規模な実行行為へは発展しにくいのです。
もっとも、幕末における暴力も制度的に認められていたわけではありません。
桜田門外の変をはじめ、幕府に刃を向ける行為は法的には犯罪として扱われ、実際に処罰も行われました。
しかし、「尊王」や「義挙」といった思想的枠組みの中では、それが正義とみなされ、称賛や同情を集める場合も少なくありませんでした。
つまり、現代と幕末の違いは「暴力が合法かどうか」ではなく、思想がそれを正当化したかどうかにあります。現代では批判を言論に収めることが社会的合意となっているため、批判のエネルギーが暴力に転じにくいのです。
陽明学を知らない庶民の動きとその影響
幕末に声を上げたのは、必ずしも陽明学を学んだ志士だけではありません。

思想を知らない庶民もまた、自らの生活を守るために動き、その行動は志士たちに大きな影響を与えました。
生活が最優先 – 陽明学を知らない庶民の動き
幕末の庶民は、尊王攘夷や陽明学といった思想に直接触れることはありませんでした。彼らにとって最も切実だったのは、飢饉や重税、そして米価の高騰です。こうした経済的不安から各地で一揆や打ちこわしが頻発しました。
これらは「幕府批判」というよりも、あくまで「生活を守るための抗議」でした。
現代においては、生活や社会への不満はデモという形で表れることがあります。
庶民の動きを利用する志士
庶民の抗議行動は、志士たちにとって政治行動を正当化する格好の材料となりました。幕末の志士は、一揆や打ちこわしを「幕府の悪政への反発」と結びつけ、尊王攘夷運動へと利用していきます。
現代では「デモは意味がない」と冷笑されることがありますが、歴史的に見れば庶民の動きは志を持つ人々の後押しとなり、政治を動かす力を持ち得るのです。
批判から暴力への変化 – 言論弾圧
もともと志士たちも批判をまずは言論で行っていました。
ところが安政の大獄のように発言の場が奪われると、批判は暴力へと転じていきます。
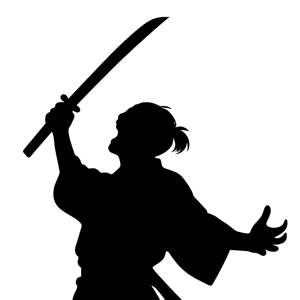
この構図は現代にも通じます。SNS規制や表現の制限は、表現の自由を守るどころか逆に不満を過激化させる危険があります。歴史に学ぶならば、「言論を封じること」は最も危うい施策であると整理できるでしょう。
言論弾圧で投獄された「吉田松陰」
安政の大獄では、尊王攘夷を唱える多くの志士が処罰されました。吉田松陰もその一人です。幕政を批判するだけでなく、老中暗殺を計画した嫌疑をかけられ、江戸伝馬町の牢に送られました。
松陰はそこで思想を曲げることなく、1859年に刑死します。彼の最期は、言論を封じられた者が「行動するしかない」と追い込まれた幕末の空気を象徴しているといえるでしょう。
現代の陽明学
以下に、今回の記事の要点をまとめます。
- 幕末と現代は、ともに政府批判が盛んという共通点を持つ
- 幕末は陽明学が思想的触媒となり、批判が行動に直結した
- 現代にはそうした思想がなく、批判は言論に収まっている
陽明学は幕末に人々を行動へと駆り立てた強力な思想でしたが、その危うさゆえに明治以降は国家的に敬遠され、現代ではほとんど忘れ去られています。
現代社会に生きる私たちは、陽明学のように「行動そのもの」を再び正当化するのではなく、「知識を日常や社会にどう生かすか」という形で応用していくことが求められています。
現代にも通じる ― 陽明学がくれる勇気
陽明学は、幕末には過激な行動を促す思想として恐れられる一面がありました。しかし本来は、知識を実践に結びつける健全な学問です。
現代でも、仕事や生活の中で「知っていながら行動しない」場面は少なくありません。陽明学の実践的な姿勢は、そうしたときに背中を押し、勇気を与えてくれる学びになるでしょう。
本サイトでは、江戸時代の学問や思想を紹介・解説した記事が多くあります。
以下の特集では、幕末の有名な「尊王攘夷思想」がどのように形作られたのか、その由来を学べる記事を集めていますので、興味のある方は是非ご覧ください。


-160x90.png)
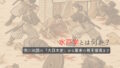
とする神道2-120x68.png)