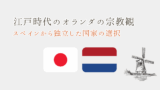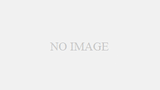江戸時代、日本と唯一交易を続けたオランダ。
その背景には、宗教改革を経て「布教しない国」となった新生国家の姿がありました。
ルターとカルヴァンの時代から、独立戦争期までの流れを年表で整理します。
年表:オランダの独立戦争と日本の歴史
凡例:
赤色背景 ー 「オランダ独立」関連
黄色背景 ー 「日蘭関係・リーフデ号」関連
| 年 | オランダ側 | 日本側 |
|---|---|---|
| 1517 | ルターが「95か条の論題」を発表し、宗教改革が始まる。 カトリック教会への批判がヨーロッパ各地に拡大。 | 戦国時代中期。細川晴元・三好長慶らが台頭。 応仁の乱(1467年)後の混乱が続く。 |
| 1521 | ルター、ヴォルムス帝国議会で教皇庁に反論し破門。 宗教改革が公的な対立へ。 | 大内義隆・毛利元就ら地方大名が勢力を拡大。 戦国の群雄割拠が進む。 |
| 1536頃 | ジャン・カルヴァンが『キリスト教綱要』を出版。 カルヴァン派の思想が広がり始める。 | 今川義元が台頭、武田信玄・上杉謙信らが活躍。 日本は鉄砲伝来(1543年)を目前に。 |
| 1541–1549 | カルヴァンがジュネーヴで宗教改革を実践、 神政的都市国家を形成。 | 1543年、種子島に鉄砲伝来。 1549年、フランシスコ・ザビエル来日。 キリスト教布教が始まる。 |
| 1550年代 | カルヴァン派がネーデルラント(オランダ)に浸透。 都市商人の間で支持を集める。 | ポルトガルとの南蛮貿易が盛んになり、 長崎などが形成され始める。 |
| 1566 | 聖像破壊運動(Beeldenstorm)。 プロテスタント市民がカトリック教会を襲撃。 | 足利義昭が還俗し、織田信長に接近。 戦国の終焉へ向かう動き。 |
| 1567–1568 | フェリペ2世が異端審問を強化、アルバ公を派遣。 オラニエ公ウィレム(ウィリアム1世)が蜂起し、 八十年戦争(オランダ独立戦争)が始まる。 | 1568年、織田信長が上洛。 足利義昭を奉じて京都入り、 天下統一の第一歩を踏み出す。 |
| 1579 | オランダ北部7州がユトレヒト同盟を結成。 事実上の独立国家の枠組みができる。 | 信長、安土城を築き権威を確立。 九州では島津氏が台頭。 |
| 1581 | オランダ共和国がスペイン王への忠誠を放棄 (君主放棄宣言)。事実上の独立を宣言。 | 信長、京都で「御馬揃え」を挙行。天下統一目前。 翌年、本能寺の変(1582年)。 |
| 1588 | イギリスがスペイン無敵艦隊を撃破。 オランダ独立戦争に有利な情勢へ。 | 豊臣秀吉が天下統一を進める。 刀狩令を発布し、武士と農民の分離を進める。 |
| 1594 | オランダ軍、グローニンゲン包囲戦で勝利。 独立勢力が北部を掌握。 | 秀吉が朝鮮出兵を計画。 国内統治を確立しつつある時期。 |
| 1598 | オランダから東インド遠征艦隊が出航 (リーフデ号を含む)。独立戦争継続中。 | 豊臣秀吉が死去。 徳川家康が勢力を拡大し、政権掌握へ。 |
| 1600 | リーフデ号が日本・豊後(大分)に漂着。 家康が乗組員を保護し、日蘭関係の始まりとなる。 | 関ヶ原の戦い。 家康が勝利し、江戸幕府成立へ向かう。 |
| 1602 | オランダ東インド会社(VOC)が設立。 国策としてアジア貿易を推進。 | 家康、海外貿易を奨励。 南蛮商人や宣教師との関係を維持。 |
| 1609 | オランダ船リーフデ号の功績を背景に、 平戸にオランダ商館を設置。 | 家康がオランダと正式に交易を許可。 日蘭関係が制度化される。 |
| 1621 | オランダ、西インド会社を設立。 世界規模の貿易・植民活動を展開。 | 秀忠の時代、幕府がキリスト教禁制を強化。 国内統制を進める。 |
| 1637–1638 | 島原の乱の時期。 オランダは幕府の要請で砲撃支援を行い、交易を継続。 | 島原の乱が勃発。 幕府が鎮圧し、キリスト教の完全禁止を確立。 |
| 1641 | オランダ商館、平戸から出島へ移転。 鎖国体制下で唯一の西洋貿易国となる。 | 出島が開設され、 オランダのみが長崎での貿易を許可される。 |
| 1648 | ウェストファリア条約締結。 八十年戦争終結、オランダの独立が正式承認される。 | 江戸幕府体制が安定。 鎖国体制の基盤が固まる。 |
関連記事:江戸時代のオランダの宗教観 ― スペインから独立した国家の選択
この年表に関連した出来事や動きについては、以下の記事で詳しく解説しています。