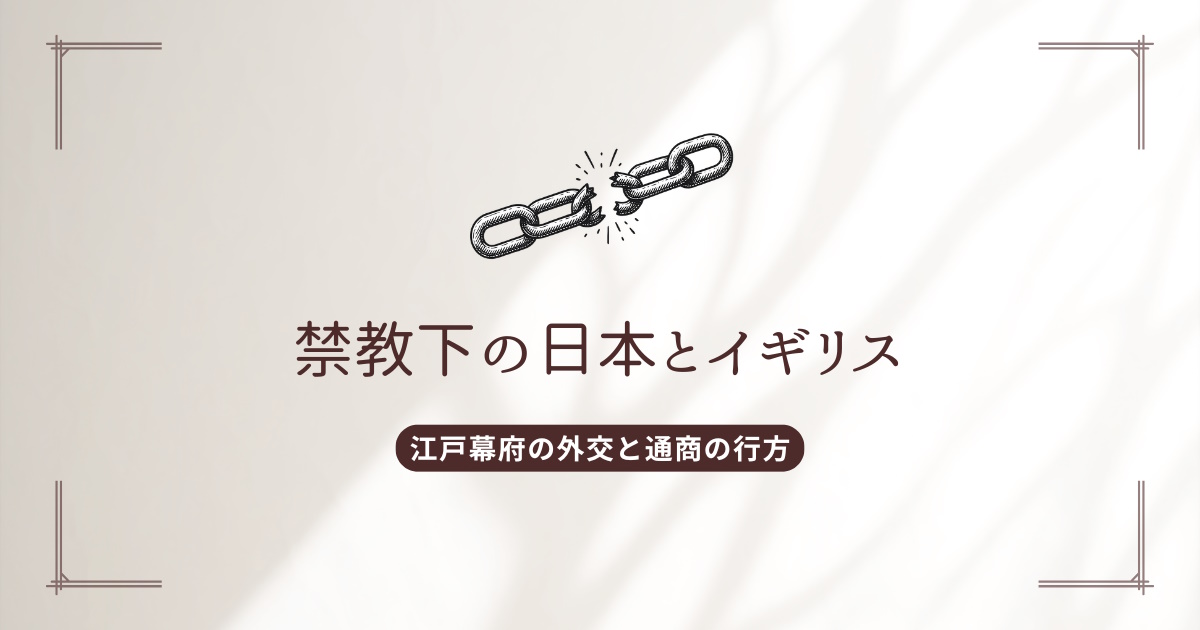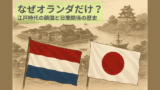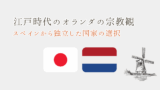💡この記事は、「日本のキリスト教禁教史特集」の一部です。
16世紀末から17世紀初頭、日本はヨーロッパ諸国との接触を通して国際社会に顔を出し始めました。しかし、キリスト教禁教という政策の下で、その関係は複雑な経緯をたどります。
本記事では、三浦按針に始まるイギリスとの交流から、平戸商館の撤退、そしてペリー来航以前の通商再開拒否までをたどり、宗教と外交の狭間にあった幕府の姿を見ていきます。
リーフデ号漂着とイギリスとの出会い
16世紀末、日本とイギリスの関係は一隻の漂着船から始まりました。
この偶然の出会いが、後に幕府とヨーロッパ諸国との外交のあり方を方向づけることになります。
リーフデ号の漂着と三浦按針の登場
1600年、オランダ船リーフデ号が豊後(現在の大分県)に漂着しました。
その船に乗っていたのが、イギリス人ウィリアム・アダムス(三浦按針)とオランダ人ヤン・ヨーステンです。2人は捕らえられ、家康のもとに送られましたが、家康は彼らの知識と見識を高く評価し、顧問として召し抱えます。

アダムスは航海術・造船技術・国際情勢に通じた人物であり、家康にとって初めての「実務的な西洋人」でした。
彼の進言により、日本はオランダやイギリスとの交易を模索し始めることになります。
オランダとイギリスに出された通商許可
アダムスの働きかけにより、1609年にオランダが、1613年にはイギリスが通商を正式に許可されます。
イギリス東インド会社は平戸に商館を設立し、絹や銀を中心に貿易を開始しました。
この時期、日本はまだキリスト教を全面的に禁じてはいませんでしたが、スペイン・ポルトガル勢力への警戒心は高まっていました。
オランダとイギリスはいずれもプロテスタント国家であり、カトリック宣教師を伴わなかったことから、幕府は比較的安心して通商を認めたと考えられます。
キリスト教政策が寛容から禁止へと変わった背景については以下の記事で紹介しています。
本記事と切り口は違いますが、三浦按針やリーフデ号の件についても触れています。
💡関連記事:江戸幕府初期のキリスト教禁止の背景 ― 家康とプロテスタント
禁教政策と通商のはざまで
江戸幕府がキリスト教を禁止する方針を固めたのは、1600年代初頭。
このときイギリスはすでに通商を許されており、幕府は「宗教を禁じながら交易を維持する」という矛盾した難題に直面します。
キリスト教禁止令と外交の両立
1612年、家康は幕府直轄地でキリスト教を禁じ、翌1614年には全国に拡大しました。
布教活動を禁じ、宣教師を国外追放とする方針です。
しかし、経済的利益を考慮し、オランダとイギリスには通商を継続させました。
幕府が重視したのは「宗教を持ち込まないこと」でした。
その点で、イギリス商館は宣教師を帯同せず、交易目的に徹していたため、オランダ同様の扱いを受けます。
オランダ・イギリスにも布教を禁ずる江戸幕府
家康死後の1616年に、秀忠は外国人管理を強化する命令を出しています。そこでは「イギリス人・オランダ人に対しても布教を禁ずる」旨が記されています。
“We were strictly forbidden to perform any religious service, to sing psalms or to read the Bible.”
「我々は礼拝を行うこと、詩篇を歌うこと、聖書を読むことを厳しく禁じられていた。」
― 日本誌(フランソワ・カロン著, 1649年)元出島商館長
イギリス東インド会社の構成員の中には信仰心の強い者も多く、商館内で祈祷や礼拝を行うこともあったと伝えられます。実際に事件化はしなかったものの、宗教を持ち込む“気配”そのものは、外交上の緊張を生んでいました。
イギリス国内の複雑な宗教事情
イギリスがローマ教皇と決別し、独自の「イングランド国教会(プロテスタント)」を立ち上げたのは16世紀のことでした。日本でいえば戦国時代の終盤、家康の時代から見ればわずか60〜70年前の出来事にすぎません。
| 西暦 | イギリス側の出来事 | 日本側の出来事 |
|---|---|---|
| 1534年 | ヘンリー8世がローマ教皇と決別し、 イングランド国教会(英国国教会)を創設 | 室町時代末期、 戦国大名が群雄割拠 |
| 1558年 | エリザベス1世が即位し、国教会体制を確立 | 織田信長が台頭 |
| 1600年 | リーフデ号が漂着、日本が初めてイギリス人と接触 | 関ヶ原の戦い、 江戸幕府の成立直前 |
有名な“ブラッディ・メアリー”ことメアリー1世によるプロテスタントの弾圧は、父ヘンリー8世の宗教改革に対する一時的な反動でした。

(血まみれメアリー)
その後、エリザベス1世の時代に国教会体制が再び確立しますが、国内ではカトリック、国教徒、ピューリタン(清教徒)が対立し、社会は不安定なままでした。
つまり、イギリスは「キリスト教国」でありながら、内部に複数の宗派を抱える複雑な国家だったのです。この宗教的背景は、彼らの外交姿勢にも影響を与えました。
補足:三浦按針の信仰
按針自身はプロテスタント信徒でしたが、日本では信仰を表に出すことを避け、政治的中立を保ちました。
その慎重さこそが、幕府の信頼を得て顧問として長く仕えられた理由の一つとされています。
イギリス商館の撤退と幕府の反応
通商を許されたイギリスでしたが、その関係は長くは続きません。
経済上の理由と、外交的摩擦が重なり、やがて日本を離れることになります。
採算の合わない貿易
イギリス東インド会社は、主に中国やインドとの貿易を中心に展開していました。
日本との交易は距離も長く、利益も薄く、オランダとの競争も激しかったため、採算が合わなかったのです。1623年、本国は日本商館の閉鎖を決定し、商館長リチャード・コックスが平戸を離れました。
スパイス諸島での「アンボイナ事件(1623年)」によってオランダとの関係が急激に悪化したことも、日本市場撤退の一因とされています。
アンボイナ事件については、以下の記事で詳しく紹介しています。
💡関連記事:アンボイナ事件から見る日蘭関係 ― 宗教不信と貿易独占
オランダだけになった西洋との交易
幕府はイギリス撤退を特に問題視しませんでした。
むしろ宗教的な懸念が一つ減ったと受け止めた可能性もあります。
結果として、オランダのみが残り、「唯一の西洋窓口」という体制が固まりました。
オランダと日本の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。
江戸時代の蘭学や、オランダが不平等条約(安政の五か国条約)の相手国だったことなど、その後の関係についても詳しく知りたい方は、是非こちらもご覧ください。
禁教下の日本とイギリスの交渉 ― ペリー来航以前の打診
17世紀後半、世界の海洋貿易はさらに広がり、イギリスも再び極東に目を向けます。
しかし、島原の乱後の日本では、その門はすでに固く閉ざされていました。
チャールズ2世の通商再開要請と江戸幕府の拒否
1673年、イギリス国王チャールズ2世は日本との通商再開を打診しました。書状は、バタヴィア(オランダ東インド会社の拠点)を経由し、長崎奉行を通じて幕府に届けられました。
しかし、その要請文には「キリスト教徒を乗せない」といった条件が明記されておらず、幕府はこれを理由に拒否します。
幕府は正式な返書を出さず、事実上の黙殺によって拒絶の意思を示しました。
これは、宗教が外交上の障壁として公式に作用した、珍しい事例です。
このとき幕府は、宗教を理由とする拒絶を「外交上の正当化」に使っており、禁教政策がすでに“国是”として定着していたことがうかがえます。
貿易を独占していたオランダの思惑
一次史料として残る「幕府への報告」文には、以下のように記されています。
「イギリス国はキリシタンを多く含むゆえ、許すべからず」
この文面は、明らかにオランダ側の評価を含んでいます。
確定的な史料は残っていませんが、日本に伝えられた文書は「英語の原本をオランダ語に翻訳した上で提出された」と考えられています。
| 段階 | 言語 | 状況 |
|---|---|---|
| チャールズ2世の原本 | 英語 | 英国王名義の親書として作成 |
| バタヴィアでの仲介 | オランダ語に翻訳 | オランダ商館が翻訳・転送 |
| 幕府への提出 | オランダ語 | 唯一受理可能なヨーロッパ言語 |
| 翻訳・報告 | 日本語(奉行・評定所向け) | オランダ語から日本語訳 |
「キリシタン多し」という判断は、仲介者の主観的コメントと考えるのが自然です。
当時、日本との貿易を独占していたオランダが、イギリス再進出に慎重な姿勢を見せていたことから、幕府への報告内容に「宗教的懸念」が強調された可能性も指摘されています。
禁教史で見えてくる「宗教と国家」
イギリスとの関係史は、江戸幕府が宗教をどのように外交に組み込んでいたかを示す貴重な実例です。
寛容と実利の国としての「オランダ」
オランダはスペインの支配から独立したプロテスタント国家ですが、その後は宗教も含めて寛容主義を国是としてきました。
現代のオランダは、ヨーロッパでもっとも宗教離れが進んだ国の一つで、2020年代初頭の調査では、実に60%以上の人が「無宗教」と回答しています。
江戸時代の日本が通商相手として「宗教に中立な国」としてオランダを評価した背景には、こうした実利的で内省的な宗教観があったともいえるでしょう。
関連記事:江戸時代のオランダの宗教観
以下の記事では、江戸時代頃のオランダの宗教観を、歴史的背景を踏まえて解説しています。
カトリック勢力によって苛烈な宗教弾圧を経験した人々は、独立のために立ち上がり、オランダという国の建国を宣言します。日本と通商を始めた頃のオランダは、独立戦争の真っただ中でした。
関連記事:江戸時代のオランダで起きた「チューリップバブル」
貿易によって莫大な利益を得たことで、江戸時代頃のオランダ経済は活況を迎えます。
富裕層の間では先物取引などの投機が広まり、
その結果、人類史上初の「バブル」が生まれました。
当時のオランダ社会を背景に、この“チューリップバブル”を日本の江戸時代と対比してまとめた記事もありますので、ぜひあわせてご覧ください。
💡関連記事:江戸時代に揺れた「オランダ黄金期」 ― チューリップ・バブル
宗教に揺れていた「イギリス」
同じプロテスタント国であっても、イギリスはオランダとは宗派も異なり、また宗教的に複雑な状況にもありました。
江戸幕府に通商再開を申し出てきた「チャールズ2世」は、母親(フランスのヘンリエッタ・マリア)がカトリック系だったこともあり、本人も後にカトリックに改宗しています。
| 世紀 | 王・政権 | 宗派 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 16世紀前半 | ヘンリー8世 | 国教会(独立) | 政治的宗教改革 |
| 16世紀後半 | エリザベス1世 | プロテスタント | 国教会体制確立 |
| 17世紀前半 | チャールズ1世 | カトリック寄り | 議会と対立、処刑 |
| 17世紀中盤 | クロムウェル | ピューリタン (プロテスタント) | 王政廃止、共和制 |
| 17世紀後半 | チャールズ2世 | 表向き国教会、 内心カトリック | 王政復古・親仏政策 |
| 17世紀末 | ジェームズ2世 → 名誉革命 | カトリック → プロテスタント | 王位継承制限、宗教安定へ |
江戸幕府による、イギリスとの通商再開拒否は、こういった「宗教的不安定」を感じ取ったものだったのかもしれません。
イギリスと日本における「宗教と国家」
現代のイギリスでは、王位継承法によって「イギリス国王(君主)はプロテスタントでなければならない」と明確に定められています。
国王は、カトリック信仰もカトリックへの改宗も認められません。
2013年改正で「カトリックとの結婚」は容認されましたが、「国王がイングランド国教会の首長を兼ねる」という伝統は今も続いています。
イギリス国王がプロテスタント信仰を求められる点は、日本の天皇が神道儀式を継承している構図にどこか似ています。いずれも、宗教そのものよりも「国家の伝統と統合の象徴」として宗教的要素を担っている存在です。
ただし、イギリスの場合は制度として国教会を持つのに対し、日本では宗教と国家が法的に分離されており、文化的儀礼として継承されているという違いがあります。
江戸時代の日本とイギリス
イギリスとの通商再開を断った歴史は、日本のキリスト教禁教が実際の外交判断に影響した、重要な出来事です。
しかし、ペリー来航後に現れたイギリスは、もはや対等な相手ではありませんでした。
軍事力を背景に不平等な条約を迫り、薩英戦争や下関戦争では、ついに日本と武力衝突します。
江戸時代の日本は、いったいどうするべきだったのでしょうか。
関連記事:列強国との不平等条約
日本は江戸時代に、アメリカ・ロシア・イギリス・フランス、そしてオランダと不平等条約を締結します。(安政の五か国条約)
その後明治時代になると、日本は西洋の各国と次々に「不平等条約」を締結していきます。
以下の記事でその背景や相手国などについて詳しくまとめていますので、関心のある方は是非ご覧ください。
本記事は、日本のキリスト教禁教史に関する以下特集の一部です。
日本の禁教史の目的や実態を知ることは、歴史の理解を深めると共に、現代の社会問題などを考えるヒントになることもあります。是非あわせてご覧ください。