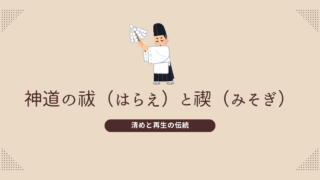💡この記事は、「日本のキリスト教禁教史特集」の一部です。
神の教えを信じることは、どの時代にも個人の自由のはずです。しかし、17世紀初頭の日本では、それが“国家への反逆”と見なされる瞬間がありました。
「人の法」より「神の法」に従う宗教と対峙した江戸幕府。
元和・長崎の大殉教やマカオ使節団事件を通して、宗教と国家の秩序を考えます。
日本の法と神の法 ― 江戸時代の危機感
日本社会では、主君や幕府への忠義が最上の徳とされていました。
しかし、キリスト教徒にとっての最上の存在は「神」でした。
幕府の命令(日本の法)と神の教え(神の法)が矛盾した場合、どちらを優先するのか――
それは幕府にとって根本的な統治不安要因だったのです。
幕府よりも神を優先 ― 法令を守らない宣教師たち
スペインやポルトガルから日本に来ていたキリスト教の宣教師たちは、幕府が直轄地での布教を禁止する法令を出した後も、その禁教令に従わず布教を続けました。彼らは表向き「使節の随行員」や「通商関係者」を装いながら、各地で信者を増やしていったのです。
キリシタン関係者の摘発や国外追放命令が繰り返されても、宣教師たちは巧みに潜伏し、活動をやめることはありませんでした。
宣教師たちの布教の目的
当時のポルトガル・スペインはアジア各地で植民地化を進めており、「布教は通商の前段階、通商は支配の前段階」とされていました。日本もまた、その“布教外交”の標的となっていたのです。
国民までも「神の法」に従う危機感
家康や秀忠は、キリスト教を単なる宗教ではなく「政治思想」として扱いました。
信者の忠誠心が神に向く限り、領主や幕府の支配が揺らぐと考えたのです。
その結果、信仰の問題は「治安維持」や「国防」の名の下で処罰対象となっていきました。
信仰の自由という概念の未成熟
当時の日本には「信仰の自由」という考え方は存在しませんでした。
宗教は共同体秩序の一部であり、個人の信念よりも「国家の安定」が優先されていたのです。
江戸幕府のキリスト教禁教政策は、教義そのものを否定するものではありません。
その出発点は、外交上の懸念――すなわち国防上の判断にありました。
しかし、「日本の法」よりも「神の法」を優先する当時のキリスト教徒は、幕府にとって国家統治を揺るがす「危険な存在」として認識されるようになっていきます。
このキリスト教徒には「日本人の信徒」も含まれます。
江戸幕府統治下の日本では、キリスト教信仰は次第に“政治犯罪”とみなされるようになり、やがて強硬な弾圧へと発展していくのです。
元和大殉教 ― 京都での見せしめ
1619年、京都で起きた「元和の大殉教(げんなのだいじゅんきょう)」は、信仰弾圧が都市へ広がった象徴的事件でした。
日本人の信徒52人の火刑
京都・鴨川の河原で、男女や子どもを含む52人のキリシタンが火刑に処されました。(一部は十字架刑、または槍で刺されたとも言われます)
処刑された52名は全員日本人キリシタンです。
当時、宣教師たちはすでに多くが国外追放となっており、日本国内で活動していたのは主に「潜伏宣教師」や「信徒指導者(日本人司祭・修道士)」でした。
当時の宣教師の報告書(ヨーロッパに送られた書簡)では、処刑の様子は以下のように記されています。
「彼らは火刑の中でも祈りをやめず、炎の中で賛美歌を歌い続けた」
「子どもも母も、互いを励ましあいながら、最後まで信仰を棄てなかった」
この姿は、見物に集まった人々の間にも衝撃を与えました。
「死をも恐れぬ信仰心」は、人々の心に畏怖と同時に疑問を残したといわれています。
殉教の時代 ― 頻発した処刑
元和の大殉教は、“頂点のひとつ”に過ぎません。
1614年の全国禁教令(秀忠)を境に、宣教師の潜伏と信徒の摘発が繰り返され、元和年間(1615〜1624)は「殉教の時代」と呼ばれるほど、処刑が頻発しました。
幕府は、宣教師追放だけでなく、「神の法を優先する信徒思想」を根絶するために、約10年にわたって京都・長崎・江戸・大坂などで処刑を続けています。
全国禁教令の経緯については、以下の記事で詳しく解説しています。
💡関連記事:江戸幕府初期のキリスト教禁止の背景 ― 家康とプロテスタント
幕府が狙った「示威」
この事件は単なる刑罰ではなく、明確な示威行為でした。
「どれほど信仰が篤くとも、国家の命令に背けばこうなる」という見せしめであり、宗教の問題が完全に“法と秩序”の領域に引き込まれた瞬間でもありました。
幕府は、苛烈な刑罰の執行を通じて、「宗教」よりも「国家」、「神の法」よりも「人の法」が上位に立つことを、社会に対して明確に示したのです。
河原での火刑の意味
京都では罪人の処刑が河原で行われるのが通例でした。
これは「穢れを市中に持ち込まない」ための宗教的配慮でもあり、皮肉にも、宗教を理由に処刑された信者たちが、宗教的儀礼の中で葬られたのです。
神道の死の穢れ(けがれ)と禊(みそぎ)について関心のある方は、以下の記事をご覧ください。
長崎大殉教 ― 宣教師処刑から国交断絶へ
3年後の1622年、長崎で宣教師と信徒55人が公開処刑されます。
この「長崎の大殉教」は、幕府がキリスト教を“国外勢力の延長”と見なしたことを明確に示す事件でした。
宣教師と信徒の処刑
長崎・西坂の丘で、火刑・斬首・磔刑が同時に行われました。処刑された中にはスペインやポルトガル出身の宣教師も含まれました。
宣教師たちは最後まで祈りを止めず、日本人信徒も静かに信仰を貫いたと伝えられます。
その場には多くの見物人が集まり、「異教徒処刑」は政治的イベントのように演出されました。
幕府はこの公開処刑を通じて、「外国宗教は日本に必要ない」という姿勢を内外に示しました。
西坂の丘の記憶
西坂の丘は、かつて1597年(江戸幕府以前)に日本二十六聖人が処刑された場所でもあります。
- 命令者:豊臣秀吉
- 年月日:1597年(慶長2年)2月5日
- 場所:長崎・西坂の丘(のちの「長崎の殉教地」)
- 処刑者:カトリック信者26名(宣教師6名、日本人信徒20名)
1862年に、ローマ教皇ピウス9世が26人を「聖人(Saints)」に列聖。 - 処刑方法:磔刑(十字架にかけた上で槍で突き刺す)
大阪・京都・堺などで捕らえられ、見せしめのために京都から長崎まで約1000kmを徒歩で連行されました。
やがてここはカトリック教徒の聖地として記念碑が建てられ、信仰と迫害の歴史を語り継ぐ象徴の地となりました。
西坂の丘や二十六聖人の殉教については、以下の記事で詳しく解説しています。
💡関連記事:伴天連追放令の実態 ― サン・フェリペ号事件と二十六聖人の殉教
スペインとの国交断絶と追放令
1623年、幕府はスペイン人の国外追放を正式に決定し、外交関係を断絶しました。
翌1624年には、その方針を徹底するためにスペイン船の来航を禁止。
これにより、日本とスペインの関係は完全に途絶することになります。
ポルトガルはスペインに併合されており、独自の外交権がありませんでした。
ポルトガルはスペイン人追放令後も細々と日本との交易を継続していましたが、島原の乱後に幕府の方針は厳しくなり、家光期の1639年に別途「ポルトガル人追放令」が発布されます。
| 用語 | 年代 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スペイン人追放令(通称) | 1623年 | スペイン人を国外追放、渡来禁止を決定 | 史料上は正式名称なし |
| スペイン船来航禁止 | 1624年 | 海上交通・貿易船の入港禁止 | 1623年令の実施命令 |
| ポルトガル追放令 | 1639年 | ポルトガル人を国外追放 | こちらも通称。正式法令名はなし |
「厳格に実施」された江戸期の追放令
秀吉の伴天連追放令は、布告こそ出されたものの、実際の取締りは比較的緩やかでした。
これに対して、江戸幕府によるスペイン・ポルトガルの追放は、法として厳格に実施されます。
その方針の厳しさを示す事例として、家光期の出来事ですが、マカオ使節団事件を取り上げます。
ポルトガル使節の悲劇 ― マカオ使節団事件(1840年)
1640年、ポルトガルから使節団が長崎に到着し、通商再開を求めました。
しかし、幕府の対応に揺らぎはありませんでした。
「再来航禁止。命令違反につき、使節61人中57人を処刑」
史料によって若干の差がありますが、『徳川実紀』『長崎実録大成』『日本キリシタン史』などの記録では、処罰の実態はおおむね以下のようになっています。
| 区分 | 人数 | 処遇 |
|---|---|---|
| 使節・上級士官・商人 | 約 57人 | 斬首・処刑(長崎西坂) |
| 通訳・書記・水夫など下級従者 | 約 4人 | 処刑を免れ、国外追放 |
助命された4人はマカオに戻り、事件の顛末を報告しました。その後、ポルトガル側は完全に日本への接触を断念します。
この事件は「マカオ使節団事件」と呼ばれ、歴史学の世界では長く評価が分かれてきました。
現代の一般的な歴史評価では、「残酷な事件」ではあるが、幕府の立場から見れば合理的かつ必然的な決断だったと位置づけられています。
幕府が守ろうとした「秩序」
幕府の禁教政策は、信仰そのものへの憎悪ではなく、支配秩序を守るための防衛策でした。
統治秩序が崩れる前兆 ― 共同体の分断
日本の社会では、同じ神仏を祭り、同じ儀礼を行うことが共同体の一体感を支えていました。
しかし、キリシタンたちはその枠組みの外にありました。
葬儀・祭礼・参拝を拒み、神仏を偶像とする考えを否定したため、村落共同体に「宗教的な溝」を生んでしまったのです。
地方役人の日記や裁許状には、以下のような記録も残されています。
「村中に異宗の徒あり、年中行事に加わらず、他家に交わらず」
幕府はこの溝を「統治秩序が崩れる前兆」と認識します。
幕府にとって村は、税の徴収単位であり、治安維持の基本単位。つまりこれは、単純な宗教の違いではなく「社会秩序の乱れ」そのものでした。そのため、排除や改宗は政治の一部として行われたのです。
天下安寧の国家秩序 ― 家康・秀忠の国家観
徳川家の国家観は、「君臣の秩序を守ることが平和である」というものでした。
彼らには、戦乱を終わらせて得た平和を維持する必要がありました。
そのため、1614年(慶長19年)の「キリシタン禁止令(禁制令)」には、宗教を否定する言葉ではなく、「天下の安寧を乱す」「民心を惑わす」「法度を軽んずる」といった、秩序を守ろうとする文言が並びます。
現代の「人の法」と「神の法」
現代社会における「人の法」と「神の法」についても考えてみましょう。
代表的な宗教における「神の法」の位置付け
一般的には、「人の法(憲法や法律)」が上位にあり、その枠内で宗教や信仰の自由が保障されるという方針がとられます。
日本において「神の法」は宗教教義の一部にすぎず、法的な拘束力をもちません。
それでは世界はどうなのでしょうか。
世界の代表的な宗教について、「神の法」と「人の法」の関係性を以下表にまとめます。
| 宗教 | 「神の法」と「人の法」の関係 | 補足 |
|---|---|---|
| キリスト教 | 神の法は道徳原理。人の法に従う | 政教分離を原則とする |
| ユダヤ教 | 宗教法は信者内の規範。国家法を尊重 | 厳格派は信仰内で神の法を絶対視 |
| ヒンドゥー教 | ダルマ=倫理原理。国家法とは別 | 現代インドでは完全に政教分離 |
| 仏教 | 戒律=修行規範。国家法と無関係 | 政治に干渉しない |
| イスラム教 | 区別がない(神の法=国家法)※1 | シャリーア(イスラム法)として体系化 |
宗教内部の思想傾向として「神の意志>人間の法」という価値観が部分的に残っている宗教や教派はあります。
※1 現代の世界宗教の中では、イスラム教(特にシャリーア体系)以外に「神の法」を「人の法」よりも上位に位置付けている宗教は、基本的に存在しません。
イスラム教のシャーリアについて少し確認してみましょう。
シャーリア ― イスラム教の「神の法」
イスラム教の厳格な国々では、神の法(シャリーア:Sharia)そのものが国家の法体系の根幹になっており、「人の法」と「神の法」は分離していません。そのため、“どちらを優先するか”という発想そのものが、基本的には存在しません。
トルコやエジプト、インドネシアなどの国々では、イスラム教が主流であっても、近代的な世俗法体系(人の法)が採用されています。このような国では、日常生活ではイスラムの教えを守りつつ、国家運営は世俗法に基づくという形をとっています。
ただし、信仰上の原則としては、どの国のイスラム教徒も「神の法が最も正しく、人の法はそれに従うべきもの」という価値観を持っています。
たとえ世俗法の国であっても、個人の内面では「人の法よりも神の法が上位」という意識が生きています。
イスラム教徒は「外国の法」に従うのか ― 契約の順守
イスラム法学には、「契約(アフド)」という重要な概念があります。
ムスリムがイスラム圏以外(非イスラム国家=ダー・アル・ハルブ)に滞在するとき、その国の入国条件や法律を受け入れて暮らすことは、契約を結ぶこととみなされます。
イスラム法ではこの契約を破ることは重大な罪とされるため、結果として――
「異国にいる間は、その国の法を守るのがムスリムとしての義務」
という考えが成立します。
これを「契約の遵守」と呼び、コーランにも次のような教えがあります。
「あなたがたは契約を守れ。まことに契約については責任が問われる。」
(コーラン 16章91節)
つまり、滞在先の法に従うことは、イスラム教的にも神の教えに反しないのです。
原理主義的解釈では異なる見方もある
イスラム世界の中でも、原理主義的な一派――例えば一部のサラフィー主義者やイスラム過激派は、「神の法以外に従うのは不信仰(クフル)である」と主張します。
この思想は「タウヒード(唯一神信仰)」を極端に解釈したもので、人間が作った法を神の法と同列に扱うこと自体を否定します。
いわゆる「イスラム国(IS)」や一部の過激組織はこの立場を取っており、彼らにとっては、外国の法に従うことは“信仰の裏切り”になります。
しかし、これはイスラム教徒全体から見れば少数派の過激な解釈であり、世界中の大多数のムスリムはこれを拒否しています。
江戸幕府の決断は正しかったのか
江戸幕府は、国家の安全と社会の秩序を守るために、キリスト教を排斥しました。
国民はすべて寺院の檀家として登録され、「信教の自由」は存在しませんでしたが、その社会では、すべての人が「人の法」に従う秩序が保たれ、長い平和の時代が続きました。
江戸幕府の決断は、宗教を弾圧したとして非難されるべきなのでしょうか。
それとも、国家の安定を守った英断として評価されるべきなのでしょうか。
もし現代において、「人の法」よりも「神の法」を優先する人や宗教が現れたとしたら、私たちは、どのように向き合うべきなのでしょうか。
関連年表:
【年表】江戸時代初期のキリスト教禁止の背景と実態 ― 家康から秀忠の時代まで
家康から秀忠の時代までの流れを、時系列で整理しています。
関連記事:家光期の制度化と島原の乱へ
信仰を弾圧され、貧困にあえいでいた島原の人々は、キリスト教を旗頭にした反乱「島原の乱」を起こします。
以下の記事では、家光の時代に行われたキリスト教禁止の制度化と弾圧、そしてその後に起きた島原の乱についてまとめていますので、是非合わせてご覧ください。
また本記事は、以下の「日本のキリスト教禁教史」特集の一部です。
日本のキリスト教禁教の背景や実態を詳しく知りたい方は、是非こちらもご覧ください。
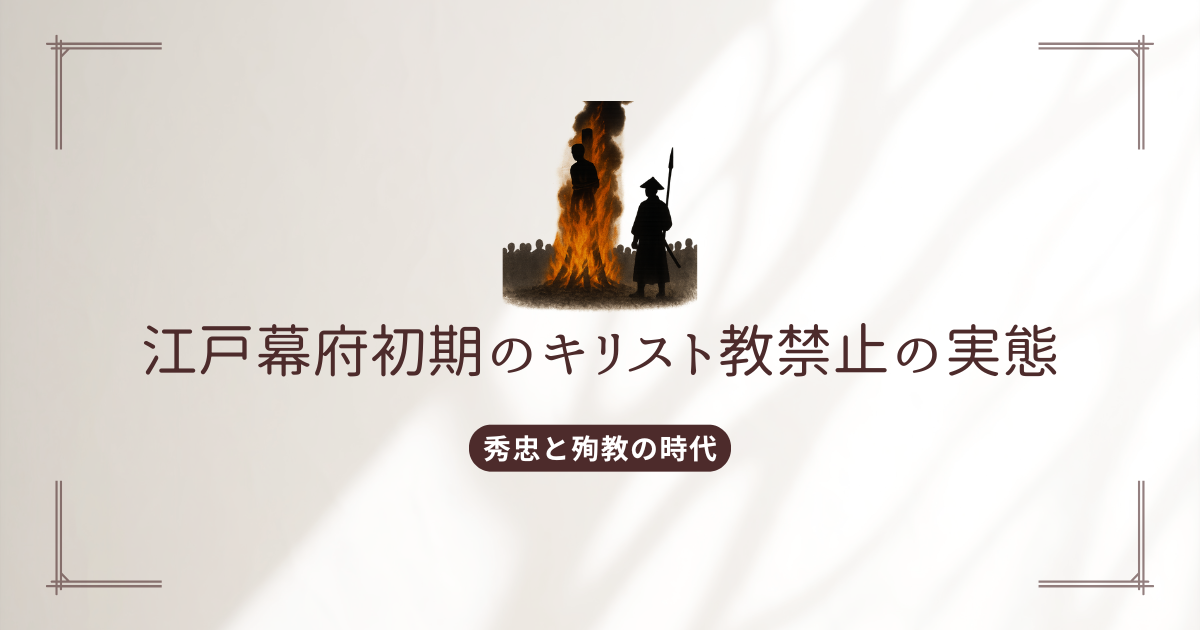
とする神道2-320x180.png)