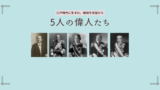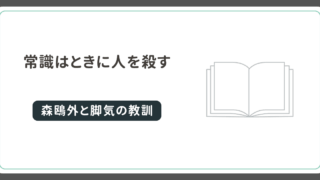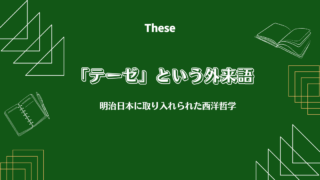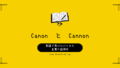当たり前のように使う「ズボン」や「ボタン」。
不思議なことに、服飾系の外来語にはフランス語に由来したものが多くあります。
その響きの奥には、明治の日本が憧れたフランス文化の記憶が息づいています。
身近な言葉に残るフランスの影
私たちが何気なく使っている「ズボン」や「ボタン」。どちらも当たり前の日本語のように思えますが、実はその語源をたどるとフランス語に行き着きます。
フランスの言葉がどのように日本語に溶け込んでいったのでしょうか。
フランス語由来の代表的な服飾外来語
日常の中にある「おしゃれな響き」の言葉の多くは、フランス語が元になっています。以下の表を見ると、その影響の広さが分かります。
| 日本語 | 原語(仏) | 発音(仏) | 意味 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボタン | bouton | ブトゥン | 留め具 | 「芽」「吹き出物」と同語源 |
| ズボン | jupon | ジュポン | 下着・ペチコート | 意味変化して日本で定着 |
| コサージュ | corsage | コルサージュ | 胸飾り | 花飾りとして輸入 |
| ベレー | béret | ベレ | 平たい帽子 | フランス兵の帽子から |
| マント | manteau | マントー | 外套 | 軍装・礼装用語から定着 |
どれもいまや完全に日本語として定着していますが、いずれも明治期の西洋化の中で取り入れられた語ばかりです。
現代フランス語のズボン(jupon)
語源となった jupon は、現代フランス語では「スカートの下に履くペチコート」を意味します。
しかしこの言葉は、いまのフランスではすっかり古風な響きとなり、「祖母世代の言葉」とされています。
一方で日本では、音の響きが「ズボン」となり、男性の下衣を指す言葉として定着しました。
同じ単語でも、文化の違いによって全く別の意味を持つようになった好例といえるでしょう。
幕末から明治へ ― 日本がフランスに学んだ時代
では、なぜ日本語の服飾語にはフランス語が多いのでしょうか。
それは、明治初期に日本が「フランス文化」をモデルとして近代化を進めたことに関係しています。
幕府が招いたフランス陸軍顧問団
幕末の江戸幕府は、ナポレオン3世が治めるフランス第二帝政と接近し、1867年にフランス陸軍顧問団を日本へ招きました。
彼らは戦術や軍制だけでなく、軍服の仕立て方まで指導しました。当時の兵士たちは、青い外套に金のボタンをつけた「フランス式軍装」に身を包んでいました。
つまり、日本で最初に「洋服」を着たのは、政治家でも貴族でもなく、軍人たちだったのです。
最初はフランスをモデルにした明治新政府
明治政府が成立した直後(1868〜1873年ごろ)、国家制度を整える際にはフランスを主なモデルにしていました。
法律・警察・教育の仕組みの多くがフランスの制度を模倣しており、「文明=フランス」という価値観が当時の日本社会を支配していました。
- 法律:ナポレオン法典を参考にした草案が初期に作られた
- 警察制度:フランス内務省を参考
- 教育制度:リセ(中等教育)型の体系を模倣
- 陸軍:幕府から引き継いだフランス式軍制
洋服もまた「文明開化の象徴」として扱われ、フランス語の服飾用語が自然に定着していったのです。
西園寺公望とパリ留学
明治の知識人の中には、直接フランスで学んだ人々もいました。
のちに首相となる西園寺公望は、青年時代にパリのリセで教育を受け、フランスの思想や文化に深い影響を受けました。彼のような留学経験者たちは、日本に帰ってからも「フランス語=教養」「フランス=文明」という価値観を広める役割を果たしました。
西園寺公望は、ペリー来航前に生まれ、昭和を見届けた人物でもあります。
以下の記事では、江戸時代から昭和までを生きた偉人を紹介していますので、関心のある方は是非ご覧ください。
ドイツに学ぶ転換 ― それでも残ったフランス語のことば
1870年、ヨーロッパで普仏戦争が起こり、フランスがドイツに敗北します。
日本が最初にヨーロッパを視察した岩倉使節団が見た光景は、敗戦国となったフランスと、急速に台頭するドイツの姿でした。
この戦争は、明治政府が近代化の方向性をドイツ式へ切り替える象徴的な契機となりました。
それでもなお、服飾用語にはフランス語が残り続けました。
軍服・洋装の「定着力」
いったん社会に広まった服装文化は、簡単には変えられません。
軍服・制服・礼装といった衣服の基準がフランス式で定まっていたため、それに付随する言葉――たとえば「ボタン」「ズボン」「マント」など――も変わらなかったのです。
軍制はドイツ式になったにもかかわらず、言葉はフランス語のまま使われていたこの現象には、制度と言葉(文化)の「定着速度の違い」が見られます。
- 制度(軍制・法制・教育)は、国家の意思で短期間に切り替えられる。
- 言葉(服飾用語・日常語)は、人々の生活や感覚に根づくもので、一度定着するとほとんど変わらない。
明治日本は、ドイツ式の軍事国家を目指しながらも、その外見(服)や言葉のレイヤーでは、フランス文化の香りを残したままだったのです。
こうしてフランス語の服飾語は、明治から昭和を経て現代まで生き続けることになります。
ズボンが「男性の象徴」となった明治時代
明治日本では、軍人や工場労働者など、近代化を支えた男性たちが、動きやすく実用的な理由から「ズボン」を着用するようになっていきました。
これが社会全体に広がるにつれ、「ズボン=男性的」「スカート=女性的」という新しい性別の区分が生まれていきます。
現代ではスカートが「女性らしさ」の象徴とされますが、その価値観の起点は明治時代にあります。
当時の「洋装」が性別の象徴を形づくった背景については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:ドイツに学んだ明治日本
明治時代の日本は、軍制だけでなく、医学や哲学など様々な分野をドイツに学びます。
明治期を代表する知識人・森鴎外は、ドイツ留学で西洋医学を学んだ人物で、文学作品だけでなく、日本のペスト防疫や脚気の対応など医学分野での活動も知られています。
明治時代に「ドイツから学んだ日本」に関心のある方は、是非以下の記事もご覧ください。
言葉の中に刻まれた歴史
いま私たちが何気なく使っている「ボタン」や「ズボン」という言葉。
その響きの奥には、かつての日本が西洋文明を吸収しようとした明治の記憶が刻まれています。フランス語の服飾語は単なる外来語ではなく、「近代日本が最初に夢見た西洋」の象徴でした。
言葉の歴史をたどることは、文化の記憶を読み解くことでもあります。
日本語の中にも、歴史がある
「ズボン」は外来語として日本に取り入れられ、その語源には政治や文化の影響が深く関わっていました。一方で、純粋な日本語にも、時代の流れの中で形や意味が変わってきた言葉があります。
近年、世界でも広く使われるようになった Kawaii(かわいい) という日本語。
この言葉には、かつて「かわいらしい」と「かわいそう」という二つの感情が重なっていました。
以下の記事では、古語「かはゆし」にまで遡り、日本人の感性がどのように変化してきたのかを探ります。